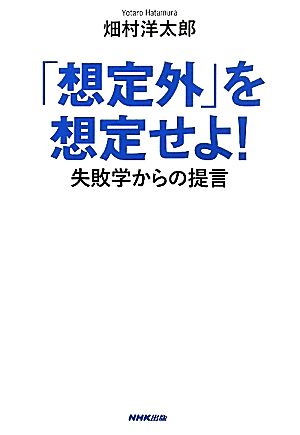「想定外」を想定せよ! の商品レビュー
「自分で」全体像を把握、マニュアル化の弊害、仮想演習、逆演算、あえて「悪意の人」となる姿勢など、実践的内容多数。想定外を想定しないのは『バカの壁』(養老孟司)にも通ずる話。
Posted by
☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0654238X
Posted by
防災に限らず、かなり有用な考え方。想定外でも、あり得ることは起こる。そのとき、全体像が分かっていれば適切に対応できるし、被害も最小化できる。ものづくりにおける暗黙知の重要さにも触れており、参考にしたい。自分の頭で考えて実践して、やっと身に着く大事な概念。
Posted by
テレビ講座を元にしていて、平易な内容。六本木の回転ドアの事故をきっかけとしたドアプロジェクトを軸に、暗黙知の消失による事故の発生を指摘。後半は、東日本大地震時の津波について、想定外を想定した対応について分析。
Posted by
https://www.nhk-book.co.jp/shop/main.jsp?trxID=C5010101&webCode=00814992011
Posted by
[2013.13]発生した物事の問題点や失敗をその後に活かすための「失敗学」から東日本大震災を振り返る一冊。 「起こり得ること」は「起こる」のであって、ゼロでなければ何事も可能性はある。それはポジティブなことにもネガティブなことにも言えるだろう。 想定外を想定するためには「全体を...
[2013.13]発生した物事の問題点や失敗をその後に活かすための「失敗学」から東日本大震災を振り返る一冊。 「起こり得ること」は「起こる」のであって、ゼロでなければ何事も可能性はある。それはポジティブなことにもネガティブなことにも言えるだろう。 想定外を想定するためには「全体を把握すること」が必要。 新しい組織と、成熟した組織を例に挙げての解説も分かり易かった。 専門的なことを極めるプロフェッショナルになることは素晴らしいことだが、マニュアルに従っているだけでは、想定外のことが起きた時に対応できない。そのためにも常に、自分の目で全体を把握しておくことが大切なのだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
無茶を言うなよ、畑村さん!タイトルが独り歩きしますよ! http://www.amazon.co.jp/review/R2159LEZ2U6HXA/ref=cm_cr_rdp_perm
Posted by
起きてしまった失敗を次に活かすための学問「失敗学」を提唱する著者が,今次震災に際し,対処法を考える。現地調査も行ない,被災地のカラー写真も何点か収録。 人は見たくないものは見ないし,考えたくないことは考えない。そのために発生頻度が少ないことは起こらないとしてしまいがち。だから...
起きてしまった失敗を次に活かすための学問「失敗学」を提唱する著者が,今次震災に際し,対処法を考える。現地調査も行ない,被災地のカラー写真も何点か収録。 人は見たくないものは見ないし,考えたくないことは考えない。そのために発生頻度が少ないことは起こらないとしてしまいがち。だから「想定」は甘くなりがちで,いざ「想定外」のことが起こると対処できずに途方に暮れてしまう。 「想定」の範囲を決めるにも,起こりうることは起こる,ということを念頭にする必要がある。その上で,「想定外」にも対応できるような的確な判断も求められる。うまくいった「想定」はニュースにならず,なかなか記憶に残らないが,そういう成功例にも目を止めなくてはいけない。例えば,中越地震では走行中の新幹線が初めて脱線したが,この程度で済んだのは,阪神大震災の教訓に学んで補強工事等を済ませていたから。マスコミは失敗が起こるとそれに注目して大きく報道するが,本来はこういう事例にもしっかりと光を当てていくことが望ましい。 報道等によって大きな災害や失敗は記憶されるが,それがいつまでも持続するものではない。個人の場合は規模によって3日,3月,3年程度で忘れられ,組織では30年,地域や社会でも300年もすれば忘れさられてしまう。失敗はそもそも伝わりにくく風化やすいという特性もある。 著者はそういう失敗の特性をふまえて対応を考えることが有益ということだが,なんだか抽象的で具体的な対処法はあまり提言されていなかった。「現地・現物・現人」として,現地に赴き,事故にまつわる現物を見て,体験した人に話を聞く,これが基本と強調するが,万人にできるものでもない。 それに本書は以前刊行されていた本を下敷きに,震災の分を追加して作られた本らしく,ところどころつぎはぎな印象。例えば「本質安全」と「制御安全」の話は,回転ドア事故には似つかわしくても震災・津波とは関連も薄く,浮いた感じがした。ちなみに原発事故の話は触れられてなかった。残念。
Posted by
想定は物を作る人が勝手に決めたもので、その範囲を超えた領域にある想定がいは起こり得ないのではなく、確率は低いかもしれないけど起こる可能性のあるものだ、ということ。 100%の絶対安全の想定などあり得ない。 想定とは物事を考えるために人為的に、あるいは意図的に作られた境界にすぎない...
想定は物を作る人が勝手に決めたもので、その範囲を超えた領域にある想定がいは起こり得ないのではなく、確率は低いかもしれないけど起こる可能性のあるものだ、ということ。 100%の絶対安全の想定などあり得ない。 想定とは物事を考えるために人為的に、あるいは意図的に作られた境界にすぎない。
Posted by
「失敗学から見た津波被害の真因とは?」というタイトルに惹かれて読み(聞き?)はじめたけれど、単なる震災被害の検証本ではなかった。(もちろん、今回の震災における津波被害が甚大になった原因についても 1 先人からの教訓を忘れたこと 2 (行政をはじめとする組織の)最悪の事態への対...
「失敗学から見た津波被害の真因とは?」というタイトルに惹かれて読み(聞き?)はじめたけれど、単なる震災被害の検証本ではなかった。(もちろん、今回の震災における津波被害が甚大になった原因についても 1 先人からの教訓を忘れたこと 2 (行政をはじめとする組織の)最悪の事態への対策を怠ったこと などを指摘。「見たくないものは見えない」といった人間の心理が想定外を生む構造についての指摘にははっとさせられた。) 「津波てんでんこ」(=自分の生命は自分で守る)といった防災教育の重要性、「マニュアル化により人は考えなくなる」(=先人が技術継承のため知恵を残しても後進は試行錯誤により学ぶことがないため偽ベテランになるおそれあり)などいろいろ考えさせられることが多かった本。ぜひおすすめしたい本!
Posted by
- 1
- 2