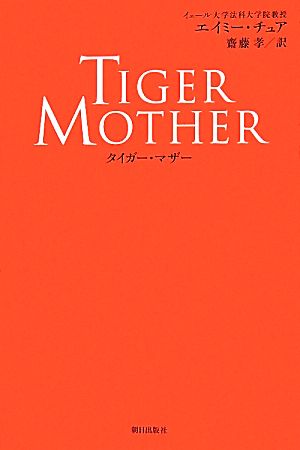タイガー・マザー の商品レビュー
面白すぎて読破。彼女のやり方は極端で、過激で、読みながらいつかは、このやり方が破綻するだろうなという期待感を持って読むんだけど、最後の方はなぜか落ち着きを見せ、これはこれでアリなのかも、と思わせるのが不思議。そして彼女の言い分もわかる(子供の自主性に任せるという西洋式の教育方法が...
面白すぎて読破。彼女のやり方は極端で、過激で、読みながらいつかは、このやり方が破綻するだろうなという期待感を持って読むんだけど、最後の方はなぜか落ち着きを見せ、これはこれでアリなのかも、と思わせるのが不思議。そして彼女の言い分もわかる(子供の自主性に任せるという西洋式の教育方法が、必ずしも子供の能力を伸ばすわけではないこと)。それからネットで見つけた著者の若さと美貌にびびりました。
Posted by
すごい鬼母。 突き抜けすぎてむしろ尊敬。 (こうはなれないけど) この人は娘にも超絶厳しいけど、それ以上に自分にも厳しそう。キャリアがそれを物語っている。 中国ママの教育ってすごいなぁー、とろただただ関心しま本(決していいとは思わないが) 子育てってほんと多種多様だなぁ…
Posted by
最初の2ページで「ねばならない、すべき」ばかりの教育方針に強い抵抗感を感じる。子どもをまるで信用しない、甘えを許さない感じ。最後まで読むと「少しは」これもアリなのかなとも思う。母親が子どもたちと真っ正面からぶつかっているから、子どもたちもぶつかってこれる、そういう関係性がいいみた...
最初の2ページで「ねばならない、すべき」ばかりの教育方針に強い抵抗感を感じる。子どもをまるで信用しない、甘えを許さない感じ。最後まで読むと「少しは」これもアリなのかなとも思う。母親が子どもたちと真っ正面からぶつかっているから、子どもたちもぶつかってこれる、そういう関係性がいいみたい。真似をしようとも思わないし、身近にこういう教育をする人がいたら、自分は止める側だろうな…と思う。この出版に向けての作業が、家族関係の再確認という必要な作業になっていることが良かった。
Posted by
子どもの自主性を重んじて、子どものやりたいままに習い事などをやらせ、満足のいかない結果であっても褒め称えて自信を与えようとする欧米流子育てを全面否定した中国系エリートワーキングマザーの子育て本。欧米人は子どもの幸せを声を大にして言う割に、子どもは大きくなると親に寄り付かないという...
子どもの自主性を重んじて、子どものやりたいままに習い事などをやらせ、満足のいかない結果であっても褒め称えて自信を与えようとする欧米流子育てを全面否定した中国系エリートワーキングマザーの子育て本。欧米人は子どもの幸せを声を大にして言う割に、子どもは大きくなると親に寄り付かないという子育ての失敗をあざ笑い、親は一日何時間にも及ぶピアノやバイオリンのレッスンをさせるだけでなくきっちり付き添い、勉強もすべて1位を目指させる。2位ならけなす。毎日が戦場のような厳しい子育てをしても、子どもはいつまでも親のことを思いやる優しい子どもになると断言して突き進む彼女の子育て本を読んで、なぜか安堵する自分がいる。だいたい、近頃流行の育児本は「子どもたちに自信をつけるために」いつも穏やかに子どもに接し、やさしく励ます母親像が強要される。子育てをしている人なら分かると思うが、子どものことを思えば思うほど、それはとても難しい注文なのだ。もっと勉強もできてほしいし、「いいこ」になってほしい。自分に余裕がない時はどうしても自分の価値観を子どもに押し付けてしまうこともある。そういう子育てもアリ、と思うことでぐっと肩の荷が降ろせたり、しました(^ ^;)
Posted by
確かにメリハリといった点で、欧米式と中国式の中庸が重要かと思う。 ただ、本書全体を通しては共感しきれない部分が多かった(単純に価値観が異なるということであって、考え方を否定するものではない)。 一時期、ユダヤ人富豪の教育論が話題となり、自分も読んだが、それ以降は私にはこのユダヤ...
確かにメリハリといった点で、欧米式と中国式の中庸が重要かと思う。 ただ、本書全体を通しては共感しきれない部分が多かった(単純に価値観が異なるということであって、考え方を否定するものではない)。 一時期、ユダヤ人富豪の教育論が話題となり、自分も読んだが、それ以降は私にはこのユダヤ人教育論の方がしっくり来る。 博物館や美術館、図書館などに頻繁に通う。ボーイスカウトなどで実践を意識させる。 いずれにせよ、よほどの神童ではない限り、子どもたち自身がしっかり答を出していこうとするプロセスが大切なのではないか。
Posted by
おもしろい訳ではないけど、中国式と欧米式の教育方法の違いがわかった。私は中庸の教育方法派かな。中国式は、将来の幸せの為に今を犠牲にするが、今に幸せを感じられなかったら、逃している事だっておおくあるのではないかと思う。
Posted by
中国系アメリカ人の母親が超猛烈教育ママとして子育てした様子を書いた本。欧米式子育てと中国式子育ての比較も頻繁に出てくる。
Posted by
中国系アメリカ人のスパルタ式子育て ただ一般化はできないだろうと思う 登場人物が、勝ち組の中の勝ち組という人ばかり 著者は、Harvard University Law Schoolを出て Yale Universityの教授 夫は同じ経歴で、しかも人気作家らしい 著者の両親...
中国系アメリカ人のスパルタ式子育て ただ一般化はできないだろうと思う 登場人物が、勝ち組の中の勝ち組という人ばかり 著者は、Harvard University Law Schoolを出て Yale Universityの教授 夫は同じ経歴で、しかも人気作家らしい 著者の両親も高学歴の中国人 夫の両親も同じ この環境(遺伝を含め)と、スパルタ式教育と、 どちらの影響が大きいか、簡単には解らないだろう ただ、これを読んで感じたのは 子どもは忘れる、ということ。 辛い経験も、楽しく遊んだことも、忘れてしまう。 だとしたら、成長後に成果につながることをさせるべきかも ピアノやヴァイオリンもそうだし、勉強もそう。 いろいろな遊びで子どもの感覚を育てたり 楽しい経験のためにピクニックやイベントをしたり そんな成果が不明なことは、 ただ親が子どもの笑顔を見るため、と割り切るべきかもね。 もう一つ、大きく納得させられたのは 齋藤孝先生の翻訳 さすが、上手い!!
Posted by
エイミーはとても強い人。 ゴールが正しければ、手法はよしあしじゃなくて、実行する人がどれだけ信念をもってやるかが大切なのではないかと思います。 決してあきらめない、誠意に基づき決断したことを貫くこと。簡単じゃないけど参考になります。
Posted by
びっくりするぐらいのスパルタ教育で二人の娘を育て上げた 中国系お母さんの育児奮闘記。 ・友達の家にお泊りに行ってはいけない。 ・成績はオールAでなければならない。 ・2番はダメ。1番以外認められない。 等など、中国系の人の考えていることは やや(というか、かなり)度が過ぎている...
びっくりするぐらいのスパルタ教育で二人の娘を育て上げた 中国系お母さんの育児奮闘記。 ・友達の家にお泊りに行ってはいけない。 ・成績はオールAでなければならない。 ・2番はダメ。1番以外認められない。 等など、中国系の人の考えていることは やや(というか、かなり)度が過ぎているように思えます。 興味深いのは、そんな超スパルタで教育したところ、 娘はどう成長していくかがこの物語を通じて分かるところです。 結果は、一勝一敗というところでしょうか!? とはいえ、小さな頃から「強制」したおかげで、 子供たちはのめり込んだときのここ一番の集中力は、 とてつもない力を発揮しています。 そういうところは、放任主義の教育方針の人も 参考になりそうなところです。 ただ、僕は(幼少からの)スパルタには否定的ですが。。
Posted by
- 1
- 2