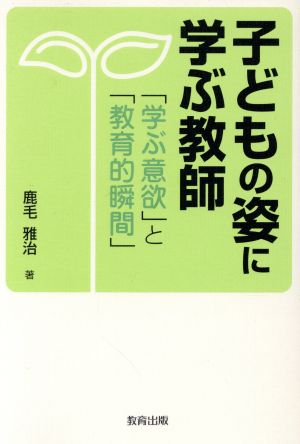子どもの姿に学ぶ教師 の商品レビュー
評価とは、してから次の実践に生かすもの。 わかってはいるんだが、なかなか 評価するための活動、をしてしまう。 3学期こそは…!!!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
教育心理学者。 「教育的瞬間」という新しい視点を与えてくれました。 授業をしていると,確かに,ある子どもの発言によって,流れが変わることがあります。そして授業が豊かに展開することがあります。あるときは,脱線していきます。でも,それが,子どもたちにとって,より楽しい学びになったりもします。 教師は,「指導案」(こうして授業を進めよう)という思いを,軽重はあるものの,ある程度もって授業に臨んでいます。そして,それから,なるべく外れないように外れないようにしようと思って進めている人が多いようです。普段もそうですが,他の教師が見に来るような授業なら,なおさら,その指導案通りに進めようとするのです。しかし,その結果,授業でのダイナミズムは失われていきます。予想外のステキな子どもの発言に気づくことなく,進んでいくのです。 鹿毛氏は,以上のような指導案による授業のことを「脚本としてのストーリー」と呼んでいます。そして,授業には,もう一つ別のストーリー「ハプニングとしてのストーリー」があるといいます。(本書213ぺ)。そして,「この二つのストーリーのインタラクションとして,世界で一回きりのユニークな授業が編み出されていく」のだと述べています。 授業研究も,指導案からのズレを指摘するばかりではなく,ハプニングを大切にした授業だったかどうかも検討してみる必要があるのではないかという指摘には,納得しました。 今,現場の授業研究に,閉塞感が漂っているのは,どうも,借り物の言葉を使って,分かったつもりになって発言する人が多いからなんだということも,納得しました。ま,なんとなく感じていたことですが,こうして言葉にしてもらうと,自分の認識のメタ認知になります。 最初から最後まで,自分の授業を子どもの視点から,そして心理学の視点から見直す,とってもいい本でした。お薦めします。
Posted by
- 1