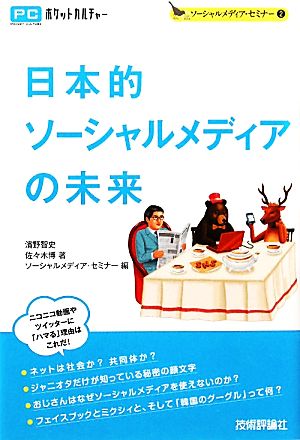日本的ソーシャルメディアの未来(2) の商品レビュー
ネットを社会学的に捉え直す視点が得られる良書。コミュニティとソサエティの概念からネットを捉え直すことで、深い考察が得られると思います。 コミュニティ(ゲマインシャフト):同期的 ソサエティ (ゲゼルシャフト) :非同期的 基本的にはソーシャルメディアはソサエティ的(非同期)だ...
ネットを社会学的に捉え直す視点が得られる良書。コミュニティとソサエティの概念からネットを捉え直すことで、深い考察が得られると思います。 コミュニティ(ゲマインシャフト):同期的 ソサエティ (ゲゼルシャフト) :非同期的 基本的にはソーシャルメディアはソサエティ的(非同期)だけれども、一瞬、同期的なコミュニケーションが成立することでコミュニティ的にもなる点がポイント。 そしてそれは、各SNSのアーキテクチャの設計によって、時間の同期のされ方が異なってくる。 Twitter :選択同期(リプライで話題を選択して同期) ニコニコ:疑似同期(コメント機能でいつでも祭り状態) この社会学的な時間の捉え方が、SNSの理解を深めることができると思います。今流行りのSNSはどうだろう。
Posted by
対話形式で、ソーシャルメディアとは何かから始まり、ソーシャルメディアの様々な視点を与えてくれる本書。その視点をひとつひとつ深く掘り下げれば、論文がごろごろ書けるなあと思いました。良書です。
Posted by
ネットはコミュニティなのか?ソサイエティなのか? そもそもネットはコミュニティと社会が入り混じっている。 ジャニオタって、誰のファンかを顔文字であらわすんだ。すごいな。
Posted by
mixiやニコニコ動画という、日本独特の進化を遂げたソーシャルメディア。その背景についての対談をまとめた本。対談の書き起こしなので、会話体でわかりやすく読むことができました。 良くも悪くも、日本は「ムラ社会」的な風土で、それゆえに「動画を通じた狭いつながり」を楽しむニコニコ動画...
mixiやニコニコ動画という、日本独特の進化を遂げたソーシャルメディア。その背景についての対談をまとめた本。対談の書き起こしなので、会話体でわかりやすく読むことができました。 良くも悪くも、日本は「ムラ社会」的な風土で、それゆえに「動画を通じた狭いつながり」を楽しむニコニコ動画や、「既知の友人とのまったりとしたつながり」を楽しむmixiが登場した、といった感じ。 LINEの電話帳に基づく濃厚かつ閉鎖的なグループチャット、Twitterの非公開アカウントを用いた私的交流といった現象を解明していくのにも役立ちそう。 全体的に、濱野さんの著作『アーキテクチャの生態系』の入門編といった感じです。私もまんまと騙され(?)、『アーキテクチャの生態系』を読み始めてしまいました。日本のソーシャルメディア入門として、お勧めいたします。
Posted by
これは面白かった! ソサエティとコミュニティの違い…とか、根本的なお話から始まっているので興味深く読みました。 年配の人向けのインターネット講座、SNS講座なんてのは、もっと広めてもいいんではないでしょうか。定年退職したおじさんたちの場合、近隣で地域コミュニティに入って行こうと...
これは面白かった! ソサエティとコミュニティの違い…とか、根本的なお話から始まっているので興味深く読みました。 年配の人向けのインターネット講座、SNS講座なんてのは、もっと広めてもいいんではないでしょうか。定年退職したおじさんたちの場合、近隣で地域コミュニティに入って行こうとするよりもネット上でコミュニティ作り上げて活動する方が活躍できて楽しいんじゃないかなぁ。
Posted by
タイトルの通り、2010年12月に行われた対談録。濱野智史氏と佐々木博氏。 何かと混同されがちな「コミュニティ」と「ソサエティ」の本来の意味合いの違いと、日本的社会の形成過程からの日本的ソーシャルメディアの捉え方を、とってもすっきり言いきってくれていて面白かった。日本人の対人意...
タイトルの通り、2010年12月に行われた対談録。濱野智史氏と佐々木博氏。 何かと混同されがちな「コミュニティ」と「ソサエティ」の本来の意味合いの違いと、日本的社会の形成過程からの日本的ソーシャルメディアの捉え方を、とってもすっきり言いきってくれていて面白かった。日本人の対人意識や集団における立ちふるまい方、ネットとの接し方などなど、ソーシャルメディアの変遷を見ると考察できることってたくさんあるのよねと改めて。 日本人が「ソサエティ」コンテクストで対人関係を築くのが苦手な理由として、固定化された「学校クラス制度」が大きな原因っていう考察はなるほど感ありましたね。いじめをなくしたければ、小学校の時点から大学のような選択授業制にすればいいのかも。あの「クラス」というコミュニティの帯びているそこはかとない残酷さを、思い出してました。
Posted by
見かけによらず良書。二時間足らずで読める割に、社会学的な見地とかも織り込まれてて面白かった。 結論がもう少しインパクトあれば、という気もしたけど、まぁ正論か、という感じで終わった。 読者層的にヒットだと思うのは、マスコミ系以外を先行してるけどマスコミに興味ある人。そして私はそこな...
見かけによらず良書。二時間足らずで読める割に、社会学的な見地とかも織り込まれてて面白かった。 結論がもう少しインパクトあれば、という気もしたけど、まぁ正論か、という感じで終わった。 読者層的にヒットだと思うのは、マスコミ系以外を先行してるけどマスコミに興味ある人。そして私はそこなのでよかった、ので★5つ。ちょい甘ですが。
Posted by
ソーシャルメディアに関する機能論から文化論まで、2時間そこそこでわかりやすくさっと網羅できる本。 どうせ講演録と放っていた本でしたが、読んでみたらえらい良書でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なぜツイッターやニコニコ動画が流行るのか、 なぜアメリカ人の方が日本人に比べてSNSをうまく使えるのか、 50年後はどうなっているのか、などが分かりやすく面白く書かれていた。 今、旬なことを取り上げているので読みがいがあった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
濱野氏の「アーキテクチャーの生態系」を読んでいたので、公演を本の形にしたことに興味を持って読んだ本。 濱野氏が、社会学の概念である、コミュニティとソサエティの二元論から、それぞれの社会の成り立ち、それぞれの特性を説明し、今の日本の状況もこの概念を用いると非常にわかりやすいことがわかった。 特に今の学校の文化が、時代遅れのコミュニティ志向が強いために、いろいろな制度疲労がみえやすいことの指摘は非常に理にかなっていると思った。 公演の本なので読みやすいが、内容は非常に詰まっていると思う。
Posted by