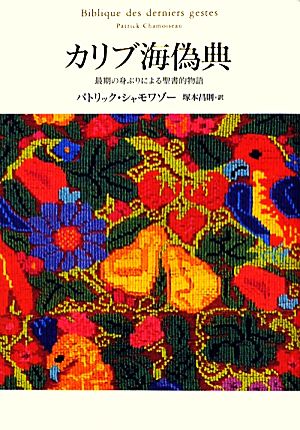カリブ海偽典 の商品レビュー
今年最初は他に決めていたのに、パラパラしたらあまりにも面白く広く色彩豊かで一気に終えてしまった・・・勿体ない。植民地支配に抵抗した英雄が身振りで紡ぐ、小さき人びとの物語。圧巻です。
Posted by
書評家、トヨザキ社長のおすすめにより読み始めましたが、、、なげーよ(950p.)。厚すぎるよ(5.4cm)。持ち歩きにくいよ。そしておもしれーよ。マルケスの百年の孤独とかお好きな方にはおすすめです。 舞台は、カリブ海に浮かぶフランスの海外県の小島マルティニーク。 北南アメリカ...
書評家、トヨザキ社長のおすすめにより読み始めましたが、、、なげーよ(950p.)。厚すぎるよ(5.4cm)。持ち歩きにくいよ。そしておもしれーよ。マルケスの百年の孤独とかお好きな方にはおすすめです。 舞台は、カリブ海に浮かぶフランスの海外県の小島マルティニーク。 北南アメリカ、アフリカ、中東、東南アジア、世界各地の植民地支配への抵抗運動に参加した(と称する)男が、死の床で半ば錯乱しつつ回想する数奇な一生。 1.不確かな始まり ホンネ島の心が動く 臨終の始まりにあたって、果てしない人生で繰り広げた反植民地戦争の数々を反芻するかわりに、バルタザール=ボデュール=ジュール氏は、精力のおき火に掻き立てられ、彼の存在を高揚させた七百七十二の恋のことを考えた。 プロローグ。臨終までの三十三日間にわたって、主人公が身ぶりでその人生を語りだすまでのいきさつについて。 2.魔法にかけられた子供時代の三十二の恋をめぐる不確かな物語 主人公バルタザール=ボデュール=ジュール氏の幼年時代。出生の際、スペルのおばあさんのような強力な女悪魔に死の呪いをかけられた主人公を両親は必死に守りますが、家族とその周辺には呪いによって死が蔓延します。両親は、森に生きる良い魔法使い=マントーに子どもを託し、死んでしまいます。子どもはマントーと一緒に生活し、森で生きる術、女悪魔から身を守る術を学びながら成長していきます。 3.青年時代におけるあれこれの恋愛をめぐる数々の不確かな物語 女魔法使いは呪いを解いたり、難産を助けたりする仕事をしているのですが、この世のものではない者に胎まされた女の助産の仕事に付き添っているとき、主人公はその女の美しい娘に出会い、一目で恋に落ちます。そして、娘の叔母に勉強を教えてもらうという名目で家に通うようになり、やがてその美しい娘と叔母の家でいっしょに暮らすようになります。叔母は植民地主義に対する怒りで男(のような外見)になっており、急進的な共産主義者として、主人公にこの世にはびこる植民地主義とその悪行を叩きこみます。世界に抑圧と不公正を見て憤慨する叔母と対照的に、美しい姪は世界の良い面ばかりを見る優しい夢見がちな女性で、家に引きこもりサン=ジョン・ペルスの詩とこの世のものではない者たちとの交感に耽っています。主人公とこの叔母・姪との共同生活と女悪魔の襲来による破滅、その後主人公がこの世のあらゆる抑圧に抵抗する反逆者になるまでの経緯。 4.老年期の残りの愛をめぐる数々の不確かな物語 世界各地で反逆者として戦った主人公は、老境に入り故郷の島に戻ります。フランスの海外県になり、グローバリゼーションの波にのまれた故郷の島の変貌ぶりにとまどいつつも、あいかわらす植民地支配への抵抗活動をやめず、観光産業に破壊される自然環境を守るエコテロリストに、あるいは若者を麻薬漬けにする麻薬組織の根拠地の破壊などの活動を積極的に行うようになります。また、地元出身の英雄として多くのラジオ番組に出演し、自分の驚くべき経験や人生訓などをまくしたてるようにもなります。しかし、娘のようにかわいがった姪の死をきっかけに、そうした活動に関心を失い、世から隠れ過去の追憶の中に生きることに。やがて迎えた臨終のときに主人公が出会うものは。 以上はあらすじのあらすじのようなもので、本筋(と思われる)話のまわりに、まるでジャボチカバの実のように多くの逸話・ほら話・おとぎ話が挿入されます。 マルティニークに住んでいた原住民はヨーロッパ人に皆殺しにされ、その後、白人とアフリカから連れてこられた奴隷たちが住むようになった島です。色々な意味で、それぞれ故郷から引き離されている、こうした島に生まれた人間がアイデンティティを確立する困難さがうかがえました。 日本翻訳文化賞を受賞されているそうで、長いけど、文章表現は平易で読みやすかった。
Posted by
世界各地の独立戦争に参加したマルチニック出身の老人の臨終に立ち会い、彼の「身振り」によって示される人生の回顧を記録した、という体裁の小説。 だがこの小説の柱となるのは戦いの記憶ではなく、幼年~青年期に遭遇した数々の偉大な女性に関する記憶である。 彼女らを通して今は失われてしまっ...
世界各地の独立戦争に参加したマルチニック出身の老人の臨終に立ち会い、彼の「身振り」によって示される人生の回顧を記録した、という体裁の小説。 だがこの小説の柱となるのは戦いの記憶ではなく、幼年~青年期に遭遇した数々の偉大な女性に関する記憶である。 彼女らを通して今は失われてしまったマルチニックの伝統というか文化というか習俗といったものが、多分に幻想的に語られている。 そしてその彼女たちの身振りを通じて、それを無意識に真似ることで、老人自身マルチニックの伝統を引き継いでいたことに気づくのである。 一方でこの小説のもう一つのテーマ、「支配-被支配」関係との戦いという面もしっかり表現されている。 老人が若かりし日は支配者は見えやすかった。植民地主義者が支配の権化で、彼らを打ち倒すべく独立闘争のなかに身を投じることが、支配-被支配関係の打破に繋がると思われた。 しかし植民地支配を脱却しついに手に入れたはずの自由のもとでも、違ったかたちで支配-被支配関係が継続していることを、老人は年老いて故郷に戻って発見する。 それは例えば資本主義のシステムそのものという、以前に比べ戦いにくいものに姿を変えていた。 支配関係を倒すだけでは別の支配がそれに取って代わるだけ、というジレンマから脱することは、この世において果たして実現するのか。 老人はその事実に愕然とし、自分の人生を失敗と捉え、臨終の宣言をするのである・・・。 こう書くと救いのない終わりのように見えるが、それでもどこかに「支配-被支配」が存在しない世界が築けるのではないか。いかなる支配関係をも超越する偉大なる愛をもって人々が接し合う、そうした社会は本当に実現できないのか。 この問いに微かな希望を持たせて終わるラストはなかなか清々しい。 非常に分量が多く、本自体の重量も重く(なぜ上下二分冊にしなかったのだろう。通勤途上に読むのが大変だった)、とっつきにくい印象を与えるが、読んで損はない、充実した小説。 『テキサコ』よりも楽しめた。
Posted by
- 1