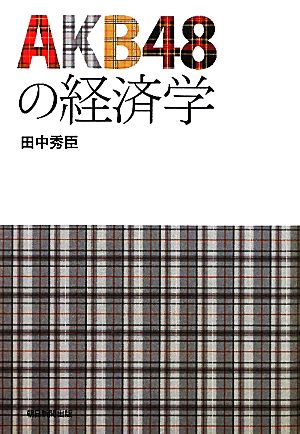AKB48の経済学 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
AKB48については興味がなく、この際だから読んでみようと思った。 AKB48の入団テストや競争システムなど知らないことが多かった。この団体の経済的システムが大相撲と似ているとの指摘におーなるほどと思った。
Posted by
ターゲットは若くてお金がない層だから、1000円以上の本にしない、入場料も3000円と安い。ふつうなら1万円くらいする。 おニャン子はテレビの視聴率低迷とともに終了してしまったから、その反省を活かしている。 アイドル個人の収入や安い、今までの投資を考えたら仕方がない。それでもイン...
ターゲットは若くてお金がない層だから、1000円以上の本にしない、入場料も3000円と安い。ふつうなら1万円くらいする。 おニャン子はテレビの視聴率低迷とともに終了してしまったから、その反省を活かしている。 アイドル個人の収入や安い、今までの投資を考えたら仕方がない。それでもインセンティブが働くから安くてもやる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
AKB48グループを大相撲の組織に例えている。 個々のタレントのマネジメントは各芸能事務所が行い、 集団による公演のマネジメントはAKSという統括事務所がある。 同じように大相撲でも個々の力士については各相撲部屋が行い、 興行としての「本場所」「巡業」は相撲協会が責任を持つ。 このように経済学という一見すると敷居の高い、馴染みのない分野についてAKBという大衆文化を通じて分かりやすく説明している。 AKBが好きな人はもちろんのこと、AKBについての予備知識がなくても十分楽しめる内容となっている。
Posted by
「心の消費」というのはなるほどと思った。少しこじつけのような部分もあるが全体として得るものは結構あった。 経済学の入門書、読み物的な感じで読むとよい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
AKBが何故ここまでブレイクしたのか興味を持っていました。 そのヒントをつかめればと思い、正月の時間のある間に読み進めました。 全222ページ。3時間で読める。 内容は著者があとがきで書いているように、「AKBの魅力を経済学者が伝える」という内容。 タイトルに「経済学」という文字が入っているものの経済学的な分析やアプローチは非常に少なく、また著者の明確な主張もありません。 本の中では「AKBって~に似てるよね」とか、「~と解釈できるよね」といった著者の一見解が書いてあります。 これらのことから、恐らくターゲットとしてAKBに興味を持つ一般層を想定していると思われます。 本文の中に小難しいことは皆無ですので至極とっつきやくスラスラ読める反面、読んだところで何かを得るということもないと思われます。 個人的にはAKB48キャラクター分類マトリクスを載せる意味を見いだせず、むしろその部分に著者が著者の好きなAKBを好きに語るというスタンスを感じました。 話の小ネタ程度に読むのは悪くないけど、繰り返して読む機会は無いと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本を買うのがちょっと恥ずかしかったです。 ① AKB48とデフレ 現在でこそCD売り上げにおいて爆発的な数字をたたき出しバブル的に売れているAKBであるが、初期のAKBの売り出し方はむしろデフレ下であることを強く意識したリスク回避的で堅実な売り出し方であるといえる。例えばそれは価格設定に表れていて、一般的なライブに比べれば劇場の観覧料は安いし、写真集も作りこそそれほど良くないが割安である。加えてターゲットはあまりお金を持っていない学生などの層であるから価格は安く抑えなくてはならない。こうした価格設定によりコアなファンを数千人でも掴んでしまえば、ビジネスの規模が縮小しこそすれ何とか活動を続けていけるという、元本保証の取引のようなビジネスなのである。 今日のプレゼンで「抱き合わせという麻薬のような販促で売上を向上させることは本誌の魅力を減ずる」とのFBを頂いたが、AKBの麻薬のような販促もこうした初期の基盤づくりがあるからこそ成り立っているのだろう。実際秋元康はバブリーに稼げるときに稼げるだけ稼いで、下火になってからもそれなりのビジネスを続けていこうという魂胆なのだろう。 ② 物語消費論と記号消費論、心の消費 大塚英志氏は「大きな物語」が喪失された現代での消費形態として物語消費というものを指摘している。物語消費とは人々が商品の持つ作り手が生んだ物語の満足できず、消費者が自ら小さな私的な物語を作り上げることを指す。東浩紀氏はさらにここから論を展開させ記号消費論を展開させる。記号消費の中で人々はもはや小さな物語にすら目を向けることなく、典型的なパーツなどの記号といったさらに矮小化された細部の断片を消費するとしている。 また筆者はこうして消費の対象が段階的に矮小化されていく傾向を、デフレが根本的な原因となっていると指摘する。デフレ下の文化では当然コストの小さい消費が好まれるので、ネット上でのコミュニケーションのような自分で生産して自分で消費するという傾向も前述の文化・消費形態の成長に拍車をかけている。 ③ AKBと日本の就労形態 吉田さんがプレゼンでAKBの実力主義的な構造を外資の企業に例えていたが、本著ではむしろ日本の大企業の就労形態とのアナロジーを示している。AKBの上位メンバーでは全体の平均年齢より年齢層がやや高い。熟練型年功序列社会の中では年齢とともに実力の向上も見込まれるために実際にはゆるやかな年功序列が形成されるのである。また過去にアイドルであったタレントが現在もママドルなどと呼ばれ活躍している様子は終身雇用的であると揶揄している。結果としてアイドル業界での高齢化は今後も緩やかに進んでいくだろう。
Posted by
TOPPOINT 2011年2月号より。 AKB48の成功事例から 不況期にビジネスで成功するためのヒントを得る。 著者は上武大学教授。
Posted by
きっかけは、美崎栄一郎さんの講演で紹介されたことでした。 感想としては、非常に興味深く読ませていただきました。 著者のいう、流行や文化は、そのときの経済状況を反映する、とのことから、現在のデフレ不況下において、なぜAKB48に人気が集まったのか、また大相撲との共通性、日本の雇用...
きっかけは、美崎栄一郎さんの講演で紹介されたことでした。 感想としては、非常に興味深く読ませていただきました。 著者のいう、流行や文化は、そのときの経済状況を反映する、とのことから、現在のデフレ不況下において、なぜAKB48に人気が集まったのか、また大相撲との共通性、日本の雇用システムとの類似性などを独自の視点でまとめています。 まさしくヒットの裏には必ず何らかの理由があるということを教えてくれます。 しかし、このモデルは完全なものではありません。現在の不況の克服もそうですが、いろいろな面で模索が続くのでしょう。 <この本から得られた気づきとアクション> ・流行には理由がある。その理由を突き止めることで、打開へのヒントがつかめるかもしれない。 ・過去の歴史と比較することで(ここでは、おニャン子クラブやモーニング娘。)、見えることがある。歴史を学ぶことは重要だ。 <目次> プロローグ AKB48で日本経済がわかる 第1章 不況に強いビジネスモデル 赤字覚悟の低料金講演 インターネットの普及と音楽業界のビジネスモデル転換 ターゲットは若くて収入の低い おたく おニャン子クラブの類似点、相違点 おニャン子のビジネスモデルを継いだモーニング娘。 おニャン子とモー娘から何を学んだか 「もしかしたら私も」と思わせる! 不況に強い演歌歌手、不況に弱いアイドル歌手 コアな客層をガッチリつかむ宝塚 第2章 デフレ不況で増殖する「心の消費」 デフレカルチャーとは何か デフレが生んだ消費行為 社会現象にまでなった「心の消費」 不況はアイドルグループを生む 暗い世相に輝いたアイドルたち 「萌え」と「癒し」は内向き志向の反映か デフレカルチャーと嫌消費 デフレ不況の希望の光 アイドル人気に経済の牽引力は求められない 第3章 全国的に認知された「おたく市場」 物語消費論と記号消費論 精神文化としてのデフレカルチャー ゼロ年代の想像力の結晶 おたくへの視線の変化とAKB48の登場 なぜ一人勝ちを続けるのか 第4章 大相撲とAKB48と日本型雇用 インサイダーが強いアイドル業界 相撲部屋と芸能事務所の類似点 総選挙システムによる番付 入り口の透明性とファンとのふれあい重視 成果主義、その実態は熟練型年功序列 意図して生み出された逆転人事による刺激と息抜き アイドルの高年齢化と終身雇用 第5章 アイドルグループの経済分析 集団化によるリスク分散 アイドルの会社的組織化 パッケージ売りとバラ売りの経済学的論考 実はパッケージ売りではないAKB48 AKB48型ビジネスモデルの泣き所 第6章 「ローカル」か「グローバル」か 地方から表舞台に出るルート 若い世代の地方回帰 内にこもる若者たち ご当地アイドルの時代到来か サブカルチャーのグローバル化とローカル化 海外おたく文化の源流 第7章 アイドル高年齢化のその後── 「身近にいる女の子」の小さな物語 AKB48キャラクター分類マトリクス 今後の課題、出口戦略 いつまでAKB48のメンバーでいられるのか
Posted by
コンテンツの力としてではなく、システムやビジネスモデル、マーケティングとして語れることの豊富さがAKB48の新しさなのだと思い知りました。大相撲との類似性には納得しました。
Posted by
「AKB48がわかれば、日本経済がわかる」として、今日の構造的な不況のもとで成功を収めるAKB48を、経済学的な観点から分析しようとした一冊です。 1990年代から2000年代にかけてのデフレや経済の停滞が生み出した新たな消費(文化活動)である「デフレカルチャー」のもとで、人...
「AKB48がわかれば、日本経済がわかる」として、今日の構造的な不況のもとで成功を収めるAKB48を、経済学的な観点から分析しようとした一冊です。 1990年代から2000年代にかけてのデフレや経済の停滞が生み出した新たな消費(文化活動)である「デフレカルチャー」のもとで、人々はブログに代表されるような「生産と消費が一致」、「心の消費」、という2つの特徴をもつ活動に、多くの労力を傾けるようになっている、と筆者は指摘します。 こうした消費傾向が主流になりつつあるなかで、AKB48の「テレビではなく専用劇場型」、「入口の透明性」、「徹底した低料金」「会いに行けるという敷居の低さ」などの戦略は非常に親和性が高い。すなわち「デフレに強いビジネスモデル」というわけです。それゆえ、現在の一人勝ち的な状況があるのだと… 本来、大学教員である筆者が高校生向けの公開講座として考えていたものがベースとなっており、それゆえ難解な理論や概念もなく、内容はとても分かりやすくなっています。 一方で、「日本経済がわかる」かというと、そこには若干の疑問符が付きます。(筆者も触れていますが)AKB48が消費されるアイドル市場、あるいはそこでAKB48の成功を誘引したプロダクトコンシューマーや「心=消費財」という傾向は、あくまで経済や社会の一部でしかないので、日本経済全体のものとして過度に一般化されるべきではありません。 それはともあれ、今日一種の社会現象と化しており現在進行形のヴィヴィッドな現象であるAKB48は、「経済学的にはこう理解できるよ」と優しく教えてくれる、そんな魅力をもった一冊です。
Posted by