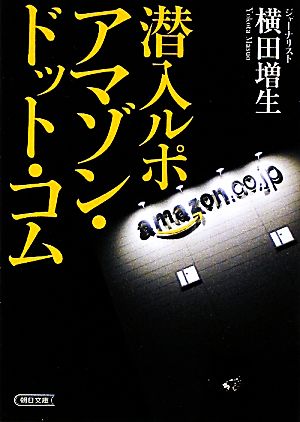潜入ルポ アマゾン・ドット・コム の商品レビュー
記者、編集者目線でもこれほどエネルギーに溢れて仕事をしてる筆者に刺激を受けたのと、 アマゾン配送センターでのアルバイト経験で描かれていた社内の人間の階級格差が、自尊心の格差、希望格差に繋がっているという意見に圧倒された。 自分の仕事の意味を理解して、意義を感じて、自分の仕事に胸...
記者、編集者目線でもこれほどエネルギーに溢れて仕事をしてる筆者に刺激を受けたのと、 アマゾン配送センターでのアルバイト経験で描かれていた社内の人間の階級格差が、自尊心の格差、希望格差に繋がっているという意見に圧倒された。 自分の仕事の意味を理解して、意義を感じて、自分の仕事に胸を張って好きでいられることがどれだけ大切なことかを感じさせられた。 そして当時革命的だったであろうAmazonのシステムを成り立たせる裏側には、泥臭くアナログに仕事をする人間の存在があるというのも忘れてはいけないなと思った。 この本が、職場で所在不明に取り残されていた本だというのにまた皮肉を感じる…
Posted by
トヨタの絶望工場を参考にした(ヒントにした)と著者は語っているが、同じ潜入ルポながらまったく違うものになっている。トヨタには希望があったが、アマゾンには最初から希望はない、というのが印象的。また、マーケットプレイスにも触れているが、これも出品者は絶対に大儲けできない仕組みになって...
トヨタの絶望工場を参考にした(ヒントにした)と著者は語っているが、同じ潜入ルポながらまったく違うものになっている。トヨタには希望があったが、アマゾンには最初から希望はない、というのが印象的。また、マーケットプレイスにも触れているが、これも出品者は絶対に大儲けできない仕組みになっているようだ。綿密な計算があらゆるところで張り巡らされている。
Posted by
本来の筋もだが、マーケットプレイスのくだりがそういう事かと。 再販制度については自分の意見が決められない。 この本実はAmazonの中古で購入して読んだのだ・・
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『アマゾン・ドット・コムの光と影』情報センター出版局 (2005年4月19日発売)は読んでいた。本書は二部を追加して2010年に文庫本として発行されたものである。 アマゾンがマーケットプレイス(中古本)で一円本を1冊売る方うが新刊を売った場合の二倍以上の利益があるのだとか、更に中古本に1000円以上の値が付けば利益は四倍になる。この手終料ビジネスには、コストも作業も在庫も発生しない。マーケットプレイス(中古本販売)は09年アマゾン全体の三割を占め、アマゾンの利益の源泉になっている。 アマゾンの創設者、ベゾスの理念とは「顧客第一主義」そして「小さな書店の時代に戻すこと」それらをインターネット(オンライン書籍販売)を使って実現しようということである。顧客第一主義が行き過ぎることで、そこで働く労働者の疲弊は著しい。彼らはベゾスにとっては顧客として認知されていない。 ________________________ 『アマゾン・ドット・コムの光と影』 2014年7月12日 以下レビュー 流通現場はシステム化されており、人手が必要な仕事も将来的に機械化される可能性がある。雇用の崩壊により労働力は更に流動的になる。潜入ルポを行った著者は、現場で労働する人達とアマゾンで本を購入する顧客層の違いに気づく。日本にも格差社会は確実に広がっている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年(本書第一部につき底本05年)刊。タイトルどおり、アマゾン・ドット・コムにおける販売対象商品の物流現場に、自らアルバイトとして勤務した体験談を叙述する第一部。さらに、その後の状況につき①ブック・オフとの関係、②アマゾンのマーケットプレイスの販売・収益の構図、③電子書籍キンドルへの識者評価を叙述する第二部とに分別。いやあ、面白いなぁ。第一部はその生々しさがいい(①時給が900→850円に下がる模様、②残業代負担法定アップ分に待ったをかける新シフト制設定とアルバイト募集、③興味を引く秘密主義)。 まともな生活設計を立て得ないアルバイトの時給や短期契約、派遣会社のピンハネ実態は。読破済みのB企業論で展開されているのと類似なので、ここでは問わない。が、レートによるが、米国アルバイト時給が1200~1600円で組合運動(内容不明だが、ストまでいかず団体交渉か)が起きたという事実は記銘すべきか。レイオフされたが…。また、マーケットプレイス(少ないながら利用歴有)の1円古本の儲けのカラクリと価格設定用のソフトの存在には吃驚した。アを地主・出店者を小作人に準えるのも秀逸。 最期に、ダンピング等も懸念される価格自由競争は寡占を招き、その結果、価格決定権を寡占企業体が掌握。メーカーは単品利幅を大きくすべく、徐々に値上げへ。かかる構図が書籍で起こっていいのか。車や家電製品と違い、多数の情報が公平に行き交い、その結果、流通情報の価値が決まるという性質を持つのが書籍。アは多数の情報を知らしめる機能を一定程度持っているが、学術書未満だが有益情報を含む書の出版ハードルを上げる結果にならないか、という?が本書から沸き起こった。杞憂かも知れないが…。
Posted by
文字通りアマゾン・ドット・コムの潜入ルポを含めて分析した一冊。 流通センターの作業はアマゾンの根幹に関わるものなので、非常に面白かった。
Posted by
「私たちが注意を払う相手は顧客であって、競争相手ではありません。競争相手をよく観察し、学ぶところは学ぶ。また、良いサービスを顧客に提供していれば、自分たちもできるだけそのサービスを採り入れようとする。でも、競争相手を意識するつもりはまったくありません。」 この本は著書が物流セン...
「私たちが注意を払う相手は顧客であって、競争相手ではありません。競争相手をよく観察し、学ぶところは学ぶ。また、良いサービスを顧客に提供していれば、自分たちもできるだけそのサービスを採り入れようとする。でも、競争相手を意識するつもりはまったくありません。」 この本は著書が物流センターにアルバイトとして潜入した体験談に基づく。最新鋭のサービスの裏にある効率を求めた業態管理。冒頭の言葉を表すのがまさにアマソンだろう。楽天などそもそも競争相手ではない。 購入した冊数ではなく、購入回数でランキングに反映されるのは知らなかった。勉強になる。アマゾンで一位という売り出し方が流行ったのを思い出す。 著者は、アマゾンの現場が本の帯を重んじない点に違和感を抱く。本当の本好きは帯も大事にするという主張だろうか。私は帯は付属品だと考えている。帯のために買っているのではない。中身にお金を払っているのだ。ある人が言っていた、本を集めるのが好きな人は紙の本を買えばいい、本を読むのが好きな人は紙の本でなくてもいい、と。紙の本、ただそれだけのために愛着など湧かない。 ベゾスの秘密主義を恐怖心に起源を求めるのは面白かった。
Posted by
巨人アマゾンを、貶めるのでもなく持ち上げるのでもなく、リアルに描いている。もはや生活に必須となったアマゾンの内部が、どうなっているか興味を持ったことなど無かった。 実に面白い。
Posted by
働く人間を交換可能な部品とみなすことは、市場主義、合理主義の一つの回答なんだろう。「欧米流の」と冠詞をつける必要もない。日本だってどこの国だって、似たようなことはやってきたし、これからもやっていくのだろうから。嫌だったら努力して抜けだせ、と言われれば反論はしにくいし、どんな仕事だ...
働く人間を交換可能な部品とみなすことは、市場主義、合理主義の一つの回答なんだろう。「欧米流の」と冠詞をつける必要もない。日本だってどこの国だって、似たようなことはやってきたし、これからもやっていくのだろうから。嫌だったら努力して抜けだせ、と言われれば反論はしにくいし、どんな仕事だって熱意と誇りをもって、と上滑りな理想論を振り回されても何も変わりはしない。 中の人がどういう働き方をしていようと客には関係ない。特にAmazonは、客にとってはキーボードとディスプレイの向こうにある便利なサービスにすぎず、顔が見えるのは宅配便のお兄さんだけなのだからなおさらだ。問い合わせやクレームのメールを送れば返事はあるけれど、テンプレートのそこここに固有名詞を埋め込んだだけ。優秀なAIと配送ロボットが完成すれば、Amazonに人間は不要だ。すべてが交換可能な部品なら、それでよい。もちろん、客は困らない。 そういう未来がぼくらは欲しいのかなあ、とAmazonでぽちっとしながらふと考える。客は一方で働き手でもある。効率の名のもとに、少なくとも若干は、楽しく働ける場を減らしていくことは本当に「ぼくら」のためになるのだろうか。
Posted by
直近に読んだ横田氏の最新刊よりは読みごたえがあった。 実際にアマゾンの集荷施設でアルバイトとして働いた上でのルポなので、そこで働く方々の人間模様を含めて説得力がある。著者が言うように、これからは(既に?)労働者が二極分化していく傾向は確かにあるのかもしれないが、日本全体を見渡...
直近に読んだ横田氏の最新刊よりは読みごたえがあった。 実際にアマゾンの集荷施設でアルバイトとして働いた上でのルポなので、そこで働く方々の人間模様を含めて説得力がある。著者が言うように、これからは(既に?)労働者が二極分化していく傾向は確かにあるのかもしれないが、日本全体を見渡せばどうなのだろうか。 それにしても、本書を読んで、アマゾンをもっと利用してみたくなった。アマゾンはこれまで何となく食わず嫌いで、本のネット注文はジュンク堂系のサイトを利用しているのだが、アマゾンに浮気してしまいそうである。
Posted by