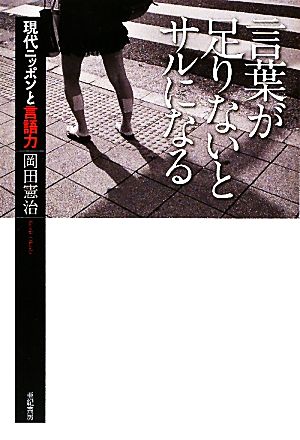言葉が足りないとサルになる の商品レビュー
ひとつの事実に対して人それぞれの真実が宿る。マスメディアによって踊らされる情報は受け手側の真実へと洗脳する。それほどメディアの力は強く、私たちが峻別するリテラシーの熟練度は学校教育にまで遡る。"真実はいつもひとつ" と豪語するコナン少年はホラ吹きの第一人者であ...
ひとつの事実に対して人それぞれの真実が宿る。マスメディアによって踊らされる情報は受け手側の真実へと洗脳する。それほどメディアの力は強く、私たちが峻別するリテラシーの熟練度は学校教育にまで遡る。"真実はいつもひとつ" と豪語するコナン少年はホラ吹きの第一人者であり、初めの関門としてここから現実を見定める鍛練を必要とする。テストに出る言葉だけを鵜呑みにするのではなく、言葉を出来うる限り漫遊することが大切であり、見誤っても良いから発声すると知らなかった世界を体感できる。自らの言葉を己の耳で聞くとわかる瞬間に出会う。そこで知ることがその人の真実なのだ。あらかじめ梱包された真実(もどき)はすぐに飽きる。それが消費社会の真実に気付く。世界はそんな小さな範疇ではないし、言葉は複雑に絡み合っている。"ウケる" "ヤバい" で終えると世界も終わる。
Posted by
10年も前の本なのか。最近の本かと思った。自分自身の言葉が足らないことを見つめ直したい。もっと豊穣な言葉で子供に語りかけないと、と反省。
Posted by
3章の「言葉が感情を形成している」とい文章には非常に強い印象を受けました。感情が先で、その中で言葉を選ぶものだと思っていました。
Posted by
サッカー選手のパフォーマンスと言葉の関係を結びつけて論じたあたり、わかりやすくて面白かったな。なるほど、と思う。言葉にするって、実生活をふりかえってもたいへんなことで、ナチュラルなままでそんなに豊富な言葉がでるわけじゃないんだよね。訓練とか知識が必要、というかね。それをただ単にイ...
サッカー選手のパフォーマンスと言葉の関係を結びつけて論じたあたり、わかりやすくて面白かったな。なるほど、と思う。言葉にするって、実生活をふりかえってもたいへんなことで、ナチュラルなままでそんなに豊富な言葉がでるわけじゃないんだよね。訓練とか知識が必要、というかね。それをただ単にインテリの繰り言とするのではなく、言葉があってこその現実生活、スポーツのパフォーマンス、芸術の達成なのだ、というつながりが、トントントン、と入ってきて面白かった。 全体的にやや冗長、というか著者の人がノリノリで書いたんだろうなぁというあたりもみられたけど、それはご愛敬だろうね。もっと読まれていい本だと思うけど、そのあたりの削り方かなぁ、なんて、偉そうだね。 いろいろ参考になった。また読み返したいね。
Posted by
なるほどと思った文章 「寂しいときは「寂しい」という言葉を使わないで歌を創る、シナリオを書く、そして小説を産み出すというのが人前で何かを見せる者たちの最低限のお約束だった」 その例として「東京だったョおっ母さん」で説明している。歌詞の中では一言も書いていないが「戦死した兄に逢いに...
なるほどと思った文章 「寂しいときは「寂しい」という言葉を使わないで歌を創る、シナリオを書く、そして小説を産み出すというのが人前で何かを見せる者たちの最低限のお約束だった」 その例として「東京だったョおっ母さん」で説明している。歌詞の中では一言も書いていないが「戦死した兄に逢いに母と二人で靖国神社に来た」ということを、「優しかった兄さん」と「九段」の「桜の下」で逢えるとい表現で示している。「ここが浅草よ。お祭りみたいに賑やかね」という部分は、田舎でひたすら重労働するだけの年老いた母にとって、賑やかな出来事とはお祭りだけであるという、母さんの切なくも慎ましい人生の様相を醸し出している。と言うのだ。 知らなかった、この歌がここまで豊かな表現で切ない気持ちを表していたとは!
Posted by
「言葉が足りないとサルになる」かどうかは分からないが、言葉を話そうして使わないと使えなくなってしまう。 普段からの言葉の使い方しかり、話し方聞き方などを改めるべきかと考えさせる本。 ゆず(歌手)を好きな人は読まないほうがいいです。笑
Posted by
題が辛辣 ワタシはサルか?! 今からよむー 「気持ちにぴったりの言葉を探して体裁を 整える」というやり方を変えて 「とにかくたくさん言葉を使ってみると 不思議とできないと思い込んでいたことが できていることに気がつく」 ふむ。
Posted by
確かに最近、言葉が粗末にされているように感じる。 それには学校教育のまずさも原因のようである。 そして、著者も言う通り、最近の日本語の歌の歌詞の酷さ。 それは私も以前から思っていたことである。 最近の歌の「そのまま」を歌った情緒ゼロの歌詞の多いこと。 薄っぺらくて仕方がない。 そ...
確かに最近、言葉が粗末にされているように感じる。 それには学校教育のまずさも原因のようである。 そして、著者も言う通り、最近の日本語の歌の歌詞の酷さ。 それは私も以前から思っていたことである。 最近の歌の「そのまま」を歌った情緒ゼロの歌詞の多いこと。 薄っぺらくて仕方がない。 それが分かる人には、言葉の重要性が分かるのだろうけれど、あのような歌詞で育った若者達は、なかなかそれには気付かないだろう。 やはり小さいころから豊かな言葉に囲まれた環境が大切なのだと思う。 言葉が気持ちを作り、 バカなしゃべりを続けるとバカになる ということを肝に銘じて、言葉と向き合っていきたいと思う。 あまり集中して読めなかったので、本書は再読したいと思う。
Posted by
言葉で丁寧に伝えることを放棄し出すと、途端に人間関係は薄っぺらいものになっていくと日々感じる。 でも、言葉を紡ぐ訓練って大人になってからなかなか身に着くもんじゃないよな〜とも思う。一生懸命こちらが言葉を紡ごうと努力した時に、それにに対して反応が薄くて言葉が返ってこないとがっかり...
言葉で丁寧に伝えることを放棄し出すと、途端に人間関係は薄っぺらいものになっていくと日々感じる。 でも、言葉を紡ぐ訓練って大人になってからなかなか身に着くもんじゃないよな〜とも思う。一生懸命こちらが言葉を紡ごうと努力した時に、それにに対して反応が薄くて言葉が返ってこないとがっかりすることも多いけど、信念を持って、言葉と、言葉が導いてくれる思考に向き合っていきたいと思った。
Posted by
ヤベェ!マジ、チョーヤバくね?などという言葉でしか世界を語らなければ、直ぐに馬鹿になる。言葉で様々な想いや状況を言葉で伝える練習をしなくては。
Posted by