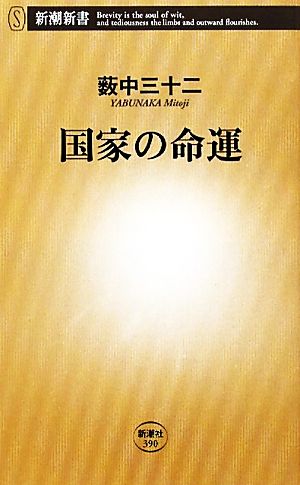国家の命運 の商品レビュー
見た目のソフトさとは真逆で、大阪出身の阪神ファンという熱き外交官・藪中氏が提唱する日本の針路。外務省時代にはアメリカとの交渉で何度も「No !」を言い続けた筆者が、最近の政治決着において常に譲歩させられている日本の外交にモノ申す。中国や北朝鮮の脅威への対峙・アジア諸国との連携やT...
見た目のソフトさとは真逆で、大阪出身の阪神ファンという熱き外交官・藪中氏が提唱する日本の針路。外務省時代にはアメリカとの交渉で何度も「No !」を言い続けた筆者が、最近の政治決着において常に譲歩させられている日本の外交にモノ申す。中国や北朝鮮の脅威への対峙・アジア諸国との連携やTPPへの積極参加など、外交のテクニックに留まらない国際的視点からの処方箋を提言する。
Posted by
六カ国協議とかでよくテレビに出てた外交官の本。そんなに重くなく面白く読めた。移民を増やそうというのは同意見。
Posted by
国際的な仕組み作りをリードする。 世界における国家の立ち位置を方向付ける。 世界情勢と国家の将来ビジョンを深く考えて自分なりの回答を持っていないとできない仕事であるが、一般の会社でも同じ事が言える。特に、受け身の姿勢ではなく仕組み作りをリードする、の部分。外交だけでなくビジネスで...
国際的な仕組み作りをリードする。 世界における国家の立ち位置を方向付ける。 世界情勢と国家の将来ビジョンを深く考えて自分なりの回答を持っていないとできない仕事であるが、一般の会社でも同じ事が言える。特に、受け身の姿勢ではなく仕組み作りをリードする、の部分。外交だけでなくビジネスでも日本人は同じ問題を抱えているなぁ、と感心。
Posted by
北朝鮮の拉致問題のニュースで拝見したのが初めてだったと思う。外交官として国益を守るために様々な修羅場をくぐってきた人の言葉には重みがある。もっと主張すべきは主張していかなくてはならない。 アフガンで農業・医療・教育で現地に深く根ざして貢献しているように、日本として何ができるのかを...
北朝鮮の拉致問題のニュースで拝見したのが初めてだったと思う。外交官として国益を守るために様々な修羅場をくぐってきた人の言葉には重みがある。もっと主張すべきは主張していかなくてはならない。 アフガンで農業・医療・教育で現地に深く根ざして貢献しているように、日本として何ができるのかをもっと胸を張って主張すべきというのは確かにその通りだと思う。われわれがもっとそういうことを理解して、日本がどのようなことができるかをきちんと言えるようにならなくてはならない。そうでないと外圧に屈し続けることにもなりかねない。
Posted by
1.この本をひと言でまとめると 外交官の仕事のエッセイ 2.お気に入りコンテンツとその理由を3から5個程度 ・外交交渉の要諦 I 敵を知り、己を知る(p95) →本番の前によく調べ尽くしておく重要さを説いている。有力議員まで調べるのがプロ意識を感じさせた。 ・1.ウ...
1.この本をひと言でまとめると 外交官の仕事のエッセイ 2.お気に入りコンテンツとその理由を3から5個程度 ・外交交渉の要諦 I 敵を知り、己を知る(p95) →本番の前によく調べ尽くしておく重要さを説いている。有力議員まで調べるのがプロ意識を感じさせた。 ・1.ウソをつかず、欺かない2.絶対に必要なことと、融通のきくことを分け、優先順位を相手に分かるように伝える3.ダメなこと、デリバー(約束できるかできないか)できないことは、はっきりと言う(p107) →ビジネスやプライベートでも使えそう。国同士の交渉でも人間関係が効いてくるのは面白い。 ・日本流の「Yes,we can」(p60) →アフガニスタンでのODAの具体的内容は初めて知った内容。アメリカに対してよく主張してくれました。 ・私論―5つの提言(p85) →危機感を強く感じている点は全く同じ意見。問題を指摘するだけでなく案を出すところがよい。 3.突っ込みどころ ・第一章「アメリカ離れ」のすすめ は、なぜ離れる必要があるのか、どうやって離れるのかがよくわからない。 ・外交官の仕事がよくわかったが「国家の命運」というタイトルは大げさ ・第五章 北朝鮮はなぜ手ごわいか 最初に過大な要求(p126)とあるが、“交渉の初期段階ではいわゆる「ダメもと」、無理は承知で、まずは目一杯の要求をすることが少なくない”(p108)と何が違うのか? ・私論―5つの提言(p85)→懸念される問題の対策も書いてほしかった。 ・東アジア共同体やTPPの話は記述が浅すぎる。 ・ところどころに自慢話が入っている。 4.自分語り ・全体的に広く浅く、エッセイ的。もう少し突っ込んだ話、交渉の核心部分を書いてほしかった。 ・度々引用されていた「日本辺境論」が気になった。 ・著者は日本のよいところを外国にアピールしたという点で、いい仕事をしたと思う。
Posted by
外国との交渉には、それぞれの専門領域のものが当たるべきではないかと考えたこともあったが、本書のような外交官の著書を見ると、やはり交渉の専門家は必要だと感じる。よく考えると、ビジネスでも営業がいるように、交渉する専門はやはり必要なのだと思う。 信頼関係を確立するツボ ?ウソをつか...
外国との交渉には、それぞれの専門領域のものが当たるべきではないかと考えたこともあったが、本書のような外交官の著書を見ると、やはり交渉の専門家は必要だと感じる。よく考えると、ビジネスでも営業がいるように、交渉する専門はやはり必要なのだと思う。 信頼関係を確立するツボ ?ウソをつかず、欺かない ?絶対必要なことと、融通の利くこととを分け、優先順位を相手に分かるように伝える ?ダメなこと、デリバーできないことは、はっきりと言う 交渉では、相手のペースにはまって、有効な反論ができないと負けなのである。
Posted by
外交官の仕事が分かる本。 途中で著者の性格が出る部分があるが、今の世の問題もうまく定義できている。若い人にこそ読んでほしい本。 下手に外交官の交渉方法は特殊な部分が多いので真似はしないでほしいかなーなんて思ったり。 ただ政治を、一票を考える上で、とてもいいと思う。
Posted by
著者の薮中三十二氏は、2008~2010年に外務事務次官を務めた外交官。大阪大学法学部3回生のときに外務省専門職として外務省に入り、入省後外務省上級職(外務キャリア)に合格した、事務次官としては異色の経歴を持つ。 本書では、1980年代後半の北米局課長としての日米経済交渉から、2...
著者の薮中三十二氏は、2008~2010年に外務事務次官を務めた外交官。大阪大学法学部3回生のときに外務省専門職として外務省に入り、入省後外務省上級職(外務キャリア)に合格した、事務次官としては異色の経歴を持つ。 本書では、1980年代後半の北米局課長としての日米経済交渉から、2000年代のアジア大洋州局長としての北朝鮮核問題の6ヶ国協議、更に経済・政治担当外務審議官、外務事務次官としての体験を振り返ったものである。但し、自ら「外交インサイダーとしての立場を利して、個々の政治家について論評したり、暴露的レポートをお届けしたりするつもりは毛頭ない」と語っているように、関わった外交関連の課題の全てがカバーされているわけではなく、回顧録というよりは、外交交渉に関する普遍的な問題・ポイントをまとめたものという印象が強い。 印象に残ったポイントとしては以下である。 ◆総じて日本人はロジックが苦手。日米経済交渉でも、対米の「ご理解いただきたい(please understand)」、対内的な「これでは日米関係がもたない」の二つのフレーズがよく出てきたが、論理性を欠いた考え・表現は役に立たない。 ◆日本ほど自国への視線と評価に関心を寄せる国民は他にいない。外からどう見られるかに神経をすり減らすくらいならば、国際社会において日本に有利なシステムをどのようにして作るかにもっと関心を向けるべき。 ◆交渉相手が英語を母国語とする場合は、通訳を使った方がいいこともある。通訳がいれば、相手の話が通訳されている間に「次の一手」を考える時間ができる。また、言い間違いや誤解を恐れて集中力が途切れるくらいなら、通訳を使う方がいいし、一向に構わない。 ◆最終局面で交渉に臨むとき、合意のモメンタムを逃さずに行動することが大事。本国に戻って最終了承を取り付ける必要があっても、交渉官同士の信頼関係ができていればまず問題はない。まとめは、勇気をもって決断すること。誰もが満足することはありえないので、大事なのはバランス感覚、これならいける、という読みである。 日本外交交渉に関わる思考は、ビジネスの現場にも通じるものとして参考になる。 (2010年10月了)
Posted by
2013.11.22 am 12:43読了。課題図書。元外交官が外交の裏側や日本の置かれた立場、実態について語る。本のタイトルからは想像できない内容。タイトルは少し格好つけ過ぎのような気がする。『タックス・ヘイヴン』と似たような雰囲気。外交に関する本は初読。外交交渉の手法について...
2013.11.22 am 12:43読了。課題図書。元外交官が外交の裏側や日本の置かれた立場、実態について語る。本のタイトルからは想像できない内容。タイトルは少し格好つけ過ぎのような気がする。『タックス・ヘイヴン』と似たような雰囲気。外交に関する本は初読。外交交渉の手法について知ることができて良かった。シェルパの存在も初めて知った。著者の考えの根拠についてはもう少し掘り下げて欲しい部分もあった。加えて、改めてメディアの影響力の大きさを感じた。背景を知り、視点を変えることで、問題は異なる姿を見せることを実感。日本のメディアはもっと多様化するべきだ。政治や外交、諸外国に関する知識が必要と痛感。類似書籍を読んで考えを深めたい。
Posted by
元外務事務次官の藪中さんの実録。 外交、という交渉事の最上級ステージをどのようにとりしきるか、については自信の経験をもとに非常に示唆にとんだ解説だった。国家を背負っている立場から、最初は高めのたまを投げる。その上で各省の実情を把握して振り幅を決めて、最終的に60vs40になるよう...
元外務事務次官の藪中さんの実録。 外交、という交渉事の最上級ステージをどのようにとりしきるか、については自信の経験をもとに非常に示唆にとんだ解説だった。国家を背負っている立場から、最初は高めのたまを投げる。その上で各省の実情を把握して振り幅を決めて、最終的に60vs40になるように交渉をすすめる。このへんのノウハウは日常にも活かせるものだろう。 それと、非常に共感したのが日本における最大の問題はデモグラフィー(人口動態)であるということ。少子高齢化、というが高齢化はよい、世界に誇って良い。少子化、がまずい。労働力人口の減少は、どんなすばらしい経済成長にも変えられない。これを止めるためには、出生率をあげるか、移民を受け入れるかしかない。薮中さんは割りと後者を推している感があったが、個人的には前者に注力すべきだと考えている。 いずれにしろ、今後の日本というマクロの視点でも、日々の交渉ごとというミクロな視点でも、とてもためになる本だった。
Posted by