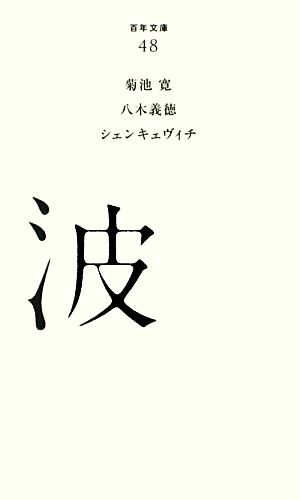波 の商品レビュー
人生における幸せとは?と考えさせる三編。中でもシェンキェヴィチ『燈台守』は荒波を超えて凪に憧れる老境を描いて心に残る。57/100
Posted by
「俊寛」 こうあってほしい。 人間の強く自然な生きる姿を見せられた思いがする。 文明とか立場とか、それ以前の純粋な生きる力。 その姿は美しい。 その心は自由だ。 いい小説だった。 「劉廣福」 なんという好人物。 大きな丈夫な体に、きれいな心を持っている。 それをちゃんと感じて理...
「俊寛」 こうあってほしい。 人間の強く自然な生きる姿を見せられた思いがする。 文明とか立場とか、それ以前の純粋な生きる力。 その姿は美しい。 その心は自由だ。 いい小説だった。 「劉廣福」 なんという好人物。 大きな丈夫な体に、きれいな心を持っている。 それをちゃんと感じて理解する人たちが、彼の周りにいる。 そして、一見、学が無い愚か者のように見えて、本当は賢い。 神様みたい。 心が洗われるお話でした。 「燈台守」 今まで自然の厳しさに打たれていた男が、安住の地を望み、とうとう手に入れた平穏。 それは人に破られたのか。 いや、やはり、望郷の念という、人として自然な感情によって乱されてしまったのだ。 あらがえないものがあるのだろう。 ・・・しかし、仕事をしてからゆっくり読めばよかったのに、とも思う。 結果として故郷へ戻りたくなって、その場を去ることになったのかもしれないけれど。 仕事や生活を忘れるほどの衝撃に襲われて、故郷の言葉や思い出に再会したのだなあ。
Posted by
名前は超有名だけど読んだことはなかった菊池寛。これを読んでみての印象はインテリエンタメ。ロケーションは平安時代の鬼界ヶ島。パッと目に浮かぶ明快なストーリーラインで読ませる。結論は予定調和。芥川龍之介なんかが近いんだろうか。
Posted by
シェンキェヴィチ の『燈台守』が、一番波のテーマにあっていて、情景が細かに描かれている。 荒波に揉まれるように、人生の手のひらから、大事なものをひとつひとつ取りこぼしてきた老人が、やっと終の棲家に出来ると思ってたどり着いた燈台。 そこから見える景色の美しさ。 突然、ふたたび波にさ...
シェンキェヴィチ の『燈台守』が、一番波のテーマにあっていて、情景が細かに描かれている。 荒波に揉まれるように、人生の手のひらから、大事なものをひとつひとつ取りこぼしてきた老人が、やっと終の棲家に出来ると思ってたどり着いた燈台。 そこから見える景色の美しさ。 突然、ふたたび波にさらわれてしまう幸せ。しかも、思いもよらない形で。
Posted by
図書室の奥深くからみつけました。「百年文庫」シリーズは、ここ100年間に世界中で書かれた短編小説を、一つのテーマに沿って本にした、いわゆる「アンソロジー(作品集)」。その中の一冊、「波」がこの本のモチーフになっている。 平家に反逆したために島流しになった惨めな僧侶は、どのよう...
図書室の奥深くからみつけました。「百年文庫」シリーズは、ここ100年間に世界中で書かれた短編小説を、一つのテーマに沿って本にした、いわゆる「アンソロジー(作品集)」。その中の一冊、「波」がこの本のモチーフになっている。 平家に反逆したために島流しになった惨めな僧侶は、どのようにして新しい人生に気付いたか。時代は飛び、満州の日本人が経営する工場にひょっこりと現れた、どもりのひどい、取るに足りないと見られた男が、いくつかの冒険を経て、工場で誰よりも信頼される工人になったいきさつ。そして最後の物語では、世界を放浪し、あらゆる運に見放された、ポーランド人の老いた兵士が、パナマ運河の灯台守の職を最後に得るが、そこに思いがけない事件が起こる・・・。 短編小説なので、意外にすぐ読める。時代を旅するタイムマシンのような本。このシリーズは傑作だー!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
百年文庫13冊目は「波」 収録は 菊地寛「俊寛」 八木義徳「劉廣福」 シェンキェヴィチ「燈台守」 菊地寛の「俊寛」が既読であとは初めて。 「俊寛」は日本版ロビンソン・クルーソーみたいな話。だいぶ昔に読んだので忘れていたが、筋のインパクトはある。たぶん初めに読んだ時も面白かったと思ったような気がする。芥川も「俊寛」というのを書いていたらしく、ふうんと思う。芥川ほとんど読んだ気がするけどなんか覚えていない。たぶん同時期に読んでいるので、同じタイトルに何か思ったと思うんだが… 最後の俊寛、ええ顔してたと思う。 「劉廣福」 劉廣福のたくましさがいい。後で知ったけどこの作品で芥川賞なんだとか。最近の芥川賞作品のひねり方からしたら、なんだか新鮮に思えるぐらい話はわかりやすい。八木義徳の他作品も調べてみて「私のソーニャ」とかも何か面白そうだったのだけど文芸文庫は品切れ状態… 残念。 「燈台守」 ポーランドの叙事詩「パン・タデウシュ」(作中では「パン・タデウシ」と表記)が引かれて「おっ」と思った。やはりポーランド人の心の支えだったのだろうかとしみじみ思う。手元の文芸文庫を読み返そう。しかしこの話、最後のはしごの外し方が「笑ゥせぇるすまん」風。最後にきらきら光っていたスカヴィンスキの眼には希望もあったと信じたい。
Posted by
運命の波に襲われた人間たちの生き方。と裏表紙の紹介にある。読みながら塞翁が馬という言葉がピッタリな物語ばかりだと感じた。『俊寛』は特に素晴らしい!
Posted by
- 1