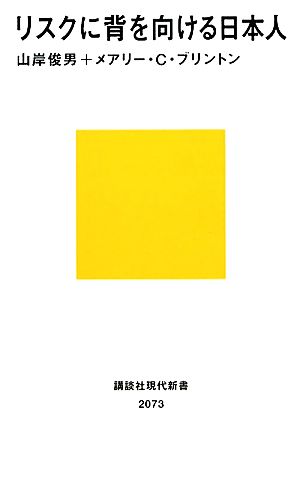リスクに背を向ける日本人 の商品レビュー
山岸先生の”安心”と”信頼”に関する研究を踏まえて、日本人(日本という社会)の「ひきこもり」状態を、リスクに背を向ける態度として、論じる対談本。対談相手はメアリー・C・ブラントン先生。 対談形式なので、大変読みやすい。章ごとに二人の論点がまとめてある点もわかりやすい。 個人的には...
山岸先生の”安心”と”信頼”に関する研究を踏まえて、日本人(日本という社会)の「ひきこもり」状態を、リスクに背を向ける態度として、論じる対談本。対談相手はメアリー・C・ブラントン先生。 対談形式なので、大変読みやすい。章ごとに二人の論点がまとめてある点もわかりやすい。 個人的には、今まさに道を踏み外そうとしている(人の道ではなく!次の就職先を決めずに会社を辞めようとしている)ので、その通りと思う点が多々あった。 会社を辞めるつもりだと、周囲の人に徐々にリークし始めているのだが、その中で言われるのが「だんなさんに養ってもらうんだね」というコメント。意外に多くてびっくりする。今の会社は、男女や年齢の差別がなく、知力と体力さえあればいくらでも成り上がることができる組織風土であるが、個人として付き合うと、まだまだ「転職先を決めずに会社を辞める」=「パートナーに養ってもらう」ことだと理解されるのだなあと、改めてびっくりする。 私としては、パートナーに養ってもらうことはあまり考えておらず、今あるたくわえを戦略的に使って、今後のキャリアの選択肢を拡張していくつもりなのだが、リスクを取って会社を辞めてフリーの立場になるという選択は、まだまだ今の会社のような比較的ラディカルな社会においてさえ少数派な様子。 これは、日本人の意識ということだけではなく、本書で触れられているように、道を外れた人に対してセカンド・チャンス、サード・チャンスを提供することを前提としていない社会制度が影響していることの表れといえる。 本書でも説かれているように、グローバリズムがすべてではないし、マーケットにすべてをゆだねることが、社会問題の解決につながるとは思わない。しかし、グローバル化にさらされている現状を考えなければ、何も手を打たずに負け続けるのは、日本人としてあまりにも悔しい。 山岸先生は、本書の最後を、「王様は裸だ!」と叫び続けることが重要だと締めくくっている。自分の人生やキャリアに悪影響を及ぼしているにもかかわらず、会社を辞めたら生きていけないと思い込んで会社にしがみつく(=リスクに背を向ける)必要はない、ということを、個人のレベルからアピールすること。それが今、自分が会社を辞めるにあたって、周囲の仲間に、「王様は裸だ!」と叫ぶことだと信じている。
Posted by
日本の安心を作っていると思われていた終身雇用が、リスクを高めているという部分に納得させられた。 人材の流動性の高さはセカンドチャンスを作り出す。逆に言えばセカンドチャンスがあれば無理にとどまる必要がなくなり、流動性がうまれる。 これからの社会を作る世代としてはこの基本構造を頭...
日本の安心を作っていると思われていた終身雇用が、リスクを高めているという部分に納得させられた。 人材の流動性の高さはセカンドチャンスを作り出す。逆に言えばセカンドチャンスがあれば無理にとどまる必要がなくなり、流動性がうまれる。 これからの社会を作る世代としてはこの基本構造を頭に入れて自分と社会を考えていきたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「安心社会から信頼社会への転換」という山岸氏の著書の一貫したテーマは本書においても随所に見られるが、その中でも「若者にとって現在の日本社会はリスクが大きすぎる」という主張がとても説得力のあるものとして展開されている。 また、ステレオタイプなアメリカ人と日本人のリスク観の違いを否定しており、そうした違いが生じる社会背景に目を向けている点で、従来の日本人論とは一線を隔しているように感じられる。 本書ではメアリー氏との対談という形式をとっているが、対談にありがちな安易な妥協はお互いにしておらず、結論において両者の主張の違いが鮮明になったことは興味深かった。
Posted by
山岸さんは、北海道大学の先生で社会心理学、メアリーさんは、ハーバード大学の社会学の先生。 山岸さんの本は、合意形成手法の観点から社会心理学の本を読んでいて、その参考文献か何かでこの本を購入。 全体を通してもっともな話が多いが、対談で、話があっちゃこちゃいっていて、繰り返し...
山岸さんは、北海道大学の先生で社会心理学、メアリーさんは、ハーバード大学の社会学の先生。 山岸さんの本は、合意形成手法の観点から社会心理学の本を読んでいて、その参考文献か何かでこの本を購入。 全体を通してもっともな話が多いが、対談で、話があっちゃこちゃいっていて、繰り返しの話も多い。 おもしろいと思った視点 ①山岸:高齢化の問題は、高齢者が働き続けると経済効率がおちるが、高齢者の能力を活かすことができる方向へ産業のあり方を変えていくべき。(p179) 当然、定年制も批判しているのだが、今の組織の体制だと、十分能力とやる気があるのに、後輩に押し出されてしまう、それがないと後輩もやっていけないので、定年制については、微妙な意見となる。 さしあたり、定年制をかえられないのであれば、自分の能力で定年後も働けるよう、能力をみがくしかない。 ②山岸:社会科学というのは、人々が自分たち自身で自分をしばりつけている状態から助けをする学問。(p67) ③山岸:日本が政策としてやらなければならないのは、労働市場を整備すること。これまでは、クビを切らない、切らせないという方向に進んできた。(p220) 全員、非正規雇用でもいい、その代わりセーフティネットをきちんと整備するというのが山岸さんの主張。 そのとおりだと思うが、経済学者以外でこういうことを言う先生はめずらしい。 全く、復興に関係のない本になったが、それなりにおもしろかった。 参考文献としては、ジェイ・ジェイコブス『市場の倫理 統治の倫理』(日経ビジネス人文庫)、メアリー・c・ブリントン『失われた場を探して』(NTT出版)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
対談形式になっているので、ざっくりとした議論ばかりで、対談者同士の思想や背景が曖昧なままになっています。 例えば、山岸俊男ならば、専門の社会心理学の実験結果や自著による研究結果を対談で述べていますが、何故そういう結論に至ったのかが不明瞭です。ただの思いつきで言っているのか、それとも確たるものや論拠があって言っているのか、その境界が曖昧な箇所があります。 対談形式にすることで読者に分かりやすく伝わると思う、と冒頭で述べていますが、論拠が曖昧だと鵜呑みにはできませんし、それは世間話レベルを免れませんので、信憑性に欠けると感じます。まぁ一長一短ですね。 再チャレンジのある社会作りを目指す、これが本書の要点です。 聞こえは良いですが、果たしてどうなんでしょうか? いまの日本社会の閉塞感の現況は、本書にもあるように「再チャレンジができない(或いは本書に即して言えばリスクを取れない)社会構造に問題がある」のですが、ではこの社会構造が改革されたとして、その先にあるのは何でしょうか?快楽主義でしょうか。 本田由紀氏も指摘する通り、日本は職業訓練をする教育機関が脆弱で、それが故に終身雇用が機能してきた。本書の主張と合致する部分が多く、なるほどと唸らせられますが、要は「様々な経験を積んで、自分の好きなもの、安寧ででる場所に落ち着いたらいい」。 それについては僕自身も思うところで、例えば「家庭に居場所がない」とか、「職場では肩身の狭い思いをしている」とか、「今ニート状態で世間に顔向けできない」とか、それぞれに窮屈な思いをしている人がいる現状で、それならば多少ヘンな世界でも、自分自身が安寧できる居心地のよい世界へ行けばいい。我慢からの解放です。 「石の上にも三年」という諺の本来の意味は、「冷たい石の上でも三年も座りつづけていれば暖まってくる。我慢強く辛抱すれば必ず成功することのたとえ」ですが、これを上記のような考えに基づくと、この諺の意義が変わる危惧はあります。 どんどん世界に飛び込んで、たくさんの経験を積んで、最終的には自分の居心地の良い場所に落ち着く。逆に言えば、「居心地の良い場所を見つけるために努力する」となり、経験を積まなかった人、あるいは経験を生かせなかった人は、ドロップアウト人生に陥るという危険性はあります。それが怖いんです。変革を求める人にとっては、チャンスはあればあるほど有利ですが、安定を求める人にとっては、この上ない脅威の世界でしょうね(笑) ともあれ、社会通念や常識、制度や法整備が未だ統一されないままにあるのが日本社会の現状。だから社会がぐちゃぐちゃになる。 所々に違和感を覚える箇所がありました。 例えば離婚問題。「嫌々で結婚生活を続けるよりも、スパっと離婚した方がいい」という件は、あまりにも短絡的で学者とは思えません。それこそ倫理の問題もありましょう。 また、定年制の問題等については、経済と絡んでくるので、簡単に定年を引き上げるのが良いとは断言できません。 まして、若者の職が少ないのに、それを熟練した(あるいは経験豊富な)定年間近な人材を再雇用するとなると、ますます世代間格差が広がるのは明白です。高齢者は所得プラス年金、一方で、若者は所得すら危うい状態。 若年者の職と高齢者の職のトレードオフの関係を、うまくマネーサプライに関係付けて議論すべきだと思います。 拙速な議論もありますが、総合評価としてはA+にします。
Posted by
色々な話題が盛り込まれていて少々論点がぼやけてしまっているが、1)再チャレンジできる社会でないことが日本人にリスクをとることをためらわせている、2)集団での相補依存関係の中で社会のあり方というものは規定される、ということを主軸に論を展開している。特に、雇用のあり方を考えるうえで、...
色々な話題が盛り込まれていて少々論点がぼやけてしまっているが、1)再チャレンジできる社会でないことが日本人にリスクをとることをためらわせている、2)集団での相補依存関係の中で社会のあり方というものは規定される、ということを主軸に論を展開している。特に、雇用のあり方を考えるうえで、面白い視点が得られた。
Posted by
暫くの間、外資系企業に腰掛けていた。沈没した黒船からかろうじて下船して日本に戻ってみると、集団主義、横並び、同調圧力に支配される村社会を強く意識するようになり、息苦しくなった。本書は、そんな私のモヤモヤ感を社会学的な視点で2人の学者が見事に解説してくれた。 「セカンドチャンスの...
暫くの間、外資系企業に腰掛けていた。沈没した黒船からかろうじて下船して日本に戻ってみると、集団主義、横並び、同調圧力に支配される村社会を強く意識するようになり、息苦しくなった。本書は、そんな私のモヤモヤ感を社会学的な視点で2人の学者が見事に解説してくれた。 「セカンドチャンスのない社会の方が却ってリスクが大きい。」 終身雇用と年功序列によって雇用を守る制度は、一度大企業正社員という身分を手放すとやり直しのきかない労働市場であり、社会の閉塞感と将来不安を招き、経済停滞に繋がる。 私は「At Your Own Risk」の社会の方が泳ぎやすい。 何も行動を起こさないで、大企業にしがみついて不平不満ばかり漏らして不安を抱えている転職未経験者の人達と、常に解雇や倒産リスクがつきまといながらもそれに屈せず挑戦する人生を歩んでいる外資系やベンチャー企業の人達とでは、後者の人達の方が、人間的に魅力的な人が多い。あくまでも私の個人的経験だけど、概ねそういう傾向。 ただ、一方で、震災以降、日本人の底力というのは、集団主義であるということも感じるようになった。
Posted by
自分が、普段感じてる事を明快に語ってくれているような部分が少なからず有り、有意義に読み終えた。 311以後、何年も漠然と感じて来た不安が、それなりに真っ当であったのか?とか思わざるを得ない日々であるが、このような著作が、数十万~100万の規模で売れるようになって欲しいものです。...
自分が、普段感じてる事を明快に語ってくれているような部分が少なからず有り、有意義に読み終えた。 311以後、何年も漠然と感じて来た不安が、それなりに真っ当であったのか?とか思わざるを得ない日々であるが、このような著作が、数十万~100万の規模で売れるようになって欲しいものです。結局、タイトルは、不安にさせるような状況や将来に対する不安の種から目を逸らしてきている人々へ向けれらているように思う。 身の回り、実際の生活の事だけを考えて生きていけば、どのような状況が待ち受けているのか?そうしたいのは当然だけど、状況は、それを許さない。
Posted by
セカンドチャンスの無い状況の中、「空気を読み、周りに嫌われない」生き方に徹することは、社会に適応するための自然な成り行き。まるでカメレオン。the pillowsではないけれど、出来損ないでも不器用でもいいから、自分の色をしっかり持った「ストレンジカメレオン」で居たい。
Posted by