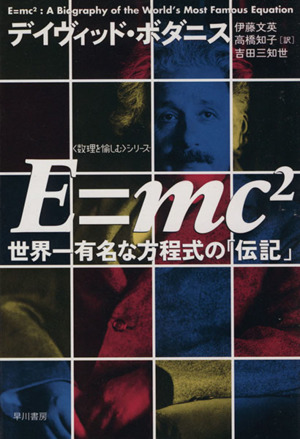E=mc2 の商品レビュー
タイトルに「伝記」とあるように、E=mc2をアインシュタインをはじめとした、歴史的に関わった人や出来事を軸に紹介している。本書はアインシュタインのみでなく、式を構成するE, =, m, c, 2の各要素にまつわる人や歴史も紹介しているところが面白い。 その発見から実用化、そして宇...
タイトルに「伝記」とあるように、E=mc2をアインシュタインをはじめとした、歴史的に関わった人や出来事を軸に紹介している。本書はアインシュタインのみでなく、式を構成するE, =, m, c, 2の各要素にまつわる人や歴史も紹介しているところが面白い。 その発見から実用化、そして宇宙へと話は発展していき、どのようにE=mc2が関係しているかを分かりやすく説明している。原子爆弾が作用する過程の段階的な描写は、どれほどのエネルギーがいかに短時間で作用したかが分かり、とても興味深い。
Posted by
小さい頃に相対性理論の本を読んで、よくわからなかった人におすすめの本。 人間の想像力が宇宙を包み込む、という気さえした一冊。 E=mc2が今の世界の常識の一端を担っていることがわかる また、E=mc2の電気と磁気、放射線、原爆開発、太陽、ブラックホールへのつながりを示す。 ...
小さい頃に相対性理論の本を読んで、よくわからなかった人におすすめの本。 人間の想像力が宇宙を包み込む、という気さえした一冊。 E=mc2が今の世界の常識の一端を担っていることがわかる また、E=mc2の電気と磁気、放射線、原爆開発、太陽、ブラックホールへのつながりを示す。 読むのは時間がかかる。
Posted by
はじめに 第1部 誕生 1 1905年、ベルン特許局 第2部 E=mc2の先祖 2 エネルギーのE 3 = (イコール) 4 質量(mass)のm 5 速度(celeritas)のc 6 2(2乗) 第3部 若かりし頃 7 アインシュタインとE=mc2 8 原子の内部へ 9 真昼...
はじめに 第1部 誕生 1 1905年、ベルン特許局 第2部 E=mc2の先祖 2 エネルギーのE 3 = (イコール) 4 質量(mass)のm 5 速度(celeritas)のc 6 2(2乗) 第3部 若かりし頃 7 アインシュタインとE=mc2 8 原子の内部へ 9 真昼の雪の中、ひっそりと 第4部 成熟期 10 先手、ドイツ 11 ノルウェー 12 後手、アメリカ 13 午前8時16分 広島上空 第5部 時間が果てるまで 14 太陽の炎 15 地球をつくる 16 インドのバラモンが天空に目を向ける エピローグ アインシュタインのほかの業績 付録 他の重要人物のその後 謝辞 解説 アインシュタインがみんな悪い/池内了 文献案内 注 20110331 E=MC2の伝記 光は物質的な「もの」である。いかなる時も磁気が生み出す電気と、電気が生み出す磁気とが馬跳びをするように進み、追いつこうとするものをあっという間に置き去りにしてしまう。それゆえ、光速が万物の速度の上限となり得るのだ。 最終的に、注ぎ込まれたエネルギーは凝縮されて、等価の質量に変化する.端からは、シャトル全体の質量が増大しているように見える。最初はわずかしか増えないが、エネルギーを注ぎ込みつづければ、質量も増え続ける。
Posted by
・読んだ理由 三体を読み、物理に興味を持ったから。 ・感想 前半がe=mc2の生まれた経緯、後半はその方程式がどのように利用されたかが書かれている。 前半の内容目的で読んだため、後半は途中で読むのをやめた。 相対性理論について、ふわっとした理解しかしていなかったが、この本を読ん...
・読んだ理由 三体を読み、物理に興味を持ったから。 ・感想 前半がe=mc2の生まれた経緯、後半はその方程式がどのように利用されたかが書かれている。 前半の内容目的で読んだため、後半は途中で読むのをやめた。 相対性理論について、ふわっとした理解しかしていなかったが、この本を読んでもあまり変わることはなかった。 光速度が一定であるために、色々変なことが起こるんだなぁといった感じ。 表題の式については、 光速に近い物体にさらに加速度を与えても、速度は光速に達することなく、加えられたエネルギー分の質量が増えていく。 = エネルギーと質量は光速というパラメータで関連する。 といったようなふわふわした解説だったように僕は感じた。
Posted by
この方程式について徹底的に紹介されていた。 構成する文字ひとつひとつの意味を紹介し、方程式の誕生から現在まで、そして宇宙の終焉まで方程式が生き続けている。
Posted by
斎藤孝氏が、「知識を深める本」として紹介されていたので、手にとってみた。 全く精通していない分野に興味を持てないことは、恥だと思った。 学生の頃、歴史は嫌いだったし、古文に至っては現代語訳でいいじゃんと思っていた。試験では暗記さえしとけばいいし、将来的には、ググればいいから短期記...
斎藤孝氏が、「知識を深める本」として紹介されていたので、手にとってみた。 全く精通していない分野に興味を持てないことは、恥だと思った。 学生の頃、歴史は嫌いだったし、古文に至っては現代語訳でいいじゃんと思っていた。試験では暗記さえしとけばいいし、将来的には、ググればいいから短期記憶狙いで一晩で暗記していた。 今となっては、もったいないことをしていたとしか思えない。 先人達の歴史があって今の私たちが存在するから、歴史を知ることは面白いと思う。古文は原文から様々な取り方ができるから面白い。ググればいい、ではなく知識として身に付けるからこそ、新しい知識を知った時に、複合的な考え方ができる。 学校では、勉強を好きになることも大事な営みだと感じました。 【気付き】 1.E=mc^2は、エネルギーと質量が等価であることを意味する。原子力爆弾は、この理論を活用している。 2.人類がいったん手にした知識は手放すことができない。アインシュタインは原爆開発を目的としていたわけではなく、死ぬまで後悔した。 3.全く精通していない分野に興味を持てないことは、恥だと思った。精通していない分野にこそ新しい学びがある。 【今後改めたいこと】 1.日常で気になったことをメモしておき、本で知識を身につける。例えば、電子レンジはどのような原理で温めているのか、花粉症はワクチンがないのか、など。 2.仕事で作ったモノが悪用されないか、という視点から考えてみること。 3.楽しみ方を考えながら勉強する。
Posted by
アインシュタインの偉大な発見・発明である相対性理論の根幹となる方程式 E=mc2の背景とその後の展開を人物紹介を中心に詳しく、書いている。科学史の解説書という位置付けで読み進めても面白い。
Posted by
物理学の重要な転機がとても分かりやすく書かれている。 単純な式の説明本ではなく、この式に至る歴史、発表後数十年の、現実に使われた歴史についても、とても細かく分かりやすく記載されているノンフィクション。 この式を中心に、様々な物理学の知識、歴史について学べる良本。
Posted by
面白かった。自分が何を知りたいのか長年良く分からなかったが、この本をきっかけに少しだけ自分が探るべき分野に近づいたような気がする。
Posted by
文系の自分だが、理論の深いところはわからないけれども概略は理解できた。興味深い本、この後宇宙関連や原爆関連の本を読む基礎となると思う。 E=mc2を伝記的に書くには長々しいところや、後半の理論の実証実用を照らしたところは駆け足すぎるように思われる。 この本を手掛かりに出てきた人物...
文系の自分だが、理論の深いところはわからないけれども概略は理解できた。興味深い本、この後宇宙関連や原爆関連の本を読む基礎となると思う。 E=mc2を伝記的に書くには長々しいところや、後半の理論の実証実用を照らしたところは駆け足すぎるように思われる。 この本を手掛かりに出てきた人物の伝記を読みのも面白いだろう。
Posted by