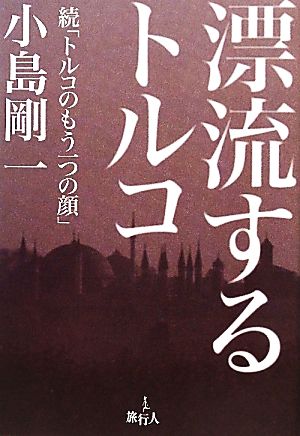漂流するトルコ の商品レビュー
前書を読んで感銘を受けていたので、本書が発行されてすぐに購入していましたが、やっと読む時間ができました。ということで前書(トルコのもう一つの顔、中公新書)を読んだ立場からの書評となりますが、まだ前書を読まれていない場合は、そちらから読まれることをおすすめします。 ただ前書を読ま...
前書を読んで感銘を受けていたので、本書が発行されてすぐに購入していましたが、やっと読む時間ができました。ということで前書(トルコのもう一つの顔、中公新書)を読んだ立場からの書評となりますが、まだ前書を読まれていない場合は、そちらから読まれることをおすすめします。 ただ前書を読まれた方の大半は感銘を受けて本書も購入されていると思うので、そもそも書評などいらないのでは?という気もしますが純粋な感想文および小島氏に敬意を表して記載します。 前書と同様、本書の大きなテーマはトルコで少数民族が話す言語についてです。言語学者としての小島氏はフランスに拠点を置きつつも、現地調査を通じてこれらの言語を研究しますが、前書と同様に小島氏は各所でトルコ政府の妨害、嫌がらせ、そして一部友情関係?も生まれます。また現地調査では、すでに有名人となっている小島氏を歓迎する(そして再会する!)現地少数民族の人々との交流が描かれるなど、涙あり笑いあり怒りありのまさに「喜怒哀楽」が全面にこもっている本です。そして著者のフラストレーションが全面的に伝わってくるのが、トルコの新聞、マスコミ、政府とのやりとりでしょう。小島氏が書いていないこと、意図とは全然違うことを記事にして、自分たちの都合の良い方向に持って行こうとするシーンが多数あり、著者の憤りが十分に伝わってきます。そういう背景を知ってしまうと、本書は小島氏の真の意図が記載されている貴重なマスコミュニケーション手段だという側面もあります。 もちろん著者は純粋な言語学者ではありますが、そこかしこに少数民族に対する判官贔屓的な記述も多く、やはりそこは人間、完全な中立にはなれないよな、とは思いつつ、またそこが著者の人間くささを感じ、暖かみを感じさせる点でもあります。 またさすがに言語学者が書いた本だけあって、注釈がやたらと出てきますが、内容的には下手な小説家が書くヒューマンタッチ小説よりもおもしろいです。ただ全般的には著者のフラストレーションがかなり伝わってくる本でもあるので、そこはあまり感情移入しすぎないことをおすすめいたします。
Posted by
フランス在住でトルコ少数民族の言語を研究している言語学者小島剛一先生の本、第二段。 今回もトルコ国内での少数民族の弾圧がひしひしと伝わってくる。民衆は権力者にはなかなか逆らえないし、逆らう場合は死を含めて色々な覚悟を持たなければならないことがわかる。 インターネットやスマホが普及...
フランス在住でトルコ少数民族の言語を研究している言語学者小島剛一先生の本、第二段。 今回もトルコ国内での少数民族の弾圧がひしひしと伝わってくる。民衆は権力者にはなかなか逆らえないし、逆らう場合は死を含めて色々な覚悟を持たなければならないことがわかる。 インターネットやスマホが普及した現在ではどうなっているんだろう。今度は現在のトルコがわかる本を読んでみよう。 インターネットは誰でも書けるから石石石石玉石石石石混淆という表現は笑えた。
Posted by
【「今朝までは,誰にもこの話をするわけにはいかなかったんだよ,お上に告げ口されるのが怖くってね」と言った途端,涙は見る間に大粒になり,隠そうとした指の間からぽたぽた滴り落ちた。それは,幼な子が大人からの侮辱と体罰に耐えて何十年も人目を忍び,声を殺して流し続けた涙だったのだ】(文中...
【「今朝までは,誰にもこの話をするわけにはいかなかったんだよ,お上に告げ口されるのが怖くってね」と言った途端,涙は見る間に大粒になり,隠そうとした指の間からぽたぽた滴り落ちた。それは,幼な子が大人からの侮辱と体罰に耐えて何十年も人目を忍び,声を殺して流し続けた涙だったのだ】(文中より引用) トルコ共和国内の諸言語の研究にのめり込み,ついには国外退去処分を喰らった経緯を記した『トルコのもう一つの顔』。同著で中東関係者にとどまらない幅広い読者を獲得した小島剛一によるトルコ再訪,そして再度の追放処分までを綴った作品です。 読み方は人それぞれ異なると思うのですが,まるでハードボイルド・スパイ小説を読んでいるような感覚を覚えるのは自分だけではないはず(もちろん小島氏はスパイでもなんでもないのですが......)。また,その時々のトルコにとっての「踏み越えてはいけない一線」が感じ取れるのも本書の魅力の一つです。 今のトルコを小島氏はどう見るだろうか☆5つ
Posted by
前作の「トルコのもう一つの顔」の後の小島さんの体験がもとになっています。前作の出版までのいきさつや,再度トルコを訪問しての言語調査での出来事など,実際に体験した人にしか書くことのできない記述を興味深く読みました。 前作の感想にも書きましたが,この作品で触れられているような状態...
前作の「トルコのもう一つの顔」の後の小島さんの体験がもとになっています。前作の出版までのいきさつや,再度トルコを訪問しての言語調査での出来事など,実際に体験した人にしか書くことのできない記述を興味深く読みました。 前作の感想にも書きましたが,この作品で触れられているような状態であった地域がますます混迷の度を深めているということについては,いろいろと考えさせられます。やはりこの地域について,いろいろ知りたいと思うものの,難しいなという印象も同時に持ちました。
Posted by
先の「トルコもう一つの顔」の続編的な本。 「トルコもう一つの顔」から約20年、その間にトルコを取り巻く国際状況も変わり、EU加盟をもくろむトルコも一応少数民族語の使用緩和を行っているが、20年前とさほど変わらないトルコ政府の”闇”を描いている。
Posted by
前著ほど陰鬱ではないが、それでもトルコという「国家」が嫌いになり、根を持つ「庶民」が好きになる本。それにしても言語というのはなんと政治的で、だからこそ個々人の根源、アイデンティティに関わるものなのか。もっと国家と言語に自覚的にならなくては。
Posted by
政府に弾圧され続けるトルコの少数民族の言語と、その生活の実態を、スパイと疑われながら、調査し続けた著者。前著『トルコのもう一つの顔』(中公新書)が、まるで推理小説のようなスリルに満ちた物語と、著者の少数民族に対する愛情に涙が出たと絶賛され、長らく続編が待望されながら20年。前著で...
政府に弾圧され続けるトルコの少数民族の言語と、その生活の実態を、スパイと疑われながら、調査し続けた著者。前著『トルコのもう一つの顔』(中公新書)が、まるで推理小説のようなスリルに満ちた物語と、著者の少数民族に対する愛情に涙が出たと絶賛され、長らく続編が待望されながら20年。前著でトルコを国外追放されたあと、再びトルコへの入国を果たし、波瀾万丈のトルコ旅行が開始される。著者の並外れた行動力と、深い知識、鋭い洞察力が生み出した画期的トルコ紀行。 日本にいると全然ピンとこないトルコの内側の話。前著『トルコのもう一つの顔』でも思ったことだが、トルコってこんなにも色んな民族および言語があり、政治と密接につながっているのかと。。 読んでいて驚きが絶えない。確かめることは出来ないが、書いてあることが全部が全部真実だとしたら、事実は小説より奇なりだなと。そんな内容だった。
Posted by
「トルコのもう一つの顔」の衝撃から小島剛一さんが帰ってきた。トルコにあって少数民族の存在は非常に不自然な方法で不可視化されていて、それを政治的でなく言語学の純粋な対象としてすくいあげた世界的な人物、本当の信念の人というのはこういう方なのだと思う。今回はページ数も多く、旅行人社から...
「トルコのもう一つの顔」の衝撃から小島剛一さんが帰ってきた。トルコにあって少数民族の存在は非常に不自然な方法で不可視化されていて、それを政治的でなく言語学の純粋な対象としてすくいあげた世界的な人物、本当の信念の人というのはこういう方なのだと思う。今回はページ数も多く、旅行人社からの出版なので出会った腑抜けどもに執拗な訂正と言葉の鉄槌を下す姿勢は心中察するものはあるが激烈でちょっと食傷気味だが‥。兎に角こういった本がまた世にでることができたことに関係各位に感謝したい。
Posted by
興味深い内容でした。観光資源が多くある国ですが、国家としては最低。某隣国を彷彿とさせます。もっとこの事実が公になればいいですが、日本人にとってトルコという国は遠すぎる。
Posted by
偶然なのだろうけれど東部出身者と親しくなる事が多かった。 まあ進学で都会に出てきてそのまま就職できて同じく進学する為にやってきた弟妹いとこ親戚有象無象の面倒を見られるくらい成功した人もしくはその親戚、なのでクルド系の大統領(けれど彼が生きている間に一度もそのことが公的な場所で語...
偶然なのだろうけれど東部出身者と親しくなる事が多かった。 まあ進学で都会に出てきてそのまま就職できて同じく進学する為にやってきた弟妹いとこ親戚有象無象の面倒を見られるくらい成功した人もしくはその親戚、なのでクルド系の大統領(けれど彼が生きている間に一度もそのことが公的な場所で語られる事はなかった)だっている事を励みに努力できた、努力の報われた人たちなのだけれどそうではない人も沢山いる。 この本にも出てきたトルコ民族主義を掲げ、クルド人やラズ人、アレヴィー派の人々の排斥を求める極右民族主義者行動党(MHP)の選挙カーが町中を走り回っていた時、私はたまたま親戚を頼ってユーゴスラビアから亡命してきたおっちゃんがやっているサッカーグッズの店で友達へのお土産にベオグラードレッドスターズのマフラーを買っていました。 「あいつらみたいな狂った連中のせいでユーゴに住めなくなったんだ、トルコは好きだけれどあいつらは大嫌いだ」と話すおじさんのめがねの奥にある美しい緑色の目を今でも覚えています。 ”あいつら”のせいで”ゴーイチ”に会えない東部の人々がいつか小島先生をおうちに招けますように。
Posted by
- 1
- 2