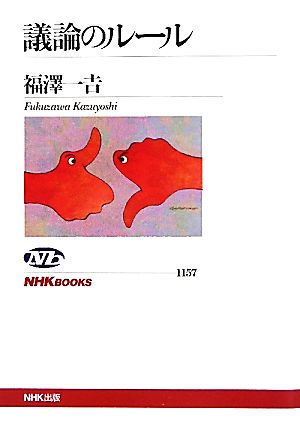議論のルール の商品レビュー
お笑いになればいい 政治家が議論をあえてずらしている のを論ってここがズレてるここがおかしい と言われても議論の参考にはならない
Posted by
国会議員の議論と爆笑問題の番組中での議論を批評しているが、題材が悪いし、指摘も的を射ていない。提示しているルール自体は納得出来るものなのに、惜しいことである。
Posted by
【由来】 ・斎藤孝 頭が良くなる議論の技術で。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
Posted by
再読。初読のときは、「言っていることはその通りなんだけど、口頭での議論について、あとからああすべきこうすべきと注文するのは、なんか後出しじゃんけんっぽくてずるくない?そりゃあ、あとから冷静に振り返るならばいくらでもあら捜しはできるだろうよ」という、いささか批判的な読後感を抱いたの...
再読。初読のときは、「言っていることはその通りなんだけど、口頭での議論について、あとからああすべきこうすべきと注文するのは、なんか後出しじゃんけんっぽくてずるくない?そりゃあ、あとから冷静に振り返るならばいくらでもあら捜しはできるだろうよ」という、いささか批判的な読後感を抱いたのだが、再読するとまったく印象が変わった。 決して後出しじゃんけん的なつっこみを入れてるんじゃなくて、対面での議論の時にはまりがちな陥穽の具体例を豊富に入れてくれている、と読むべきなんだよね。 そう見るととても納得するところが多く、非常に勉強になる。
Posted by
Posted by
とりあえず、論証と議論の対立軸をはっきりすることを意識しようと考えた。 しかし、質問の際に論証型にならないようにする、ということは難しいのではないのか…?
Posted by
なるほどと思う箇所がいくつかあるし、わかりやすかった。書くようにしゃべるね。なるほど。ただ、筆者の生産的に議論ができなければいけないみたいなかんじはなんだかなと思った。まあ、そういう本だから仕方がないのだけれども。
Posted by
「議論のレッスン」によって、議論についてや論理的に考えることの必要性をたくさん出版している福沢氏の本。 今回は、爆笑問題のテレビでのプロトコル分析、鳩山-小泉の国会での質疑応答、前原-麻生の国会での答弁のプロトコルによって、議論が成立していない面を指摘すると共に、議論のルールを...
「議論のレッスン」によって、議論についてや論理的に考えることの必要性をたくさん出版している福沢氏の本。 今回は、爆笑問題のテレビでのプロトコル分析、鳩山-小泉の国会での質疑応答、前原-麻生の国会での答弁のプロトコルによって、議論が成立していない面を指摘すると共に、議論のルールを20あげている。 議論などを行うには、言語技術教育が必要であるが、日本ではこのような教育がなされていないことが問題である。言語教育の必要性は、近年多くの場所で叫ばれているが、それをどのように体系化、カリキュラムにするかが今後の課題になると思う。 amazonからの引用で 〔 1〕 1つの文で1つの考えを表現する(ルール 9) 〔 2〕 述語を完結させる(ルール15) 〔 3〕 文と文との接続関係を意識する(ルール10) 〔 4〕〔議事録をとるために〕書くように話す(ルール11) 〔 5〕 自分の質問は実態調査タイプか,仮説検証タイプかを知る(ルール20) 〔 6〕 質問と主張とを同時にしない(ルール12) 〔 7〕 相手が自分の質問に答えているかを確認する(ルール 2) 〔 8〕 自分の質問への答えを自分でしっかりと評価する(ルール19) 〔 9〕 主張と根拠とをペアにする(ルール 1) 〔10〕 議論において1度に提示する主張は1つに限る(ルール 7) 〔11〕 まず相手の発言に触れ,次にその発言について返答する(ルール13) 〔12〕 自分の意見と相手の意見の関係を明示する(ルール 3) 〔13〕 議論の対立軸を見極める(ルール 6) 〔14〕 議論の鳥瞰図をつかみ,局所反応をしない(ルール 5) 〔15〕 議論の論点を絞り込む(ルール14) 〔16〕 人によって使われ方が異なっている言葉は内容を事前にチェックする(ルール16) 〔17〕 議論に関係ないことは言わない(ルール 8) 〔18〕 論点のシフトに注意する(ルール 4) 〔19〕 話が論理的にリンクするところに注目する(ルール17) 〔20〕 論理性が欠如した〔リンクが切れた〕話し合いを補修する(ルール18)
Posted by
シッカリした根拠と、質問(聞きたい事)を持つ。当たり前だが、討論している間に、異なる議論&話題に擦り変わる事がある。また、この本から理解できた。 質疑応答と言う、基本的な内容が出来ているかを、自分自身で問う必要がある。
Posted by
- 1