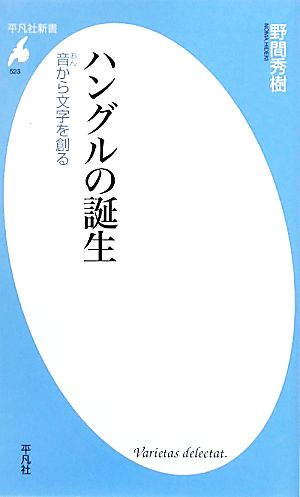ハングルの誕生 の商品レビュー
15世紀の中頃に世宗によって創始されたハングルが、音を文字に表わすという試みをどのように実現したのかということを、言語学的および歴史的観点から論じている本です。 もうすこし気楽に読むことのできる内容だと思っていたのですが、「あとがき」には「ハングルについて言語学的な視座、〈知〉...
15世紀の中頃に世宗によって創始されたハングルが、音を文字に表わすという試みをどのように実現したのかということを、言語学的および歴史的観点から論じている本です。 もうすこし気楽に読むことのできる内容だと思っていたのですが、「あとがき」には「ハングルについて言語学的な視座、〈知〉という視座から述べた書は、少なくとも新書ではなかった」と著者が語っており、その穴を埋めることを意図して書かれています。そのため、ことばづかいにやや衒学的なところが見られますが、ハングルの画期的な意義を新書を通じて幅広い読者に伝えようとする著者の熱意が伝わってくるような語り口で、韓国語についてほとんど知らないわたくしにも、おもしろく読むことができました。
Posted by
世宗が作らせた「訓民正音」。朝鮮民族に独自の文字を持たせた画期的な書物。漢字の草書体や画の一部から作られた日本のかなやカタカナと違い、一から音声学的にも適合した文字として作られた文字、ハングルの誕生と各種の角度からの解説。
Posted by
大学生の時に読んで、韓国語に興味を持ったキッカケの本。「形/音/意味」が一致していない日本語って複雑だなとも同時に思った1冊。
Posted by
◆シンプルなのに、実は独創的な人工文字ハングル。その文字としての切れ味の鋭さに驚愕すること間違いなし◆ 2010年刊行。 著者は元東京外国語大学大学院教授、元ソウル大学校韓国文化研究所特別研究員(朝鮮言語学・日韓対照言語学、音論・語彙論・文法論・言語存在論)。 先に読破し...
◆シンプルなのに、実は独創的な人工文字ハングル。その文字としての切れ味の鋭さに驚愕すること間違いなし◆ 2010年刊行。 著者は元東京外国語大学大学院教授、元ソウル大学校韓国文化研究所特別研究員(朝鮮言語学・日韓対照言語学、音論・語彙論・文法論・言語存在論)。 先に読破した「漢字伝来」が日本語における漢字の受容・変容の過程と、日本での文字形成過程を明らかにした書なら、本書は、日本と同様に漢字受容圏である朝鮮半島における、 ① 朝鮮文字の成立過程(=漢字放逐過程) と ② その極北たるハングルの言語学的特徴とを解説したもの と言える。 ①の叙述量が少ないのは、李氏朝鮮の三代・世宗がハングルを一気呵成に作り上げた事情による。 一方、叙述の大半を占める②は、実に刺激的な論考である。詳細は本書を紐解いて欲しいが、① ハングルが漢字や漢文、漢字の借字表記法としての吏読とも口駃(?。日本語訓読に近い)とも違い、文字の創出である点。 ② その文字の形態の最小基本単位が音の最小単位音素から来ている点。 ③ 音素を文字形態にする基本法則が発音時の口蓋の形態を記号化した。 というあたりだ。 シンプルかつ独創的なこの方法がハングル作成者(法則を定めた人)のシャープさを物語っているとも言えそう。 そして本書に掛ける著者の熱意。詳細な文献案内と提示、充実の事項索引。新書とは思えぬ充実ぶりが著者の本気度を語って余りある。 音素(例えば「照る」と「蹴る」におけるtとk)・形態素など、力が入る故の詳しさが読者の敷居を高くしているきらいはあるが、それでもなお一読の価値は揺るがないだろう。 漢字を捨て去った朝鮮半島に対して、表意文字の漢字を残した日本語。漢字の読みを覚えるのが容易ではないが、一度覚えたら漢字という表意文字の持つメリット=視読速読が容易との比較をしてみるのも思考実験として面白いかもしれない。
Posted by
ハングルは15世紀に、驚くほど精緻な「音の分析」をもとに創られた文字。現代の言語学者も驚嘆するその〈緻密な仕組み〉とは? 圧倒的な漢字文化の只中で、文字革命はいかに行われたのか? ハングルは、15世紀に李氏朝鮮で創られた〈文字〉である。精緻な「音の分析」をもとに創られたこの文字は...
ハングルは15世紀に、驚くほど精緻な「音の分析」をもとに創られた文字。現代の言語学者も驚嘆するその〈緻密な仕組み〉とは? 圧倒的な漢字文化の只中で、文字革命はいかに行われたのか? ハングルは、15世紀に李氏朝鮮で創られた〈文字〉である。精緻な「音の分析」をもとに創られたこの文字は、現代の言語学者も驚嘆するほどの〈緻密な仕組み〉を備えている。これほどの文字を、第四代国王・世宗(セジョン)と、彼に仕えた若き秀才たちはどのように創ったのだろうか? また、当時の朝鮮は、行政を執り行う際の文書も、歴史を記述するのも、風景や人情を詠む詩歌も、すべてに漢字が用いられてきた。しかも、隣り合う中国との外交などでの付き合いもある。日本以上に、圧倒的な漢字文化のまっただなかにあった当時の朝鮮で、文字革命はいかに行われたのか? ハングルの仕組みを〈言語学的〉に、そしてその成り立ちを〈歴史〉から見ていくことで、〈奇跡の文字ハングル〉の合理性、秘められた可能性を探っていく。 [第22回アジア・太平洋賞大賞受賞] 韓国ハングル学会より[2012年度・周時 経(チュ・シギョン)学術賞受賞]
Posted by
講演に備え、予習も兼ねて再読する。国や人と同じく本にも幸運な出会い、不幸な出会いがある。初めての海外に向かう機上で読んだケルアックの『路上』は生涯忘れ得ない一冊となった。韓国語に出会い、留学先の韓国で著者の講演を韓国語で聞けたのだから、この本との出会いは当然前者であろう。本の題名...
講演に備え、予習も兼ねて再読する。国や人と同じく本にも幸運な出会い、不幸な出会いがある。初めての海外に向かう機上で読んだケルアックの『路上』は生涯忘れ得ない一冊となった。韓国語に出会い、留学先の韓国で著者の講演を韓国語で聞けたのだから、この本との出会いは当然前者であろう。本の題名は『ハングルの誕生』であるが内容は韓国語についてだけではない。文字を創出する為には先ず言語とは何かを知る必要がある。ハングルの構造を概観しながら言語一般について改めて考えさせられた。韓国語が分らなくても充分に楽しめる筈。三読予定。 追記:自国文化の過度な礼賛は常に慎むべきであるが、本書がハードカバーの学術書としてではなく、一般教養の普及を目的とした新書版で出たことは、日本の出版文化の底力として、少し位は誇っても良いのではなかろうか。^^;
Posted by
たまたま最近読みかけだったののだが、本日が「ハングルの日」と知り、あわてて読了。ハングルとひらがな・カタカナの違いを知るには本書前半の言語学からのアプローチ、共時的分析が役に立つだろう。学習経験のある者にとってもそれなりに発見がある
Posted by
[ 内容 ] 現代の言語学者も舌を巻くほどの精緻な「音の分析」によって、一五世紀の中頃、“ハングル=訓民正音”は創られた。 圧倒的な漢字文化のまっただなか、合理的な仕組みと、美しさを兼ね備えた文字を、国王と若き学者たちは、どのように創ったのか?「音が文字になる」奇跡の瞬間を、ハン...
[ 内容 ] 現代の言語学者も舌を巻くほどの精緻な「音の分析」によって、一五世紀の中頃、“ハングル=訓民正音”は創られた。 圧倒的な漢字文化のまっただなか、合理的な仕組みと、美しさを兼ね備えた文字を、国王と若き学者たちは、どのように創ったのか?「音が文字になる」奇跡の瞬間を、ハングルの創生とともにたどる。 [ 目次 ] 序章 ハングルの素描 第1章 ハングルと言語をめぐって 第2章 “正音”誕生の磁場 第3章 “正音”の仕掛け 第4章 “正音”エクリチュール革命―ハングルの誕生 第5章 “正音”エクリチュールの創出 第6章 “正音”―ゲシュタルト(かたち)の変革 第7章 “正音”から“ハングル”へ 終章 普遍への契機としての“訓民正音” [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
韓国旅行してみて、改めてハングルについても学びたいなあ、と思う今日この頃。やっぱりルーツをたどって理解するのがいいんじゃないだろうか。
Posted by
- 1