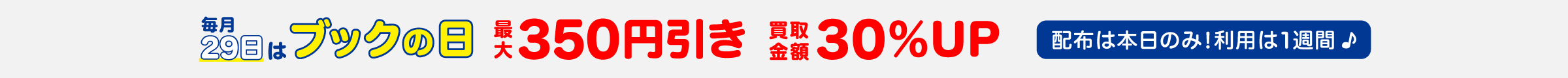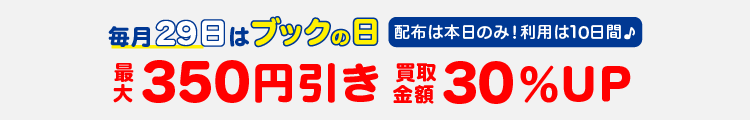転校生とブラック・ジャック の商品レビュー
今まで読んできた永井さんの著作の中では興奮度が比較的少なかった。それは私が〈私〉よりも倫理や道徳に重きを置いた読書生活を送ってきたせい。結局、どうどうめぐり?と思いつつも緻密にひとつひとつ可能性と不可能性を冷静に議論しつくしていくやりかたがやはり好き。独我論と統覚理論、統覚はカン...
今まで読んできた永井さんの著作の中では興奮度が比較的少なかった。それは私が〈私〉よりも倫理や道徳に重きを置いた読書生活を送ってきたせい。結局、どうどうめぐり?と思いつつも緻密にひとつひとつ可能性と不可能性を冷静に議論しつくしていくやりかたがやはり好き。独我論と統覚理論、統覚はカントで馴染みあったが独我論のほうのウィトは正直そんなに読み込んでいるわけではないからこの本でちょっと不明瞭だった部分が見えてきた感じ。 で、この本で散々論じられていることを言葉にできないまでも急激な不安感として幼少時に体験していたことを思い出す。下っ腹が重くなるような、胃に何かが渦巻くような不安感。あれ、解決してないというかあれにとらわれちゃった人は是非永井均を読んでほしい。
Posted by
哲学書を普段熱心に読まない、哲学についての基礎知識が欠如している私には恥ずかしながら少々難解すぎる内容だった。しかし、内容的、知識的な部分では至らないとは言え、自分の日々の態度が哲学的な志向を持っている(実現しているとは言えないかもしれないが……)と言うことを再確認できた。「独在...
哲学書を普段熱心に読まない、哲学についての基礎知識が欠如している私には恥ずかしながら少々難解すぎる内容だった。しかし、内容的、知識的な部分では至らないとは言え、自分の日々の態度が哲学的な志向を持っている(実現しているとは言えないかもしれないが……)と言うことを再確認できた。「独在性をめぐるセミナー」を通して、その議論が行われる様を追っていくことによって、哲学的なものの見方と言うものを一部窺い知ることが出来たと思う。基礎的な知識を補完してから、必ずもう一度読み直したい作品。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
懐疑論において、「間違い」とするその間違いの概念・比較の概念もまた疑いに晒されるので、問いには意味がない。それを考えると、私が私であるという思いは、たとえ妄想であっても、そう思われるということは、事実その通りである。 世界を開いているのは自分だけ。自分とは、あらゆる世界を開いている唯一の主体Aと、現実に自分を開いている唯一の主体Bの2つがある。そのとき、自分を規定するのは、心理(記憶)的連続と身体的連続、あるいはそれらを超越した形而上的な魂であるが、ブラックジャックの心理実験を用いるなら、それらは任意の時点のいまにしか存在しない。未来の私Bが私である保障は、その未来その瞬間にしかあり得ない。
Posted by
「私が私であること」はどういうことか、つまり独在性について、対話形式で書かれた哲学書です。先生と12人の学生が、提示された思考実験から議論を重ねて哲学しいく構成になっています。高度な哲学議論といえるでしょう。
Posted by
どこかの大学の入試で使われていた。題名が印象的で手に取った。読み始めたはいいものの、自分の頭では理解に及ばず、投げ出してしまった。一年以上が経って読み直したが、未だによくわからない。 私が私であると決めているのは何か。火星旅行やブラックジャックの思考実験を通じ、13人が議論してい...
どこかの大学の入試で使われていた。題名が印象的で手に取った。読み始めたはいいものの、自分の頭では理解に及ばず、投げ出してしまった。一年以上が経って読み直したが、未だによくわからない。 私が私であると決めているのは何か。火星旅行やブラックジャックの思考実験を通じ、13人が議論していく。それぞれの役割を押さえていくのがおもしろいところであり、難しいところでもある。 主張ではなく、議論し批判することで問いを深めていく。スタイルが、各人の理解をより難しくしている。 また、議論の間には学生(?)のレポートが挟まれていて、議論の補足をしている。
Posted by
「マンガは哲学する」や「〈子供〉のための哲学」などわかりやすい著作が多い著者ですが、本作は読むのに時間がかかった。こうなんだ、っていう断言がないからぐるぐるまわって、腑に落ちるポイントがない。しかし、「哲学における自分の見解というのは、問題の提示とそれをめぐる可能なかぎり多方向か...
「マンガは哲学する」や「〈子供〉のための哲学」などわかりやすい著作が多い著者ですが、本作は読むのに時間がかかった。こうなんだ、っていう断言がないからぐるぐるまわって、腑に落ちるポイントがない。しかし、「哲学における自分の見解というのは、問題の提示とそれをめぐる可能なかぎり多方向からの吟味検討それ自体であるべき」ということで、この腑に落ちなさがまさに哲学するということなんでしょう。
Posted by
いろいろなケースにおける私を定義する一冊。こういう書式での本は数あれど、これほど読み応えのあるものはそうないような気がした。存在論の中でもまさに人に薦められるものとなっている。ただ、若干難解なため、存在を考え始めた月日が浅い人にはお薦めできない。中身の中には、記憶・思考を始め、ダ...
いろいろなケースにおける私を定義する一冊。こういう書式での本は数あれど、これほど読み応えのあるものはそうないような気がした。存在論の中でもまさに人に薦められるものとなっている。ただ、若干難解なため、存在を考え始めた月日が浅い人にはお薦めできない。中身の中には、記憶・思考を始め、ダブルマンや遺伝子に関わるものまで多岐にわたっている。本自体は、何らかの答えを提示するものではなく、考えることで物事の本質を自分なりに突き詰めていくことを目的としている。生きる限り、この自分から離れることはできない。そうであるのだが、この自分を取り巻くものがいったいどこまで自分に内在しているかを考えるだけでも、自分の中に何らかの変化を起こすことにつながっているのではないだろうか。
Posted by
独在性をめぐる本格哲学書。先生と生徒たちの対話というセミナー形式を用いて、哲学的命題が立体的に構築・解体・再構築されていく様は圧巻。精読に値する一冊です。哲学は名詞ではなく動詞であるべき。本書を片手に哲学し続けよう。
Posted by
文庫が出るとついつい買ってしまう哲学者永井均。 タイトルから転校してきた中学生とブラックジャックという名の猫が問答する、永井著作にありがちなパターンかと思いきや、哲学科のゼミを思わせる濃厚な議論が展開される。 議論のテーマは「私が私であるのは何故か?」。 この議論は哲学史に...
文庫が出るとついつい買ってしまう哲学者永井均。 タイトルから転校してきた中学生とブラックジャックという名の猫が問答する、永井著作にありがちなパターンかと思いきや、哲学科のゼミを思わせる濃厚な議論が展開される。 議論のテーマは「私が私であるのは何故か?」。 この議論は哲学史において大きな問題であったに違いない。 そして一般教養としてどのような主張がされてきたのかもそれなりに知っている。 だけどまだまだ議論の余地はある。 もともと永井氏はこの問題を探求したくて哲学の道に入ったとテレビで語っていたのを見た記憶があるのだが、まさにこの本は原点を突き詰めた「今の永井均」を知ることができるのではないだろうか(読了後には「今」という言葉も使い難くなってしまうのだが・・・)。 ただし明確な答え(主張)を求めている人にはあまりオススメできない。 あくまでも問いを発して議論を深めることに重きを置いているので。 そもそも永井氏は主張(学術論文)よりも問いや議論に哲学的価値を見出しているようだ。 確かに「私が私である」という問題はそうそう解決する類のものではないので、議論するしかないのかもしれない。 ただ堂々巡りというよりは、外から内へ渦を描いて一点(≠真理・・・)に近づいている予感はした。 あくまでも哲学素人の感想にしか過ぎなくて申し訳ないが・・・。 しかし哲学科のゼミではこのようなことを普段からやっているのだろうか? もう一度大学で学べることができるのならば哲学を専攻したいのだが、恐らくゼミでは空気な学生で終わりそうで。 まあこの本に登場する12人の学生の半数くらいは存在感を示せていなかったので、そんなもんかなとも思ったりした。 「馬鹿でも哲学をやりたい」っていう高校生が読んだら勇気づけられるかもしれない。
Posted by
私にはこの哲学論議が難しくって(^^;でも、先日「プラチナデータ」を読んだばかりで、あの本では多重人格を扱っていましたが、自分というのの存在を認識するのは何かというのを考えるのは、この本を読むととても難しいって感じです。
Posted by
- 1
- 2