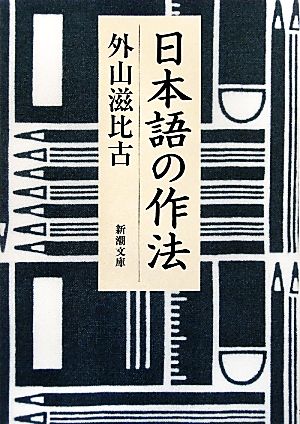日本語の作法 の商品レビュー
外山氏の文章は読んでて爽快である。 無駄に飾らない文章に、古語と現代語を融合させた格調の高い文体。箴言集を読む時の感覚と似ている。 この本を読んでつくづく思う。日本語の本質を掴み、日本語の良さをフルに発揮するのは至難の業であると。著者のように、絶え間ない研鑽が必要であると感じた...
外山氏の文章は読んでて爽快である。 無駄に飾らない文章に、古語と現代語を融合させた格調の高い文体。箴言集を読む時の感覚と似ている。 この本を読んでつくづく思う。日本語の本質を掴み、日本語の良さをフルに発揮するのは至難の業であると。著者のように、絶え間ない研鑽が必要であると感じた。
Posted by
『日本語の作法』は、外山滋比古が日本語の正しい使い方や礼儀作法について述べたエッセイ集です。この本は、日常生活での言葉遣いやコミュニケーションの重要性を強調し、以下のような主要なテーマを取り上げています。 1. 言葉の重要性 外山は、言葉が人間関係や社会生活において重要な役割を果...
『日本語の作法』は、外山滋比古が日本語の正しい使い方や礼儀作法について述べたエッセイ集です。この本は、日常生活での言葉遣いやコミュニケーションの重要性を強調し、以下のような主要なテーマを取り上げています。 1. 言葉の重要性 外山は、言葉が人間関係や社会生活において重要な役割を果たすと述べています。正しい言葉遣いは、相手への敬意や思いやりを示す手段であり、円滑なコミュニケーションを促進します。 2. 遠慮と思いやりの言葉 「ください」や「様」などの言葉の使い方について、外山はその適切な使用方法を解説しています。特に、目上の人や初対面の人に対する言葉遣いの重要性を強調し、相手を尊重する姿勢が大切であると述べています12。 3. 挨拶の重要性 挨拶は単なる形式的なものではなく、人間関係を築く上で非常に重要な要素です。外山は、挨拶が人間の価値を示すものであり、適切な挨拶ができることが成熟した大人の証であると述べています3。 4. 変わりゆく日本語 言葉は時代とともに変化しますが、外山はその変化に対しても一定の理解を示しつつ、正しい日本語の使い方を守ることの重要性を説いています。特に、SNSや若者言葉の影響についても触れています4。 5. 言葉の選び方 同じ言葉を繰り返さないことや、適切な言葉を選ぶことの重要性についても述べています。外山は、文章を書く際には一枚の原稿用紙に同じ言葉を二度使わないよう心がけていると述べています5。 6. 日常の言葉遣い 日常生活での言葉遣いについても多くの具体例を挙げて解説しています。例えば、電話のかけ方や手紙の書き方など、細かい作法についても触れています6。 まとめ 『日本語の作法』は、正しい日本語の使い方や礼儀作法について深く考えさせられる一冊です。外山滋比古の洞察に満ちたエッセイは、現代の日本語の使い方に対する新たな視点を提供し、日常生活での言葉遣いを見直すきっかけとなるでしょう。 この本を通じて、言葉の持つ力やその重要性について再認識し、より良いコミュニケーションを目指すことができるでしょう。
Posted by
外山滋比古による「たかが、あいさつ、だが、ときに人間の価値にかかわる」と、苦言を呈する痛快日本語エッセイ。
Posted by
用もないのに出す手紙、平信。用のない話、スモールトーク、四方山話の大切さを感じさせられた。平信やスモールトークが自然にできている暮らしか豊かなんだろうと思う。手紙の署名は手書きにこだわりたい。読後、そんなことを思った。相手を思いやって言葉や文章を選ぶことの大切さ、あたりまえのこと...
用もないのに出す手紙、平信。用のない話、スモールトーク、四方山話の大切さを感じさせられた。平信やスモールトークが自然にできている暮らしか豊かなんだろうと思う。手紙の署名は手書きにこだわりたい。読後、そんなことを思った。相手を思いやって言葉や文章を選ぶことの大切さ、あたりまえのことあらためて考えさせられた。
Posted by
「日本語の作法」。読後、「作法」なのだと納得しました。10年以上前に読み終えて、この度は再読です。初読のときには頷くばかりで気持ちよく読み終えました。当時、違和感を覚えていた言い回しを、その違和感の理由を分かり易く解説してもらったように思いました。 あれから10年が過ぎ、言葉遣い...
「日本語の作法」。読後、「作法」なのだと納得しました。10年以上前に読み終えて、この度は再読です。初読のときには頷くばかりで気持ちよく読み終えました。当時、違和感を覚えていた言い回しを、その違和感の理由を分かり易く解説してもらったように思いました。 あれから10年が過ぎ、言葉遣いについての違和感の内容が変わってきたようです。おそらく、定着してしまった、あまりにも頻繁に耳にするようになり耳が慣れてしまった言葉が多いのでしょう。それに気づきました。 そして、10年前には思わなかったことが、書かれている内容が細かい、そこまで細かくなくてもよいのではないか、ということです。これもまた、10年間の時代の動き、言葉の変化が心のうちに溜まってしまったためだと思います。 だから、ああ、作法なんだな、と強く思ったのです。きっと作法とはこういうものなのでしょう。 作法を形成する、その奥にある心づかいの大切さを重視したい。心づかいを大切にしても変わる作法があるのかもしれません。心づかいなくして作法が変わるとすると、それこそが無作法なのでしょう。 書かれている一つ一つの作法を大切にしたいと思いました。 最も印象に残っているのは喪中欠礼の例として挙げられている2行です。
Posted by
口が堅いのは七難隠す。 大声で話すと、知恵が逃げ出す。チャーチル元首相。 言葉遣いは相手を考え、遠慮会釈のあるのが、一人前。 日本語を丁寧に考えて使わなければならない。言葉は人の価値に関わる。
Posted by
間違った日本語の使い方を気づかずに使っていたことに気づかせられる。日本語は単一民族のみの国語であり、大切にしていきたいものである。2018.7.13
Posted by
2017/3/5 外国の言葉事情と比較しながら、日本人も最近は忘れかけている日本語の奥深さや味わいについて細やかに教えてくれる日本語についての本。日本は外国と比べて言葉はものすごく大切に扱われてきた歴史があるが、近年の日本では言葉そのものに関する関心が薄れているからこそ、日本語の...
2017/3/5 外国の言葉事情と比較しながら、日本人も最近は忘れかけている日本語の奥深さや味わいについて細やかに教えてくれる日本語についての本。日本は外国と比べて言葉はものすごく大切に扱われてきた歴史があるが、近年の日本では言葉そのものに関する関心が薄れているからこそ、日本語の礼儀作法としてはおかしな点が多々増えてきていることを指摘している。 日本語の意味を間違えた使い方、使う場面を間違えたものなど多岐にわたっている。中には、読んでいて、その言葉はそうやって使うのかと改めて知ったものというか、今まで知らなかったものもたくさんあった。実際に交わす挨拶の言葉に関するもの、手紙や文章など書面上で書く文字のこと、実際に書く文字と印刷や印字された文字が伝える印象の変化なども書いてあり、日本語についての知識をたくさん増やすことができる。
Posted by
外山先生ならではの博学がいっぱいの本であった。日頃の言葉の使い方や思いやりについて、考えるよい機会になった。
Posted by
普通に過ごしていると気づきにくい言葉の違和感や、表現者の伝える姿勢を、軽快かつ鋭く指摘する。乱れた言葉を分かって使うのと、分からずに使うのとでは雲泥の差がある。十分に意識していたつもりでも、思い至らない点が多々あったことに気づかされた。タイトルが堅いように思われたが、エッセイのよ...
普通に過ごしていると気づきにくい言葉の違和感や、表現者の伝える姿勢を、軽快かつ鋭く指摘する。乱れた言葉を分かって使うのと、分からずに使うのとでは雲泥の差がある。十分に意識していたつもりでも、思い至らない点が多々あったことに気づかされた。タイトルが堅いように思われたが、エッセイのような語り口で大変読みやすくおすすめ。
Posted by