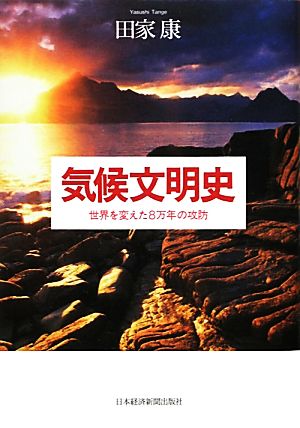気候文明史 の商品レビュー
https://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01884916
Posted by
流し読み。特に日本に関係する部分を。 今も生きるどこかの狩猟民族が、農耕の必要性をなんら感じていない、むしろめんどくさくてやる意味がわからん、みたいな話がおもしろい。 フランス革命がなぜあのタイミングでおきたか?それはそこまでに続く冷害と飢饉の中で人々がほんとうに飢えていたか...
流し読み。特に日本に関係する部分を。 今も生きるどこかの狩猟民族が、農耕の必要性をなんら感じていない、むしろめんどくさくてやる意味がわからん、みたいな話がおもしろい。 フランス革命がなぜあのタイミングでおきたか?それはそこまでに続く冷害と飢饉の中で人々がほんとうに飢えていたから、とか。 気候が歴史に関係する、という観点はおもしろい。人が歴史を作るけれど、その人の感情は気候が作っている。
Posted by
論旨が一方的で名著とは言えまいが情報量は多い。アイソトープ分析などで「古気象学」というような一分野が開拓され今後歴史学に応用が期待される。フランス革命が異常な寒冷の結果は有名。たとえば鎌倉幕府の成立も西日本の気象異変に対し温暖化した東日本の優位という具合に説く。大湿地帯だった関東...
論旨が一方的で名著とは言えまいが情報量は多い。アイソトープ分析などで「古気象学」というような一分野が開拓され今後歴史学に応用が期待される。フランス革命が異常な寒冷の結果は有名。たとえば鎌倉幕府の成立も西日本の気象異変に対し温暖化した東日本の優位という具合に説く。大湿地帯だった関東平野を開墾した農業技術や、自前の軍事力不足の朝廷の政治的怠慢は枝葉か?すると鎌倉仏教の元祖のうち唯一東国出身である日蓮の出現も気象の結果か?不凍港がほぼ無いロシアは北方領土を返還するはずはない。温暖化人口増加で大虐殺と食糧危機は?
Posted by
出アフリカの頃の話をもっと知りたい。 現生人類は一度、2000~10000人程度まで減少した。7万年前の人たちは、どうやって服を着ることを思いついたんだろう。
Posted by
気候と歴史の出来事とのこじつけにはやや違和感が感じられる箇所がいくつかあったものの、多岐な分野の代表的な研究成果に目を通されていて、とてもいい内容になっていると思います 巻末の参考文献や引用元も、一般向けに日本人が書いたものにしては珍しく多く、あまたの書きなぐりのゴミ本に比べると...
気候と歴史の出来事とのこじつけにはやや違和感が感じられる箇所がいくつかあったものの、多岐な分野の代表的な研究成果に目を通されていて、とてもいい内容になっていると思います 巻末の参考文献や引用元も、一般向けに日本人が書いたものにしては珍しく多く、あまたの書きなぐりのゴミ本に比べるととても好感が持てます
Posted by
「もし気候の変化が歴史時代に発生したとすれば、必ずや人類に影響を与えたに相違ない。・・・歴史的事件と気候の変化との間における密接な関係は想像以上に重大なのであって、往昔の幾多の大民族の興亡は、その気候的条件の良否に正比例しているようである。」(エルズワース・ハンチントン『気候と文...
「もし気候の変化が歴史時代に発生したとすれば、必ずや人類に影響を与えたに相違ない。・・・歴史的事件と気候の変化との間における密接な関係は想像以上に重大なのであって、往昔の幾多の大民族の興亡は、その気候的条件の良否に正比例しているようである。」(エルズワース・ハンチントン『気候と文明』)氏の研究そのものは、差別主義的であったり、唯物論的であったりと、今日日批判されることの方が多い。しかし、その気候と人類史の関係を照らす予言は、放射性炭素による年代測定、海底堆積物、各地氷床による古気候分析の飛躍的進歩相まって、いよいよ多くの議論と、考察を育むに至っている。現世人類の出アフリカから、およそ8万年、実はそれ以前(12万年前)にも出エジプトした人類のあったが、こちらはやがてすぐに滅びたという。では、いったい何故、現世人類は地球上に今日の生活圏を広げることができたのか。また、その生活圏にあって、民族の大移動や、帝国、大国、文明の栄枯盛衰は気候の変化といかにしてあったのか。最新の調査、研究結果が浮かび上がらせる、気候変動と歴史振動の興味深い同調。さても、こうしてみれば、今日声高に叫ばれる地球温暖化も、人類の長い歴史の一コマに過ぎない。むしろ、自分たちは「気候の安定した歴史上極めてまれな住みやすい時代にいることがわかる」。ただし、「過去において気候は緩やかに変化したことなどない。地球の気候は、つねにある状態から別のところに一気に変わってきた」、そのこともまた事実である。おそらく地球温暖化による気候変動は今後ますます加速するだろう。はたして、それが自分たちの生活、社会、精神をどのように変えていくのか、その対応対策も含めて大いに考えさせられる一冊。巻末解説も丁寧で、是非とも多くの人に読んでもらいたい。
Posted by
発行時の著者の肩書きは農林中央金庫の金融部(森林部門担当部長)で日本気象予報士会東京支部長、つまり気象予報士ではあるが学者でも専門家でもない。はじめにで気象予報士の資格を取り気象システムや古気候学の理解を深める中で歴史の変化に与える気候の影響に気がついたと書いている。著者はこの本...
発行時の著者の肩書きは農林中央金庫の金融部(森林部門担当部長)で日本気象予報士会東京支部長、つまり気象予報士ではあるが学者でも専門家でもない。はじめにで気象予報士の資格を取り気象システムや古気候学の理解を深める中で歴史の変化に与える気候の影響に気がついたと書いている。著者はこの本を研究論文でも専門書でもないと書いているが、既存の情報をまとめ直し、再構成するだけでも充分な読み物になっている。参考文献も膨大で執筆のきっかけが気象予報士仲間のすすめだということからも趣味がこうじて仕事の合間に書いたということがわかる。 気候変動の大元はどこからかと言うと、太陽活動の変化、地球の公転軌道のぶれや歳差運動、地軸の傾きなど太陽エネルギーを受け取る量の変化、氷河の増大や減少がもたらす地球表面の反射率の違いによる正のフィードバック効果(氷河がとけると黒っぽくなり熱を吸収しやすくなりますます暖かく、氷河が増えると白っぽくなりますます熱を反射しやすくなる)、海洋の循環による赤道から極への熱の移動、エルニーニョ現象などの海洋温度差がもたらす気圧配置、ジェット気流の蛇行や火山噴火、隕石の衝突による太陽光の反射と温室効果ガスなどなど。それぞれ地球全体の寒冷化や温暖化、地域ごとの気象変動につながっている。 歴史的には人類の移動は食料を求めてという理由が大きい。特に寒冷期にはそれまで取れていた作物や狩猟の獲物がいなくなると豊かな地方への侵略が始まる。例えばローマ帝国の繁栄は温暖な時代に続きそれに従いワイン用のブドウの栽培も北へと拡がった。中央アジアも湿潤化しオアシスが栄えたことでシルクロードも生まれた。一方で北のガリア、ゲルマン民族は干ばつにより度々ローマ国境を脅かしている。ガリアはローマに従っているがゲルマンの南下により時にローマに叛旗を翻している。四世紀後半寒冷化や中央アジアの乾燥が進み、フン族は西へ移動しゲルマン民族はローマに侵入し、これよりやや早く中国では黄巾の乱をきっかけに後漢が滅亡し三国史の時代から長い分裂の時代に入る。 西暦536年には世界中で異常気象があった証拠が見つかっており、夏に雪が降り、太陽は暗かった。本書では火山噴火説の一つとして紹介しているだけだがインドネシアのジャワ島とスマトラ島の間にあるクラカタウの大噴火説が有力で、世界最初のペストの流行をもたらし7世紀にはイスラム教が大きく拡がった。中国では随が統一を果たしている。 9世紀から13世紀にかけては温暖でヨーロッパ全土で農地が拡大し人口が増え、国力を増したヨーロッパは十字軍の遠征を行っている。ただし中央アジアは乾燥しており1206年以降のチンギス=ハーンのモンゴル統一、西征と重なる。1450年以降は小氷期に入り西洋ではルネサンス、中国では明代の鄭和の大航海からその後の北京周辺の万里の長城が現在の石造りの姿になっている。もちろん気候ですべてを説明できるのではないが温暖期には国力が増大し、寒冷期には社会の変革や宗教の拡大など精神面での変化が起こっているのではないかというのが著者の気づきだ。
Posted by
数多くの資料から情報を整理したような内容。洋書からの引用も多いので、目新しい情報も少なくなかった。 ・近日点と遠日点の日射量は7%異なる。 ・ミランコヴィッチは、北半球の夏の日射量が最も減少した時期に氷期が始まると考えた。 ・北半球の夏の日射量は1万4500年前から増加し、1万...
数多くの資料から情報を整理したような内容。洋書からの引用も多いので、目新しい情報も少なくなかった。 ・近日点と遠日点の日射量は7%異なる。 ・ミランコヴィッチは、北半球の夏の日射量が最も減少した時期に氷期が始まると考えた。 ・北半球の夏の日射量は1万4500年前から増加し、1万年前のピーク時には現在より8%多かった。植物年輪の放射性炭素から、1万年前から8500年前にかけて黒点数が多く、太陽活動が活発だった。 ・気候最適期には、地軸の傾きが大きく、近日点は7月だった(p.281)。 ・近日点が南半球の夏の時期に変わり、地軸の傾きが小さくなり、太陽活動も弱くなったため、5500年前から寒冷化した(ピオラ振動)。 ・前々回のミンデル氷期後の温暖化は、北緯65度の日射量が低下している段階で始まっており、その後の寒冷化も日射量の極大期よりも8000年早く始まっている。 ・太陽黒点の極大期と極小期のエネルギー放射量の差は0.1%だが、紫外線領域では8〜14%の変動がある。紫外線を吸収する成層圏が上空から地球の気温を上昇させている可能性もある。 ・気温が低下して陸上が乾燥化すると、砂漠の砂や塵が海洋に運ばれて植物性プランクトンの増殖を促すため、海洋内の二酸化炭素の固定が進んで中期的に寒冷化が進行するという仮説が出されている。 ・タヒチとオーストラリア北岸のダーウィンの気圧が逆相関する南方振動は、その後エルニーニョ南方振動(ENSO)と名付けられた。エルニーニョの発生頻度は、寒冷な時期に多く、温暖な時期に減少する。 ・北大西洋振動(NAOインデックス)が正の場合(低緯度の気圧が高い)は、高気圧西側の南西風が暖気を運ぶだけでなく、風成循環によって北大西洋海流が活発になるため、北部ヨーロッパの温暖化が促進される。 ・南北の気圧差が大きいと風を起こすエネルギーが大きくなるため、ジェット気流の風速が強まり、直線的になる。気圧差が小さいと、ジェット気流が弱まり、蛇行するようになる。小氷期には南北の気圧差が小さく、ジェット気流が蛇行していたため、天候の地域差が顕著に表れたと考えられる。
Posted by
帯に「陰の主役から歴史を読み解く」と記されるごとく、気候がどのように文明に影響したかを、時系列でリスト的に追っかけた内容。猛獣のように、気温が毎年激変するのが地球上のノーマルな姿。そしてその気気温の激変が、人類に多大なる影響を与えたと言うのは、歴史をひもとくとまさにその通り。異常...
帯に「陰の主役から歴史を読み解く」と記されるごとく、気候がどのように文明に影響したかを、時系列でリスト的に追っかけた内容。猛獣のように、気温が毎年激変するのが地球上のノーマルな姿。そしてその気気温の激変が、人類に多大なる影響を与えたと言うのは、歴史をひもとくとまさにその通り。異常気象による飢饉や病原菌の影響で人口が3分の2以上減ってしまうようなことが、歴史をみると当たり前にある。 むしろ今は、気候面からすると幸せな時代で、こんなに長く(100年以上)、気候が安定している時代は珍しいという。環境に関していえば、むしろ、人為的な懇談かの問題よりも、今後の気候の激変に備えた食料備蓄や、気候の激変に耐えられる食料の安定供給体制の構築の方が重要であろう。
Posted by
- 1