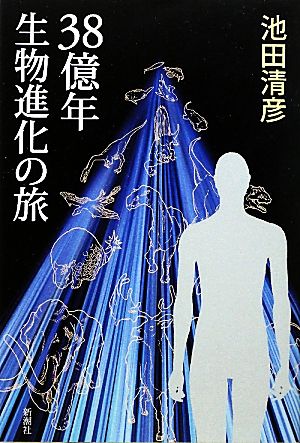38億年 生物進化の旅 の商品レビュー
2010/10/29 借りる 11/25 読み始める。 2011/1/22 やっと読み終わる。 「オスは生きてるムダなのか」が、面白かったので、池田 清彦の別の本も、読みたい! DNAがあるかどうかも重要だが、どのDNAが発現するのか、そっちも大きなポイント。 本書は、38...
2010/10/29 借りる 11/25 読み始める。 2011/1/22 やっと読み終わる。 「オスは生きてるムダなのか」が、面白かったので、池田 清彦の別の本も、読みたい! DNAがあるかどうかも重要だが、どのDNAが発現するのか、そっちも大きなポイント。 本書は、38億年がきちんと書いてあり、これまで飛び飛びだった知識が整理された。 最初に洗脳?されたのがダーウィンの進化論、 その後 知識を付け足していったのが、ネオダーウィニズム。 科学の進歩で、いろいろなことがわかれば、新しい情報を取り入れていかねば! これからは、気をつけて古い理論の本を読まないようにしよう。 内容と著者は 内容 : 生物に大きな進化が生起したあらゆる局面を時代順に追跡。 様々な現象を具体的に例示しながら、 遺伝子の突然変異や自然選択などネオダーウィニズム的理屈では読み解けない、進化の仕組みの本質を説く。 『波』連載を単行本化。 著者 : 1947年東京都生まれ。東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了。 生物学者。早稲田大学国際教養学部教授。 著書に「構造主義科学論の冒険」など。
Posted by
約38億年前から始まった生物進化の歴史を概観した本。古代生物の得体の知れなさや恐竜のスケールの大きさにワクワクし、38億年間という途方もない時間にロマンも感じられて、安易な楽しみ方かもしれないけど読んでよかった。 一番印象に残ったのは、種の多様性の観点からみるとヒトは絶滅の道...
約38億年前から始まった生物進化の歴史を概観した本。古代生物の得体の知れなさや恐竜のスケールの大きさにワクワクし、38億年間という途方もない時間にロマンも感じられて、安易な楽しみ方かもしれないけど読んでよかった。 一番印象に残ったのは、種の多様性の観点からみるとヒトは絶滅の道を歩んでいるかもしれないということ。
Posted by
鳥が恐竜の生き残りだったり、ティラノサウルスに羽毛が生えていたり。子どものころから、恐竜の研究ってずいぶん進んでいるんだな。
Posted by
38億年の進化を200頁強に纏めた。 だからと言って生物進化の入門書という訳でもない。 難しい部分は難しいし、読みやすい部分は面白い。進化の話は嫌いじゃない、むしろ好きな部類。 ブルーバックス大好きな時期もありましたから。 生命の誕生の話は難しい。タンパク質ありき、RNAありき、...
38億年の進化を200頁強に纏めた。 だからと言って生物進化の入門書という訳でもない。 難しい部分は難しいし、読みやすい部分は面白い。進化の話は嫌いじゃない、むしろ好きな部類。 ブルーバックス大好きな時期もありましたから。 生命の誕生の話は難しい。タンパク質ありき、RNAありき、DNAありき、なんだそうだけど化学記号が飛び交うと、もうチンプンカンプン。(死語?) カンブリア紀の大爆発まで来ると著者の舌も滑らかになってくるから、ここからは頁が進む、進む。 確かに進化を通しで(発生から現人類まで)書いている作品は少ないのかも。 カンブリア紀に匹敵する生命の多様化は他にもあったそうだし大絶滅も何回もあったそう。 進化とは?を判りやすく、尚且つ学問的に説明してくれる良書。 でもやっぱり好きでないと面白くは無いかも。
Posted by
そもそも、最初に生命が誕生したプロセスがまだ分かっていない。 アミノ酸までは自然の過程で合成されることは考えられるが、 そこからタンパク質が合成され、代謝を獲得し、複製機能を獲得し、 RNAやDNAといった超複雑な分子がどうやってできるのかが、まだまだいろんな仮説の域を出ていな...
そもそも、最初に生命が誕生したプロセスがまだ分かっていない。 アミノ酸までは自然の過程で合成されることは考えられるが、 そこからタンパク質が合成され、代謝を獲得し、複製機能を獲得し、 RNAやDNAといった超複雑な分子がどうやってできるのかが、まだまだいろんな仮説の域を出ていない。 進化に関しても、遺伝子の突然変異と自然淘汰だけでは説明できないことが多いらしい。 確かに、例えば鳥の羽にしても、徐々に進化していったとすれば、 その「途中」の状態が適用的だとは思えない。 羽は完成された状態までいかないと、飛ぶという機能を獲得できないので 途中が存在するとは考えにくい。 やはりそこは、一気に羽ができたと考えるほうが自然な気がする。 一気に変化が起こる仕組みとして、池田さんは遺伝子の変化ではなくて、 遺伝子の「機能の仕方が変化した」という説を唱えている。 その要因は、環境の変化などの圧力。 確かに環境が変われば、同じ遺伝子でも発生の過程において発現の仕方が大きく変わることはあるような気がする。 また、そうでもないと、種全体として大きく変わることが考えにくい。 なんかちょっと今までの疑問が晴れたような感じである。 ただちょっとこの本は、38億年の生物の歴史を短くまとめようとするあまりに 単なる説明的な箇所が多く、物語としての深みには欠ける。 そういう意味では『生命40億年全史』のほうが圧倒的に面白かった。
Posted by
真核生物が出てきたのが約21億年前で、それから約6億年前まで多細胞生物ができなかったとすると、その間に生物はなにをやっていたのか? エディアカラ生物群のほとんどはヴェンド紀末に絶滅したが、そのうちほんんお少しのものが生き残ってカンブリア紀の大爆発がおきた。 恐竜時代を夢想すると、...
真核生物が出てきたのが約21億年前で、それから約6億年前まで多細胞生物ができなかったとすると、その間に生物はなにをやっていたのか? エディアカラ生物群のほとんどはヴェンド紀末に絶滅したが、そのうちほんんお少しのものが生き残ってカンブリア紀の大爆発がおきた。 恐竜時代を夢想すると、現代の人間の悩みなんて小さいな。こういう本をたまに読むのはとても良い。 サメには幾多の困難を全部乗り越えてきた動物と言える。 陸棲から海棲になったクジラにしても、普通鵜に足がある時には、海の中に入る必要もなかったが構造が変わって足が弱小化したら、陸上より水中の方が当然生きやすい。 現代人類の共通の祖先は約14万年前にアフリカにいた小集団。 そのアフリカのホモサピエンスが約10万年前にアフリカを出て世界に分布を広げ始めた。
Posted by
【38億年 生物進化の旅】 池田清彦 地球上に生命が誕生し38億年という月日が流れた。 その38億年の間に生物は何度も絶滅の危機に見舞われ、 その都度『新しい種』が『絶滅した種』にとって変わった。 大絶滅が起きるとニッチ(生態的優位)が空き、 その時に新しい進化が起こると考...
【38億年 生物進化の旅】 池田清彦 地球上に生命が誕生し38億年という月日が流れた。 その38億年の間に生物は何度も絶滅の危機に見舞われ、 その都度『新しい種』が『絶滅した種』にとって変わった。 大絶滅が起きるとニッチ(生態的優位)が空き、 その時に新しい進化が起こると考えられている。 そのような、出来事を何度も経て今に至っている。 太古から現代に至る経緯が書かれている。 第1章:無生物から生物がいかにして生まれたのか 第2章:シアノバクテリアの繁栄と真核生物の出現 第3章:多様化-単細胞から多細胞生物へ 第4章:カンブリア大爆発 第5章:動物や植物が陸に上がり始めた時代 第6章:「魚に進化した魚」と「魚以外に進化した魚」 第7章:両生類から爬虫類へ 第8章:恐竜の進化と、鳥の起源 第9章:爬虫類と哺乳類のあいだ 第10章:ほんとうの哺乳類 第11章:様々な有蹄類たち 第12章:ヒトはどのようにしてヒトになったか 終章:進化とは何か ☆ 動物、恐竜、太古、進化などは興味のあるジャンル 新しい発見がある度に、古い定説が覆される。 わたしの知っている知識も、かなり古いようです。(^^;) この本により知識が書き換えられました。 「メモ」 【適応放散】 ひとつの系統が様々な環境に適応して、適当なニッチに はまり多様な形態をもつ種に分化していくことを指す。 【生態学的収斂(しゅうれん)】 異なる系統の生物でも同じニッチに適応したものは よく似た形態になることを指す。
Posted by
- 1