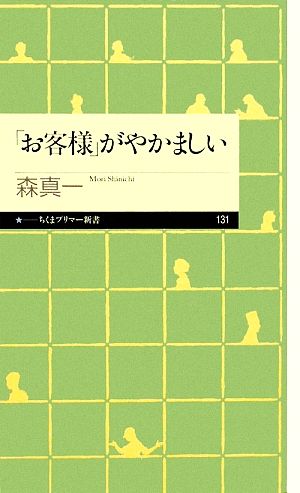「お客様」がやかましい の商品レビュー
図書館のカードが空いてた日に、目について借りてきてみた。いまの日本は、ますます「お客様」社会になってるんちゃうかという著者が、その問題点を指摘した本。 ▼店員が失礼だったからという理由で暴言・暴力が許される。そんな理由にならない理由が、まるで正当な理由としてなりたつかのように...
図書館のカードが空いてた日に、目について借りてきてみた。いまの日本は、ますます「お客様」社会になってるんちゃうかという著者が、その問題点を指摘した本。 ▼店員が失礼だったからという理由で暴言・暴力が許される。そんな理由にならない理由が、まるで正当な理由としてなりたつかのようになってしまったのが、「お客様」社会なのです。(p.52) この「お客様」社会は、とにかくお客様の不満を取り除くことに全力をあげる。しかし、その不満排除が、逆説的にも、より一層「お客様」の不満のタネをよぶのだと著者はいう。 ▼不満を徹底的に排除しようとする努力は、不満を感じる機会を減らします。しかし、それは一時的にすぎません。以前ならいちいち不満に思わなかったことに不満を感じるようになるのです。高度なレベルの気づかいを、みんながみんなに期待するからです。… 客観的には不満の要因がドンドン取り除かれてきているのに、主観的にはますます不満のタネが増えているように感じられてしまう。不満の要因を排除する徹底さの度合いが高ければ高いほど、満足への期待レベルが非現実的なほど高度になり、かえってささいなことにも敏感になって、不満や怒りを感じるのです。(p.154) その具体例として、JR脱線事故があげられている。客の不満、「定時に遅れる」「運賃が高い」「乗り換えが大変だ」といった不満を排除する努力が、つまりは「もっと速く」「もっと安く」「もっと便利にという客のさらなる期待、要望が、1分の遅れも許されない高速運転、軽い車両、若くて経験の浅い運転士の勤務になったのではないかと。 この本では働く現場(例えばスーパーやコンビニ)、教育の場(例えば大学)の例もとりあげながら、「お客様」社会が進めば、さらに客の不満は増大し、拝金主義、自主性の欠如(お客様意識)、暴力につながると述べる。 読みながら、いわゆる"公務員バッシング"というのも、「行政サービス」に対する「不満」というかたちでの「お客様」的な言動なんやろうなーと思った。住民の多くが、自分は"サービスを受ける"側で"行政はちゃんとやってくれない"と思ってしまうのは、なんというか、思うツボのような気がするけど、それは誰の思うツボなのかと。 こういう「お客様」社会からの脱却を試行錯誤するときに、『「街的」ということ』は参考になるかもと書いてあった。 お金とサービスが情報化されている場所では、いつ行ってもお客が「誰でも同じように遊べる」のがお約束。そういう場所のカタログ情報誌を見て、あっち行ってこっち行って「同じように遊ぶ」ことより、予定をたてて遊びにいったら、その予定が台無しになるような場所、それが「街的」ということ。お客になりにいかないところ、というか。 (11/10了)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 現代の日本社会は「お客様=神様」として扱うが、客の不満はゼロになるどころか、不満は増大し、自主性の欠如や拝金主義、暴力につながっていく。 「お客様」社会の問題点と脱却法を考える。 [ 目次 ] 第1章 「お客様」社会先進国ニッポン(消費者社会としての日本社会;「お客様」社会としての日本社会;広がる「お客様」化;「お客様」になれば認めてもらえる) 第2章 「お客様」による暴力はなぜ増える?(「お客様」社会は問題か?;「お客様」は「荒ぶる神様」;「お客様」が暴力的になる理由) 第3章 客を客とも思わない店員―労働者から誇りを奪う「お客様」社会(「お客様」社会の逆説;スーパーと職人;スーパー、職人、マニュアル;失礼なバイト店員が増えた理由;失礼な職人的店員が増えた理由) 第4章 教育の「お客様」社会化は、学ぶひとを不幸にする(学校教育の「お客様」社会化;「お客様」社会化した大学の現状;「お客様」社会化した大学の問題点;学校教育の「お客様」社会化マッチポンプ) 第5章 「お客様」意識からの脱却(不満排除システム;不満排除の逆説的帰結;せいぜい「お客さん」) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
店・店員に要求するレベルが高くなり、以前は気にもしなかったようなことが苦情、クレームとして表出する「相対的不満」。教育、医療、介護の臨床にまで浸透する「お客様」社会とその素地である拝金主義。教育のとこで取り上げられてるのは、たぶん久留米大学かも。授業評価アンケートのこととか載って...
店・店員に要求するレベルが高くなり、以前は気にもしなかったようなことが苦情、クレームとして表出する「相対的不満」。教育、医療、介護の臨床にまで浸透する「お客様」社会とその素地である拝金主義。教育のとこで取り上げられてるのは、たぶん久留米大学かも。授業評価アンケートのこととか載ってるしね。
Posted by
第1章 「お客様」社会先進国ニッポン (消費者社会としての日本社会/「お客様」社会としての日本社会/広がる「お客様」化/「お客様」になれば認めてもらえる) 第2章 「お客様」による暴力はなぜ増える? (「お客様」社会は問題か?/「お客様」は「荒ぶる神様」/「お客様」が暴力的にな...
第1章 「お客様」社会先進国ニッポン (消費者社会としての日本社会/「お客様」社会としての日本社会/広がる「お客様」化/「お客様」になれば認めてもらえる) 第2章 「お客様」による暴力はなぜ増える? (「お客様」社会は問題か?/「お客様」は「荒ぶる神様」/「お客様」が暴力的になる理由) 第3章 客を客とも思わない店員―労働者から誇りを奪う「お客様」社会 (「お客様」社会の逆説/スーパーと職人/スーパー、職人、マニュアル/失礼なバイト店員が増えた理由/失礼な職人的店員が増えた理由) 第4章 教育の「お客様」社会化は、学ぶひとを不幸にする (学校教育の「お客様」社会化/「お客様」社会化した大学の現状/「お客様」社会化した大学の問題点/学校教育の「お客様」社会化マッチポンプ) 第5章 「お客様」意識からの脱却 (不満排除システム/不満排除の逆説的帰結/せいぜい「お客さん」) 第4章(学校教育の「お客様」社会化マッチポンプ) 第5章(不満排除の逆説的帰結) が特に興味深かった。 人の痛みのわからない大人にはなりたくないのぅ。
Posted by
お客さんではなくお客様。 いろんな場面でお客様はいます。 そのお客様の不満はどんなおもてなしをしても 減るどころか増えるばかり。
Posted by
入江敦彦さんの『ゼロ円で愉しむ極上の京都』と併読すると面白い。 森真一さんの定義する「拝金主義」に陥っていない人の考え方がわかるのではないかと思う。 (個人的には「街のお好み焼き屋」よりずっとわかりやすい。)
Posted by
● お客様は神様であることは確かだけど、えてして、謝られる資格の乏しい人ほど声を大にして謝罪を要求したり、本当は自分が悪いことを知っている人ほどむきになって文句を言うことが多いものです。 ● 「お客様」社会は、「不満排除システム」です。不満を徹底的になくそうとする社会です。
Posted by
「お客様」とか丁寧に扱いすぎというお話。Twitterが状況を変えてくれるかも。 詳細はこちら http://blog.livedoor.jp/oda1979/archives/2594033.html
Posted by
・会社、地域で触れ合いの減少 →特別扱い(=お客様)を求める(客にはお金を払うだけでなれる) →買い物依存症の増加 ・著者の主張だと、物を買うお客が増加するから、もっと景気が良くなっても良いような気がするんだけど…うーん ・むしろ、不況で物が売れないからこそ「消費者...
・会社、地域で触れ合いの減少 →特別扱い(=お客様)を求める(客にはお金を払うだけでなれる) →買い物依存症の増加 ・著者の主張だと、物を買うお客が増加するから、もっと景気が良くなっても良いような気がするんだけど…うーん ・むしろ、不況で物が売れないからこそ「消費者 > 生産者」という力関係(お客様社会)になったと考える方が自然? ・特別扱い(=他人からの心地よいフィードバック)を求める傾向が、ネット(Twitter、mixi)でのコミュニケーションが増えた原因の1つかも →ネットでのコミュニケーションで満足して、余計物を買わなくなった?(お客様社会が物理世界から、ネット世界へシフト) ・第4章で、大学で大学生がお客様化するのを嘆く箇所が、著者が大学教授だけに妙にリアルに感じた ・ツイッターとか始める大学教授とかは、お客様(大学生)相手に疲れた心を癒す為にやっているんだろうか(ワガママし放題の人とかもいるみたいだし)
Posted by
- 1
- 2