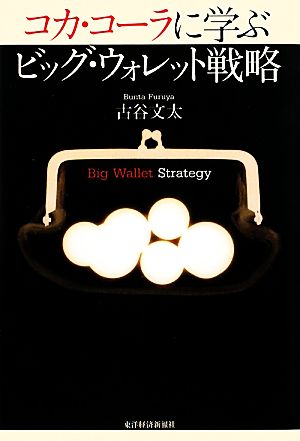コカ・コーラに学ぶビッグ・ウォレット戦略 の商品レビュー
コカコーラジャパンの限界が分かる。規模の拡大はふくすうの会社を存続させながらではすすまない。資本の統一が必要。
Posted by
株主関係が複雑に絡むコカコーラ事業体制の中で、関連会社間の枠を超えた在庫管理やサプライチェーンシステムを構築した著者による、戦略構築・推進の苦労話。コラボレーションが重要テーマとなる事業推進において、管理会計体系の統一というテーマがいかに大切かに気づかされます。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
コカコーラ社における、全体最適化を行った時の話と読めました。各自の会社を存続させたままで全体最適化を行った場合にはこのような方法もあるのだと勉強になりました。 ただ、個人的な感想としては、この戦略はコカコーラ社独特のスタイルには良く適合するとは思いますが、その他の会社でこの戦略は難しいと思います。
Posted by
コカコーラの成功の秘訣について、マーケティングではなく、経営戦略という視点から書かれたものです。 ビッグウォレットというのは、つまり小さい財布を全て包括する大きい財布のようなイメージです。 コカコーラ独特の経営手法を指しています。 コカコーラは日本コカコーラが戦略的な部分を背負い...
コカコーラの成功の秘訣について、マーケティングではなく、経営戦略という視点から書かれたものです。 ビッグウォレットというのは、つまり小さい財布を全て包括する大きい財布のようなイメージです。 コカコーラ独特の経営手法を指しています。 コカコーラは日本コカコーラが戦略的な部分を背負い、製造販売を14のボトラー社が行なっています。 つまり、それぞれが個々に最適を目指すのでは得られない収益を、全体最適を目指すことで得ようという手法です。 そのために必要なのが、 1、協業利益の見極め 本当に全体最適を目指せば収益がでるのか? 2、経済合理性に基づく意思決定基準 何をもって全体というかをきちんときめる 3、割り勘会計のルール つまり、得た収益をどこから全体に振り分け、どこまでは個々の収益とみなすのか 4、独立した機能統合組織 5全体と個々のウィンウィン関係 全体最適を目指すことで、個々でみれば損をするところもでてきます。 しかし全体最適を目指したほうが結果的に得をしているんだということをみながわかるように示すことが重要ということ。 つまり、M&Aするんじゃなくて、資本提携でもないl、ちょうどそのどっちもいいとこどりをしているのがビッグウォレット戦略といいたいらしい。 でも最後まで、なぜM&Aじゃだめなのか?という疑問が残る節がありました。 そこがもう少しわかりやすく解説されていればもっとよかったです。
Posted by
コカコーラのサプライチェーンマネジメントのお話。マーケティングではなく、経営的な視点でコカコーラのビジネスを論じています。独自のビジネスモデルが世界中で繁栄してる秘訣か。
Posted by
本日ご紹介する本は あのコカコーラのビジネスモデル の戦略についてです。 「ビッグ・ウォレット戦略」 という新しいビジネス戦略について 学びが得られます。 コカコーラといえば 飲料ブランドNo.1企業ですね。 苦労なく、ずっと安定して高収益をあげて きたように思っていたん...
本日ご紹介する本は あのコカコーラのビジネスモデル の戦略についてです。 「ビッグ・ウォレット戦略」 という新しいビジネス戦略について 学びが得られます。 コカコーラといえば 飲料ブランドNo.1企業ですね。 苦労なく、ずっと安定して高収益をあげて きたように思っていたんですが、 実は、時代の変化にともない それにあわせて戦略も変えざる おえない状況になり、 いろいろな変革を余儀なくされて いるのが意外でした。 「ビッグ・ウォレット」とは「大きな財布」 という意味です。 「ビッグ・ウォレット戦略」とは 個々の独自企業を、あたかも一つの会社のように 見立て、運営し、全体で最大限の利益を追求していく ものです。 コカコーラは2005年に本格的に本戦略を開始し、 3年間に渡って1千億円以上の原価削減を達成した とのことです。 今回参考になったのは、 日本人は、部分最適の改善はすごく得意だけれども 全体最適を考えるのはあまりうまくない。 というところ。 たしかに、日本人は仲間意識が強く 目の前の脅威や課題については 協力して力を発揮しますが、 自分以外のもっと外の全体を見ることや 遠い将来を見据えて取り組むことは 不得意なのかも知れません。 もっと広く全体を考えることは 我々にとっては、パートナー会社や 取引会社や、顧客も含めての「全体最適」 という考え方もありますし、 あるいは、もっと積極的に 他社との協業 または、顧客との協業 を考えることにつながると思います。 本書の最後に書いてある5つの価値観は、 本書の趣旨とは直接関係ないんですが、 新しい仕事に取り組んでいく上で 大変参考になる考え方だなあと思いました。 ぜひ、読んでみてください。 ◆本から得た気づき◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 複数企業の「全体最適」により、単独企業では実現できない利益を得る戦略 企業の独立は保ちながら、資本の枠を超えて1つの企業のように動く仕組み 日本人は、部分最適の改善は世界レベルだが、全体最適は不得意 「現場に全体像を見せる」=①「全体最適」のために何をすればよいかを示す ②その成果を測定できるモノサシを渡す 「ビッグウォレット戦略」の利益の源泉は、「大きな財布」で「全体最適」を追求する 尊重=自分がなれ親しんだものが「ふつう」→互いに「傾聴」し、全体での「考え方、やりかた」を創っていく チームワーク=全員が全体を見渡して、自分にできる最善を尽くす 勇気=①正しいと信じることを声に出して言う勇気 ②実行に移す勇気 ③失敗を認めて学ぶ勇気 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆目次◆ 第1章「ビッグ・ウォレット戦略」=「ウィン-ウィン」モデル 第2章 コカ・コーラのビジネスモデルの強みと弱み 第3章 コカ・コーラが実現した「ビッグ・ウォレット戦略」 第4章「協業利益」の見極め―成功要件1 第5章 経済合理性に基づく意思決定基準―成功要件2 第6章「割り勘会計」のルール―成功要件3 第7章 独立した機能統合組織―成功要件4 第8章 全体と個のウィン-ウィン関係―成功要件5 第9章「ビッグ・ウォレット戦略」の限界 第10章「ビッグ・ウォレット戦略」の可能性 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆マインドマップ◆ http://image01.wiki.livedoor.jp/f/2/fujiit0202/898f6037b871b62e.png
Posted by
著者は古谷氏である。 早稲田政経ーハザマーコカコーラー独立というような経歴で、コカコーラにおいて 本書籍のタイトルある戦略策定・実行において、財務の立場で寄与した人物である。 本書の内容は、一言で言えば、 ■TOC(制約理論)を資本関係のない企業間同士で行う事 以上である。...
著者は古谷氏である。 早稲田政経ーハザマーコカコーラー独立というような経歴で、コカコーラにおいて 本書籍のタイトルある戦略策定・実行において、財務の立場で寄与した人物である。 本書の内容は、一言で言えば、 ■TOC(制約理論)を資本関係のない企業間同士で行う事 以上である。 TOCつまり全体最適を自社工場内に適用するだけでなく、さらに範囲を 広げて適用したケース・スタディと言える。 ここで、分かると思うが全体最適というのは部分最適を辞めるという事だ。 つまり、ここでの部分最適というのは「個別企業の最適戦略」を辞めるという事。 簡単にいうと、ある個別企業の実質的(現実的ではない)利益を多少減らしても 全体で利益が(今以上に)出ればOKって事。 そう、言うは易し行うは難しであり、これを実行したケースの説明は貴重だ。 そして、実行する際に重要な事は、 1.協業利益を見極める 2.経済合理性に基づく意志決定基準の策定 3.利益配分ルールの策定 4.独立した機能統合組織の形成 5.全体のウィンーウィン関係の形成 以上の5つのポイントだ。 詳細については、本書を読んで頂くことにして、なかなか面白い内容にはなっている と個人的には思う。しかし、コカコーラだから出来たようなものだろうな(笑) なかなか、現実的には難しいのも事実。 ただ、難しいからこそ、実行出来た時の破壊力は凄まじいだろう。 以上
Posted by
ビッグウォレット戦略とは、物事を大きく考えることであると理解しました。ただ、「全体最適」と「部分最適」は矛盾するもので、全体最適を推し進めていかなくては行けない経営層としては、部分最適がうまくいかず、従業員の士気が下がってしまうことだけは避けたい。本書はそれに対するソリューション...
ビッグウォレット戦略とは、物事を大きく考えることであると理解しました。ただ、「全体最適」と「部分最適」は矛盾するもので、全体最適を推し進めていかなくては行けない経営層としては、部分最適がうまくいかず、従業員の士気が下がってしまうことだけは避けたい。本書はそれに対するソリューションにもきちんと書かれていて、非常に参考になりました。
Posted by
- 1