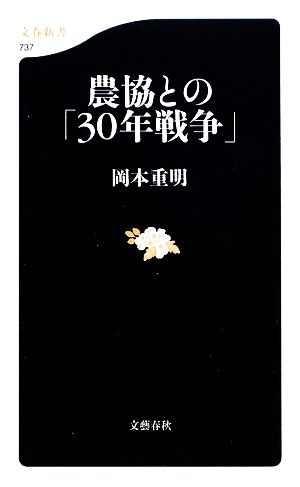農協との「30年戦争」 の商品レビュー
私が愛知県豊橋市にいて、植物の組織培養の仕事をしていた時に、よく話にきた岡本重明がいた。好奇心が旺盛で、そのうえ変人だと思った。変人とはバイタリティにあふれ、納得するまで追求するという正直者なのだ。そして、久しぶりに連絡をとって、実に30余年ぶりにあった。 30余年前の青年時代の...
私が愛知県豊橋市にいて、植物の組織培養の仕事をしていた時に、よく話にきた岡本重明がいた。好奇心が旺盛で、そのうえ変人だと思った。変人とはバイタリティにあふれ、納得するまで追求するという正直者なのだ。そして、久しぶりに連絡をとって、実に30余年ぶりにあった。 30余年前の青年時代の凄みを相変わらず持っていたが、やはりおジイになっていた。オジイになったねと言ったら、お互い様だという。確かに。相変わらず、声はでかく、毒舌は変わっていない。 「枠をはみ出た農家」というのがあり、岡本重明はまさにそのイメージにぴったりだ。 とにかく正直であることを貫抜く。簡単にいえば、不器用なのだ。 自分の思っていることを貫くことは、他人のためになると信じてやまない。 だから、「農協との30年戦争」という本まで出してしまうのだ。 岡本重明は、愛知県田原市で営農している。現在は、自分の田んぼと代行している田んぼで、合わせて160ヘクタールの稲を作っている。JA愛知みなみは、日本で一番大きい農協である。相手に不足はないのだ。 では、なぜ農協と戦うのか? 著者は、農協とは、数えきれないくらい衝突し、嫌がらせを受け、悔しい思いをしてきた。農業は、危機に瀕している。後継者不足、資材の高騰、農産物の価格の不安定性と下落。そういう中で、農業を復興し、再生しようとするが、農協は「ムラの掟」でがんじがらめにして、補助金に誘導することによって、農協の利益を取ろうとする。自立的な志向を踏みつけて、補助金付けにする。 農協が自立的な農家を助け、それが農業の発展に寄与する組織を目指しておれば、存在意義はある。 経営が悪化した農家に対し、農協は支援するどころか、貸し剥がしにかかる。「農業をやめて、土地をうって借金を返しなさい」と説得する。販路を拡大して経営を立て直す手法を指導する訳でなく、ただ返せと迫られる。農協の組合員になると、資材の購入が買掛ができる。しかし、実は一般の民間の資材屋さんより高い。補助金の窓口は、農協だ。農業機械に補助金が出るが、結局民間より高い。 どうも、自分たちの職員を養うことが最優先なのだ。田舎だから、摩擦を起こしたくないので、いやいや農協に属さざるを得ないのだ。農家の作った農産物の販売も農協を通して行う。がんじがらめにされているのだ。農協を脱会することは、和を乱す人であり、変人と言われ、勇気がいるのだ。村の掟があり、村八分の状況になる。子供達にもそれが及ぶ。 農業を始めた時には、キクを作り、その後イチゴを作った。2000坪ほどイチゴを作っていた。田原農協で変人と言われていた。それは、農業生産法人新鮮組を設立後、稲作規模拡大のために、トラクター、田植え機、乾燥機、籾摺り機など、2年間で2000万円ほど設備投資をした。購入してからドイツ製のトラクターの動きがおかしくなった。オイル交換する際にトラブルがあった。田原農協にそのことを言ったら、なんら対応しない状態が続き、同じようにドイツ製トラクターを扱っている渥美農協で修繕した。そこから、関係が悪くなっていた。田原農協の担当者は話し合いにも応じない状況だった。一方で、渥美農協からは、稲作の代行を頼まれて、稲作の規模を拡大して行った。農協が合併して、田原農協の出身者が組合長になることで、結果として稲作の代行が減った。当時の農協役員は「稲刈りは誰でもできるから、岡本に食べさす必要はない」と言い放った。しかし、農協ではうまくできず、クレームが多くなり、結局 稲作代行をすることになった。 農協なんていらない。補助金なんていらない。農家を潰す農協とは徹底して闘う。 消費者と市場を意識して、消費者の求めるものを作り、販売力をつけることによって、経営力をつけて、農家として自立した道を「新鮮組」として、取り組んでいくのだ。 私は、この本を読みながら、「常在戦場」という言葉を思い出した。農業をするというのは、自然条件、土地の環境条件、そしてその周りの人たち、の中で、自分として信じていることを実現するのは闘う必要がある。そのことが、強い想いからきているのだ。現在稲作は160ヘクタールを営農し、多くの人から委託を受けている。そして、田原市の市会議員にもなっている。変人と言われながらも、人望があることを感じさせる。新鮮組。農民であっても、義のためにたたかうサムライなのだ。
Posted by
※賛否ありな意見。多くの人は野菜作りや酪農で手一杯で販路まで拡大できないはず。。 ●農協部会は談合組織。生産量が少ない農家は独自販路は難しい。全て買い取り一定の品質で出荷が農協。資材の共同購入も。 ●経済連と農協の中抜き。高い輸送コスト、つぶれないのにコミッション、ブランド段ボ...
※賛否ありな意見。多くの人は野菜作りや酪農で手一杯で販路まで拡大できないはず。。 ●農協部会は談合組織。生産量が少ない農家は独自販路は難しい。全て買い取り一定の品質で出荷が農協。資材の共同購入も。 ●経済連と農協の中抜き。高い輸送コスト、つぶれないのにコミッション、ブランド段ボール ●ふるさと弁当構想、米一俵(60kg)1万円だが、おにぎり1400個分だと、14万円。この付加価値を取り戻す。
Posted by
地元、愛知県の農家が書かれたものだったので手に取ってみたが、予想以上に具体的な話が書かれていて勉強になった。組合長が経済連等の連合会の役員を兼ねるのは利益相反になることなど、これだけコンプライアンスが喧しくなった社会で未だに問題とされないのはどうしてなのだろうか?
Posted by
2009年の本なので、現在のJA、農業をめぐる状況はまた変化しているだろうとは思う。願わくばいい方向に変化していて欲しい。ここに書かれている、筆者の数々の体験はほんとに酷いものだと言わざるを得ない。自分の経験から、JAの組織、農家のスタンスも県によってそれぞれ違いがあるように思う...
2009年の本なので、現在のJA、農業をめぐる状況はまた変化しているだろうとは思う。願わくばいい方向に変化していて欲しい。ここに書かれている、筆者の数々の体験はほんとに酷いものだと言わざるを得ない。自分の経験から、JAの組織、農家のスタンスも県によってそれぞれ違いがあるように思う。それでも、本書が訴えている事例は嘘ではないだろうし、だとすれば、これはやはり結局、JAという組織の構造および体質の問題だと捉えるべきだと思う。 JAに限らず、組織の存在期間が長くなり、長大化すれば、機能の効率低下がおき、本来の目的が後回しになり、組織の維持のためにそのエネルギーが使われることが多くなる。 昔、役所にワープロが導入され始めた時(パソコン以前の話)、それまで清書を担当していた人の仕事がなくなるからそれは困るという話が持ち上がったというが、要はそんなことである。 なんでもかんでも競争原理を持ち込んで、弱者は救済されることもなく死滅すればいいということでもないと思う。ルールの中でフェアな競争が行われる、それがあるべき姿であり、法や行政はその環境を作り、維持する役割を果たしてくれればいい。 高齢化問題に全面的な解決策はないし、新規就農者数は僅ながら増加しているという統計もあるようではあるが、しかし全体の数から見ればまだまだ小さい数字で絶対数は足りないと聞く。 家族構成が縮小し、食育の必要性が叫ばれたり、一人一人の食への意識が下がらないような対策も必要と思う。 都市での企業活動が支える日本の国際競争力も大切。だがその労働力を支える食の環境はこのままで大丈夫だろうかと心配で仕方ない。コスト競争の中で、生産と流通の効率に重点が置かれ、懸命に続けられる企業努力はやむなしだと言うしかないが、素性のあやしい原料や、なんとか消費者に選ばれるために使われる様々な添加物。古い言葉で言えば複合汚染になるが、世代を超えての安全確認は今や現代を生きる我々自身が己の身体で実験を続けている最中だ。 本書は、この国の農業のロードマップがないことが問題だと指摘している。個々に努力して成功している農業者、企業の数はどんどん増えていっていると思う。しかし、JAという組織も含め、この国の農業のあるべき姿とそれに向かって進むべき道は本当に議論され、示されているか。もはや時間は残されていないと思う。
Posted by
農協イコール悪というのは言い過ぎかもしれないが、この著作通りの対応であったら最悪だと言われても仕方がない。 この本を読んで思ったのが、予約販売、共同購入のスケールメリットをきちんと活かせているか。販売力を強化し、出荷してくれたものを大量に高く売ることが必要である。 そのほかにも迅...
農協イコール悪というのは言い過ぎかもしれないが、この著作通りの対応であったら最悪だと言われても仕方がない。 この本を読んで思ったのが、予約販売、共同購入のスケールメリットをきちんと活かせているか。販売力を強化し、出荷してくれたものを大量に高く売ることが必要である。 そのほかにも迅速に物事に対応することは大切だし、農家を一企業だと思って作業委託しても問題はないと思う。 何はともあれ、勉強になることは多くあった。
Posted by
2010年出版の本、先日、地元の古本屋で出会いました。 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)真っ盛りですので、タイムリーですかね。 “農協をはじめとする農業団体が抱える構造的問題点を詳らかにしていく” とだけあって、これでもかという位に“農協”への批判が続きます。 といっ...
2010年出版の本、先日、地元の古本屋で出会いました。 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)真っ盛りですので、タイムリーですかね。 “農協をはじめとする農業団体が抱える構造的問題点を詳らかにしていく” とだけあって、これでもかという位に“農協”への批判が続きます。 といっても決して感情的な怒りを垂れ流しているのではなく、 論理的にまとめられていて、非常に理解しやすい内容と感じました。 “販路の構築をきちんと行えば、確実に利益の出る農場経営ができる” ビジネス的な感覚から言うと、至極まっとうな内容と思いますが、 今の農協はそれができていないとの、ことなのでしょうか。 確かに、テレビなどのCMを見ているだけでは、 金融業を生業としているのかな、くらいのイメージしかないです。 “(減反政策の結果)日本のコメ農家の競争力は急落し、 米では食っていけない農家があっという間に増えてしまった。” これが事実だとすると、本末転倒だよなぁ、、と。 個人的には“競争がない”のは“衰退”と同義だと思っています、 その“農業が成長する機会”を奪っているのが、 本来は先頭で振興していくべき農協だとすれば、うーむ。。 “農協の常識はビジネスの非常識” とまぁ、なかなか手厳しいことが書かれているのですが、 これは是非、農協側の意見と並べて比較してみたいところです。 “農協に頼らなくても農業はできる。多くの農家が薄々感じ始めている” 実家に戻るとはいくばくかの田んぼがあるため、 それなりに気になります、今後どうしていくのかも含め。 といっても、収穫物を売っているとかではなく、 あくまで土地として保持し、他人に貸しているだけらしいですが。 一度状況を把握しておかないと、かもです、、閑話休題。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・農業の悪い面を描きつつ、農家が自主的に経営に乗り出すことの重要性が分かりやすく描かれている。内容は専門的というよりは一般的であったが、とにかく分かりやすいので、ちょっとした隙間時間にも読めるところが好印象。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
うううう~、複雑な気持ちである。 最初読み始めて感じたのが、「なんじゃ、この人、世の中に対してものすごく“bitter”、怒りを持ってるんじゃないか」という印象。 ものすごく実力ある人だと思う。 後半のイラン人による規格外キャベツの商品化や身体障がい者による水耕栽培のNPOの話、東南アジアに目を向けた輸出の話、どれも新しく、自由で独創的なところに着目していて面白い。 そこが複雑な気持ちになる。 すごく面白いことをされているのに、後半に入るまでの前半部分(農協とのエピソードが中心となる部分)、は読んでいてなんだかあまり気分が良くなかった。 でも逆に自分の周りのすごい人も、確かに一見、一般社会や一般常識に対する怒りをどこか持っていて、最初会ったら理解されず印象悪かったりするんだろうなぁ、と思いつつ… だから多分この筆者は本当にすごい人なんだろう、と思う。 けれども同時に私も、人や組織の良くないところを口にするときは、よほど気を付けたい、そう思いました(というか言わなくてよいのが一番だけれども)
Posted by
TPPにも揺れる農業問題の本質を記された一冊。著者の実体験に基づいているため、説得力がある。 戦後、農地解放を行ったものの、突然、一国一城の主となった農家に農業経営はできないだろうと見透かしたように、飴を与えながら搾取を繰り返してきた政府、農協には憤りを感じる。 そのことが、ひい...
TPPにも揺れる農業問題の本質を記された一冊。著者の実体験に基づいているため、説得力がある。 戦後、農地解放を行ったものの、突然、一国一城の主となった農家に農業経営はできないだろうと見透かしたように、飴を与えながら搾取を繰り返してきた政府、農協には憤りを感じる。 そのことが、ひいては高い農産物となり、消費者に膨大な損害を与えてきたならさらに怒りを感じる。 現在も農家に対してバラマキが実施されているが、政府には農業のあるべき姿を示し、国益にかなう農業政策を実施してほしいと願うばかりである。
Posted by
著者は農協から徹底的に排斥、目の敵にされるも負けずに立ち上がったつわもの。今や年商1億を計上する専業農家の大社長。農地解放により農場主になれたはずの農家が、現実には農協や土地改良区に縛られ自由な経営さえもできない実情を訴える。農業生産を振興し農家を育成するはずの農協が自分たちの組...
著者は農協から徹底的に排斥、目の敵にされるも負けずに立ち上がったつわもの。今や年商1億を計上する専業農家の大社長。農地解放により農場主になれたはずの農家が、現実には農協や土地改良区に縛られ自由な経営さえもできない実情を訴える。農業生産を振興し農家を育成するはずの農協が自分たちの組織を守るだけのために血道をあげる。トップである農協組合長は利益相反する取引先の取締役を務め私腹を肥やす。職員もプロとしての意識が欠け能力は極めて低い。融資といえば計画書の提出もさせず、ただ人間関係のみによって行われる。横領などの不祥事も日常茶飯。腐りきった農協組織を徹底的に指弾。真っ直ぐな正論が清々しい。日本農業再生のための貴重な至言の書である。
Posted by