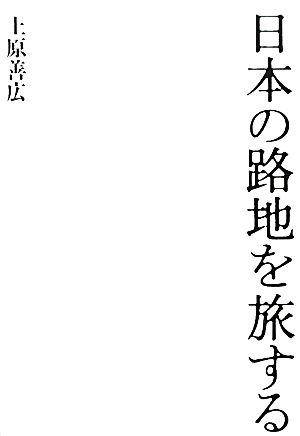日本の路地を旅する の商品レビュー
2021/10/01 大阪出身昭和55年生まれ、小学校のころ同和の特別授業があった。 人間って教科書もなんとなく記憶にある。 両親共に関西出身、母親が〇〇やから家安いわなどと、、、言った記憶もあり、わたし世代だと、どこどこは部落と知っている程度に差別はあった。私自身は、ただ住...
2021/10/01 大阪出身昭和55年生まれ、小学校のころ同和の特別授業があった。 人間って教科書もなんとなく記憶にある。 両親共に関西出身、母親が〇〇やから家安いわなどと、、、言った記憶もあり、わたし世代だと、どこどこは部落と知っている程度に差別はあった。私自身は、ただ住んでいるだけでこういう言われをしてしまうなら、正直なところ、その土地にはあえて住みたくないなと思っている。あえて人には言ったりしないが、これを差別というならそうだと思う。 昭和50年、埼玉育ち、両親は福島、熊本の40代の夫は部落というとなにそれ、穢多非人もなにそれただ無知なだけかと思う。
Posted by
隠されてることでもあるので実質的なことはほとんど何も知らなかった。寝た子を起こすなということもあるけど、知ることも大切かも知れない。
Posted by
路地とは、所謂「非差別エリア」を指す言葉で、その言葉を生んだのは和歌山県新宮市の路地出身の作家故中上健次。著者は大阪の同和地区である更池の出身で、その「路地」という表現をいたく気に入り使い、以来数十年の日本各地に点在する路地を巡る旅を淡々と繰り返している。本書は旅をしつつ自身の半...
路地とは、所謂「非差別エリア」を指す言葉で、その言葉を生んだのは和歌山県新宮市の路地出身の作家故中上健次。著者は大阪の同和地区である更池の出身で、その「路地」という表現をいたく気に入り使い、以来数十年の日本各地に点在する路地を巡る旅を淡々と繰り返している。本書は旅をしつつ自身の半生を語る。旅をして知るのは、地域によって路地での暮らしとその生計は地域性がある。例えば東北地方には存在しないと思っていた著者は本州最北端の青森にも路地を存在することを知る。夏は太鼓を作り、冬は動物の剥製作りで生計を立てている現実を知る。剥製師は「テンで3万・犬で7,8万・熊で15万で注文を受ける」と言う。続けて「弟子になりたければ150万で全てのノウハウを教える。太鼓は1ヶ月で100万、剥製は10回で50万。これで基本は全て含まれていて、開業できる」と言う。「生きた民俗学」を学んだ気がするロードムービー的ルポルタージュ。
Posted by
「日本の路地を旅する」読んでみました。 出目や生業で穢多、番太、非人と呼ばれた人と雑種賎民が部落民で、この本では多種多様な人達の区別を行わずに、路地出身の筆者が見たもの感じたことが、淡々と素直に書かれていていい本ですね。 路地と私の生活は「玄人と素人」や「彼岸と此岸」に近いような...
「日本の路地を旅する」読んでみました。 出目や生業で穢多、番太、非人と呼ばれた人と雑種賎民が部落民で、この本では多種多様な人達の区別を行わずに、路地出身の筆者が見たもの感じたことが、淡々と素直に書かれていていい本ですね。 路地と私の生活は「玄人と素人」や「彼岸と此岸」に近いような、漠然としていても明確な境界があり、案外、ワンウェイで行けるけど戻れない感じがします。もう少し勉強せねば・・・
Posted by
被差別民について深い考察や指摘があるわけではない。どちらかというと、路地(被差別部落)の痕跡をたずね、自分の半生を回顧することで自分自身をたぐり寄せる旅の、むしろモノローグに近い。 だからといって『浅い』かというとそういうことではなく、やはり差別は『構造』であることをあらためて...
被差別民について深い考察や指摘があるわけではない。どちらかというと、路地(被差別部落)の痕跡をたずね、自分の半生を回顧することで自分自身をたぐり寄せる旅の、むしろモノローグに近い。 だからといって『浅い』かというとそういうことではなく、やはり差別は『構造』であることをあらためて考えさせられた。差別自体は希薄になり若者たちはほとんど気にも留めない現代でも、構造自体は残っており、きっと折にふれ浮上してくるのであろう。
Posted by
部落についてより深く理解したいといった向きには向いていないかもしれないが、日本全国を歩き、各地の部落の人々と触れ合ったリアルな記録の臨場感は凄い。 作者が書いている通り、結局は作者自身の旅なのだが、部落を知らない人間にも確実に伝わる文章だと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
路地という言葉が被差別部落を指す事を知ったのは、実はこの本を買った後、中上健次の「千年の愉楽」を読んでからだった。普通の紀行文かと思っていたが、全く違う。しかも著者本人が大阪の「路地」出身者ということで、今まで読んだ同和問題に関する多くの本とは全く違う。外部の人間、学者とか作家が取材したものにある、差別に関する悲しみや憎しみ、怒り、あるいは差別の増幅を恐れるがゆえの遠慮や歯切れの悪さがない。冷静に、淡々と聞き取り、記述していく。おそらく取材を受ける側も「同じ側の人間」と「外部から来た人間」とでは話す内容も違う事は想像できる。地域によって、混住が進んで路地が消えつつあるところもあれば、今なお路地として存在するところもあるが、総じて高齢化が進み、消えていくのが趨勢のようだ。未だ結婚に関しては根強い差別があるというが、それもあと数世代で消えていくだろう。職業差別に関しては食肉、皮革、演芸などが路地の者の仕事であったが、それも後継者不足と他からの参入で薄まりつつあるようだ。しかし本書はそうした「同和問題のテキスト」に留まらず、著者の私小説のような要素を大いに含んでいる。大阪の食肉業者に生まれ、幼い頃に路地を出た著者は、一通りの貧しさや暴力も経験したものの、さほど差別を受けた実感はなく、路地には郷愁を感じている立場であり、路地の出であることを隠そうとはしない。しかし罪を犯して逃げるように沖縄に移り住んだ兄を訪ねるくだりには、はじめて彼の苦悩が立ち現れてくる。もちろんその犯罪は路地故に起きたものとは言えないが、彼は人生の一部として考えると無関係でもないと感じているように思える。 とにかく、今まで読んだことのない、客観的かつ個人的な、不思議なスタンスのルポルタージュであった。
Posted by
中上好きなので、手に取る。 部落=路地のもう少し踏み込んだ内容を期待したが、 すでに時代が違うのか。 ただし、すべてに足を運び、目で見て、書いていることは (当たり前だが)信頼に足るし、愛情も感じる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
被差別部落出身のライターによるルポルタージュ。被差別部落って言葉自体がもう差別だな。被差別部落については学校で習った以上の知識がない為、初めて知ることや意外な事実が多かった。誰かが必ずやらなければならない重要な、時に高度な技術も要求される仕事が忌まれたり畏れられたりするものでもあるというのは分かるが、なぜそこに差別が必要となるのかがあまり理解できない。学校では『下には下を作ることで四民制度の下層を納得させる』とか聞いたが、それだけではないような気もする。じゃあ何だと問われても説明出来ないのだが。こういう話は誰とでも出来ることではないので、未消化な感じが残る。興味半分で触れられる話じゃないが、興味半分でしか触れることを許されないような。
Posted by
被差別部落の人たちは、彼らの従事する仕事を通じて、あるいは水平社の運動により人知れず全国にあまねく人的繋がりがあることを知った。いっぽうでは、この作品を読むかぎり、若い世代の人たちの部落への偏見は失くなりつつあるのかなという気がした。このことは、学校教育の結果なのかそれとも親の世...
被差別部落の人たちは、彼らの従事する仕事を通じて、あるいは水平社の運動により人知れず全国にあまねく人的繋がりがあることを知った。いっぽうでは、この作品を読むかぎり、若い世代の人たちの部落への偏見は失くなりつつあるのかなという気がした。このことは、学校教育の結果なのかそれとも親の世代が子どもたちにこの話題を敢えて話さなくなったことによるものなのか。はたまた、宅地造成開発によって路地そのものが消滅してしまったことによるものなのか。今は、所得格差の問題の方が大きいのだろうか。
Posted by