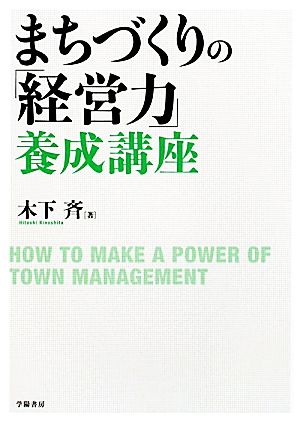まちづくりの「経営力」養成講座 の商品レビュー
・まちを1つの会社として考える ・継続性が最重要 ☆CGC(common ground community)→タイムズスクエアのホームレス自立支援 ☆長崎市浜んまち商店街振興組合連合会→商店街独自の合同決済事業や駐車場情報管理システム事業などにより各店舗の経営効率改善 : 電子決...
・まちを1つの会社として考える ・継続性が最重要 ☆CGC(common ground community)→タイムズスクエアのホームレス自立支援 ☆長崎市浜んまち商店街振興組合連合会→商店街独自の合同決済事業や駐車場情報管理システム事業などにより各店舗の経営効率改善 : 電子決済手段の合理化 ・戦略とは「いかにして現状から目標に近づくか」という「シナリオ」 →目標から逆算して今、何をしなければならないのかを明確にする必要あり →継続的な成長を可能にする希望の道と、いざという時の逃げ道を持つことに役立つ、矛と盾のような存在 →①環境分析(顧客、競合、供給、規制、新規参入補完財)、②組織分析、③目標設定、④戦略立案の4STEP ①環境分析 ・顧客を絞ることで具体的な検討ができるようになる ・無用に競合せず、互いに棲み分け、連携する道が良い →近い事業を提供する民間団体や、全く同じようなサービスを提供する行政関連機関、もしくは互いに協調できる団体がないか ☆熊本城逃しマネジメント →地方都市の中心地のビルに入居するテナントと個別に契約し、まとめて廃棄物処理を依頼する事業 →民間出資のみで経営 ☆ウェストフィールド・コーポレーション(DWC : Downtown Westfield Corporation) →都市の空洞化解決のために設立され、ビジネスファミリー層に絞ったまちづくりを実施し成功 ☆株式会社アモールトーワ →東和銀座商店街の有志で設立され、地域のためにできることを行う会社として位置付け、収益事業から得られる収益をもとに地域貢献事業に投資。仕入れルートや従業員を地域から活用しているため安定的な調達が可能。 ☆アトム通貨 →実行委員会が公認した地域貢献や環境貢献につながるプロジェクトに参加すると通貨を受け取り、地元商店街で使える ☆帯広市「北の屋台」 →1年中楽しめる屋台村 →加熱調理されたメニューに限定される既存の屋台以上に提供できる品物を増やすため、2槽式洗い場を整備するなどの「半屋内型屋台」という形態を生み出し、食品衛生法への規制対応を行なっている ・地域活性化では、失敗と解決を繰り返しながら行う「創発型」の戦略形成が有効 ・情報データベース →「統計局ホームページ」総務省 →政府統計の総合窓口 ②組織分析 ・経営資源→ヒト(人材)、モノ(設備)、カネ(資金)、情報 ③目標設定 理解と意思を組み合わせて目標を立てる 短期目標→1-2年、中長期目標→3-5年 ☆TSA(Times Square Alliance)→治安維持 ④戦略立案 ・選択と集中により、限られた資源配分を効果的に行う必要がある ・基本戦略、競争戦略(製品やサービスでの差別化、補助的機能での差別化、ブランドでの差別化、価格での差別化) ☆黒壁 ・株式会社黒壁→観光事業 ・株式会社新長浜計画→不動産取得、管理・運営 ・黒壁グループ協議会→周辺店舗と組織 ・水平展開戦略→直営支部設立方式、フランチャイズ方式、種まき方式 ☆KaBOOM!→公園整備においてノウハウを種まき方式の水平展開で行う ☆北海道グリーンファンド ☆丸亀町商店街 ☆株式会社出石まちづくり公社 第三セクター ・地域連携プラットフォーム事業 ☆有限責任事業組合 市街地経営研究機構(UMRI) ☆プラットフォームサービス株式会社 →非営利株式会社で、資金調達のために普通株の他に優先株を発行 ・資産 流動資産、固定資産、繰延資産 ・費用 固定費、変動費 →初期には固定費を低減させ、変動費型にする方が早期に黒字化を図れる ・プロマネにおいて 時間(トキ)、作業(コト)、役割分担(ヒト) ・まちづくりプロジェクト5ヶ条 ①リーダーとマネージャーを置く ②納得できるプロジェクト設計 ③違和感・不安感の共有 ④変更を積極的に取り入れる ⑤プロジェクトを止める勇気 ・ガントチャート ・マイクロ・マネジメント ・AIAエリアイノベーションアライアンス
Posted by
地域活性化に繋がる、地域の空間や食材、人材などの資源を活用した事業を、きっちりビジネスベースで考えましょう、という本。「まちづくり」というキーワードだと、よりソーシャルなディメンションを想像していたが、そのようなものはアメリカ等の事例で示されるのみ。
Posted by
まちづくりに経営の力を入れることが有効ということで、経営についての解説をまちづくりを事例に行っている。 質より量で、たくさんの事業を行うことが大切。 4~5人が核となって進めるのが適切。 リーダーとマネージャーが必要で、役割分担がある。 まちづくり機能の競合。
Posted by
内容は言ってしまえば経営する際の考え方、企業とかのhow toに近いのかな? 書かれていることももっともだし、実例も書かれていていい刺激になります。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
まちづくりというフィールドにおいて、経営の発想から様々な道筋方法を述べた本。まちづくりに携わる人はもちろんそうではない人にとってもロジカルシンキング、経営の基礎として参考になるのでは。 何をすべきかわからない→論理的志向 因果関係を整理 構造化 どう実行すべきかわからない→戦略 現状分析・目標設定 実行する人がいない→組織 組織設計 機能分担 予算がない→財務・会計 資金調達 適正投資 時期が遅れる→プロジェクトマネジメント プロジェクト管理 事業評価 ・複数の選択肢を整理するプロスアンドコンス ・ピラミッド構造のこつ ①個々のボックスに書いた内容は、それより下にあるボックスの内容を要約していること ②各グループ内の内容は常に同じ種類 ・戦略を立てるための4step ①環境分析②組織分析③目標設定④戦略立案 ・他者が行う業務をどうコントロールするか 事業に関する契約を締結しておく 提携先の代替案を検討しておく ・目標の種類 ①定性的かつ中長期的の先を見据えたビジョン型の目標 ②現実的かつ達成可能な明確な目標 ・戦略の役割 ①組織全体の経営戦略 ②個別事業の事業戦略 戦略とはやめることを決めること ・基本戦略:事業の構造決定 誰に提供するか 対象の決定 どのような事業を行うか 商品・サービス設定 自分たちが何を担うのか 担当領域 ・競争戦略:差別化の4つのポイント ①製品やサービスでの差別化 ②補助的昨日での差別化 ③ブランドでの差別化 ④価格での差別化 ・メンバーのモチベーションをあげること ①組織が推進する事業の地域における価値、意義 ②個人の目的・目標と組織業務内容のすり合わせ ・組織の巻き込み力を強化すること 関係者へコンタクトをとり、関係性を維持していくこと。 ・トキ×コト×ヒト=プロジェクト 時間×作業×役割分担 ・まちづくりプロジェクト5カ条 ①リーダーとマネージャーを置く ②納得できるプロジェクト設計 ③違和感・不安感の共有 ④変更を積極的に取り入れる ⑤プロジェクトを止める勇気 ・力と情熱のリーダー、管理のできるマネージャー ・納得できるプロジェクト設計 計画を立てる人と実施することが一致していることが理想 ・違和感、不安感の共有化 これは非常に重要。 ・一貫性は持ちつつ、変更を取り入れることが非常に重要 ・
Posted by
「まちづくり」とタイトルは書いていますが、 事業経営に全般について全体を概観するための 良書だと思います。 物販、サービス提供、組織運営、管理会計など 専門的なことについての言及は多くありませんが、 「まちづくり」の主語を、 「会社経営は」とか「NPO法人運営は」と読みかえれ...
「まちづくり」とタイトルは書いていますが、 事業経営に全般について全体を概観するための 良書だと思います。 物販、サービス提供、組織運営、管理会計など 専門的なことについての言及は多くありませんが、 「まちづくり」の主語を、 「会社経営は」とか「NPO法人運営は」と読みかえれば、 いろいろな立場の方が読める本だと思います。 個人的には徳島県・上勝町の「ツマモノ」販売事業がすごく気に入りました。
Posted by
この本の第一章は「ロジカルシンキング」。 これは経営というか仕事の基本。 この本はそんなところから始まるのである。 今までのまちづくりと言うものが いかにずさんだったかがうかがい知れる。 私がこの本を読んだのには しっかりとした理由がある。 それはまた次の機会にでも。。。
Posted by
うちの職場のいかにも頭のよい感じの女性職員からの紹介。 自分は、友人からの紹介本は必ず読むことにしている。 この本を読んで、まちづくり会社という形態が、利益をあげつつ継続性を重視する手法として重要なことがよく理解できた。 それを踏まえて、まちづくりに関して思い...
うちの職場のいかにも頭のよい感じの女性職員からの紹介。 自分は、友人からの紹介本は必ず読むことにしている。 この本を読んで、まちづくり会社という形態が、利益をあげつつ継続性を重視する手法として重要なことがよく理解できた。 それを踏まえて、まちづくりに関して思いついたアイディア。 ①まちづくりについては、NPO、LLC、LLPなど様々な組織形態を用いているが、例えば、まちづくり協同組合のようなそれに特化した組織形態を生み出す必要性はないのか。 戦前に住宅組合という制度があったが、互助的でありながら、税制特例もあるような組合形態を追求してみたい。 ②被災地の復興にあたっては、人材支援のようなソフトのまちづくり会社のほかに、実際の事業をまるごと市町村から受託するまちづくり会社が考えられないか。 ソフトの支援も重要だが、実際に、面的な土木工事、建築工事を発注したことのない市町村にとってみると、ぎりぎりの採算で、信用のおける会社を設立し、全国からスタッフをあつめて事業受託するようなシステムも考えることが必要ではないのか。 ③ごみの一括処理とか、クレジットカードの一括処理、さらには例にはあがっていないが電気の一括購入など、一定の地域の商業者、事業者が共同して購入、支払いすることによって、コストダウン、収益確保ができるビジネスモデルがあるのではないか。 この本は、かなり実務家的なガイドブックだが、実例も豊富で、まちづくりを巡る各種組織の新しい動きが理解できて有益。
Posted by
まちづくりのプロ@shoutengai が書き上げた、まちづくりの教科書。これに沿って取り組むテーマを真剣に探したいと思います。その時はお世話になりますね、木下君。
Posted by
経営学を少しでも勉強したことがある人間からしたらアタリマエのことが書いてあるばかりだが、現場にはこういった知見がやはり不足しているのかもしれない。そこまで異分野の内容でもないと思うが、経営とまちづくりはまだ離れたものなのかもしれない。こういう橋渡しに結構価値があるのだろう。
Posted by
- 1
- 2