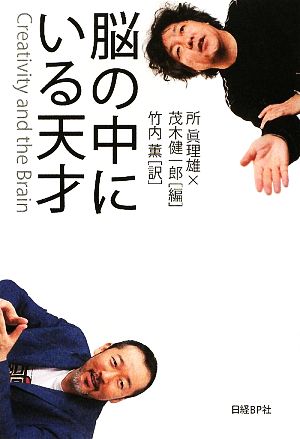脳の中にいる天才 の商品レビュー
(2009/11/14) まるでパネルディスカッションのように、ひとつのテーマを学者たちが楽しく説明してくれる。 赤ちゃんの認識力やら、言葉を発するプロセスやら、自由な発想を誘発する帽子やら、、 子育ての参考にもなろうという、楽しい本です。 はじめに 1章 脳の中にいる天才 (...
(2009/11/14) まるでパネルディスカッションのように、ひとつのテーマを学者たちが楽しく説明してくれる。 赤ちゃんの認識力やら、言葉を発するプロセスやら、自由な発想を誘発する帽子やら、、 子育ての参考にもなろうという、楽しい本です。 はじめに 1章 脳の中にいる天才 (アラン・スナイダー) 2章 脳の不思議な3秒ルール (エルンスト・ペッペル) 3章 アキレス腱と創造性 (北野宏明) 4章 赤ちゃんは創造的か? (フィリップ・ロシャ) 5章 ベイビー・トーク (正高信男) 6章 ジキル博士とハイド氏とクオリア (茂木健一郎) 7章 天才は孤独ではない (ルック・スティールス) 訳者あとがき
Posted by
クリエイティブな脳(創造性)について、色々な分野の世界的な専門家たちによる講義集。 寄せ集めなので統一感を感じられないけど、それなりに浅く広く色んな分野をさらっと読めます。
Posted by
創造性をキーワードにして、各分野の最前線で活躍する研究者が 自分の研究を語っている。 ヨーロッパの研究会で行われた講演の書き起こしを和訳したもの。 基本的な用語や背景に対して、もう少し説明がほしいという部分が いくつかあった。 しかし、未知の分野の研究を知る面白さを感じることがで...
創造性をキーワードにして、各分野の最前線で活躍する研究者が 自分の研究を語っている。 ヨーロッパの研究会で行われた講演の書き起こしを和訳したもの。 基本的な用語や背景に対して、もう少し説明がほしいという部分が いくつかあった。 しかし、未知の分野の研究を知る面白さを感じることができた。
Posted by
脳の役割の中でも、創造性に注目して、脳の役割について科学的に論じている。前半のわかりやすい内容から、後半の専門的な内容まで様々な内容が論じられている。 学習速度が速い児童が将来も創造的な人物になるとは限らない。 学術的功績を挙げた人の多くは、学校での成績は平均程度。 「普通では...
脳の役割の中でも、創造性に注目して、脳の役割について科学的に論じている。前半のわかりやすい内容から、後半の専門的な内容まで様々な内容が論じられている。 学習速度が速い児童が将来も創造的な人物になるとは限らない。 学術的功績を挙げた人の多くは、学校での成績は平均程度。 「普通ではありたくない」という気持ちが強い人が創造的。 当たり前と思っていることに対して、懐疑的になれ。 脳は、全体像を見る部分と、細部を見る部分がある、全体像を見る部分をマインドセットといい、自分の知っている事柄に合わせて物事を見る。 創造的であるためには、全体像ではなく、細部を見る必要がある。 実験で、左脳に電波を当てると全体像を見る機能が低下し、細部を忠実に書き写すようになることが明らかとなった。 偉大な研究成果は、人間間の関係により構築される。1人ではなしえない。また、動機の問題もある。誰との関わりを持たなければ、誰からの認められない環境であれば、そもそも研究をしようとは思えない。 孤立した個人に注目していると、創造性の非常に重要な事項を見逃すこととなる。 30ミリ秒以上ないと、人間は知覚できない。また、3秒を越える自称についても、はっきり覚えることが出来なくなる。 話すことにより、問題解決に道筋が出来ることがある。 創造的な行動の無効には常に他人からの目線がある。 赤ちゃんが言語を覚えるのは、教える親の行動が重要な要素をしめる。
Posted by
マインドセット 考える帽子 相補性、創造性 ロバストネス(強靭さ) 仮想ホムンクルス ジキル博士とハイド氏
Posted by
題名が一人歩きしている。 外国の先生方は『創造性』についてわかりやすくかいつまんでいるが 日本の先生方は好き勝手に自分の研究してることやらを 話してるだけである。会議を起こした本のようだが、列席してた 訳者には筋が理解できていることは推察できるが、 本としての内容は破綻してる。 ...
題名が一人歩きしている。 外国の先生方は『創造性』についてわかりやすくかいつまんでいるが 日本の先生方は好き勝手に自分の研究してることやらを 話してるだけである。会議を起こした本のようだが、列席してた 訳者には筋が理解できていることは推察できるが、 本としての内容は破綻してる。 特に日本の先生方のページが酷い。 何をいってるのか、いいたいのかさっぱりわからないどころではない。 数ぺージ抜けてるのでは?これでおわり?結論は? と思うことばかり。国際会議でこんな話し方をしているとしたら 日本のサイエンスもがっかり。という印象。 ソニーの研究所がらみの雰囲気が背骨に漂う本書だが 低空飛行のソニーの理由がわかった気がした。 「クオリア」というトレンドな単語に心脇踊る人なら 楽しめる内容かもしれないが、間違っても1600円の価値はない。
Posted by
- 1