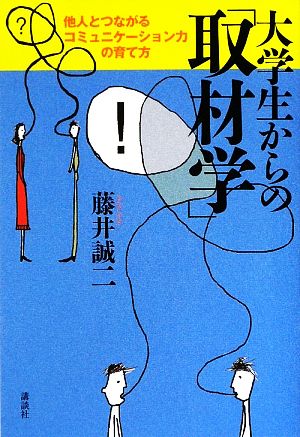大学生からの「取材学」 の商品レビュー
ああ、読んでからすぐに記録つけてへんかったから、全然覚えてない。ただ、さすが藤井さんだと思ったような記憶はあるから、深いことが書かれていたように思う。まぁ、これはいつかまた読む本でしょう。
Posted by
ノンフィクションライターが大学で行った「取材学」の講義をまとめたもの。バーチャルなコミュニケーションが増える中,「生身の人間」と対峙することの意味,大切さなどを説く。最近,色んな人と交渉する機会が増えて,メールでのやりとりを重ねるけど,やはり最後は自分の肉声で伝えることが必要だな...
ノンフィクションライターが大学で行った「取材学」の講義をまとめたもの。バーチャルなコミュニケーションが増える中,「生身の人間」と対峙することの意味,大切さなどを説く。最近,色んな人と交渉する機会が増えて,メールでのやりとりを重ねるけど,やはり最後は自分の肉声で伝えることが必要だな,と感じていたので,タイムリーな本でした。人と直接関わるのは確かに面倒だけど(いや,私が面倒だと思うだけかもしれないけど),結局それがあるから自分の中に一つ一つ経験を積んだ厚みが出るんじゃないのかなあ,と遅ればせながら気づいた次第。大学生のコミュニケーション能力向上には非常に有用な講義ですね。本読むだけじゃなく,やはり人間から伝えられたい内容でした。
Posted by
読んでいて、「コミュニケーションとは、こういうものなんだよ」と、教えられている気がした。その辺は自己啓発本などに通じる部分があると思った。真新しいことが書いてあったわけではない。結局は取材というものは、いかにして他者とのコミュニケーションを円滑にさせるかに尽きるのだなと、本書を通...
読んでいて、「コミュニケーションとは、こういうものなんだよ」と、教えられている気がした。その辺は自己啓発本などに通じる部分があると思った。真新しいことが書いてあったわけではない。結局は取材というものは、いかにして他者とのコミュニケーションを円滑にさせるかに尽きるのだなと、本書を通して強く感じた。また、ものを書く上ではその中に「不整合性」を取り入れるべきであるという主張はとても勉強になった。その「不整合性」の重要性については、辺見庸『反逆する風景』で詳しく述べられているらしいので(本書でも何度も引用されている)、次はそちらを読んでみることにする。
Posted by
「コミュニケーション力」も取材の一歩から 「知るは一時の恥、知らぬは一生の恥」… 事務職、営業職を問わず、人とコミュニケーションする力 =「人の話を聞く力」が必要だ。 その基本の力がつく方法を伝授。 社会の肌触りを体感する。 自分の身のまわりを掘り下げる。 相手の怒りから...
「コミュニケーション力」も取材の一歩から 「知るは一時の恥、知らぬは一生の恥」… 事務職、営業職を問わず、人とコミュニケーションする力 =「人の話を聞く力」が必要だ。 その基本の力がつく方法を伝授。 社会の肌触りを体感する。 自分の身のまわりを掘り下げる。 相手の怒りから逃げてはいけない。 「あたりまえ」のことをする。 パターン認識で相手との共通項をさがす。 「出会う」プロセスも大切。 「場」と「空気」も大切。 相手の「見た目」は情報のかたまりだ。 「反逆する風景」(犯罪者の家族が楽しく生活していることなど) を無視してはいけない。 共同体や文化背景からくる「言葉」を読む。 必ず「生身」に触れること。 …以上のことを学びました。 「人とつながる」ということはどういうことなのかを 教えてくれます。 情報化が進んだ現代ではネットで調べただけで つい「分かった」気になってしまいますが、 やはり実際に「生で」会わないとその真髄は 感じ取れないんですね。 私も筆者のように「足で書く」ことができるように なりたいと思いました。
Posted by
- 1