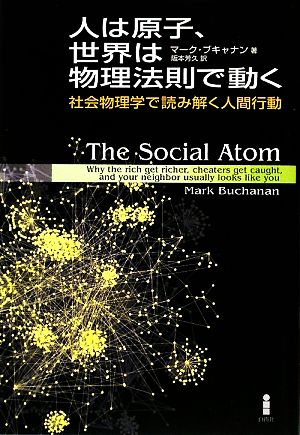人は原子、世界は物理法則で動く の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
社会現象は人間ではなくパターンで捉えることができる。そのパターンをもたらすものは訳者解説に要約されており、 ①人間は本質的には理性による論理的思考が不得手で、むしろ直観に頼って思考し、判断を下すこと、 ②他者との関わりあいのなかで学習し、適応していくこと、 ③進んで人の価値まねをしようとすること、 ④仲間との協調を志向する一方で、協調を目指す同じで論理に従って、よそ者に対しては盲目的な敵意を向ける傾向があること の4つである。 人間が理性ではなく直感に支配され、それが生み出すパターンとして差別、偏見、富の偏在、独裁、ブームがあるとしたら、それは抗いようがない。なんとも恐ろしい話である。
Posted by
邦題がミスリーディングな気がする。 「世界は物理法則で動く」ではなく「社会学の世界も、自己組織化や同期現象といった複雑系のタームを使って説明されつつある」程度の内容。原著のThe Social Atomも「社会の基本要素」くらいの意味じゃないかなぁ。
Posted by
社会物理学を紹介した本。社会現象の多くは、人間そのものではなく、パターンで考えれば説明がつく。物理でいえば、水の分子をいくら詳しく調べても、津波のパワーについて説明できないのと同じことだ。事例をあげてパターンという考え方を説明されるが、それがなるほど納得できる。 パターンで考えた...
社会物理学を紹介した本。社会現象の多くは、人間そのものではなく、パターンで考えれば説明がつく。物理でいえば、水の分子をいくら詳しく調べても、津波のパワーについて説明できないのと同じことだ。事例をあげてパターンという考え方を説明されるが、それがなるほど納得できる。 パターンで考えた場合、人間は(も)似た特徴を持ったもので集まりやすい。もしもそれを利用した扇動者が現れたり、またはちょっとした出来事がきっかけとなった場合、私たちはこれまで友好な関係を築いていた違う特徴(肌の色、思想など)を持つ人間を、別の集団のものとみなし、攻撃しかねない。現代の社会は、表面上は穏やかだが、実はこういった危うさを内包している。これは怖い話だ。 文章が読みやすいので、難解には感じなかった。社会物理学に興味を持った。
Posted by
・複雑系の入門書。 ・株価の予測シミュレーションが大変うまくいったとの説明があるが、それがあまり普及していないのは何故?という素朴な疑問。 ・行動経済学、進化心理学などに触れつつ、最後は単純な行動パターンをコンピュータでシミュレーションする事によって、複雑な事象を実験的に説明でき...
・複雑系の入門書。 ・株価の予測シミュレーションが大変うまくいったとの説明があるが、それがあまり普及していないのは何故?という素朴な疑問。 ・行動経済学、進化心理学などに触れつつ、最後は単純な行動パターンをコンピュータでシミュレーションする事によって、複雑な事象を実験的に説明できるという複雑系の話に落とし込んでいる。 ・偉大な将軍は技量よりも幸運が生んだ産物なんですよ、とフェルミは結論づけた。 フェルミがグローヴズ将軍にあなたの基準では「偉大な将軍」とはどのような指揮官を言うのかと尋ねると、ダロ一ヴズは戦いで5回連続して勝利を収めた指揮官と言った。 次にフェルミが優秀な将軍は何人いますか」と聞いたのに対して、グローヴズはほぼ100人に3人の割合になると答えた。 フェルミは.将軍たちがまったくの幸運のおかげで勝利を収めるとしても、連戦連勝を5回つづける可能性は32分の1であることを指櫛した。 だから、将軍か100人いれば、そのなかには5回連続して勝利を収めた将軍がほぽ3人は見つかって当然なのである。
Posted by
フリーのサイエンスライターであるマーク・ブキャナンによる社会物理学の本(阪本芳久訳)。 著者は、以前は「ネイチャー」でも編集者をされていたらしく、自然科学に関する知見は 確かかと。 著者の主張は、「人間はバラバラの存在なのに、構成する世界には一定の法則が働く。」というものだ。 ...
フリーのサイエンスライターであるマーク・ブキャナンによる社会物理学の本(阪本芳久訳)。 著者は、以前は「ネイチャー」でも編集者をされていたらしく、自然科学に関する知見は 確かかと。 著者の主張は、「人間はバラバラの存在なのに、構成する世界には一定の法則が働く。」というものだ。 その法則というのは、人間は利他的に行動するというものだ。 人間が利他的である理由やそれによる社会生活での恩恵、それとは逆に利他的であるにもかかわらず戦争がおこる理由、 などに触れている。 この本の特徴は文系の人間でも全く抵抗なく読める点である。 数式は全く出てこない。 そして、サイエンティストの名前よりも社会科学者の名前の方がよく出てくるぐらいだ(アダム・スミスがたぶ ん一番多く、他にはヒューム、デュルケーム、マルクスなど)。 自然科学らしい証明はないので、人によっては物足りないかもしれない。 しかし、物理的な絵をイメージできる点が純粋な社会科学とは違うこの本のユニークな部分だろう。 デュルケームやウェーバーの言うことは何となく分かる気はするのだが、絵は浮かばない。 一方、この本はタイトルから絵をイメージできて、その上で主張としては社会学のような摩訶不思議さがある。 専門を問わずにワクワク読める、素晴らしい本だ。
Posted by
- 1