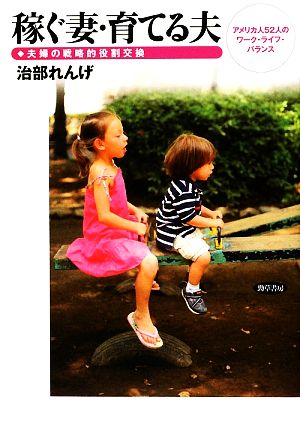稼ぐ妻・育てる夫 の商品レビュー
面白い。ワークライフバランスというば政府に「育児支援を」と要望をあげるのが定番だが、そもそも財政難の日本に期待したところでどこまで成果が期待できるのか。翻って、日本より保育園事情の悪いアメリカさえも日本より出生率が高い。なぜなのか。もしかしたら、日本の少子化対策への答えはここにあ...
面白い。ワークライフバランスというば政府に「育児支援を」と要望をあげるのが定番だが、そもそも財政難の日本に期待したところでどこまで成果が期待できるのか。翻って、日本より保育園事情の悪いアメリカさえも日本より出生率が高い。なぜなのか。もしかしたら、日本の少子化対策への答えはここにあるのではないかと思ったり。
Posted by
アメリカでの育児と仕事の両立の事例集。それを元に日本との比較も。 アメリカは日本ほど育児支援は無い。それでも何故、社会への女性進出が進んでいるのか、等々。 ただあくまで高学歴者、高収入の夫婦の話でもある。格差の大きいアメリカで平均的にはどのような結果が出ているのだろう? 個人的に...
アメリカでの育児と仕事の両立の事例集。それを元に日本との比較も。 アメリカは日本ほど育児支援は無い。それでも何故、社会への女性進出が進んでいるのか、等々。 ただあくまで高学歴者、高収入の夫婦の話でもある。格差の大きいアメリカで平均的にはどのような結果が出ているのだろう? 個人的には参考になる、共感する点多数。買って置いておこうかな。お勧め。
Posted by
この本で知ったいちばん意外な事実は、アメリカは保育園事情がとても悪いということ。質もさることながら、とにかく保育料が高い。道理でベビーシッターがドラマや映画でひんぱんに出てくるわけだ。 男性の給与レベル低下が女性の地位向上につながってしまったというのも面白い。 アメリカでも家事や...
この本で知ったいちばん意外な事実は、アメリカは保育園事情がとても悪いということ。質もさることながら、とにかく保育料が高い。道理でベビーシッターがドラマや映画でひんぱんに出てくるわけだ。 男性の給与レベル低下が女性の地位向上につながってしまったというのも面白い。 アメリカでも家事や育児の分担は、やはり女性のものという考えは根強いが、柔軟な雇用体系や労働市場の流動化が進んでいることが女性の就業の継続につながっている。 労働時間について自分で交渉するなどは個人主義のアメリカらしい。 アメリカとの比較で日本は保育園が充実し、公的負担や産休・育休制度が整っていることがわかった。それでも就業をあきらめる女性が多いのか、改めて考えさせられる。周囲のバックアップのなさ、子どもの可愛さ、色々ではあるが。 著者が提案するような、少子化対策は有効だと思うが、ある一定の年齢以上の男性には赤ちゃんとふれあう機会を作っても、逆に「あんなに可愛い子を預けて働くなんて考えられん!」ってことにもなりかねないな、と。 やはりワークライフバランスが根付くには世代交代は不可欠な要素と思う。政治家も企業のトップも50代以下になったら相当変わりそうな気がする。
Posted by
ワークライフバランスは少子化対策には必要な考え。 仕事と生活の調和推進官民トップ会談で「仕事と生活の調和憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定したとのこと。 数値目標として以下が掲げられた。 ①6歳未満の子供を持つ男性の育児・家事関連時間を現状の一日60分から...
ワークライフバランスは少子化対策には必要な考え。 仕事と生活の調和推進官民トップ会談で「仕事と生活の調和憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定したとのこと。 数値目標として以下が掲げられた。 ①6歳未満の子供を持つ男性の育児・家事関連時間を現状の一日60分から、2017年までに1日2時間30分に増やす ②週労働時間が60h以上の雇用者の割合を10.8%から半減させる。 ③年次有給休暇取得率を現状の46.6%から完全取得にする で日本企業がすべきこととして ①柔軟な働き方を推進する ②良い成果主義を進める ③管理職の資質を見直す ④ ①~③を経営効率の観点で考える 特に②では何時間働いたかでなく、どんな成果をあげたかに注目する必要があるという点が大切。 部下と上司のジェネレーションギャップにも理解が必要 まだまだ過渡期なのかな。。。
Posted by
- 1