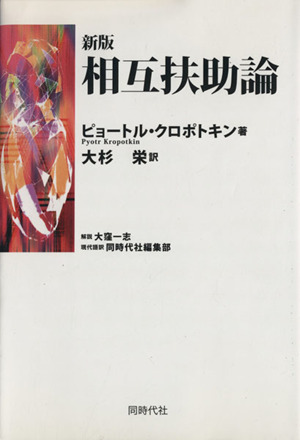新版 相互扶助論 の商品レビュー
序章の頃はまるっきり???だったが、結論に至る頃になると、相互扶助の概念が腹落ちし、序論を読み直すと!!!と理解できる。深遠な印象を抱いた。
Posted by
日本のアナキズムの源流となったクロポトキン。その主著であるこの本では、人々の相互扶助、今でいえば生活上関係のある人々、あるいは目に見える人々同士の助け合いというのが、生物一般から今日までの人間の歴史上において、普遍的に見出される原理であり、それが人間の無意識下においてなされるいわ...
日本のアナキズムの源流となったクロポトキン。その主著であるこの本では、人々の相互扶助、今でいえば生活上関係のある人々、あるいは目に見える人々同士の助け合いというのが、生物一般から今日までの人間の歴史上において、普遍的に見出される原理であり、それが人間の無意識下においてなされるいわば本能的な行為であるということを論じている。 さらに、19世紀以降の近代においては個人主義的な教育と教養によって相互扶助のマインドが抑圧され、貧者を無視して個人の利益を追求することが是とされるようになったという狂気性を批判する。 執筆当時(1890)の学問的傾向として唯物史観的に書かれている側面はあるにしても、その内容と近代批判は鋭く、道徳論に依拠したものより具体性があり、その後の議論の方向性を知らないのでなんとも言えないが、共同体の重要性を解いているところからして共同体研究としても寄与する部分多かろうと思う。 果たして昨今、我々は我々自身を他者との関わりの中から見出すということが言語学からも政治学からも心理学からも言われている。 人はなんで生きるのか、ということの一つの解としても、この本はあるといえる。
Posted by
もと革命家のピョートル・クロポトキンさんの著作で、アナーキスト大杉栄さんの翻訳です。人間にはあい助け合うという心性が備わっていてそれによって生き延び進歩してきたというのがこの本の内容です。 人間同士の生存競争、万人による闘争という社会契約説の前提は間違っているという、常識をひっ...
もと革命家のピョートル・クロポトキンさんの著作で、アナーキスト大杉栄さんの翻訳です。人間にはあい助け合うという心性が備わっていてそれによって生き延び進歩してきたというのがこの本の内容です。 人間同士の生存競争、万人による闘争という社会契約説の前提は間違っているという、常識をひっくり返す論述になっています。しかも、この説明がこの世の中をクロポトキンさん自身の目で丁寧に観察した結果から導き出されたものなので私にはとても説得力がありました。 養老さんの「バカの壁」を読んだ時のように、「また、逆に考えさせられていたんだな…」と教育がいかに一部の者の利益のために多くの庶民に偏った物の見方を強いているということを思いました。 自分の思いが行き詰って行き場を失ってしまった時には、その思いの前提となったそれまでに受けた教育によって既に頭の中に張り付けられたウソかもしれない各種の理論について点検してみる必要があります。橋本治さんの言われていた、「二流の理論」や「自分の頭で考える」の意味を思いました。
Posted by
- 1