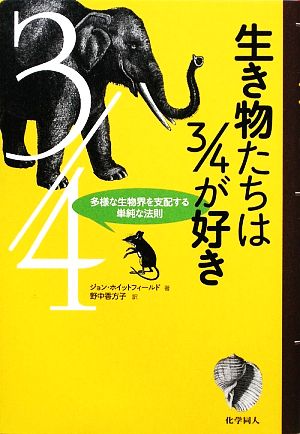生き物たちは3/4が好き の商品レビュー
☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA88856349
Posted by
生物は多様である。 が、その多様性のなかに、一貫した法則性を求めようと、物理学的というか、数量的なアプローチで、生物学に挑んだ人たちの話しをまとめたもの。タイトルにでてくる3/4の話しだけではない。 でも、やはり一番面白いのは、3/4の話しかな。 つまり、生物の体の大...
生物は多様である。 が、その多様性のなかに、一貫した法則性を求めようと、物理学的というか、数量的なアプローチで、生物学に挑んだ人たちの話しをまとめたもの。タイトルにでてくる3/4の話しだけではない。 でも、やはり一番面白いのは、3/4の話しかな。 つまり、生物の体の大きさとエネルギー消費量や寿命などとの関係を調べると3/4とか、1/4とか、いう定数がいろいろなところで出てくる。 では、なぜ、分母は4なのか? 研究の初期では、計量の難しさもあって、2/3といった、分母が主張されてたのだが、分母の3というのは、理論的に理解しやすい。つまり、我々の住む空間は3次元だということをベースに、生物の体重や表面積、エネルギー消費の話しを考えていれば、分母が3というのは説明可能とのこと。 なぜ、分母は4なのか。 本当は、われわれの住んでいる空間は4次元なのか? なんて思っていると、どうも答えは、複雑系的なネットワークとか、フラクタルといったことと関係していそう。血液とか、樹液をフラクタルに分かれて行くネットワークで供給していくと考えると、4次元的な状態が発生する、というのが今一番もっともらしい説明らしい。 という話しは、なかなか面白かったのだが、もう少しその辺の説明が分かりやすく記載されていれば良かったのにな、と思った。 この本は、研究者ではなく、科学ジャーナリストが書いた物で、人物紹介を中心にしていて、何でも自分で、現地にいって体験しようというところが、読みやすく、また共感するわけだが、一方では、科学的な説明の部分が簡単すぎて、今ひとつ、知的なスリルは味わえないところがあるかな? それにしても、生物を説明しようとすると、3次元でなく、4次元が必要みたいで、相対性理論と量子力学を統合しようとすると最低でも5次元、超ひも理論とか、M理論とかになると、10次元とか、11次元必要だということになるんだなー、と思うと感慨深い。 これって、プラトンの洞窟の比喩みたいですね。つまり、人間は洞窟のなかで、外からの光の影が洞窟の壁に映るのをみて、それを現実だと思っている、というやつ。 世界は、やっぱり複雑で、そのままでは統一的に理解することはできないので、目に見えないもう一つの軸(=次元)が必要となる。 で、その軸は、実在する、と考えるのか、あるいは複雑なものを理解するための補助線みたいなもので、理論上の便法と考えるのか、なんて形而上学的な思考に誘われるのであった。
Posted by
動物の代謝は体重の3/4乗に比例する。それはなぜか。多くの生物学者、あるいは生態学者が生物学を統一の法則・理論で説明しようとしてきたことがよくわかる。物理学のように。ただし、方程式とはメカニズムであり、多くのもっともらしい仮説は立てられてきたものの、そのメカニズムを完全に説明する...
動物の代謝は体重の3/4乗に比例する。それはなぜか。多くの生物学者、あるいは生態学者が生物学を統一の法則・理論で説明しようとしてきたことがよくわかる。物理学のように。ただし、方程式とはメカニズムであり、多くのもっともらしい仮説は立てられてきたものの、そのメカニズムを完全に説明することはできていないと。 おもしろんだが、最後まで答えは当然出てこず、もやもやがやや残る。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
代謝率が体重の3/4乗に比例する理由や熱帯にどこよりも多くの種が見られるのはなぜなのかといった、生物界の謎に取り組んできた人達とそのアイディア(説)を18世紀後半から現代までにわたって紹介する本です。 ある説が紹介されて、なるほどと思って読んでいくと、その説にはこういう矛盾があって次の説では・・、というのが続きます。アップダウンの激しい坂道を走らされているようで読み進めるのがちょっときついですが、言われると確かになぜなんだろうと思う生物界の謎と説が載っていて面白いです。私が気に入ったのは、代謝率は毛細血管の数に比例する(そして最適なネットワークを作るモデルで毛細血管を作ろうとすると毛細血管の数が体重の3/4乗に比例する)というのと、熱帯は気候が安定しているから種がより特殊化し、より狭いニッチに適合して、自然環境をより細かく分割できるようになって多様化が進んだという説でした。
Posted by
生物の形態計測、代謝速度などの研究の歴史を追いながら、生物の多様性になんとか法則を捉えようとした科学者達の試みを書いた本。これから研究を始める大学生は読んでみると いいかも。単純に知識を得るために読むのもオススメ。若者にウケやすい書き口だったと思う…
Posted by
これほど複雑に見える生物界の中に、それらを貫く「単純な法則」などというものが、本当にあるのでしょうか? 結論から言えば、かなり有望なものは、少数ながらも確かにあるようです。 著者は、ロンドンで活動しているサイエンスライターで、昆虫進化の研究によりケンブリッジ大学の博士号も持...
これほど複雑に見える生物界の中に、それらを貫く「単純な法則」などというものが、本当にあるのでしょうか? 結論から言えば、かなり有望なものは、少数ながらも確かにあるようです。 著者は、ロンドンで活動しているサイエンスライターで、昆虫進化の研究によりケンブリッジ大学の博士号も持っているとのこと。また、NATURE誌でのキャリアもあるそうです。つまり、生物学的な基礎はばっちりもっていると思われます。その著者が、生物学に物理学的なアプローチを持ち込むことで、多様性ではなく統一性を追究しようとする生物学の一分野に焦点を当てて、これまでの成果や論争をわかりやすく要約しています。 本書を貫く問題意識は、次のようにまとめられます。「多様性こそがその本性であるのように印象づけられる生物界の中に、本当に統一理論などがあるのだろうか?」「確固とした法則・理論をほとんど見いだせないのは、生物学が未熟だからなのだろうか?」「もし仮にそうだとしても、物理学的なアプローチを持ち込むことは、生物学においても有効なのだろうか?」 物理学に比べて生物学が劣っているなどと、(本音ではともかくも)表だって語る者は、物理学の世紀と呼ばれた前世紀(特に中盤まで)ならともかく、生物学の世紀と予想されている(もちろん異論も不確定性もあるでしょうが)21世紀においては、もはやほとんど存在しないでしょう。とは言え、本書を読んですなおに共感できる読者と、生物のデリーケートな部分を捨象して数式で捉えようとするようなアプローチに、何となく傲慢さや嫌悪感を抱いてしまう読者とが、おそらく両方いるでしょう。 私個人としては、研究のアプローチは多様であってよいと思っていますし(他のアプローチを真っ向否定する論調は好きではありませんが、本書はとても冷静に筆を運んでいて、その点でも好感が持てます)、科学読物としても十分に面白いと思います。生物学、特に生態学などの比較的マクロな対象を扱う分野のこれからの動向を感じるために、一読しても損はないでしょう。特に、かつて科学読物のベストセラーとなった『ゾウの時間 ネズミの時間』(中公新書)を面白く感じた方には、より本格的な近著として、本書はお薦めの一冊です。
Posted by
1 数学に魅せられて―プロローグ 2 おだやかな炎 3 グラフの傾きを変える 4 類似性を求めて 5 ネットワーク化 6 生命の速度 7 木を見て森を知り 8 聖女ロザリアに導かれて 9 フンボルトの贈り物 10 草の葉のニュートン 11 追い求めるものは―エピローグ
Posted by
「代謝量は体重の3/4乗に比例する」などの法則についての本。これまでの歴史と現在の解釈がまとまってます。
Posted by
地球上に住む生物に存在する普遍的な規則について紹介したものです。 あらゆる種にわたって体重と代謝率などには一定の関係が存在しアノマリーと呼ばれています。具体的には標準代謝が体重の3/4乗に比例するといった法則が有名でこれがタイトルの意味です。本書ではその発見の歴史から数理モデルに...
地球上に住む生物に存在する普遍的な規則について紹介したものです。 あらゆる種にわたって体重と代謝率などには一定の関係が存在しアノマリーと呼ばれています。具体的には標準代謝が体重の3/4乗に比例するといった法則が有名でこれがタイトルの意味です。本書ではその発見の歴史から数理モデルによる説明までが書かれています。エネルギー運搬のネットワークでアノマリーを説明するのですが、モデルの詳しい内容は本書では分かりません。引用文献がわりと充実してるので詳細を知りたい人は論文を読むことになるでしょう。 後半では、ある地域に存在する種の数がどのように決まっているかという問題提起に始まり、個々の生物ではなく生物の集団に見られる「法則」についても書かれています。島モデルや中立仮説も紹介されていますが本書の記述では詳細がやはり分からないでしょうね。
Posted by
- 1