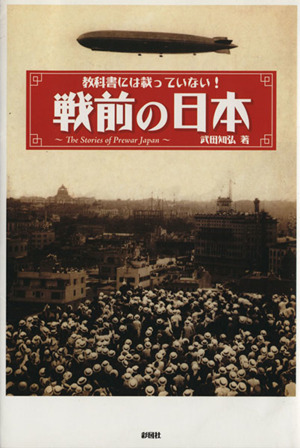教科書には載っていない!戦前の日本 の商品レビュー
「戦前」というと、何か、貧しくて言論の自由もない、暗黒時代だった・・・というような刷り込みがされてしまっているが、決してそんなことはない、というのを、写真を交えて説明してくれている本。 そのこと自体はとてもよかったのだが、「戦前は決して悪くなかった。ただ、戦争のおかげでめちゃく...
「戦前」というと、何か、貧しくて言論の自由もない、暗黒時代だった・・・というような刷り込みがされてしまっているが、決してそんなことはない、というのを、写真を交えて説明してくれている本。 そのこと自体はとてもよかったのだが、「戦前は決して悪くなかった。ただ、戦争のおかげでめちゃくちゃになってしまった」という論調がちょっとどうも、ね。
Posted by
戦前というと、軍国化の黒い歴史がバイアスとなって負のイメージがのしかかるが、そこを除くと、意外と明るかった時代。貿易大国、経済大国、教育大国。自分たちが気づかなかっただけで、実は世界の超大国だったと言える。しかし、血盟団事件や5.15事件、2.26事件にも象徴されるように、社会腐...
戦前というと、軍国化の黒い歴史がバイアスとなって負のイメージがのしかかるが、そこを除くと、意外と明るかった時代。貿易大国、経済大国、教育大国。自分たちが気づかなかっただけで、実は世界の超大国だったと言える。しかし、血盟団事件や5.15事件、2.26事件にも象徴されるように、社会腐敗と暴力が跋扈していたのも事実で、その動乱の歴史から目を離すこともできない。
Posted by
面白かった。戦前の日本の様子が娯楽的な視点で書かれていた。 中には知らない知識も多く、サクッと読めた。
Posted by
戦前の日本の風景についてランダムに書かれています。 資料・データとしては興味深く、面白いものがあります。国際的には日本の経済成長(世界恐慌からいち早く脱したこと)や貿易摩擦(イギリスとの綿製品の国際シェア逆転)、国内の経済格差の拡大など社会背景や世相を掘り下げていくことで、戦後と...
戦前の日本の風景についてランダムに書かれています。 資料・データとしては興味深く、面白いものがあります。国際的には日本の経済成長(世界恐慌からいち早く脱したこと)や貿易摩擦(イギリスとの綿製品の国際シェア逆転)、国内の経済格差の拡大など社会背景や世相を掘り下げていくことで、戦後との対比ができるようになるのではないかと思っています。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
モルヒネやヘロインはアヘンからの抽出物であるが薬局で手に入った。中国や台湾で流行っており当局の規制の目をすり抜けた。覚せい剤の有効成分のヒロポンは薬局でも買え、軍隊でも恐怖感減少のため特攻隊員に配布された。終戦後、軍から大量に闇市に流れた。 日本は歴史上亡命者や難民をほとんど受け入れてこなかったが、1917年のロシア革命のときに数千人が来た。巨人のスタルヒンもその一人。 戦前の日本は世界有数の貿易大国。第一次世界大戦中に紡績業が躍進。中小が乱立していたイギリスと違い財界人たちが協力して大規模工場を作った。1936年英国1917百万ポンド、日本2708百万ポンドと完全に逆転し、イギリスとの貿易摩擦が起こった。インド市場から締め出された日本は満州に市場を求めていった。 綿製品以外は自転車が主要輸出品。1937年に機械系輸出品目のトップになた。その次が玩具。舶来品の玩具を研究史セルロイドや金属を使ったおもちゃや電気仕掛けの模型、ゴムマリ、人形など。マッチや洋傘、ブラシなど世界的なシェアを獲得していた。 日本は古来から教育意識が高かった。寺小屋などの教育機関が発達しており、幕末期の江戸の識字率は世界でも驚異的な高さ。 米国でエジソンが電気事業を始めたのは1880年。それから7年後に日本でも電気が通っていた。 科学技術は欧米に遅れていたが通信は最先端だった。 1964年に新幹線が世界最速を記録して開業した。下地は弾丸列車計画で東京都大阪を4時間半で結ぶもの。戦局が悪化して中止になった。 満州への輸送が必要になったため計画され、最終的な計画は東京都北京を結ぶ。 戦前は国を挙げて学問を推奨していた。明治初期は16等級にクラスが分かれていて半年に一回のテストで席が決まった。義務教育は小学校まで。しろばんばの主人公は公立中学校に入るために家庭教師をつけてもう特訓をしていた。どうにか中学校に入っても高校は全国に35校しかなく1割りしか進学てきなかった。高校の定員と帝国大学の定員はほぼ同じなので高校までが大変。 多摩は軍事大都市。
Posted by
祖父祖母の生きた戦前の様子はほとんど語られることがなく、日本独自の良かった部分など、戦後の風潮の中で否定をされてきているように感じます。このような内容がもっと世の中に出てきて戦前の日本について再評価される議論が出てきても良い気がします。またこの延長で野口悠紀雄氏の「1940年体制...
祖父祖母の生きた戦前の様子はほとんど語られることがなく、日本独自の良かった部分など、戦後の風潮の中で否定をされてきているように感じます。このような内容がもっと世の中に出てきて戦前の日本について再評価される議論が出てきても良い気がします。またこの延長で野口悠紀雄氏の「1940年体制」の主張を読んだりすると入って行きやすいのかもしれません。
Posted by
両親は戦前の生まれですが、戦前の様子を聞いた記憶がありません、幼かったので記憶がないのか戦後の苦しい思い出が強烈のようで、私にとって戦前の昭和は全くの未知の世界でした。特に戦後の奇跡の経済成長というのも、この本を読むことで、奇跡ではなく回復しただけという印象を受けました。 む...
両親は戦前の生まれですが、戦前の様子を聞いた記憶がありません、幼かったので記憶がないのか戦後の苦しい思い出が強烈のようで、私にとって戦前の昭和は全くの未知の世界でした。特に戦後の奇跡の経済成長というのも、この本を読むことで、奇跡ではなく回復しただけという印象を受けました。 むしろ幕末や明治維新の頃の日本のほうが教科書によく載っていたのかもしれません。この本は戦前の日本が記されています、今まで知らなかった世界を垣間見て、興味深く読むことが出来ました。 以下は気になったポイントです。 ・昭和4年の吉原では、泊まりが3~10円であり、現在の貨幣価値にすると、1~3万円である、1円=3000円程度(p26) ・覚醒剤の有効成分の一つであるメタンフェタミンは19世紀末に日本で合成され、1938年には疲労回復剤として大日本住友製薬から「ヒロポン」として発売された、1951年覚醒剤規正法により規制され現在に至る(p36) ・昭和4年(1929年)に飛行船(ツェッペリン号)はアメリカを出発してシベリア、日本を経由して世界一周をした。2500ドル=5000円(1ドル=2円)であり、家一軒が建てられる金額であった(p63) ・戦前の経済成長も凄いものがあり、1908~17年:3.09%、1918~27年:1.50%、1923~1932年:2.35%の成長があった、明治維新から第二次世界大戦前までの70年間で、日本の実質GNPは約6倍、実質賃金は約3倍、実質工業生産は約30倍、実質農業生産は約3倍である(p67) ・昭和4年(1929年)に始まった世界大恐慌において、日本は昭和8年には回復基調になり、9年には世界大恐慌以前の経済水準に復帰している、これは当時の先進国比較で5年も早い(p69) ・日本の綿製品の輸出量は、昭和3年にはイギリス製品の37%、7年には92%、11年には追い抜いている、輸出先はインド及び中国、これによりイギリスとの経済摩擦を生み、インド市場から締め出され中国(満州)に集中した、自転車も同様の状況(p75) ・昭和7年にはドイツなどの製鉄大国を差し置いて日本の鉄が選ばれた、その他にも、マッチ・洋傘・ブラシ等も世界的なシェアを獲得していた(p77) ・アメリカでエジソンが電気事業を始めたのは1880年であるが、そのわずか7年後には日本でも電気が通っていた(p87) ・1928(昭和3)年10月の人口調査によると、大阪市の人口は233万で、東京の221万人より多く人口首位であり、世界6番目の都市(ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、シカゴ、パリ)であった、昭和7年に再編成した東京市に1位を奪われるが、文化や産業をリードした(p101) ・高校(全国に35校)に入学できたのは全体の1割程度であり超難関であったが、高校の定員と帝国大学の定員は同じであった(p117) ・明治初期の婚期は早かったが、昭和15年(1940)頃には、男性28歳、女性24歳が初婚の平均年齢であり、現在と比較してそれほど早くない、離婚率は3.39(昭和16年)であり、現在(2.30:平成14年)より高い(p127、130) ・昭和4年の平均寿命は、男:50.94、女:51.20歳であり、ローンを組めても15年程度であった(p141) ・明治22年(1889)に帝国議会がスタートすると、華族は貴族院になれた、公候爵は30歳以上全員に議席が与えられ、伯爵以下は半数を7年毎に改選、歳費(給料)はなし(p169) ・4大財閥(三井、三菱、住友、安田)は、終戦時の全国の会社の資本金の50%を占めていた、GHQに解体された財閥は15(p172) ・徴兵忌避の方法として、270円(現在の270万円)の支払いや、長男になるための養子縁組、明治16年の法改正後は、学歴(26歳迄)があった(p209) ・多摩は軍都であったので20万人もの労働人口がいた、戦前は国家予算の30~80%が軍事費(現在は6%程度)であった(p215)
Posted by
これはかなり面白い。戦前、当時の人々がどんな暮らしを送っていたかを小ネタ形式にコンパクトに揃えた、まさにタイトル通り「教科書には載っていない戦前の日本」でした。 当時のミステリを読んでるとちょいちょい出てくる『カフェーの女給』とはどんなお仕事だったのか(そして、どこまでエロサービ...
これはかなり面白い。戦前、当時の人々がどんな暮らしを送っていたかを小ネタ形式にコンパクトに揃えた、まさにタイトル通り「教科書には載っていない戦前の日本」でした。 当時のミステリを読んでるとちょいちょい出てくる『カフェーの女給』とはどんなお仕事だったのか(そして、どこまでエロサービスしてくれるものだったのか←!)が気になっていたのですが、本書でスッキリ解決。 吉原の遊郭の話から戦前の不良少年(今で言う、厨二病的な通り名やグループ名が格好良すぎる。笑)、白系ロシア人の移民の話があると思えば、丸の内サラリーマンの豪華なランチ事情、履き物を脱いで上がるデパートなど、もう、どれを読んでも「へぇー!」の連続。 多様かつ雑然とした当時の雰囲気が少し掴めた気がします。
Posted by
帝都上空に浮かぶ飛行船ツェッペリン号。本書はそんな写真が表紙の本である。 コンビニで見つけて思わず買ってしまいました。 本書は戦前の日本の生活を紹介している。 写真が多いのも嬉しい。
Posted by
戦前の日本と言うと,どうしても戦争に関することとか,渋沢栄一等に関することに集約される傾向が高いように見えますが,それ以外の戦前の日本の姿をまとめた貴重な書ではないかと思いました. 戦前は外国人留学生が非常に多かったようで,最盛期には2万人以上いたようです.戦後,1万人を超えた...
戦前の日本と言うと,どうしても戦争に関することとか,渋沢栄一等に関することに集約される傾向が高いように見えますが,それ以外の戦前の日本の姿をまとめた貴重な書ではないかと思いました. 戦前は外国人留学生が非常に多かったようで,最盛期には2万人以上いたようです.戦後,1万人を超えたのが80年代に入ってからのようですので,当時の交通事情を考えれば驚異的な数字と言えると思います.
Posted by
- 1
- 2