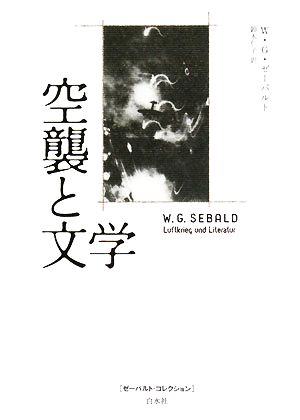空襲と文学 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『アウステルリッツ』、『土星の環』などで有名なドイツの作家、W・G・ゼーバルトの評論集。 ゼーバルトは先の大戦でドイツが経験した、連合国軍による空襲の悲惨な記憶を、戦後の社会が封印し、それを記録すべき文学者のほとんどが黙殺してしまったことを指摘しています。 しかし、その歴史はその場に立ち会った人々にとって、たしかに痛ましいものです。空襲のあとに逃げ惑う人々が殺到する駅で、婦人がトランクを落としたところ、その中から空襲で亡くなった子どもの遺体が転がり出てきた、ということもあったようです。 当事者にそれを思い出すように強いるのは酷なだけに、数少ない報告や記録から、我々は真摯に学ぶ必要があるのではないでしょうか。 本書でもたびたび言及されていますが、日本も空襲により火の海となっただけに、よその国の出来事として読むことができませんでした。 日本は先の戦争での痛みを直視できているといえるでしょうか。ドイツ同様、目を背け続けているようにおもえてなりません。 ゼーバルトに興味がある方は、本書から読んでみるのもよいかもしれません。『アウステルリッツ』『土星の環』は話題が目まぐるしく変わり、読みやすい本ではありませんが、ゼーバルトがどんな文学を評価しているのかを知れば、それらの著作を読み解くヒントになるかと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
W・G・ゼーバルトは数々の賞をとった『アウステルリッツ』で一躍有名になったドイツの作家だ。 ゼーバルトは、先の大戦中に英軍が行った無差別絨毯爆撃に対して、戦後ドイツの作家が何故か沈黙を守っていることについてチューリヒ大学で講義を行った。ゼーバルトの異議申し立てに対 し、当の作家たちから批判が起きたことはいうまでもない。『空襲 と文学』は、「空襲と文学論争」と呼ばれるその論争についての作家の言い分をはじめ、戦後ドイツ作家のあり 方を問うた「アルフレート・アンデルシュ」論他二編の作家論を収めた評論集である。 「イギリス空軍の大勢が一九四〇年に是認し、四二年二月を以て莫大な 人的資源と戦時物資を動員して実施された無差別絨毯爆撃が、戦略的ないし道義的にそもそも妥当であったのかどうか、あるいはいかなる意味において妥当で あったのかという点については、四五年以降の歳月、私の知るかぎりではドイツにおいて一度も公的な議論の場に乗せられたことはない。詮ずるところ、その もっとも大きな原因は、何百万人を収容所で殺害しあるいは苛酷な使役の果てに死に至らしめたような国の民が、戦勝国にむかって、ドイツの都市破壊を命じた 軍事的・政治的な理屈を説明せよとは言えなかったためであろう。」 この後、ゼーバルトは、他の理由も挙げているのだが、長くなるので引用はここらでやめておく。事 態は日本でも似たようなものだ。東京大空襲をはじめ、日本各地を襲った無差別爆撃について、日本が公的に議論した事実はあったのだろうか。原爆の跡地に 立つ碑にさえ「あやまちは二度とくり返しません」という意味の言葉が記されているくらいだから、日本人もまたドイツ国民と同じく「明らかな狂気の沙汰に対して ぶつけようのない憎悪を胸にためていたにしろ、空襲の罹災者のうち少なからぬ者が、空襲の猛火をしかるべき罰、逆らえぬ天罰であるとすら感じていた」ので はなかろうか。 破れた国の側の戦争犯罪が厳しく処断されるのは分かる。しかし、戦争が終わった後、勝った国の側の戦時下の行動について、その是非を問うことはできなかったのか、という問いかけはただにドイツ人だけの思いではないだろう。政治外交レベルでは難しいかもしれないが、文学の世界でなら問題提起もあり得たのでは、という思いはたしかに残る。 先の戦争について、現役自衛官の論文が問題になったが、その陰謀史観は論外であるにせよ、共感する者も多いと漏れ聞 く。公式見解から見れば大きく外れた被害妄想的な歴史観が罷り通るのは、国民のすべてが納得できるような冷静かつ客観的な分析をないがしろにしてきたせいである。そうした態度が今回のような問 題を引き起こしたのではないか。 ゼーバルトの異議申し立ては、戦後ドイツの知識人の欺瞞的な態度に対して向けられたものであるが、日本においても 戦後処理のどさくさに紛れて、過去をうやむやにして今に至った人々が政財界は勿論のこと知識人の間にも少なくない。庶民ならなおさらのこと。臭いものには蓋をしてすましているが、 蓋の下には腐敗したガスが充満して今にも爆発しそうになっている。国際的な不況、失業者の増大と点火要因はそろっている。若い世代には、「自虐史観」のレッテルに耐えられず急進的なナショナリズムに傾斜する者も増えている。払わずにすませてきたつけを払う時が来ているのではないだろうか。
Posted by
なぜドイツ人は、ドイツ作家は、第二次大戦中の連合軍による戦略的空爆について口を閉ざすのか。歴史的資料や作品をひもときながら、発展したドイツの土の下に眠る「廃墟の記憶」を掘り起こすエッセイ。 大江健三郎を引用しながら、被爆者の沈黙との類似点を指摘しているのも興味深い。
Posted by
「大都市ほぼ軒並み、小都市も多数が破壊されるというおよそ看過すべからざる、今日に至るまでドイツの相貌を決してきた事実は、一九四五年以降に書かれた作品においては、まったき沈黙、不在として遇されてきたのである。文学のみならず、家庭の会話から歴史記述にいたるまで、事態は同様であった。勉...
「大都市ほぼ軒並み、小都市も多数が破壊されるというおよそ看過すべからざる、今日に至るまでドイツの相貌を決してきた事実は、一九四五年以降に書かれた作品においては、まったき沈黙、不在として遇されてきたのである。文学のみならず、家庭の会話から歴史記述にいたるまで、事態は同様であった。勉強熱心で知られるドイツの歴史家たちは、このテーマについては口裏を合わせたように、私の知るかぎり一冊の包括的な研究どころか、基礎研究さえ表わしていない。わずかに軍事史家、ヨルク・フリートリヒが、自著『戦争の法則』の第八章において、連合軍の壊滅作戦の展開と結果を詳述しているのみである」 連合軍によるドイツ空爆がもたらした凄惨な被害・廃墟について客観的な記録であれ創作物であれ人々の公然とされる記憶であれ、まがい物やお茶を濁す程度のもの以上の記録がほとんどないのではないか、またそれはなぜかということについての講義と、ナチスの時代を描いた3人の作家についての小論で構成している。3人とは著者が意外なほど感情的になって唾棄している日和見主義者のアルフレート・アンデルシュと、葛藤の和解と忘却を拒否して覚えているという拷問を自分に課したジャン・アメリーとペーター・ヴァイスについて。3人ともここで初めて知ったけれど、なかなか興味深く描かれています。 専門の著者が調べるかぎりはまともなものがほぼ無いというレベルで、終戦直後のドイツの無残な廃墟の記録が希少であり、不自然に封じ込められ踏み越えられた「被害者」ドイツとしての屈辱や悲しみ苦しみ恐怖、痛みの経験はどこに回収されたのか、あるいはまだどこかに燻っているのか? ドイツが受けた過剰とも言える「報復」は自分たちが引き起こしたことだと納得しているのだろうか? 答えは出していないけれど、著者は一面で復興と経済活動へと昇華されたとして以下のように記していて、この部分が著者の不吉な予感のようなもののように思えた。それが当たっているかは別として。 「しかし、奇跡の経済復興には、これら多少とも歴然とした要因に加えて、純粋に精神的な次元の触媒があった。それこそが、ひた隠しにされた秘密、すなわち自分たちの国家の礎には累々たる屍が塗りこめられているという秘密を水源とする、いまなお涸れることのない心理的なエネルギーの流れだったのである――いまなお結束させているものは、その秘密にほかならない」
Posted by
ドイツ人は日本人から見たら戦争責任に対する意識は高いが、逆にその分、被害者としての面が抑圧されていることを知った。
Posted by
- 1