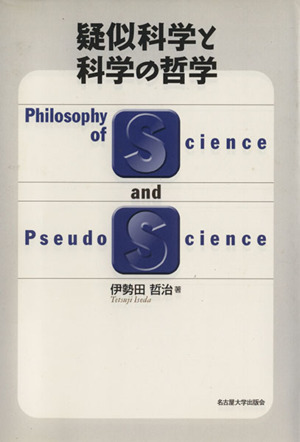疑似科学と科学の哲学 の商品レビュー
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1945055387411210536?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by
2023-04-25 大変刺激的で面白かった。ぼんやりと考えていた「科学とはなにか」という問いに関する論考がこれでもかと詰まっている。 結局明確な答えは出ていないが、明確な答えが出ないという感覚も腑に落ちた。 特に疑似科学系に吸い寄せられる人、反射的に拒絶する人、必読。
Posted by
【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA60429793
Posted by
科学って何なのか考えるために、逆に科学じゃないものについて考えるというやり方でやってて、それが良い。科学哲学がどんなことやってんのかについても理解が深まった気がする。
Posted by
科学とは何かという問いを提起する具体的な実例を紹介して、これまでの各解決案をそこに適用してゆく議論の形でした。実例を用いた議論によって視野を広げることができます。そのため、これから歴史的に科学哲学を学ぼうと思っていた私にとって、素晴らしいイントロダクションとなりました。という...
科学とは何かという問いを提起する具体的な実例を紹介して、これまでの各解決案をそこに適用してゆく議論の形でした。実例を用いた議論によって視野を広げることができます。そのため、これから歴史的に科学哲学を学ぼうと思っていた私にとって、素晴らしいイントロダクションとなりました。というのは、歴史の勉強は広い視野を要求するからです。 実例を挙げつつ、科学とは何かと問う上で疑似科学を考えることは役に立つといいます。しかし、科学と疑似科学をそれぞれ特徴づけることはできても、そのあいだに明確な線を引けない。ということを議論が進むにつれ読者は勘づきます。そこで著者が結論のために用いたものは何か。私はそれについて全く知らなかったので、著者が用いたものに興味を持ちました。 それと、もう少し最近の議論も知りたいです。
Posted by
具体的な事例(創造科学、占星術、超心理学、代替医療)に照らして科学哲学で何が問題になるのかを示してくれる良書だと思う ベイズ主義が科学哲学の問題にこれほど鮮やかに適用できるとは知らなくて、5章を読んで胸のすく思い! 研究している身としても、改めて方法論について思いをめぐらすきっか...
具体的な事例(創造科学、占星術、超心理学、代替医療)に照らして科学哲学で何が問題になるのかを示してくれる良書だと思う ベイズ主義が科学哲学の問題にこれほど鮮やかに適用できるとは知らなくて、5章を読んで胸のすく思い! 研究している身としても、改めて方法論について思いをめぐらすきっかけになって良かった。天文学を念頭に読みすすめていたので実在論/非実在論の項は特に思考をめぐらすことができた。 個別のエピソードとしては、機械論的世界観が優勢の時代にニュートンが物体同士が触れていないのに重力が伝わるなんてことを言い出して「神秘主義への退行だ」などとライプニッツとかに厳しく批判されたって話がおもしろかったな。
Posted by
切り口としてスキャンダラスとも言える疑似科学、つまり 占星術や代替医療、超心理学や創造科学などを用いては いるが、中身はきちんとした、そしてとてもわかりやすい 科学哲学の入門書。疑似科学と科学の間にいかに線を引くか ということをテーマに科学哲学の様々な考え方を解説して くれる。前...
切り口としてスキャンダラスとも言える疑似科学、つまり 占星術や代替医療、超心理学や創造科学などを用いては いるが、中身はきちんとした、そしてとてもわかりやすい 科学哲学の入門書。疑似科学と科学の間にいかに線を引くか ということをテーマに科学哲学の様々な考え方を解説して くれる。前に読んだ「科学哲学の冒険」よりは少し踏み 込んだ内容になっているかな。 著者はベイズ主義を推しているようで、今まで何冊か科学 哲学の本を読んできた身としてはそこが少々気にはなった。 人それぞれ考え方や立場があるということなのだろう。
Posted by
読書録「疑似科学と科学の哲学」3 著者 伊勢田哲治 出版 名古屋大学出版会 p145より引用 “超能力という目に見えないものの存在を主 張するなら,せめて超能力の実用化につなが るレシピを示せ,とこういう答えである。” 目次から抜粋引用 “科学の正しいやり方とは? 科学は...
読書録「疑似科学と科学の哲学」3 著者 伊勢田哲治 出版 名古屋大学出版会 p145より引用 “超能力という目に見えないものの存在を主 張するなら,せめて超能力の実用化につなが るレシピを示せ,とこういう答えである。” 目次から抜粋引用 “科学の正しいやり方とは? 科学は昔から科学だったのか? 目に見えないものも存在するのか? 科学と疑似科学と社会 「程度」の問題” 哲学博士である著者による、科学と疑似科 学を区別する境界を探る手法を記した一冊。 帰納法から統計的手法まで、科学的に正し く判断する方法を、具体例をあげて記されて います。 上記の引用は、超能力と介入実在論につい て書かれた一文。一部の人だけが使えるだけ だと、その他の人にとっては脅威になりかね ないでしょうから、積極的に誰にでも使える ようになる方法を示してほしいものです。 そういう事が出来る世界を舞台にした、ライ トノベルがありますね。 物事をしっかりと見つめて、何が本当で何 が間違っているか、慌てること無く対処でき るようになりたいものです。 ーーーーー
Posted by
***** 「科学的」とは何かを哲学的に考える、その探索の過程として「疑似科学」と呼ばれるものを問う。 統計学という探索手法によって担保する、ということがいかに科学のカバー領域を広げることに貢献したかが突き刺さった一冊。 *****
Posted by
これは面白い。「科学と擬似科学の間に明確な線引きは可能だろうか?」という問いを中心に置きながら、20世紀における科学哲学の論点を整理していくことで科学的なものの在り方がどの様に変遷していったのかを理解する事ができる。また各章の冒頭に創造科学や占星術、代替医療といった疑似科学を例に...
これは面白い。「科学と擬似科学の間に明確な線引きは可能だろうか?」という問いを中心に置きながら、20世紀における科学哲学の論点を整理していくことで科学的なものの在り方がどの様に変遷していったのかを理解する事ができる。また各章の冒頭に創造科学や占星術、代替医療といった疑似科学を例に挙げられているためか、常に具体例との対比で考えさせる構成になっているためか教科書的な退屈さは全く感じられなかった。あとがきで述べられている「健全な懐疑主義」、まっとうに疑う姿勢とその技術の必要性については心の底から同意したい。
Posted by