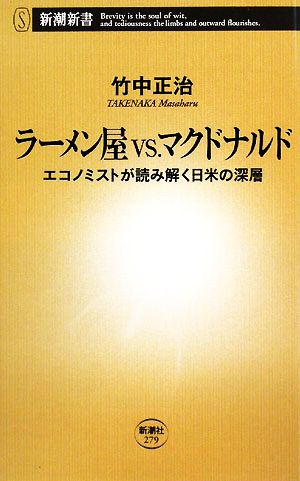ラーメン屋vs.マクドナルド の商品レビュー
2014年10月2日読了。ラーメン屋とマクドナルドの違い、に代表される日米の主に経済面での違いについて読み解く本。米国で活躍するエコノミストの著書だけあり、私が期待したような食物に関する話題はなかったが、そこそこ面白く読めた。日米の違いは巷で言われる「文化的要因」に根ざすものでは...
2014年10月2日読了。ラーメン屋とマクドナルドの違い、に代表される日米の主に経済面での違いについて読み解く本。米国で活躍するエコノミストの著書だけあり、私が期待したような食物に関する話題はなかったが、そこそこ面白く読めた。日米の違いは巷で言われる「文化的要因」に根ざすものではなく、単純に日米の法制度の違いや所得分布の違いにより人々が合理的に行動した結果に過ぎない・統計上日米の人々の思考に有意な「文化的差異」は見られない、という説はなかなか面白い。「日本人もアメリカで活躍できる。なぜなら、この私が活躍できているからだ」とでも言いたげな著者の自慢話は勘弁してもらいたいが・・・。
Posted by
地元のブックオフで購入する。正直、期待していませんでした。しかし、非常に興味深い本でした。また、読みやすい本です。まず、この本を読んで、難しいと思う人はいないでしょう。興味を持ったのは、リスクマネーの供給源です。日米の差は、リスクマネーです。国民性に由来すると指摘されています。そ...
地元のブックオフで購入する。正直、期待していませんでした。しかし、非常に興味深い本でした。また、読みやすい本です。まず、この本を読んで、難しいと思う人はいないでしょう。興味を持ったのは、リスクマネーの供給源です。日米の差は、リスクマネーです。国民性に由来すると指摘されています。それに対して、この本は資産構成の差に由来すると指摘している。多くの中流階級は、リスクマネーの供給源ではない。これは、日米ともに同じである。リスクマネーの供給源は、金持ちである。この層の厚みが、日米の違いである。生命保険、銀行、投資信託等の機関投資家は、リスクマネーを供給するのではないのか。そんなことはないそうです。あくまでも、彼らは、顧客の代理人に過ぎない。リスクを嫌う顧客の銀行は、リスクを嫌う。リスクを厭わないヘッジファンドは、リスクを嫌わない。これは、面白い仮説です。今後、この人を注目したいと思います。
Posted by
専門的な部分で難しいところも少しあるが、面白い。 文化の違いを新たな視点から知ることができる。 日本の無謬信仰。失敗を認めようとせずに同じ過ちを繰り返す。 小さい失敗を許容しながら、致命的失敗にしないことが、重要。 日本の文字文化。会話に弱い。 アニミズム。人ではない、す...
専門的な部分で難しいところも少しあるが、面白い。 文化の違いを新たな視点から知ることができる。 日本の無謬信仰。失敗を認めようとせずに同じ過ちを繰り返す。 小さい失敗を許容しながら、致命的失敗にしないことが、重要。 日本の文字文化。会話に弱い。 アニミズム。人ではない、すべてのものに魂が宿っている。 だからアメリカが超人的力をもつ人をヒーローにするのと対照的にアトムなどロボットがヒーローになる。
Posted by
日米比較文化論 エコノミストが書いた日米経済に関する比較論。 日米の文化の違いなど社会的視点からも比較をアプローチしているのが面白い。 また筆者の経験をもとにした内容も織り込まれており、 エッセイ的な要素もあり、経済という堅苦しい内容にもかかわらず、さくさくと読み進めることが...
日米比較文化論 エコノミストが書いた日米経済に関する比較論。 日米の文化の違いなど社会的視点からも比較をアプローチしているのが面白い。 また筆者の経験をもとにした内容も織り込まれており、 エッセイ的な要素もあり、経済という堅苦しい内容にもかかわらず、さくさくと読み進めることができる。 各章のタイトルからも筆者独自の比較アプローチが伝わってくるだろう。 第1章 マックに頼るアメリカ人vsラーメンを究める日本人 第2章 希望を語る大統領vs危機を語る総理大臣 第3章 ディベートするアメリカ人vsブログする日本人 第4章 ビルゲイツvs小金持ち父さん 第5章 一神教vsアニミズム 第6章 消費者の選別vs公平な不平等 様々な視点から物事をアプローチしてみる。 自分しかない独自の視点。 この本からユニークな視点を持つことの大事さも学んだ。
Posted by
日米比較の一冊。 文化、宗教、経済、政治から、サブカルチャーまで。 エコノミストによる一冊なので、経済について比較されるところが、やや多いがそれでも、中々に面白い。 ただ、冒頭の武道について触れているのだが、型を"form"と訳しており、本来の意味から離れて...
日米比較の一冊。 文化、宗教、経済、政治から、サブカルチャーまで。 エコノミストによる一冊なので、経済について比較されるところが、やや多いがそれでも、中々に面白い。 ただ、冒頭の武道について触れているのだが、型を"form"と訳しており、本来の意味から離れている。恐らく、この著者は武道に携わったことはないのであろう。 著者自身が危惧していたステレオタイプを、冒頭で既に自ら披露している。 各章題が興味を惹く、良いセンスなので、御紹介。 第1章 マックに頼るアメリカ人vsラーメンを究める日本人 第2章 希望を語る大統領vs危機を語る総理大臣 第3章 ディベートするアメリカ人vsブログする日本人 第4章 ビルゲイツvs小金持ち父さん 第5章 一神教vsアニミズム 第6章 消費者の選別vs公平な不平等
Posted by
日米の違いが納得いくように書かれています。ところでこの内容が難しいと思う僕はダメですか?勉強不足ですか?
Posted by
「すべての人が同じものを欲しがって、なおかつそれが少しずつ変化していく事」が市場原理主義の究極の姿だとすると、マクドナルドやiPadのようなアメリカ型の商品が理想ということになる。でも僕は「ラーメン屋さんの秘伝のたれ」を追い求めたいな。 「アーティストは自分の創作したいものを作...
「すべての人が同じものを欲しがって、なおかつそれが少しずつ変化していく事」が市場原理主義の究極の姿だとすると、マクドナルドやiPadのようなアメリカ型の商品が理想ということになる。でも僕は「ラーメン屋さんの秘伝のたれ」を追い求めたいな。 「アーティストは自分の創作したいものを作って、結果として売れたり売れなかったりする。職人は受注があって初めて仕事が始まる。アーティストは創作に好きなだけ手間暇をかけるが、職人は発注者との関係で時間と予算が限られた中で腕を振るう。」アーティストとして職人へ進化したい。
Posted by
タイトルを読んで外食産業の話かとおもいきや、内容はアメリカと日本の違いについての話です。 アメリカ人が日本人に比べてプレゼン能力が高い理由は、日本の文字文化にあるという。 英語は日本語に比べてものすごく単純なため、小学校において学習に費やす時間が少ない。その分、アメリカの小...
タイトルを読んで外食産業の話かとおもいきや、内容はアメリカと日本の違いについての話です。 アメリカ人が日本人に比べてプレゼン能力が高い理由は、日本の文字文化にあるという。 英語は日本語に比べてものすごく単純なため、小学校において学習に費やす時間が少ない。その分、アメリカの小学校では口頭で自分の意見を述べる訓練がされているそうです。 一方、ひらがな、カタカナ、漢字の3語を使いこなし、繊細な表現が可能な日本語の学習においては、とにかく「書く」ことを重視しているようです。 アメリカにおいて"Book Report"などといった、いわゆる読んだ本の感想を口頭で述べるという課題があるそうですが、日本の場合は「読書感想文」を書いて終わり。 つまり、ディベートがない、ブログに似ています。 実際に、世界的に見てもブログの書き込み言語のシェアで日本語が占める率は英語より多いそうです。もちろん人口でみたら英語ユーザーの方が圧倒的に多いそうです。 「書く」ことを学んできた日本人と「口頭」で述べる事を学んできたアメリカ人の違いが、プレゼン能力の差をつくっているというのです。 これを悪いことと見るか良いことと見るか難しい所だとは思いますが、「書く」訓練をさせられてきた日本人の行き着くところが、匿名性の高いブログや掲示板サイトの書き込みだとすると、あまり良いことばかりには思えませんね。。
Posted by
タイトルに惹かれて購入したのだが、ほとんど論点として出てこなかった。しかし、アメリカの政治経済について、様々な見方が示されており、興味深く読みました。
Posted by
日本とアメリカの経済の違いについて、またそれに関する一般的な誤解について書かれた本。 銀行員時代に教わったセールストーク 「アメリカの一般家庭では資産の3割を投資で保有してるんですよ」 のからくりを知ることができた。
Posted by