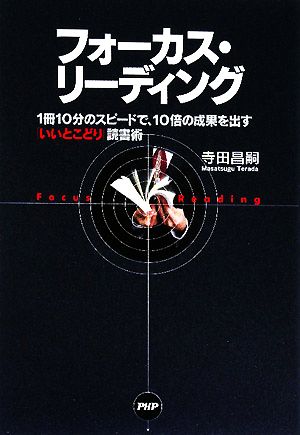フォーカス・リーディング の商品レビュー
"右脳速読"とか、オカルト的なものを排した、地に足の着いた速読法。 自分は、著者の開発した"SRR速読ソフト"を使って訓練していたことがある。役に立ったのかはわからないが、ボケ防止にはなってたかもしれない(笑)。 斉藤英治氏の2日セミナ...
"右脳速読"とか、オカルト的なものを排した、地に足の着いた速読法。 自分は、著者の開発した"SRR速読ソフト"を使って訓練していたことがある。役に立ったのかはわからないが、ボケ防止にはなってたかもしれない(笑)。 斉藤英治氏の2日セミナーにも出たことがある。本書の方法も、それと通じるものがあったような(スキャニング、スキミング)。 いつの間にか"頭から読む"方法に戻っていた。1冊10分の境地には達していない。 内容の薄いビジネス書でも2時間くらいはかかるし、300ページを超えるような専門書だと、2~3日では読み終わらない。 速読というより、"情報処理能力の開発"という意識で取り組むのが吉。
Posted by
※以前に読んだ本の登録 ざっくりメモ 1冊の本をどれくらいの時間をかけて読むのか、短い時間で読むためのノウハウが詰まった本。超人的な速読のような読み方ではなく、どのように時間コストを削減して読むのかの読み方の考え方が勉強になる。 また1冊の本を理解するのに3回くらい読むことや、...
※以前に読んだ本の登録 ざっくりメモ 1冊の本をどれくらいの時間をかけて読むのか、短い時間で読むためのノウハウが詰まった本。超人的な速読のような読み方ではなく、どのように時間コストを削減して読むのかの読み方の考え方が勉強になる。 また1冊の本を理解するのに3回くらい読むことや、速読するときの目の意識の仕方は少し参考になった。 メモ ・本を読むほど成長できる、丁寧に読むほど学びが多くなるわけではないことを理解する。 ・どう読むかではなく、何を読まずにすませるかも考える。意識すべきは速さではなくフォーカス。 ・本を通じて著者の思索の跡をなぞっただけで知った気になっていけない。自分の頭で考える作業をすること。頭を働かせない読者はマイナスになる。 ・読書自体が目的ではない、本を読んで目的を達成することである。何のために本を読むのか?何を手に入れたいのか?読むことに価値があるのか?
Posted by
・あえて積ん読する 読みたいという気持ちを増幅させる 繰り返し読むことも重要 ・著者との対話 著者との対話を意識する。意見を押しつけられる一方向の読書ではなく、自分の考えと擦り合わせる双方向の読書を実践する ・本はあくまで参考文献 これが一番印象に残った。 本を読んでメモしなけれ...
・あえて積ん読する 読みたいという気持ちを増幅させる 繰り返し読むことも重要 ・著者との対話 著者との対話を意識する。意見を押しつけられる一方向の読書ではなく、自分の考えと擦り合わせる双方向の読書を実践する ・本はあくまで参考文献 これが一番印象に残った。 本を読んでメモしなければならないのは本に書いてある言葉ではなく、読み解く過程で自分が考えたことである。 (本に書いてある言葉は本を開けばまた確認できるが、その瞬間の自分の思考には二度と会うことができない)
Posted by
時間をかけずに、効率的に、その本を真に理解するための読書法。 速読法に関する箇所は、個人的にはやや疑問。 早く読むことのデメリットもあると考えているため。 ただし、読書に臨む姿勢という点については、これまでの自身の読書に向かう姿勢に対して、 多いに反省をするとともに、改めて読...
時間をかけずに、効率的に、その本を真に理解するための読書法。 速読法に関する箇所は、個人的にはやや疑問。 早く読むことのデメリットもあると考えているため。 ただし、読書に臨む姿勢という点については、これまでの自身の読書に向かう姿勢に対して、 多いに反省をするとともに、改めて読書という貴重なインプットの場をもっと有効活用したくなった。 まずは、本を読むことの目的を読む前に今一度見直す。 読後の成長という漠然としたものは当然として、どういった知識を仕入れ、どうありたいのか? また、読書にかかっている自分の人生の時間というコストをよく考え、 目的をキチンと踏まえた上で、無駄な読書はしないようにする。 この2点をよく認識し直し、読書という行為が目的化しないように心がけを改める。
Posted by
いかに、速読するかがテーマ。 じっくり本を楽しみたい、基礎的な本をじっくり読み込みたいという方には不向き。膨大な資料から、必要な箇所を短時間で抽出したいという目的であれば、価値はあると思います。感じたことばは、 ①フォーカス、②スキミング、③スキャニング です。
Posted by
本があふれている。何をどう読むかではなく、何を読まずに済ませるか、を考える必要がある。 最近の新刊書は、文字数だけで見ると小学生向けの本と同じレベル。 買ってきた本はその日のうちにすべて目を通る。 「これから」本を分けておく。読み返すものはこちらに分類。 読書の時間は天引き。 ...
本があふれている。何をどう読むかではなく、何を読まずに済ませるか、を考える必要がある。 最近の新刊書は、文字数だけで見ると小学生向けの本と同じレベル。 買ってきた本はその日のうちにすべて目を通る。 「これから」本を分けておく。読み返すものはこちらに分類。 読書の時間は天引き。 アウトプットも時間効率を考える。 メモを取るよりも、行動する。 1冊の本で、ひとつでも行動が変わったら十分。
Posted by
•ダイレクト出版のフォーカスリーディング三日間集中講座を購入して、補助教材として読書。 •ポールシーリィ氏のフォトリーディングと基本的な考え方は同じのように感じた。すべての速読学習に言えることだが、速読する目的を明確にする、目の視野を拡げて文字を風景の様に観る、文字から浮かび上...
•ダイレクト出版のフォーカスリーディング三日間集中講座を購入して、補助教材として読書。 •ポールシーリィ氏のフォトリーディングと基本的な考え方は同じのように感じた。すべての速読学習に言えることだが、速読する目的を明確にする、目の視野を拡げて文字を風景の様に観る、文字から浮かび上がる白い集中した意識で読む(自分はこの意識は潜在意識ではないかと思う)という方法は共通している、と思う。
Posted by
速読の非科学性を排除して、読むスピードを追求し、内容をしっかりと頭に叩き込む方法を解説しています。 読む本によって、読み方によって、スピードを変えるのは、まさにその通りですね。 速読に魔法のような方法はありません。 何のために読むのかも、大切ですね。
Posted by
読書スピードを早めて多くの本を 読めるようになりたい! 読書スピード(input)を早めて outputの時間を増やしたい! そんな人にはヒントをくれる本です! 感想 読書を通じて人生を豊かにして欲しいという筆者の想いが伝わってきます!読書一つとってもこれだけやりようがある...
読書スピードを早めて多くの本を 読めるようになりたい! 読書スピード(input)を早めて outputの時間を増やしたい! そんな人にはヒントをくれる本です! 感想 読書を通じて人生を豊かにして欲しいという筆者の想いが伝わってきます!読書一つとってもこれだけやりようがあるのだなぁというのに驚いたのと、明日から意識してトライする事をそれこそフォーカスして使わないと役立てないのかなぁと感じさせてくれます。 ▽フォーカスリーディングとは何か? –リターンをクリアにしてフォーカスする読み方 –1冊10分で10倍の成果につなげる技術の型 –トレーニングを経て身につく技法 ▽フォーカスする事がなぜ大事なのか? –フォーカスしないと情報の取捨選択ができない。 –取捨選択するからスピードが上がる。 –即ちその本を通じてどう成長したいのか? にフォーカスする事。 ▽どのように身につけるのか? –心/TPOを決める。 (T→納期が迫ってる! (P→提案書の提出!) (O→提出しないとコンペ負け!) –技/段階的にトレーニング (1週目30分(15分下読み15分本ちゃん読み)) (2週目30分(10分下読み15分本ちゃん読み5分振り返り)) (3週目30分(10分の本ちゃん読み20分の処理)) –体/立って読むと呼吸法 ※本書では他にもいくつも紹介されています。 参考メモ① 読書の投資対効果=input力(筆者の力※仕入×あなたの経験値/読書にかけた時間)×output力(ビジネス力) ※経験値が0.5等であれば、何度も同じ本を読むと言うアプローチの方が良い場合がある。必ずしも多読が○という訳ではない。 参考メモ② 狩猟採集型→いいとこ取り読書 農耕型読書→じっくり時間をかけて言葉と格闘しながら、行間を感じ取るそんな読書。古典とかを読むのに向いているかも。宮里流ゴルフ子育て法では静筋と動筋という表現で、静筋とは集中力を高く保ち、冷静に思考、分析、判断する頭脳で、読書で養われると。 ※素早く身につくモノは素早く忘れる 参考メモ③ 時は流れない。それは積み重なる。サントリーウィスキーのCM。 参考メモ④ 本は読み重ねなければ意味がない。最低3回重ね読もう。 ※inputに10分は目指すが実際、わかる→できるにする為には最低3回やinputの倍以上の時間が必要なのかなという感じ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
速読の技術についてもいろいろ書いてありますが、読書の心構えについても参考になることが色々書いてあります。昔フォトリーディングのセミナーをうけた事があるのですがそれとは別のアプローチが興味深かったです。 速読というといかに本をたくさん読むかの視点になりますが、ここで著者は釘をさします 一番響いた部分の引用 多読が奪う一冊の価値 多読をすること自体が目的となると、本来読後のフォローにあてられるべき時間が、次の1冊のために奪われていきます。量を求めることの弊害はここにもあります。 読んで手に入れた知識を生かすにせよ、さらに深めるにせよ、「読んだ後」こそ重要なのです。知識をしっかりと定着させるために、何度も読み返しながら思索にふける。あるいは自分の現場で実行してみる。そんな大事な作業が、次の「読む楽しさ」に奪われていくわけです。哲学者ショウペンハウエルの言葉を借りれば、「多読すればするほど、読まれたものは精神の中に、真の跡をとどめない」(岩波文庫『読書について』より)ということなのです 引用ここまで 速読に関する考え方はいろいろあるでしょうが、せっかく読むのであれば身につけたい、そのあたりまえのことを忘れないようにしたいと思います。
Posted by