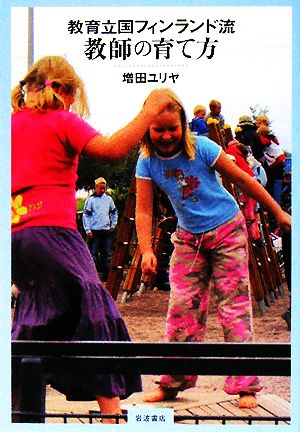教育立国フィンランド流教師の育て方 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
体育の授業で釣り 学校にサウナ 算数は嫌い 子どもの姿は世界共通 教師の力量が全て 魅力あふれる人になれ 「好奇心旺盛、何かのプロ、人間関係が円滑、自然体」 子どもたちから質問攻め 基礎を徹底するためのテスト グループ学習1〜8 作家と作品の分析 テーマを与え、担当を決める 時間は20分 教師は、常に学び続けなければならない
Posted by
教員経験のある著者が、フィンランドのいくつかの教育現場の様子をインタビューを含めて取り上げた一冊。著者に教員経験があり現状をふまえた上で書いているので、「日本の教育現場との違い」を意識しやすい一冊。 日本の教育との違いを問われたフィンランドの校長の答え「オペッタヤ、オペッタヤ、...
教員経験のある著者が、フィンランドのいくつかの教育現場の様子をインタビューを含めて取り上げた一冊。著者に教員経験があり現状をふまえた上で書いているので、「日本の教育現場との違い」を意識しやすい一冊。 日本の教育との違いを問われたフィンランドの校長の答え「オペッタヤ、オペッタヤ、オペッタヤ(教師、教師、教師)!」(p.43)に尽きるのかな、と。 まず、教員が医師と並ぶ尊敬される職業で、大学の教員育成課程は修士含む6年課程であるにもかかわらず、倍率10倍を越える人気学部であること。高校卒業後に大学に行く、とは限らないので、年齢・職歴の多様性を持ちつつもほんとに教員になりたい人が教員になるし、それに合わせた高度な指導が行われる。 また、「実習生ガイダンスの研修」(p.113)に代表される現役教員向けの研修課程が、すごく合理的に機能していること。似たような研修があってもそれがうまく機能していない印象をうける日本と何が違うんだろう、という印象を受ける。時間が足りないのか、研修体系が悪いのか、そもそも教員のレベル差に起因するのか、違いが気になった。 そういう人を取り上げているんだろうけど「この先生はこういう『ずばぬけたもの』があって、それを自他(生徒・教員)ともに認めている」教員が、それを生かして授業を展開している感はある。 それでいて(そうであってこそ?)、フィンランドの教育の基本は「平等である=おちこぼれを作らない」ことらしい。 矛盾しているのかもしれないし、モチベーションの低い生徒にとって「目の前のこの人、尊い」以上のきっかけはないともいえる。 PISAの高得点で視察者が増え、視察時に「一校の訪問につき200ユーロを学校に支払わなければならなくなった」(p.142)フィンランドから学べること、それは「フィンランドと日本の違いは『ちょっとした違いの積み重ね』」なのかな、と。少なくとも「フィンランドに一度視察に行ったら、学校変わった」的なことはないのかも知れないな、という印象を受けた。
Posted by
環境や教育方法が違っても、子どもに関する悩みは同じだと改めて思った 政治や経済云々よりも教育が国を支える、だから人間を育てようという考え方がよい
Posted by
日本もかつては教育立国と呼ばれていたはずだが。 現在学力世界一と言われているフィンランドの教育現場のレポート。 教育を大切にしない国の発展は無いと思うのだが、日本は反省しなければならないだろう。 フィンランド流を真似るだけで良い結果が出るとは思えないが。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なんだ、社会の認識が誤っているから教育がおかしいってことになってるんじゃん。餅は餅屋に、教育は先生に! フィンランドがこの本にあるような懐の深い考え方をできるのも、共産主義的素養があるからって気がして、簡単には見習えないなって思う。どうやら、そのフィンランドも漏れなく自由主義の影響を受けてきているようだけれど、いつまでうまくいくかな? でも、教員の水準を高くしているから、臨機応変に対応していくことができるんだろうな。 たぶん、移民の経済格差や教育格差とかがネックになってくるんだろうが、どうなっていくのだろう。興味津々。でも移民教育にもきちんと力を入れているあたり、先見の明があるね。 ___ p10 教育省は予算集めだけ 教育省と国家教育委員会は相互不干渉である。いーなー。最近の日本では政治が教育に干渉しまくっている。政教分離はどこ行った。教育の責任とか言うけれど、そんなん土台無理な気がするんだ。あんまり責任を追及すると、暴走が起きると思うんだよね。 p11 コアカリキュラムは指導要領ほど細かくない 教師への信頼と教師の実力があるからできる。民主党時に教員免許取得要件を修士卒にするってあったけれど、今思えばそれは正しいと思った。院の時代に教育実習をたくさんできるようにするのはいいことだった。 p16 教育の目的は多様性 フィンランドは各自治体が自分の地域の構成員を作り上げるという意識が強い。地域にはいろいろな職業人が必要である。農家、工務店、教師、小売店、etc…多様な人材を育てなくてはいけないのである。でないと将来自分たちが生きていけなくなるから。 たぶん、フィンランドは賃金格差が小さいんではないかな。だから多様な就職先に人材が散っていける。今の米国や日本は格差があるから優秀な人材の就職先は一極集中になる。なんとかしてくれ。 p17 ブランド欲のなさ!! 日本人や中国人はすぐ学歴を聞きたがる。中国が昔から学歴社会を作ってきたからしょうがないけど、なかなか変わらないものだね。 p20 フィンランドは真っ当なことをしているだけ それや!この一言にすべて詰めこまれた。 p29 いちいち配慮しない でた、フィンランドの真っ当なこと。もうね、日本は気にすることがなくなって無理やり心配しているよね。運動会で一位になれない子の気持ちとか、授業参観で親が来れない子の気持ちとか。 p95 2007年のフィンランド高校生銃乱射事件 よく聞く「おとなしい子だったのにぃ…なんで…」的な事件。冷たい家庭の最悪の結末。こういった事件はどうしようもないよね。 でも、さすがにこれは配慮しないわけにはいかないよな。 p133 情報選択能力を伸ばそう もう知識は十分。情報が溢れている。これからは必要な情報を選ぶ力をつけるのが大事である。 それな。日本みたいなテスト結果の評価に重きを置く教育では伸ばしにくい力。評価の考え方を何とかしなくてはいけないですよね。 p156 教育は実力をつけるもの フィンランドの真っ当なこと。実力がついてなかったら、義務教育でももう一年。嫌々ではなく、自己判断でもう一年やるところが意識の違いだよね。 p176 愛国心について 「そんなん教えようと思って出来るもんではない。」フィンランドの真っ当。 大人が国を愛せれば、子供もそれを見習うんではないかな。安倍さん。 p176 日本には余裕があるのよ そうなんだよね、ハイレベルな社会だから、能力の見合わない人間が出てくるんだよね。自分でハードル上げて、飛べなくてフラストレーション高まっているだけなんだよね。 日本は余裕を怠惰・驕りととらえる慣習があるから、苦しい。 日本の課題は余裕をどう捉えていくかである。生かすも浪費するも自分たち次第である。 p185 しわ寄せ 最近のフィンランドでも家庭に余裕がなくなってきているらしい。夫婦共働きや50%くらいの離婚率やら。保護者が子供の成長を支え切れなくなって、そのしわ寄せが学校に来る。 このままいくと、フィンランドでも教育に過剰な責任が課せられて、首が回らなくなってしまうのか!? ___ 増田ユリヤさんの本はほかのも全部読んでみようと思う。そういう好感触な内容だった。
Posted by
フィンランドの教育事情がよくわかった。 現役教師の方が書かれているせいか、先生方へのインタビューも多く、意外と多様なバックグラウンドの方が教師になっているんだなと思った。 日本だと大学の学部を出てそのまま教師になる方が大半だろうが、大学=>学校補助=>大学院や、大学=>就職&...
フィンランドの教育事情がよくわかった。 現役教師の方が書かれているせいか、先生方へのインタビューも多く、意外と多様なバックグラウンドの方が教師になっているんだなと思った。 日本だと大学の学部を出てそのまま教師になる方が大半だろうが、大学=>学校補助=>大学院や、大学=>就職&自分を見つめ直す=>教育大学院など、異分野から来る方もいるようで面白いな。 教員採用も結構柔軟に対応してくれるようで。 移民は想像より少なかったが、母語学習を週2時間保障し、交通費も支給しているのに驚いた。移民に「フィンランド人になってほしいわけじゃない」とい意見も見られ、大らかだな〜と思う。2007年に学校で銃乱射事件が起きても監視強化をするのではなく、不安に思っていることを声を出して話し合うことを大切にするのにも現れている。 以下は特に心に残ったことメモ: ・高校は単位制で好きなことを深堀できるが勉強は大変、 ・政治に無関心で居られる日本には、まだそれだけの余裕があるのでは ・愛国心は人にこれこれこうだから、と教えられるものではない。
Posted by
PISA調査や全国学力試験以降、世界的に注目されるようになったフィンランドの教育。でもその秘密は、教科書でも学校でもなく、教師の専門性にあった。フィンランドの教師はその専門性の高さから、子どもからだけでなく、政府や教育機関、市民からも支持を得ている。教師とはどうあるべきか、また、...
PISA調査や全国学力試験以降、世界的に注目されるようになったフィンランドの教育。でもその秘密は、教科書でも学校でもなく、教師の専門性にあった。フィンランドの教師はその専門性の高さから、子どもからだけでなく、政府や教育機関、市民からも支持を得ている。教師とはどうあるべきか、また、日本の教員養成機関の課題を考えさせられる。
Posted by
ここ最近学力世界一として注目されている、フィンランドの教育のよい面だけでなく課題も、フィンランドの教師へのインタビューを通して実態としてレポートしているところに好感が持てます。
Posted by
今まで何冊か フィンランドの 教育についての本を 読んだが、 この本が一番分かりやすかった(^^*) 分かりやすさとともに バランスのよい感じ。 珍しくフィンランドの 教育実習にも触れていた うん、満足満足。 なにより作者自身が 高校教師であり フィンランドの教育を...
今まで何冊か フィンランドの 教育についての本を 読んだが、 この本が一番分かりやすかった(^^*) 分かりやすさとともに バランスのよい感じ。 珍しくフィンランドの 教育実習にも触れていた うん、満足満足。 なにより作者自身が 高校教師であり フィンランドの教育をみて 日本の教育について 悩んでる姿が 文章にみえて、 親近感がわいた。 おすすめ
Posted by
日本にあるものよりもアチラの国にあるものが無条件に断然優れているなんて話を聴くと、やっぱりちょっと眉につばを付けてしまう。別に日本は誰にも負けないと思っているわけではなくて、同じ人間のやっていることなのだから、無条件に優れているとか、そういうのってあんまりないのではないかと思う...
日本にあるものよりもアチラの国にあるものが無条件に断然優れているなんて話を聴くと、やっぱりちょっと眉につばを付けてしまう。別に日本は誰にも負けないと思っているわけではなくて、同じ人間のやっていることなのだから、無条件に優れているとか、そういうのってあんまりないのではないかと思うからだ。 まして、教育の話になるとなおさらで、カエサルの言葉ではないけど「人は自らの見たいものを見る」、つまり作者が自分の主張を述べるための材料として、都合のいい一面だけを取り上げているのではないかって思ってしまう。 もっとも、常に全体像を冷静に見なければ意味がないのかと言えばそういうわけではなくて、学ぶべきものは常にあるし、「この部分はうちよりも優れている」と率直に認めて、そのよいところを取り入れる努力をするというのは大事なことだと思うのだ。そういう意味でこの本は、学ぶべきものがたくさんあふれている感じで興味深く、また楽しく読めた。 教育立国を支えるのは、一にも二にも教員の質であるというのは、なるほどその通りだと思う。そしてその言葉に恥じないだけの立派な先生がたくさんいるように読んでいて思った。だけど、個々の先生の才能と努力ということではすまない部分がいくつもあって、そのうち特に3つが、強く印象に残った。 ひとつは教員養成のシステムである。特に日本でいうところの教育実習のやり方が徹底していて、確かにこれなら実践的な力を持つ先生を育成することが出来るだろうと思う。教員を養成する資格というものがあって、その資格を持っている現場の先生がたくさんいて、そういう先生がつきっきりて教員の卵(つまりは後輩)を育てる。しかも、そういう先輩が納得するまで実習が終わらない、なんていうのはものすごいシステムだと思う。 もうひとつは、先生個々の力量や努力だけに頼らず、きっちりとチームを組んで子供を支援する考え方が徹底していること。学校の中に専門家によるチームがいくつも組まれ、それが先生のバックアップをしている。規模というか取り組み方の本質が僕の知っている学校とはずいぶん違う。あえて無理矢理近いものをさがすと、医者かな。毎週会議があって、一人一人の子供の状況をチェックし、不安な面があれば対応をする。これを、「学校の先生」の裏で専門家がやっている。子供だけではなく、教職員にも無理をさせない、無理をさせると破綻するって前提がまずあって、その上できめ細かく子供をケアするには、こういうシステムが必要だって考えていく感じだ。 最後が、そういうのを全部含める形で、子供一人一人を大切にする姿勢が徹底していること。特別な教育的支援が必要な子供たちを、可能な限り普通教室に入れ、丁寧に指導できるだけの人手と知恵を投入するやり方などはとても印象的だった。人手と知恵とによって、落ちこぼれをつくらない。真に、個々の能力に応じた教育を、集団の中で保障していく、そういう感じがよい。教員養成だって、全体指導はもちろんなのだけど、それ以上に個々の子供の様子をどう把握し、それにどう対応するかを大切にしているように思う。 まあ、ため息をつきながら読み終えたわけだ。最初に書いたように、都合のいい面だけを取り上げているのではないかと思ったりもするのだけど、仮にそうだとしても十分に刺激的である。教育行政の話などになればキリはないかもしれないが、個々の教員が自分の問題として、目標にするべき要素もたくさん持っているような気がする。 フィンランドの教育はこのところ非常に注目されているけれど、それもなるほどなと思いながら読んだ。「学習到達度調査の順位」という結果にこだわる必要はないと思うけど、真に子供を大切にする教育立国のあり方というのは学びたい。順位を上げるために手段を選ばず、ということにだけはならないように。
Posted by
- 1
- 2