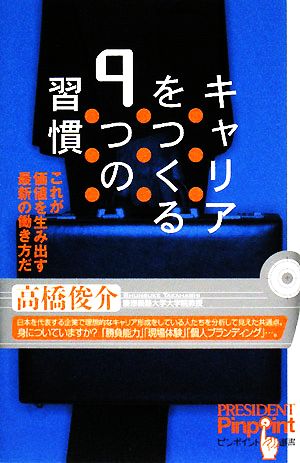キャリアをつくる9つの習慣 の商品レビュー
[ 内容 ] 目標・計画・意思だけでは、道は拓けない。 日本を代表する企業で理想的なキャリア形成をしている人たちを分析して見えた共通点=「9つの仕事習慣」を身に付けよう。 [ 目次 ] 1 9つの習慣その1 勝負能力 2 9つの習慣その2 現場体験 3 9つの習慣その3 ネット...
[ 内容 ] 目標・計画・意思だけでは、道は拓けない。 日本を代表する企業で理想的なキャリア形成をしている人たちを分析して見えた共通点=「9つの仕事習慣」を身に付けよう。 [ 目次 ] 1 9つの習慣その1 勝負能力 2 9つの習慣その2 現場体験 3 9つの習慣その3 ネットワーク 4 9つの習慣その4 仕事に意味付け 5 9つの習慣その5 個人ブランディング 6 9つの習慣その6 相手の価値観を理解する 7 9つの習慣その7 ポジティブに巻き込む 8 9つの習慣その8 経験と気付きで学ぶ 9 9つの習慣その9 仕事の言語化、仕事の見える化 10 これからのキャリアの条件 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
一般的な精神論に終わらない内容 表紙、分かりずらいけど、ビジネスマンがスーツケースを持っているイラストですね。 個人的に興味があったのは、 1つ目の習慣:勝負能力 - 3つの動機の分類 5つ目の習慣:個人ブランディング - サラリーマンとプロフ...
一般的な精神論に終わらない内容 表紙、分かりずらいけど、ビジネスマンがスーツケースを持っているイラストですね。 個人的に興味があったのは、 1つ目の習慣:勝負能力 - 3つの動機の分類 5つ目の習慣:個人ブランディング - サラリーマンとプロフェッショナルの違い 8つ目の習慣:経験と気づきで学ぶ - ラーニング・カーブ 特に、こんなラーニング・カーブは今まで見た事がありませんでした。 そんな仕事は無駄だ、とか、効率が悪いとか言う前に、いろんな仕事を体験し、 そこでしか学べないものを学ぼうよ!そうすると、キャリアの幅が広がるよ!
Posted by
目新しいことはなく、当たり前のことだが、それがなかなか難しい。 確かにキャリアって大きな目標はあったとしても、そこまでの道はどうなるかわかんないでしょう。5年後ですらわからない世の中ですから。(笑)
Posted by
最近、自分のキャリアについて考えを深められる本を読むのにはまっている。 スローキャリア、キャリアショックなどの本を含め、 高橋俊介のそれは、 新しく、かつ自分の言いたいことをよく突いてくれている文が多いので 読みたくなる本が多い。 まだまだ少ないこの選択肢を応援されているような...
最近、自分のキャリアについて考えを深められる本を読むのにはまっている。 スローキャリア、キャリアショックなどの本を含め、 高橋俊介のそれは、 新しく、かつ自分の言いたいことをよく突いてくれている文が多いので 読みたくなる本が多い。 まだまだ少ないこの選択肢を応援されているような気持ちになる。 うん。これでいいんだな、と。
Posted by
人は"動機"で動いている ⇒大きくキャリアに影響する ⇒"動機"に応じて、キャリア設計の考え方も異なる "遊び"も大事な要素 ⇒最近のホワイトカラーは"論理性"の思考が強い (山)
Posted by
高橋先生の最新刊なので、図書館で予約。 手に取ってみて、あちゃ。20代半ば〜後半くらいの社会人対象の本でしょうか? ゆったりした行間の133ページの本で、すいすい読めます。ビジネス誌「プレジデント」の特集をリライトしたものかな? とはいえ、高橋先生の本は、読むだけで元気になれます...
高橋先生の最新刊なので、図書館で予約。 手に取ってみて、あちゃ。20代半ば〜後半くらいの社会人対象の本でしょうか? ゆったりした行間の133ページの本で、すいすい読めます。ビジネス誌「プレジデント」の特集をリライトしたものかな? とはいえ、高橋先生の本は、読むだけで元気になれます! キャリア系の本は、計画→実行というパターンを踏めないからこそ今の私があるんですけど、、と思ってしまうような、計画性やら努力やらを強制される息苦しさを感じることもあるけれど、これは大丈夫です。 もっと本質的なことを、迷える子羊たちに教えてくれるような印象です。 スミマセン。コメントというより、私の独断に満ちた独り言です。 で、9つの習慣だけ以下に記す。 1:勝負力 2:現場体験 3:ネットワーク 4:仕事に意味づけ 5:個人ブランディング 6:相手の価値観を理解する 7:ポジティブに巻き込む 8:経験と気づきで学ぶ 9:仕事の言語化、仕事の見える化 若手社員向けビジネス書ですが、仕事に前向きになれたので、自己啓発にカテゴライズしてみた。
Posted by
実はこの本の真骨頂は、内容ではなくそのタイトルにあります。 キャリアとはゴールではなく習慣である、というテーゼこそが高橋先生の主張するところです。 「9つの〜」なんてタイトルだけ見るとよくある「How to本」の類と誤解されそうですが、内容的には先のテーゼを具体例からスタートして...
実はこの本の真骨頂は、内容ではなくそのタイトルにあります。 キャリアとはゴールではなく習慣である、というテーゼこそが高橋先生の主張するところです。 「9つの〜」なんてタイトルだけ見るとよくある「How to本」の類と誤解されそうですが、内容的には先のテーゼを具体例からスタートしてきちんと特化⇒汎化したロジックを説明しています。 高橋先生は多作なのでどれから読み始めればいいのか選びにくいのが難点(?)ですが、この本なんかは入門用としていいのではないかと思います。
Posted by
ページ数135P と薄めの本 中身もまとまりがあり 読みやすかった 読みやすいから 内容がうすいのかと思いきや 要点の返し読みをしたら 自分をゆさぶってくれる言葉が ぞろぞろできてことに 驚いた 好ましいキャリアを築いている人の特徴 1価値を創造し提供している人 2仕事を...
ページ数135P と薄めの本 中身もまとまりがあり 読みやすかった 読みやすいから 内容がうすいのかと思いきや 要点の返し読みをしたら 自分をゆさぶってくれる言葉が ぞろぞろできてことに 驚いた 好ましいキャリアを築いている人の特徴 1価値を創造し提供している人 2仕事を楽しんでいる人 3貪欲に成長している人 なにに揺さぶられたたかというと 行動という形に現れるその裏側にある 動機 というポイントだった 成功動機 社交動機 感動動機 自己管理動機 〜したい という動機があって 行動につながる そして その動機が人によって違う さらに 自分の中に 強い動機 と 弱い動機があり その自分の中の強弱 優先順位 と他人の動機の強弱 優先順位の違いが 人間関係のトラブルになる という事に 改めて気づいたことだった よかれ と思ってしたこと が 反感をかう というのはこういう事かと。。感じたのであった。
Posted by
◆何を身につけていけばいいのか悩んでいる若手社員の、考え方のヒントになるような本。 ◇日ごろどのように仕事に取り組んでいるか、日々の習慣の積み重ねによって、その人のキャリアの質は決まる ◇自分のもっているどの動機が、現在の仕事にどのように活かせるかを考え、そこに火をつけるとい...
◆何を身につけていけばいいのか悩んでいる若手社員の、考え方のヒントになるような本。 ◇日ごろどのように仕事に取り組んでいるか、日々の習慣の積み重ねによって、その人のキャリアの質は決まる ◇自分のもっているどの動機が、現在の仕事にどのように活かせるかを考え、そこに火をつけるというのが、仕事を楽しみながら成果をあげるコツであり、好ましいキャリアづくりの第一歩だといえよう ◇世に流通しているキャリアづくりの方法論や考え方は、最初に高い目標を持つことを説くものがほとんどだが、それはコミットメント系の達成動機やパワー動機などをもった人にとってのみ有効なのであって、決して万人向けではない ◇自分が得た知見や確信、自分の考えを抽象性の高い言葉で「こうだ」と表現でき、さらに「たとえば」と迫力ある事例で説明できる、これが人を「ポジティブに巻き込む」伝達能力であり、これが自然にできる人のことを、コミュニケーション能力があるという ◇仕事と趣味ではどこが違うのか。それは、価値を創造し提供しているかどうかという点だ ◇プロフェッショナルとサラリーマンの違いはなにかといえば、それは仕事を通じて価値を生み出し、それを顧客や社会に提供することを常に意識しているかどうかの差だ ◇「自分が人にされて平気なことでも、それがたまらなく不快だと感じる人もいる」ということがわかっていない人、さらにその違いを受け入れられない人は、キャリアもうまくつくっていけない ◇現代のように環境の変化が激しい時代だと、過去の経験はすぐに陳腐化してしまうので、常に学習し変化に対応できるよう、誰もが自分を変容し続けていく勇気をもつべき ◇どの仕事が自分に合っているかどうかなどということは、実際に自分で働いてみないかぎりわかりはしないのだ。もっと正確にいうなら、その仕事に何年か従事してはじめてやりがいもわかるし、また、その仕事を通して成長することで、次に進むべき道もみえてくる
Posted by
今やっていることにしても これからするにしても、まずその状態を 楽しめるようにする。 そんなことを考えさせられる一冊。
Posted by
- 1
- 2