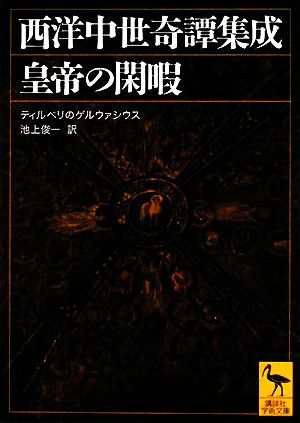西洋中世奇譚集成 皇帝の閑暇 の商品レビュー
(借.新宿区立図書館) ティルベリのゲルウァシルスによりまとめられた西洋中世驚異譚集。キリスト教伝説色が強いもの、(当時のインドなど)世界の驚異、そして近隣ヨーロッパ(アルル、イングランドなど)の伝説的なものが集められている。中世の民俗や世界を知るために重要な書物とのこと(訳者解...
(借.新宿区立図書館) ティルベリのゲルウァシルスによりまとめられた西洋中世驚異譚集。キリスト教伝説色が強いもの、(当時のインドなど)世界の驚異、そして近隣ヨーロッパ(アルル、イングランドなど)の伝説的なものが集められている。中世の民俗や世界を知るために重要な書物とのこと(訳者解説参照)。読み物としてキリスト教関係は少々退屈、世界の驚異は割とどこかで見たような感じ。残りの量的に多くはないが著者の身の回りで採集されたと思しい話は面白く読めた。
Posted by
原書名:Otia imperialia ad Ottonem 4 imperatorem ex manuscriptis
Posted by
大学生のときに購入して依頼10年近く塩漬けにしていた本。 ようやく読了。 キリスト教的説話からは、論を展開して皇帝に諭すような章もあってそこは多少キリスト教の予備知識がないととっつきづらいかなと思います。 それと、「驚異」のうちいくつかは現代科学で説明つきそうなものもあるかな?...
大学生のときに購入して依頼10年近く塩漬けにしていた本。 ようやく読了。 キリスト教的説話からは、論を展開して皇帝に諭すような章もあってそこは多少キリスト教の予備知識がないととっつきづらいかなと思います。 それと、「驚異」のうちいくつかは現代科学で説明つきそうなものもあるかな? そういった意味では中世の感性を感じ取ることができておもしろいです。
Posted by
12~13世紀の聖職者・ティルベリのゲルウァシウスが著した"Otia Imperialia"(1209-1214)の第三部を全訳した書。アルル王国を中心とする世界各地の「驚異」譚、全129篇を収録する。 本書は、ティルベリのゲルウァシウスが主君たる神聖ローマ皇...
12~13世紀の聖職者・ティルベリのゲルウァシウスが著した"Otia Imperialia"(1209-1214)の第三部を全訳した書。アルル王国を中心とする世界各地の「驚異」譚、全129篇を収録する。 本書は、ティルベリのゲルウァシウスが主君たる神聖ローマ皇帝オットー4世の為に物した奇譚集(の第三部)を邦訳したものである。激務に勤しむ皇帝の気晴らしの為ゲルウァシウスが本書で紹介するのは「自然のものでありながら、わたしどもの理解を越えた物事」たる《驚異 mirabilia》、即ち世界各地の奇譚・伝説どもである。古代ローマの詩人にして「魔術師」たるウェルギリウスの伝説、煉獄より出でて生者に死後の世界の秘密を教える幽霊、異形の人種や豪華絢爛な宮殿のある「インド」の情報――。ゲルウァシウスが長きに渡り暮らしたアルル王国を始め、イタリア、ブリテンなど世界各地の奇譚が、時には他の文献を基に、時にはゲルウァシウス自身の見聞を基に多数紹介されている。語られる《驚異》の数々はどれも興味深く面白いものであり、また史料的にも貴重なものばかりである。それらの記述を通してゲルウァシウスたちが生きた時代の社会や価値観も透けて見える本書は、中世ヨーロッパの豊潤な伝承世界に触れる最適の書と言えるだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 西洋史の泰斗ジャック・ルゴフが「先駆的民俗学者」と呼んだティルベリのゲルウァシウスによる奇譚集。 南フランス、イタリアを中心にイングランドやアラゴンなどの不思議話を一二九篇収録。 幽霊、狼男、人魚、煉獄、妖精、魔術師…。 奇蹟と魔術の間に立つ“驚異”は「人間と世界の在り方の反省へと、謙虚に誘う」神聖な現象だった。 中世人の精神を知るために必読の第一級史料。 [ 目次 ] 磁石 アグリジェントの塩 雪花石膏 エジプトの無花果の樹 生長して灰に帰するペンタポリスの果物 月の満ち欠けにしたがう石 三つの賜物 フルクトゥアールムの墓地 カミッサの窓 ル・ピュイの家々〔ほか〕 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
- 1