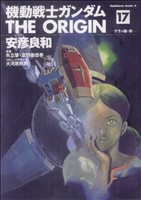機動戦士ガンダム ジ・オリジン(17) の商品レビュー
これまで読んだ続きの『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 16巻~18巻』の三冊を嫁さんが古本屋で買ってきてくれていました。 早速、息子と一緒に読みました。 -----story------------- ≪16巻≫ オデッサに散る、哀戦士たち! 連邦軍は、ジオン軍地球侵...
これまで読んだ続きの『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 16巻~18巻』の三冊を嫁さんが古本屋で買ってきてくれていました。 早速、息子と一緒に読みました。 -----story------------- ≪16巻≫ オデッサに散る、哀戦士たち! 連邦軍は、ジオン軍地球侵攻軍の本拠地オデッサを攻略すべく進軍を開始した。 ホワイトベースは新型MSの襲撃にあい、足止めをくらう。 その情報を嗅ぎつけた「ガイア」率いるドム中隊がホワイトベースに迫る! ≪17巻≫ 運命の出会い― 「ララァ・スン」! ホワイトベースは、補給のため中立都市サイド6へと寄港した。 そこで「ミライ」はかつての婚約者「カムラン」と、「アムロ」は生き別れた父とそれぞれ再会する。 さらに「アムロ」は運命の少女、「ララァ・スン」と出会うのであった。 ≪18巻≫ 新たに芽生える「シャア」の野望とは!? サイド6で運命的な邂逅をはたした「ララァ」、「シャア」と「アムロ」は再びテキサスコロニーで再会することになる。 そして「シャア」と「セイラ」の出会い。 「シャア」は新たなる野望を「セイラ」に伝えるのだった・・・ ----------------------- いやぁ… 本当に面白い。 一気に読み進んでしまいますね。 このあたりは、テレビ版とは微妙に(結構!?)違っていて、それはそれで面白いし、愉しめますね。 特に「シャア」と「セイラ」の思い出の場所… テキサスコロニーの闘いは、とてもエキサイティングな展開で、早く次のページが捲りたくなる衝動を抑えながら読みました。 マンガの方が「シャア」と「セイラ」が出会うシーンが詳しいのも嬉しいところですね。 またまた、次が読みたくなりました。
Posted by
ララァが登場。さらにアムロとシャアの初めての出会い。キャメル艦隊、コンスコン艦隊の撃破でアムロがニュータイプとして覚醒していく。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
中立コロニーサイド6にて変わり果てた父と再会したアムロはその帰り道、雨宿りのため立ち寄ったコテージでララァと出会い、再び彼女に会おうと向かった先でシャアと生身での初対面を果たす。カムランやコンスコンも登場。酸素欠乏症となったテム・レイの狂いっぷりと彼と接するアムロの温度差に悲しくなる。シャア、車の中でくらいその変なヘルメット取れよ。
Posted by
アムロ対シャアのモビルスーツ対戦は何度かあったから、これが初対面て思い難い。 だって、合ってなくても会話してるし(笑) しかし、ララァって現在で言うところの天然キャラだったんだな、と。 いや、電波系か?
Posted by
原点のアニメ版(映画込み)でも力が入っていた場面だけあって、ことさら原作「富野演出」と作者のスタンスの違いが明確に現れている気がする。 情報量をあえて削って端的に切り取っていた人の情感・心の動きを、安彦版では執拗(すぎるくらい執拗)に追い、時にスピード感を犠牲にする。反対に、対コ...
原点のアニメ版(映画込み)でも力が入っていた場面だけあって、ことさら原作「富野演出」と作者のスタンスの違いが明確に現れている気がする。 情報量をあえて削って端的に切り取っていた人の情感・心の動きを、安彦版では執拗(すぎるくらい執拗)に追い、時にスピード感を犠牲にする。反対に、対コンスコン隊戦でのガンダムの鬼神のごときヒロイックな活躍は「戦闘の一断面」として割り切られ、より大局的な構図が重視されている。 ブライトの不器用な態度、スレッガーの男気、テム・レイの悲惨さ、ララァの一種理解しがたい魅力、そういったものを丁寧に追う筆致はさすがの一言。 サイド6の偽善的・独善的だが政治的に正しく、住人にとってはたいへん住み良いコロニーという表現は、原作が追いきれなかった説得力を持っていた。 父と子というテーマにこだわる作者が、「アムロが父の呪縛を乗り越えるより先に、父の方から退場してうやむやになってしまった」という流れをほぼそのまま踏襲しているのはなんだか意外だった。「ニュータイプという概念を世代論以上の要素にすべきでない」という作者が、はたしてララァを今後どう描いていくのかは興味深い。
Posted by
- 1