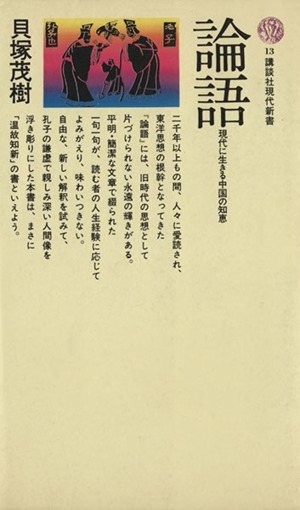論語 の商品レビュー
学校で習ったのとは違う解釈がなされていて、興味深かった。 既に数回この本を読んでいるが、新たな発見や新たな感動がある。
Posted by
京都大学で教鞭をとった貝塚茂樹氏の著。初版は1964年と古いが、氏の言葉の解釈は現代社会の世相や人のあり方などにも充分通じるものがある。論語の普遍性を改めて感じる。
Posted by
20140307読了 1964年出版。漢文、現代語訳、解説が並び、分かりやすい。数千年昔の、現代の事情とはかけ離れた時代背景の中で語られている言葉なので、それを踏まえて解説されている。●「吾れ十有五にして学に志す…」「故きを温めて新しきを知る」「これを知る者はこれを好む者に如かず...
20140307読了 1964年出版。漢文、現代語訳、解説が並び、分かりやすい。数千年昔の、現代の事情とはかけ離れた時代背景の中で語られている言葉なので、それを踏まえて解説されている。●「吾れ十有五にして学に志す…」「故きを温めて新しきを知る」「これを知る者はこれを好む者に如かず…」などなど、知ってるな~という言葉がちらほら出てくる。6世紀ごろから江戸時代まで「論語」が日本で道徳書だった名残は、今の自分にも息づいているのかも。
Posted by
論語の一部の原文•訓読分を解釈付きで纏められている。 生きた時代も国も違う人間の言葉だけれど、尊ぶ事やら想いは似たようなものになるのだなと感じ入る。 以下、印象に残った引用。 子曰わく、君子は徳を懐い、小人は土を懐う。君子は刑を懐い、小人は恵を懐う。(p.81) =故郷を...
論語の一部の原文•訓読分を解釈付きで纏められている。 生きた時代も国も違う人間の言葉だけれど、尊ぶ事やら想いは似たようなものになるのだなと感じ入る。 以下、印象に残った引用。 子曰わく、君子は徳を懐い、小人は土を懐う。君子は刑を懐い、小人は恵を懐う。(p.81) =故郷を出て、世に出ることを志しなさい。 子曰わく、位なきを患えず、立つ所以を患う。己を知る莫きを患えず、知らるべきを為すを求むるなり。(p.84) = 誰かに取り立ててもらえないことに腐るな、人に知られてないことを気にするな。人に知られるに値する実力をつける努力をしなさい。 子曰わく、徳は孤ならず、必ず隣あり。(p.93) =徳を実行している時、自分だけでは?と孤独を感じがちになるが、必ず良き理解者が現れるはずである。 子の曰わく、力足らざる者は中道にして廃す。今汝は畫(かぎ)れり。(p.124) =やる前から出来ないと言うな。始めから自分の力を諦めている人間にはなってはならない。
Posted by
とても分かりやすい。自分が生まれる前に発行された本だが、ちっとも古くさくない。ただ、ちょっと中国礼賛的な部分が散見されるのでマイナス☆一つ。
Posted by
(2013.08.19読了)(2011.01.19購入) 副題「現代に生きる中国の知恵」 『論語』は、教科書で読んだので読んだつもりでいたのですが、物語や随筆のなかで引用されているのを読んだぐらいで、まとめて読んだことはなかったようです。 Eテレの「100分de名著」で取り上げら...
(2013.08.19読了)(2011.01.19購入) 副題「現代に生きる中国の知恵」 『論語』は、教科書で読んだので読んだつもりでいたのですが、物語や随筆のなかで引用されているのを読んだぐらいで、まとめて読んだことはなかったようです。 Eテレの「100分de名著」で取り上げられていたのでその放送テキストを読んだついでに、読んでしまうことにしました。 とはいえ、この本も、『論語』の全文ではありません。著者が選んで中国古代史の知識を生かしながら、時代背景を考慮しながら解説しています。 『論語』は、孔子が書いたわけではなくて、孔子が亡くなった後に、弟子たちが、孔子の言ったことを思い出しながら、収集してまとめたもののようです。 「孔子言行録」といったところでしょうか。 孔子は、国を治めるにはどうしたらいいのか、ということを考えていたのでしょうから、日本の江戸時代にもてはやされたことは、皆さん御存じのことと思います。 読んでみると、どこかで聞いた事があるものもあるし、しらないものもあります。なるほどというのもあるけど、よく分からないものもあります。 とりあえず、概要がつかめたというところです。 【目次】 まえがき はじめに 『論語』の読み方 1 学而編 学問の勧め 2 為政編 理想の政治 3 八佾編 伝統の擁護 4 里仁編 徳について 5 公冶長編 聖賢の言行 6 雍也編 幸福について 7 述而編 教育について 8 孔子の追憶 9 孔子の政策論 略年表 関係地図 索引 ●『論語』(13頁) 『論語』は、紀元前五五二年に生まれ、紀元前四七九年に死んだ中国の聖人孔子が、弟子たちとの間にかわした問答を記録した本です。 ●人間観察(47頁) 中国人は、他人のことばをすぐは信用しません。ことばよりも、その人の行動によって、その人の人がらを判断します。 ●知るとは(53頁) たしかに自分の知っていることは、知っていると人にいってよろしい。自分のほんとうに知らないことは、知りませんと他人に答えないといけない。それが、ほんとうの知ることなのだよ。 ●就職(84頁) 地位が得られないことを気にかけるな。それにふさわしい実力をたくわえることに努力せよ。人に知られないのを気にするな。人に知られるに値することに努めよ。 ●旅行(90頁) 父母が生きていられる間は、遠方に旅行してはならない。行くときには必ず行く先を明らかにすることだ。 ●志(113頁) 孔子は、「年寄りのかたには安心され、友だちには信頼され、子供にはなつかれる、私はそんな人間になりたいと思う。」と答えられました。 ●礼(135頁) 学問を志す人間は、いろいろな文献を広く読んで、知識を広くするとともに、これを礼というものを中心として統一しなければいけない。 ●遊ぶ(145頁) 目的とか義務とかいうことでなく、無目的に学問・音楽・スポーツなどの世界に楽しみ遊ぶこと、それが人生の至上の幸福だと説いているのです。 ☆関連図書(既読) 「孔子『論語』」佐久協著、NHK出版、2011.05.01 「中国の歴史(上)」貝塚茂樹著、岩波新書、1964.09.25 「中国の歴史(中)」貝塚茂樹著、岩波新書、1969.04.20 「中国の歴史(下)」貝塚茂樹著、岩波新書、1970.03.20 「世界の歴史(1) 古代文明の発見」貝塚茂樹著、中公文庫、1974.11.10 「中国古代再発見」貝塚茂樹著、日本放送出版協会、1978.10.01 (2013年8月20日・記) 内容紹介 amazon 2000年以上もの間、人々に愛読され、東洋思想の根幹となってきた『論語』には、旧時代の思想として片づけられない永遠の輝きがある。平明・簡潔な文章で綴られた一句一句が、読む者の人生経験に応じてよみがえり、味わいつきない。自由な、新しい解釈を試みて、孔子の謙虚で親しみ深い人間像を浮き彫りにした本書は、まさに「温故知新」の書といえよう。
Posted by
いろいろな論語本でも引用されている貝塚氏の本。1964年初版。内容は入門書に最適。書体が古めかしいのもいい。
Posted by
あまりにも有名な「論語」を古典の時間にちょこっとかじったぐらいで、今まで手をつけなかったため、超有名なフレーズである、 ・「温故知新」 ・「巧言令色少なし仁」 ・「朋あり遠方より来たる、亦た楽しからずや」 ぐらいしか知らない。ちょうどBSで「恕の人-孔子伝」が放送されていること...
あまりにも有名な「論語」を古典の時間にちょこっとかじったぐらいで、今まで手をつけなかったため、超有名なフレーズである、 ・「温故知新」 ・「巧言令色少なし仁」 ・「朋あり遠方より来たる、亦た楽しからずや」 ぐらいしか知らない。ちょうどBSで「恕の人-孔子伝」が放送されていることもあって、今回このダイジェスト版ともいうべき本書を手にした。 ここで一つ認識しておきたいのは、「論語」は孔子の著作ではなく、孔子の弟子たちが孔子の言葉を集めて一冊の本に仕立てたのだということである。著者の貝塚氏は中国古代史の専攻であるからその道のエキスパートである。そのためかこれまでの一般的な解釈と異なる新説も紹介しており好奇心をそそられる。 もう一つ私のうろ覚えの一節に 「我れ欲せざるところ、これを人に加うることなかれ」 であったが、これに似たフレーズはあるものの言葉が違うし、用法・解釈においても違うものしか見当たらなかった。私はこのうろ覚えの一節のとおりそのままに受け取っていたが、本書では弟子の子貢がこの一節を孔子に語ったところ、実際にできるのかと子貢が孔子にたしなめられたというシチュエーションで出てくるのだ。私が思っている一節と同じものなのだろうか。ぜひ別本で真偽を確認しなければならなくなった。 入門書的にはこの程度でよいのかもしれないが、なんとなく物足りなかった。
Posted by
論語――儒教の原典とも言われる、論語であるけれど、原文が漢文であることに加えて、宗教の「教」がつけられていることから、少し距離を感じてしまうけれど、実際は非情にわかりやすい生き方の教えが綴られているだけである。だけ、というと語弊があるけれど、別段難しいことが書かれているわけではな...
論語――儒教の原典とも言われる、論語であるけれど、原文が漢文であることに加えて、宗教の「教」がつけられていることから、少し距離を感じてしまうけれど、実際は非情にわかりやすい生き方の教えが綴られているだけである。だけ、というと語弊があるけれど、別段難しいことが書かれているわけではなくて、それこそ、心得のようなものが記されているだけだ。要するに、儒教を宗教として解する必要もなければ、そこに難解な教義を見出す必要もない。ただひたすら実践に重きを置いた教えなのである。 そして、教え自体も一つ一つは非情に短くて、日本語訳にしてみても数行程度で終わるものも多い。中には十行くらいいくものもあるが、一行くらいで終わってしまうものも多々ある。著者は所々に文意には含まれていない文章を付け足してくれるので、内容への理解度が原文だけを読むよりも格段に深まる。古文として論語に触れるときは、原文に近しい訳のほうがむしろありがたかったけれど、内容理解のためにはむしろ訳文として内容を充実させてくれた方がありがたくもある。 さて、現代的には封建的であるとして評判の芳しくない儒教であるものの、こうして内容に触れてみると、それは権力者が意図的に一部分を抜き出して用いたりしたせいであって、孔子自体は別段封建的を強制していたわけではないことが知れる。例えば、家父長に絶対服従しなければならないとは説いていないし、意見する権利も認めている。また、神に対して不平を垂れているあたりが、キリスト教などとはまるで違って、孔子の人柄のようなものをしみじみと感じさせられる。また、老荘思想の影響も受けているようで、どことなく無為自然を彼自身も望んでいるような節がある。恐らく当初は政治的にばりばり活動していたのだけれど、人に囲まれてのんびりと教え暮らしている間に、どうにも、かつかつ働くよりも趣味として生きがいとして学問に親しみながら、のびのび生活することにこそ価値を見出したのではなかろうか?彼の発言は所々で矛盾していたり、実践主義でありながらもときにそれが詭弁であったりもするが、しかして、それはむしろ彼がいつからかカウンセラーのような役割を果たしていたからなのかもしれない。色々な弟子たちの相談にのり、時に励まし、時に路を指し示し、時に戒めて、時に賞賛し、時に共にのんびりと一日を過ごす、道徳に厚いと言われる孔子だけれども、実は親しみやすいおじいさんだったのかもしれない、そういう顔が見え隠れする一冊。だから、論語をバイブルにするのは行き過ぎであるし、だからといって封建的であるとして否定するのもナンセンスで、孔子の優しさみたいなものに触れられればいいのではないでしょうか?
Posted by
こちらの講談社現代新書『論語』は抄訳であり、中央公論新社版から出ている二種類の全訳注『論語』とは中味の構成も文章も異なる別作品。『論語』二十編の前半部分を主に抄訳し、語りかけるような文章に仕上がっています。 貝塚茂樹先生による『論語』訳としては、この講談社現代新書版が先ですから...
こちらの講談社現代新書『論語』は抄訳であり、中央公論新社版から出ている二種類の全訳注『論語』とは中味の構成も文章も異なる別作品。『論語』二十編の前半部分を主に抄訳し、語りかけるような文章に仕上がっています。 貝塚茂樹先生による『論語』訳としては、この講談社現代新書版が先ですから、中央公論新社版の礎となる作品でしょう。作品自体は初めて『論語』を読もうとする人を前に話されているような文体ですし、分かりやすい言葉で書かれていますから入門書として最適です。 また、講談社現代新書版を読み終わってから、さらに中央公論新社版を読み比べてみると、貝塚先生の思索をなぞることができて愉しいです。たとえば第1章の冒頭、講談社現代新書版は「学びと時(とき)にこれを習う」とありますが、中央公論新社版では「学びと時(ここ)にこれを習う」と変化しており、解釈も変化しています。まさに『論語』を味わうようすを追体験している感じです。
Posted by
- 1
- 2