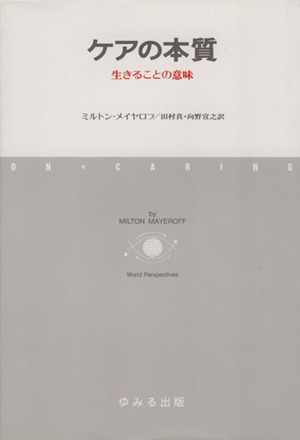ケアの本質 の商品レビュー
自分がこの仕事をしていく上での羅針盤の1冊。 言葉にならない思いを聴き取るために、皮膚の下に入り込む。なぜそれをするのか、なぜそれが好きでなぜそれを生業としたのか、言葉に表すことが下手くそな自分の思いを言語化してくれたような1冊。 少しぎこちなさを感じる和訳がすごく好きで、原...
自分がこの仕事をしていく上での羅針盤の1冊。 言葉にならない思いを聴き取るために、皮膚の下に入り込む。なぜそれをするのか、なぜそれが好きでなぜそれを生業としたのか、言葉に表すことが下手くそな自分の思いを言語化してくれたような1冊。 少しぎこちなさを感じる和訳がすごく好きで、原版の表現が気になって原版も購入。両者共に大好き。
Posted by
ミルトンメイヤロフ ケアの本質 生きることの意味 哲学から見たケアの本質論。ケアの本質は「他者の成長をたすけること」にあるとしている 他者の成長をたすけるケアは「他者を自分自身の延長と感じ考える」とある。自分と他者の距離が近すぎて、ミイラとりがミイラになるように、ケア...
ミルトンメイヤロフ ケアの本質 生きることの意味 哲学から見たケアの本質論。ケアの本質は「他者の成長をたすけること」にあるとしている 他者の成長をたすけるケアは「他者を自分自身の延長と感じ考える」とある。自分と他者の距離が近すぎて、ミイラとりがミイラになるように、ケアする人にケアが必要になるように思う ケアをする空間は、自分が必要とされている場所であり、自分の居場所があることは、自分が生きる意味である、という論調。「人は 自分の場を発見することによって、自分自身を発見する」は名言 「場の中にいることにより、人生に没頭できると同時に〜人生を競争と感じることから解放される」は、なるほどと思う 「自律とは、私が自己の生の意味を生きることである〜私は最初から自律的であるわけではない。自律とは、成熟や友情の深まりと同じく、ひとつの達成なのである」
Posted by
実ははじめて読んでいろいろショックを受けている。そうなのか!内容はまあおだやかな内省的哲学エッセイ、っていっていいと思う。宗教色はそれほど濃くない。まあこれは「愛」の哲学の本だわ。1970年ぐらいってこういう試みがいろいろなされてたってことかなあ。
Posted by
言いたいことは分かるんだけど、何故そう言えるのかという正当化?論理?がなくて、すっきりしない。裏を返せば、分かる人には分かるというやつかと。 ケアとは自己の成長を促進する行為でもある。 他者へのケアのためには自己へのケアが必要で、自己のケアのためには他者へのケアが必要、という相...
言いたいことは分かるんだけど、何故そう言えるのかという正当化?論理?がなくて、すっきりしない。裏を返せば、分かる人には分かるというやつかと。 ケアとは自己の成長を促進する行為でもある。 他者へのケアのためには自己へのケアが必要で、自己のケアのためには他者へのケアが必要、という相補的関係への言及が面白い。他者の自律を積極的に望むのだから、依存とは明確に違う。(現象学を勉強すれば、すんなり理解できるのかもね) ケア労働をしている人なら実感としての理解はできると思う。
Posted by
ケアの相互性、場の中にあること、副題でもある、生きることの意味 ケアはスキルじゃなくて、でも同時に深い知識や知恵などの能力を求めるものだということが丁寧に丁寧に書かれている
Posted by
ケアという言葉は看護や介護の業界のキーワードだ。しかし、この本のいうところの”ケア”は、解説にあるように「ケアの持つ意義を、単に医学と看護学の充実・進歩、治癒力の強化、あるいは学習の向上、福祉の拡大に求めるのではなく、ケアの動態と過程、すなわちケアそのものに見いだしている」(p...
ケアという言葉は看護や介護の業界のキーワードだ。しかし、この本のいうところの”ケア”は、解説にあるように「ケアの持つ意義を、単に医学と看護学の充実・進歩、治癒力の強化、あるいは学習の向上、福祉の拡大に求めるのではなく、ケアの動態と過程、すなわちケアそのものに見いだしている」(p228)として、それにとどまらない内容をもっており、看護や介護業界の人間以外にも意義深いものだと捉えられている。 しかし、私はむしろ看護師やヘルパー、相談員などの仕事でケアに関わる人間はこの本の内容を自分たちへ向けられたものだと思わないほうがいい。ましてや実行できるなどとは考えないほうがいいと思う。 実際、この本で看護師などが取り上げられることはまずない。あるとしても、ケアには専門的な知識が必要だと説く箇所くらいだ。取り上げられる多くの例は、人へのケアには親子、アイディアや作品に対するケアには哲学者(著者は哲学者だ)や芸術家が挙げられる。こういう人たちは長期間にわたって”ケア”に取り組める人たちだ。長い時間をかけて同一の対象をケアし続けるというのは、仕事でケアに携わる人には与えられ難い条件だ。また、著者はケアする相手に「ケアを受容する能力」(p75)が必要だと考えているが、看護師やヘルパーは、そのような能力がない人を相手にするのが往々として求められている。 それでもこの本を読む価値というのは、”ケア”という哲学的な概念が、人間や人生に対する洞察を深めてくれるからだ。この本を読もうと思う看護や介護の職業人は、一度自分の仕事と距離を置いて、より広い、一人の人間として視点から”ケア”の意味を取り出さないといけないのではないか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
チェック項目17箇所。本書は、読者自身をケアの動態に巻き込んで展開する稀有な著作である、独自の仕方で本書に向かわれることを望みたい。一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することをたすけることである。私たちは、ケアには知識が必要でないとか、誰かをケアすることは、たとえば、単に好意や温かい関心を示すことだけであるかのように言うことがある、しかしケアするためには、私はその人の要求理解しなければならないし、それに適切に応答できなければならないし、しかもまた、好意があるだけではこのことが可能でないのは明らかである。忍耐はケアには重要な要素である、忍耐のおかげで、私は相手にとってよいときに、相手にそった方法で、相手を成長させることができるのである。ケアする人は忍耐強い、なぜなら、相手の 成長を信じているからである、しかし相手に忍耐を示すと同時に、自分自身に対しても忍耐せねばならない、相手および自分を知り、理解し、発見する機会を、自らに対してつくっていかねばならない。他者をケアする中で、あるがままの相手を見つめなければならないのであって、私がそうあって欲しいとか、そうあらねばならないと感じる気持で相手を見つめることではないのである。相手を信頼することは、まかせることである、つまりそれは、ある危険な要素をはらんでいるが、未知への跳躍なのである、いずれも勇気のいることである。ケアにおいては、他者が第一義的に大事なものである、すなわち、他者の成長こそケアする者の関心の中心なのである、相手に焦点が当てられたときにのみ、その成長の欲求に呼応することができるのである。ケアするには、ときに特別な資質あるいは特殊な訓練を必要とする、一般的なケアができるということのほかに、ある特定の対象に対してもケアできなければならない、精神病患者に対するケアでは、特殊な訓練以外に、人間関係についてのなまはんかでない感受性が要求される。ケアする人は相手に自分自身をゆだねている、つまり依存される存在として自分自身を差し出している。両親は、子供が自らをケアできるようになるまで子供をたすけるのであるが、だからといって、それで親子の関係を終わらせてしまうつもりではない、同様に私たちは友情に ついても、相手の成長を互いにたすけ合うような成熟した友情が、無限に続いてくれることを望むのである。私は成長したいという私自身の心からの欲求をよく理解し、それにこたえることができてはじめて、相手に関しても、その成長したいという欲求や努力が理解できるのである。ケアにおいては、相手とともにいるということは、とりもなおさず相手のためにいるということでもある、成長しようとし、自らを確立しようと努力している相手、その人のために私はいるのである。自律は自己理解を前提とする、その理解がないと、結局、自分が自分の障害となってしまい、どうどうめぐりするしかないのである。私が実際に私自身をケアするうえで、私はいったい誰であるか、何のために努力をしているのか、私が必要としているものはそもそも何なのか、その必要を満足させるには何が要求されているのか、ということの理解がなければならない。より 包括的な理解がなければならない、すなわちこれは、私が何に身をゆだねるべきなのか、自分に対して何が要求されているのか、何が自分を補って完全なものにしてくれる対象なのか。人は自分の場を発見することによって自分自身を発見する、その人のケアを必要とし、その人がケアする必要があるような補充関係にある対象を発見することによって、その人は自分の場というものを発見する。
Posted by
翻訳が読みにくい感じでしたが、対人援助職にとって、ケアするということを考え直し、共感できる一冊です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルからは、福祉や介護に関わる方用の専門書に思えてしまい ます。しかし、本書は一部の専門家向けに書かれたものではありま せん。著者自身、「ケア」を、親が子供のケアをするというような 非常に日常的な意味で使っています。アイデアをあたためる行為す らも著者にとってはケアなのです。 「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長する こと、自己実現することをたすけることである」という文章で始ま るこの本を、私は深い感動と驚きをもって読み終えました。 大袈裟なようですが、ここには、自分が悩んできたことの全てが書 かれているように思えたのです。 まさに、副題にあるとおり、「生きることの意味」について考えさ せ、ヒントをくれる本です。 部下や同僚との人間関係がどうもうまくいかない、子どもや妻との 関係が今いちしっくりこない、と言った日常的な人間関係の悩みか ら、自分が一体いかに生きるべきかわからない、という根本的な悩 みにまで、この本は答えてくれます。 特に、ビジネスマンにとっては、自分のリーダーシップのあり方を 見直す良いきっかけを与えてくれることでしょう。 社長や部長は必読です。 訳が悪く、決して読みやすい本ではありませんが、若い人にも、人 生経験の豊富な方にも、男女や職業を問わずに、是非、読んで頂き たい本です。 ************************************************************ ●編集後記 ************************************************************ 今年はやはり母の死を看取ったことが、個人的には大きな体験でし た。母の生涯は、父を支え、3人の子を育て上げるために全てを捧 げたものでした。 母の膵臓がんが発見されたのは、2年前の9月、私の娘が生まれた 直後です。2年あまりの闘病生活は、父の献身的な介護に支えられ ました。最期は、自宅で家族全員に看取られながら静かに逝きまし た。美しい最期でした。 「あなた達3人を食べさせることに必死になっていた頃が人生で一 番楽しかった。もう全員が家庭を持って、子どももできたので、私 の役割は終わり。もう何も思い残すことはない」 母は、闘病中、何度もそう私に言いました。 内村鑑三は、人が後世に残せる最大のものは、「勇ましい高尚なる 生涯」だと言っています。お金や事業や学問は才能や運に恵まれた 人にしか残せないかもしれないが、誰でもその気になれば残せるの が、「勇ましい高尚なる生涯」なのです。これが後世への最大遺物 なのだと内村は述べます。 母の死は新聞で報道されるようなものでなく、本当にどこにでもあ る平凡な72歳の主婦の死です。 しかし、その死に様を見届けながら、母の生涯こそ、「勇ましい高 尚なる生涯」であったのだなと思いました。 母から受け継いだこの遺物をきちんと私が花開かせ、また子に伝え ていかないといけませんね。 そういう意味でも、母の死は、自分がいかに生きるかということに ついて、大きな責任を自覚させてくれるものとなりました。 来年まであと数日。 どうか良い年をお迎えください。 本年は大変お世話になりました。 来年も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
Posted by
ケア、という概念について。 これは基本的には看護とか福祉の分野で使われる言葉だけど、著者は教育、芸術、哲学などかなり広い範囲にケアの概念を敷衍する。 という意味で別に福祉とか全然興味ない人にも勧める。 内容はというと、やや押しつけがましいというか理想論とでもいうべき考え方に多少...
ケア、という概念について。 これは基本的には看護とか福祉の分野で使われる言葉だけど、著者は教育、芸術、哲学などかなり広い範囲にケアの概念を敷衍する。 という意味で別に福祉とか全然興味ない人にも勧める。 内容はというと、やや押しつけがましいというか理想論とでもいうべき考え方に多少辟易するものの、短く簡潔な考察は分量以上に示唆的。 ケアのインタラクティブな側面を重視することは、日頃から気にしていたことでもあるので興味に合致したからでもあるのだろうけど。
Posted by
- 1
- 2