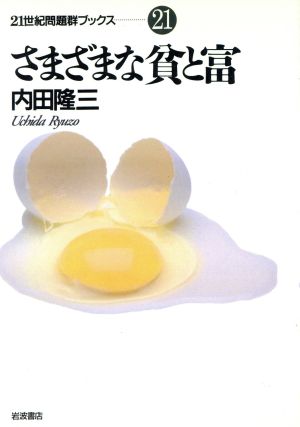さまざまな貧と富 の商品レビュー
著者らしい観点で貧と富の分析を行なっている。飢餓海峡、砂の器、人間の証明という三つの小説の比較のところは秀逸。
Posted by
貨幣経済システムの成立によって、人間の欲望や社会のあり方にどのような変化がもたらされたのか、さらに、これからの経済的発展が、人びとの生き方にどのような変化をもたらすのか、といった問題を、いくつかの観点からスケッチした本です。 著者は、日本の伝統社会の中に貨幣経済的な「富」が持ち...
貨幣経済システムの成立によって、人間の欲望や社会のあり方にどのような変化がもたらされたのか、さらに、これからの経済的発展が、人びとの生き方にどのような変化をもたらすのか、といった問題を、いくつかの観点からスケッチした本です。 著者は、日本の伝統社会の中に貨幣経済的な「富」が持ち込まれたとき、人びとはどのような対応をおこなったのかという問題に触れています。ここで著者は、民俗学者の小松和彦による「異人殺し」の伝説を参照します。価値増殖を果たす貨幣の「呪術的な力」に 直面した人びとは、伝統的なゼロ・サム経済に生きていた共同体の論理との折り合いをつけることが求められました。このような要請が、村を通過する「異人」の金を強奪したという物語を生むことになったと考えることができます。 次に著者は、西洋に目を向け変え、マルクスやウェーバーらの仕事を念頭に置きながら、産業資本主義の成立によって人びとの精神にもたらされた変化のスケッチをおこなっています。貨幣経済という「場」の中で「欲望の主体」として自己形成するような心性が形作られた歴史的経緯について論じられるとともに、マルクスによってそうした経済システムを支えている「労働者」と呼ばれる人びとが、固有の厚みを持った実存であることが改めて発見されることになったことに注意しています。 著者自身の考えがはっきりと提出されているわけではないので、少し散漫な印象を感じてしまったのも事実ですが、取り上げられているテーマそのものについては興味深いと感じました。
Posted by
- 1