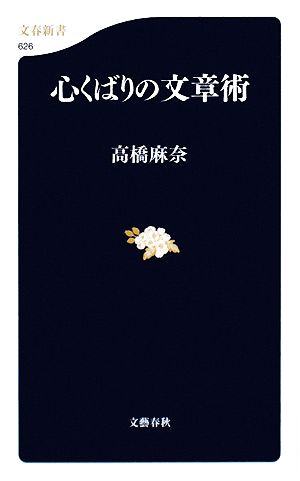心くばりの文章術 の商品レビュー
文章がダメな人って、見様見真似ができなかったってことなので、文章を読まないとか、読解力がないって問題を抱えてる可能性があると思ってて、そうなると薦める本が難しくなる。理系の作文技術を薦めにくい。そーゆー観点で、これは薦めやすい本かな。
Posted by
「心を配る」際は何であれ適量であることが 大事だと思わされました。 企画書や報告書など具体的なビジネスシーンで どんな文章が「心配り」された文章なのか紹介される例文が 私にはちょっと「心配られ過多」に感じました。 その比喩表現…変やで(笑)とツッコミながら読むには 楽しいんですけ...
「心を配る」際は何であれ適量であることが 大事だと思わされました。 企画書や報告書など具体的なビジネスシーンで どんな文章が「心配り」された文章なのか紹介される例文が 私にはちょっと「心配られ過多」に感じました。 その比喩表現…変やで(笑)とツッコミながら読むには 楽しいんですけども♪ 少々きちんと文章を書かなければならない機会があり、 読んでみた1冊。あんまり参考になりませんでした残念。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【ポイント】 文章を書くときは、読み手の心理を強く意識する。 読み手の心理に応える文章になっているかをチェックする。 【GOODフレーズ】 カバー裏側:上手く書く秘訣は、「心くばり」にある。読み手への配慮を心がける事から、書くべき事と書き方の両方が見えてくる。 【所感】 この著者の主張を基にすると、 文章(書籍)を読んで難解だと感じた場合、 その原因のひとつは、著者の書き方である。 つまり、書き手の責任である。 本を出している知識人のうち、そのことを意識している人はどの程度いるだろうか? 個人的には、第2章の内容が参考になった。 内容:★★★★☆ 分かりやすさ:★★★★★ 【目次】 第1章 文章の心得とは? 第2章 説明するにも「心くばり」あり 第3章 アピールするにも「心くばり」あり 第4章 実践で書くにも「心くばり」 第5章 日頃の文章を高める「心くばり」 第6章 文章を磨くための「心くばり」 【要点】 ・作業の内容 → 「作業が必要となる理由」を追記 ・自分の主張 → 「根拠(理由)」を追記 読み手の立場に立って読み直し、読み手が抱く疑問を想像する。疑問に答えているかをチェック。 ・情報の整理の仕方(指針)を意識する。 例) 時間の流れ、構造、場合分け、並列的、階層 ・概要を書くことで、読み手に全体像を把握させる。 ・補足するときの接続詞「なお」「ただし」 → 補足だという意図が伝わりやすい ・図面 → ポイントだけを表現する。 → 登場人物と、登場人物どうしのつながり・関係とで、ポイントが表現されているかチェック。
Posted by
文章を書く際の基本的なことが書かれていて良書だと思います。ただ、私が類似本をたくさん読んでいるせいか、残念ながら目新しい発見がありませんでした。
Posted by
日々必要な仕事上の文書を、どうすればわかりやすく書けるのか。 簡潔にして説得力のある文を書けるかどうかは、仕事の成否、ひいては自分の運命をも左右しかねない。 それは突き詰めて言えば、「読む人の立場に立つ」ということに尽きるのだが、そうは言ってもどうすればそれが実践できるのかが悩み...
日々必要な仕事上の文書を、どうすればわかりやすく書けるのか。 簡潔にして説得力のある文を書けるかどうかは、仕事の成否、ひいては自分の運命をも左右しかねない。 それは突き詰めて言えば、「読む人の立場に立つ」ということに尽きるのだが、そうは言ってもどうすればそれが実践できるのかが悩みどころ。 この本では、「心くばり」をキーワードにして、豊富な文例とともに、分かりやすい文を書くための考えかたを解説する。 著者は、初心者向けの解説書に定評のあるテクニカルライター。 私も著書を何冊か持っている。その柔らかくも明瞭な文体は、意識的に練り上げられたものらしい。 そんな作業の積み重ねがこの本に結実したのだろう。 各章最後の「おさらい」だけでも、折にふれて読み返せば、文章を組み立てる助けになりそうだ。
Posted by
- 1