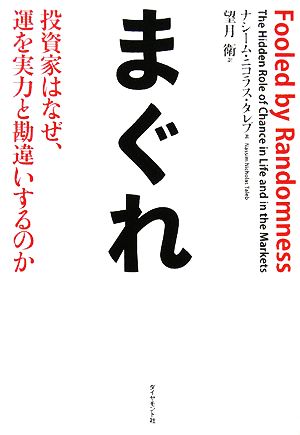まぐれ の商品レビュー
著者の言うように運やまぐれはとても大事 それを継続するために 運を呼び込む生き方、行動も大事 実力も大事 と個人的に思う
Posted by
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1878729736979124301?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by
最初に、この人ある程度資産ありそうだけど友達いないだろうなと思った。 帯に顧客に読ませたくないって書かれてたけど、皮肉とまぐれ、たまたま、運とそういうことに落とし込んだ方が合点が行くと。そういうことを永遠聞かされ(読まされ)そりゃそうだよね。って変に賛同する方は読まれるとプラスに...
最初に、この人ある程度資産ありそうだけど友達いないだろうなと思った。 帯に顧客に読ませたくないって書かれてたけど、皮肉とまぐれ、たまたま、運とそういうことに落とし込んだ方が合点が行くと。そういうことを永遠聞かされ(読まされ)そりゃそうだよね。って変に賛同する方は読まれるとプラスになるんじゃないですかね。 又、物事を懐疑的に捉える方にとってもプラスになりそう。
Posted by
ちょっと難しい。結果とその原因や発生する確率、リスク調整後のリターンなどをみないと本当にその行動や選択が良いものなのかは判断できない。確率の大きさとインパクトの大きさに広く深く思考をして、選択をしていくことで大きな成果が得られることもある。
Posted by
「株式投資の本で有名なものを」と借りてきたが、同時期読んでたマルクスアウレリウスの「自省録」のおかげで共感がより深くなった(気がする)。 てかほんとこれですよね。職場は私を除いて美貌の太実家高学歴体育会系が多かったですけど多くの人がこんなマインドセットのようでした。 まぐれ。そう...
「株式投資の本で有名なものを」と借りてきたが、同時期読んでたマルクスアウレリウスの「自省録」のおかげで共感がより深くなった(気がする)。 てかほんとこれですよね。職場は私を除いて美貌の太実家高学歴体育会系が多かったですけど多くの人がこんなマインドセットのようでした。 まぐれ。そう、まぐれ。
Posted by
著者は独特の書体であり、性格もよく現れた文章を書く。運を実力と勘違いしている投資家が非常に多く、やがて全財産が吹き飛ぶ。ダーウィンの進化論に見立て運に頼っている投資家はやがて吹き飛び絶滅するなど内容は非常に面白い。何度も読みたいし、ブラックスワンも読んでみたい。
Posted by
著書の書き方が難解で分かりにくい。気になったところを箇条書きにする。 ①あまりにも高過ぎるパフォーマンスは一見スキルがもたらしたものであるかのように見えるが、それは間違っている。良過ぎるパフォーマンスは運である。過剰にマーケットに適合するとそうなる。相場というものは参加者が非常...
著書の書き方が難解で分かりにくい。気になったところを箇条書きにする。 ①あまりにも高過ぎるパフォーマンスは一見スキルがもたらしたものであるかのように見えるが、それは間違っている。良過ぎるパフォーマンスは運である。過剰にマーケットに適合するとそうなる。相場というものは参加者が非常に多いので、確率論的にも数年にわたってアウトパフォームできる人間はあり得る。 会社の出世競争もこの類に似ている。運良く開拓できた、自分の在任期間時に大きい案件が決まったなどがあり、在任期間で上位に行くと次の転勤が良くなる。そこでは、良かった人間同士で争う構図になり、顧客、機会などはどんどんその人間に集まるため、一度外れると戻れない。レバ型ETFを買うイメージ。 ②高パフォーマンスに陽が当たるのは生存者バイアスが働いている。下手くそは駆逐されている。 ③マーケットは短期に捉えると、見えるのはリターンではなくリスクでありノイズである。そこだけを捉えて一喜一憂をすべきではない。 ④どんな人間も合理性のみでは生きていけず、必ずヒューリスティック(経験則)で物事を見てしまう。 過去のマーケットがこうだったから、今後こうなるとか、この出来事は過去起こったことがない、とかいう出来事は意外と頻繁に起きる。 ⑤確率と期待値を混同してはいけない。例えば1000回で999回は1ドル儲かるけど、1回は1万ドル損する取引は行うべきだろうか? 期待値は-9.001ドルになり、行うべきではない。計算すればわかるのに、目先の利益に走っていないか?
Posted by
投資。金融。確率。 冒頭では一応エッセイであると書かれている。 直接、投資に関係する内容は意外と少なめ。 著者が非常に博識な人のようで、哲学的だったり文学的だったりして、内容はかなり難しく感じた。 しかし、理解できた部分はかなり面白い。 投資的には、ストップロスと損小利大がとても...
投資。金融。確率。 冒頭では一応エッセイであると書かれている。 直接、投資に関係する内容は意外と少なめ。 著者が非常に博識な人のようで、哲学的だったり文学的だったりして、内容はかなり難しく感じた。 しかし、理解できた部分はかなり面白い。 投資的には、ストップロスと損小利大がとても大切。 リスクの重要性と、人間が確率をどれだけ理解できないかが学べた。
Posted by
ヘッジファンドのトレーダーにして大学教授の著者が、金融市場の問題点を指摘した本。トレーディングの成功は、ほとんどの場合、手腕によるものではなく、まぐれに過ぎないと断じており、偶然が果たす役割を過小評価していると主張している。これを裏付けるいくつかの説明は面白く、また役に立つ。相場...
ヘッジファンドのトレーダーにして大学教授の著者が、金融市場の問題点を指摘した本。トレーディングの成功は、ほとんどの場合、手腕によるものではなく、まぐれに過ぎないと断じており、偶然が果たす役割を過小評価していると主張している。これを裏付けるいくつかの説明は面白く、また役に立つ。相場の中では、ノイズは無視し、シグナルは受け取らないといけないとし、マスコミは人の注意を引ける雑音(ノイズ)を垂れ流す有害な存在と分類し、歴史は雑音がほとんど取り除かれており、学ぶべきものとしている。また、トレーディングで避けるべき典型的なこととして、自分のポジションと結婚する、シナリオを変える(運の向き方でトレーダーになったり長期投資家になったりする)、損したらどうするというゲームプランを事前に決めていない、などを挙げており改めて勉強になる。また、自己矛盾は恥ではないとしており、過去の行動から全く自由なことがソロスの成功の理由の一つと分析するなど興味深い話が多い。感情と理性の間で決断することの難しさでは著者もいろいろ考えており、人間味を一層感じることもできる。
Posted by
まぐれ pxii 記者のほとんどには、それほどひどい思い込みはない。結局、このジャーナリズムという商売は純粋にエンターテイメントであって、真理の探究ではないのだ。ラジオやテレビは特にそうだ。大事なのは、自分達は単なる芸人なんだということが分かってなくて、自分はインテリだと思ってそ...
まぐれ pxii 記者のほとんどには、それほどひどい思い込みはない。結局、このジャーナリズムという商売は純粋にエンターテイメントであって、真理の探究ではないのだ。ラジオやテレビは特にそうだ。大事なのは、自分達は単なる芸人なんだということが分かってなくて、自分はインテリだと思ってそうな連中には近寄らないようにすることだ。 p35 感情を隠せる人なんてほとんどいない。行動科学者たちによると、人は何か能力があるからリーダーになるのではなく、むしろちょっとした肉体的なシグナルで、まったく実体の伴わない印象を他人に与えることが出来るとリーダーになる。そんな印象は今時では、例えば「カリスマ性」と呼ばれている。 p178 人の業績を正しく判断できない以外にも、社会的ないたちごっこという要素がある。お金持ちになり、お金持ちの住むご近所に引っ越すと、また貧乏人も同然になる。その上さらに心理的ないたちごっこが加わる。豊かさに慣れてしまい、そこが満足度を測る基準になってしまう。どんなに豊かになっても(ある程度以上は)決して満足が得られない人がいるという問題は、幸せを論じる専門的な議論の対象になってきた。 p183 起こる可能性のあるすべての歴史のなかから、そのひとつがまったく偶然に実現しただけなのに、私たちはそれを全体の代表的なひとつだと思い込み、他に可能性があったのをすっかり忘れてしまう。端的に言うと、生存バイアスがある場合、一番成績がよかった結果が一番目につくのだ。どうして?負け犬はのこのこ出てきたりはしないのである。 p221 私たちの脳は非線形を扱うようには出来ていない。例えば二つの変数の間に因果関係がある場合、人は原因の方の変数が安定していれば結果のほうの変数も必ず安定しているものだと思う。
Posted by