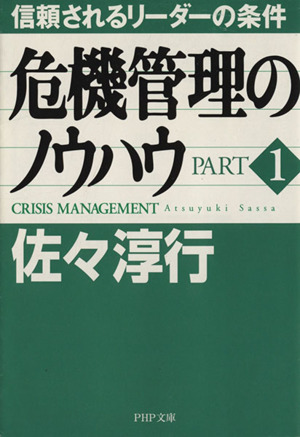危機管理のノウハウ(1) の商品レビュー
危機管理の重要性が叫…
危機管理の重要性が叫ばれていますが、これを読むとまだまだ甘いなという気がします。
文庫OFF
ミスター危機管理、佐々淳行氏の著書。 個別具体的な技術・方法論的な部分は、古い本だけに陳腐化も見られるが、本書で語られる、危機に対処する組織論、リーダーシップ、危機管理論の根本は今なお色褪せない。そのような本書は、組織に生きる人にとっての危機管理のバイブルと言えるだろう。
Posted by
「危機管理」(crisis management)ということばがひろく受け入れられるようになるきっかけをつくった本です。 「危機管理」とは、(1) 危機の予測および予知、(2) 危機の防止または回避、(3) 危機対処と拡大防止、(4) 危機の再発防止の4段階について、それぞれの...
「危機管理」(crisis management)ということばがひろく受け入れられるようになるきっかけをつくった本です。 「危機管理」とは、(1) 危機の予測および予知、(2) 危機の防止または回避、(3) 危機対処と拡大防止、(4) 危機の再発防止の4段階について、それぞれの段階で何をなすべきかを方法論的に検討するものです。こうした研究は、アメリカで、全面核戦争防止という軍事的な観点から生まれたものですが、石油危機、通貨危機、災害、治安問題などの各分野で、こうした発想の必要性が認められるようになり、さらに民間レヴェルでもひろがりを見せるようになったと、著者はまとめています。 第一巻の本書では、危機管理に必要な基本的な発想と、交渉力、統率力、組織管理のための具体的な方法が論じられています。 生動感のある文章でつづられていて、著者自身が領事として海外で見聞したさまざまな事例や、古今東西の具体例をあげながら、危機管理の実際にせまっており、おもしろく読むことができました。
Posted by
人間順調な時だけでなく、逆風やピンチの時が必ずあります。そんな時にどう対処すればいいのか。基本的な心構えを著者の実例と共に紹介する一冊。危機の時に誰が何をしたのか、その結果も簡略に書かれているので、お勧めです。
Posted by
昭和54年当時に警察・防衛官僚としてトップを極めた著者が書いた危機管理としてトップリーダーシップ論はこれから合併の混乱を想定し、読んでおくべきと考えました。戦争、プロ野球、犯罪、中国の文革などの例から教訓は「準備は悲観的に、実行は楽観的に」「タフ・ネゴシエーター」「5W1Hの中で...
昭和54年当時に警察・防衛官僚としてトップを極めた著者が書いた危機管理としてトップリーダーシップ論はこれから合併の混乱を想定し、読んでおくべきと考えました。戦争、プロ野球、犯罪、中国の文革などの例から教訓は「準備は悲観的に、実行は楽観的に」「タフ・ネゴシエーター」「5W1Hの中でもまずWhatを情報として」「Count on meの精神」ということ。またトップが現場を視察するときのべからず集も納得です。東郷元帥、乃木将軍などの人徳、またミッドウェーの南雲大将の命令の変更が招いた敗北が印象に残りました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
短い単語で考え方、やり方を示している。 information hungry need to know 5W-1H communication gap prepare for the worst Banzai charge Precemeal attack follow through not, but better than nothing capacity and conpetence wai ju nei tao follow me c3 system count on me order, counterorder,disorder Gesselshaft gemeinshaft double eagle rest and recreation one grenade sense of humour 著者は警察出身とのこと。 それにしては粋だ。
Posted by
何度か佐々氏の公演を拝聴したことがある。大変話がお上手で面白く、同意できる点が多いのだが、人によってはちょっと自慢話に聞こえて鼻につくところもあるのではないか。この本もちょっとそんな感じ。
Posted by
- 1