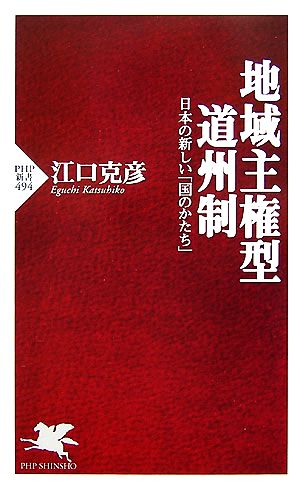地域主権型道州制 の商品レビュー
Sun, 09 Aug 2009 1年半前の発売当時から読んでみたかった本なんだが 機会が無く先送りになってた・・ サンデープロジェクトで 地方分権の話題が出て 自民のマニフェストと 公・民などのマニフェストを比べたときに 民主党のマニフェストには「地域主権」が含まれるが 自...
Sun, 09 Aug 2009 1年半前の発売当時から読んでみたかった本なんだが 機会が無く先送りになってた・・ サンデープロジェクトで 地方分権の話題が出て 自民のマニフェストと 公・民などのマニフェストを比べたときに 民主党のマニフェストには「地域主権」が含まれるが 自民のマニフェストには道州制だけ書かれて 地域主権 が抜けているという指摘があった, その時にコメンテーターがこの本をかざしていた 「んんん? その違いは?」 つまりは,道州制をとっても,その道州を霞ヶ関から押さえつけるモデルも十分に存在しうるし,中央からの地方分権を進めるとそうなってしまう公算も高いということだ. ひ-, 各道州が課税権を持つ事が,やはり大切だ. 行政・立法と市民の「距離」を一定以内に確保する事は,非常に重要だ. それは市民の政治に対する主体性に繋がっていくし, また,行政サービスを行う側にとっても,現場を見て施策決定がしやすいので 変な事をしにくくなる. 中国や北朝鮮の,社会主義国家の非効率性の話を聞いた後に 日本の箱物行政,地方への補助金漬けで 無駄なものを作っている非効率 特殊法人のムダ などの話を聞くと 「どこがちがうのか?」 と思う. 本書冒頭で筆者が中国高官に言われたとすることば 「日本のほうが中国より社会主義ですねぇ」 日本も高度経済成長を終えて20年近い. 現在の中国がひたはしっている官僚主義的社会主義国家のモデルを抜けて, 多様性を是とする進化を遂げる為には地域主権道州制(的なもの)は不可欠だろう. もう,いらんことするくらいなら減税してほしい. ちなみに, 一つ気付いてへんこんだことは 著者の江口氏は 僕が酷評した 「2025年 伊野辺(イノベ)家の1日」 と同一著者だと言うことだ・・・・orz.....
Posted by
明治維新、欧米列強と伍していくため、日本中の力を東京に集中させる必要があった。それから百年。日本の中央集権はなまじ性能が良かったため、時代や状況に適応しきれなくなっているにもかかわらず、今日まで維持されてきた。いまや中央集権はわが国にとって諸悪の根源になりさがっている。すべてが中...
明治維新、欧米列強と伍していくため、日本中の力を東京に集中させる必要があった。それから百年。日本の中央集権はなまじ性能が良かったため、時代や状況に適応しきれなくなっているにもかかわらず、今日まで維持されてきた。いまや中央集権はわが国にとって諸悪の根源になりさがっている。すべてが中央からのお仕着せで地方の活力を奪ってしまっている。中国に日本は社会主義国家かと揶揄される所以である。日本の全人口の10パーセントが全国土0.5パーセントの中に集中しているのは異常。欧米では、企業一つをとっても決して首都に本社が集中するということはない。元気なEUは、共通の経済基盤のもとでお互いに主体性をもって加盟国が競争しあっている。今こそ地域格差をなくし全国各地が繁栄の拠点となる地域主権型道州制が求められている。劈頭には夢の地域主権型道州制が描かれている。決して夢物語だけで終わらせるわけにはいかない。
Posted by
以前、札幌保守研の勉強会で道州制について勉強したときは、あまり関心も無かったのですが、今回ひょんなことから関心を持つようになって読んでみました。この本は、地域主権型道州制がいかに日本の発展に良いかを詳細に熱く説明してくれていて、勉強になります!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] ヒト、モノ、カネ、情報がますます一極集中する現在の日本。 東京だけが極端に繁栄発展し、その他の地域は衰退貧困の一途をたどる。 地方は座して死を待つしかないのか? 日本がいま必要としているのは、これまでの延長線上にある改革ではない。 中央集権体制を早急にあらため、「国のかたち」を抜本的に変えることである。 『地域主権型道州制』とは、全国を12の道州、300の基礎自治体に再編することで、繁栄発展の拠点を十数カ所つくる統治形態である。 「全国どこでも元気」にするための緊急提言。 [ 目次 ] 序章 二〇XX年、新しい日本のすがた 第1章 日本に『地域主権型道州制』を導入する 第2章 なぜ東京だけが繁栄するのか 第3章 中央集権システムの限界 第4章 いかに国が地方をコントロールしているか 第5章 「地方分権」では解決できない 第6章 『地域主権型道州制』はこうする 第7章 住民密着の『地域主権型道州制』 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
日本の新しい「国のかたち」 静岡県は東海州 人口の適正規模が出てたけど政令指定都市とかどうなるんだろう?
Posted by
本書はPHP総合研究所の社長で、道州制ビジョン懇談会など政府の懇談会委員などを歴任している筆者が、道州制導入のビジョンについて示したものである。道州制について大枠を捉えることができる。 筆者は道州制導入の目的を「日本を元気にすること」であるとする。制度疲労を起こした中央集権体...
本書はPHP総合研究所の社長で、道州制ビジョン懇談会など政府の懇談会委員などを歴任している筆者が、道州制導入のビジョンについて示したものである。道州制について大枠を捉えることができる。 筆者は道州制導入の目的を「日本を元気にすること」であるとする。制度疲労を起こした中央集権体制の下で東京だけが繁栄し地方が疲弊する現状を打開するためには、地方分権では十分ではなく、国の形を根本から変える道州制の導入こそが必要である。 明治維新以来日本の地方政策は「自治の原則」よりも、国土が平均的に発展することを目指す「均衡の原則」を重視してきた。 しかし、経済発展も果たし社会資本の整備も進んだ現在の日本においては住民の志向性は多様化しているのであり、住民により近い政府が住民の要望に基づいた自治を進めることこそが求められる。 これまでの地方改革の延長線上ではない根本的な改革として道州制が必要である、という点は非常に共感できるし、自主財源と権限を持った道州が誕生することで、筆者が序章で書いているような(序章は「20XX年、新しい日本のすがた」と題され筆者による道州制導入後の各州の発展イメージが描かれている)日本発展の可能性があることも頷ける。 ただ、一体それを誰がやるのだろうか。 筆者の導入までの手順では世論喚起に続いて、担当大臣・諮問会議の設置、首相の決断・国会の決議と言う順で示されていたが国の形を根本から変えるという大きな決断として道州制を掲げる政権が誕生することは現時点ではあまりイメージできない。 しかし、小さな改革を積み重ね課税自主権など財源の伴わない中途半端な制度になってしまうのでは意味がないことは筆者の強調するとおりである。 それに加えて道州制導入後にも課題はあるように思われる。筆者のイメージでは、各道州は移譲された権限を基に独自の政策を推進・発展していくが、知事のリーダーシップや職員の政策立案能力など実際にそう簡単に上手くいくとも思えない。 と言って、やる前から言っても始まらない。他に何かいい手があるのか。というその点は筆者の言う通りであると思います。
Posted by
戦後日本を発展に導いた「中央集権体制」を改め、これからの日本を築いていくためには「地域主権型道州制」を実施することが好ましい。 これは現在の都道府県をなくして、全国を十二の道州に分ける制度のこと。 各道州がその地域特有の環境に合わせて、それぞれが税財源などを掌握し、住民が密着...
戦後日本を発展に導いた「中央集権体制」を改め、これからの日本を築いていくためには「地域主権型道州制」を実施することが好ましい。 これは現在の都道府県をなくして、全国を十二の道州に分ける制度のこと。 各道州がその地域特有の環境に合わせて、それぞれが税財源などを掌握し、住民が密着した政治や行政を行えるようにする。 本の最初はシナリオプランニングで良いことだけ書かれていて、理想的で面白かった。 これからの日本を考える上で、非常に勉強になった一冊。 ただ全体的にこの本には、制度を導入した時に起こり得る問題があまり書かれていなかったから、自分でこれから調べていかないとなって思った。
Posted by
日本のあり方について考えさせられる一冊です。 官僚主導型の中央集権体制では限界があることは目に見えています。 そこでいま議論されているのが道州制。 確かにこの本は、かなりの部分で理想を語っているところもありますが、 日本の未来を考えたら、政治体制の抜本的改革が必要なのではないか、...
日本のあり方について考えさせられる一冊です。 官僚主導型の中央集権体制では限界があることは目に見えています。 そこでいま議論されているのが道州制。 確かにこの本は、かなりの部分で理想を語っているところもありますが、 日本の未来を考えたら、政治体制の抜本的改革が必要なのではないか、と考えさせられた一冊でした。
Posted by
現在の中央集権制度について説明する記述には教科書的なところも多く、あまり読んで面白い本ではない。ラディカルなことを言っている割には、著者の熱い思いみたいなものがあまり伝わってこず、やや無味乾燥だし。 それでも、地方分権ではなく地域主権型道州制こそが必要、という主張には強く納得す...
現在の中央集権制度について説明する記述には教科書的なところも多く、あまり読んで面白い本ではない。ラディカルなことを言っている割には、著者の熱い思いみたいなものがあまり伝わってこず、やや無味乾燥だし。 それでも、地方分権ではなく地域主権型道州制こそが必要、という主張には強く納得する。日本がやらなきゃいけない改革はさまざまあろうが、この地域主権型道州制も必須の改革なんじゃなかろうか。 区割りをどうするとか国と道州、市の役割分担をどうするとか、細かい部分での議論、異論はあろうが、最初はおおまかに括っておいて、あとからいくらでも微修正を繰り返せばいいと思う。要は、善政競争が活性化するかどうかなのだから。
Posted by
道州制はこれからの国のあり方として考えるべき形だと思います。この筆者がいうように「道州制によって行政が遠くなる」というイメージは間違っていて、「国の行政が道州に、県の行政が市に降りてくる」ので、むしろ行政は近くなるのです。そしてそれによって独自の行政サービスをすることができ、住民...
道州制はこれからの国のあり方として考えるべき形だと思います。この筆者がいうように「道州制によって行政が遠くなる」というイメージは間違っていて、「国の行政が道州に、県の行政が市に降りてくる」ので、むしろ行政は近くなるのです。そしてそれによって独自の行政サービスをすることができ、住民のチェック機能も働くというメリットがあります。 ただし、この本では道州制が完璧かのように書かれており、しばしば論理が破綻している印象を受けました。これまでの中央集権的な国家の果たした役割を認めていながら、これからは絶対的に間違っているというのは少し極論です。世の中に「絶対」ということはないので、絶対に道州制がいい、とはいえないと思います。 とはいえこれから10年間ほどで道州制の議論はかなり進み、もしかしたら10年後には道州制に移行しているかもしれませんね。 そして私の関心としては、沖縄が沖縄州としてちゃんと独立できているか、ということです。独立、だけでなく経済的にも自立しているか、ということが問題になるのでしょう。
Posted by
- 1
- 2