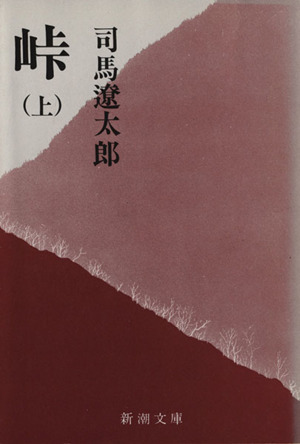峠(上) の商品レビュー
幕末の長岡藩士、河井…
幕末の長岡藩士、河井継之助の物語です。日本中をかなり自由に回って勉強してます。幕末の騒ぎの中、小藩の藩士ということもありますが、まだ歴史の表には表れません。
文庫OFF
郷土の有名人の話です…
郷土の有名人の話ですので読んでみましたがうーん・・という感じ。ちょっと期待はずれ。
文庫OFF
明治維新の際、故郷の…
明治維新の際、故郷の国である長岡藩を守るべく新政府に対抗した河合継之助の話。
文庫OFF
幕末における越後長岡藩の家老、河合継之助を題材とした歴史小説。 上下巻のうち、上巻では、江戸・横浜への遊学や山田方谷への弟子入り、藩政改革(賭博の禁止や娼妓の禁止など)を中心に物語が進行する。時代としては、徳川慶喜の大政奉還まで。 以下、感想。 司馬遼太郎が無名の歴史上の人物であ...
幕末における越後長岡藩の家老、河合継之助を題材とした歴史小説。 上下巻のうち、上巻では、江戸・横浜への遊学や山田方谷への弟子入り、藩政改革(賭博の禁止や娼妓の禁止など)を中心に物語が進行する。時代としては、徳川慶喜の大政奉還まで。 以下、感想。 司馬遼太郎が無名の歴史上の人物である河合継之助を題材にした理由は、上巻だけを読む限りでは見当たらない。確かに、坂本龍馬のような先見の明に富んだ人物として描かれている。また、織田信長のように合理的精神の持ち主であるようにも伺える。 継之助は、奇抜かつ斬新な思想を持っており、中途半端な行動は起こさない人物のようだ。そして、非常な自信家でもある。 このような人物像に作者は惹かれたのかも知れない。様々な逸話は読んでいる側としても痛快であった。 ただ、無名の人物であるが故か、挿話の寄せ集めの感は否めず、この後、どのような物語となっていくのか、歴史にどのような足跡を残したのか、楽しみにしながら下巻に進みたいと思う。
Posted by
長岡藩の河井継之助を主人公にした幕末小説。徳川三百年とは、徳川体制からどうやって近代の体制に移行できるか、そして日本にやって来た諸外国に追いつけるか、継之助を通して分かりやすく描かれている。 徳川譜代の長岡藩、その中でも大きくない河井家だが、継之助は時代を理解し、その枠組みの中...
長岡藩の河井継之助を主人公にした幕末小説。徳川三百年とは、徳川体制からどうやって近代の体制に移行できるか、そして日本にやって来た諸外国に追いつけるか、継之助を通して分かりやすく描かれている。 徳川譜代の長岡藩、その中でも大きくない河井家だが、継之助は時代を理解し、その枠組みの中で、どうやって長岡藩が生き残れるかを考える。江戸へ出て、横浜を訪れ、今度は備前松山に師を訪ねる。 継之助は、藩主に認められ藩の要職に就き、改革を次々と実行する。目的は財を蓄え、近代兵器を調達し、時代がどのように動くにせよ、スイスのように自立、中立できること。しかる後に、継之助は、横浜に来たスネルから、洋砲と洋銃を調達する。 大政奉還は、徳川慶喜の奇手だったが、朝廷側の薩摩藩に見切られ、徳川家存亡の窮地に追い込まれる。
Posted by
再読、★評価は読了後に。 なかなかに面白い、主人公に共感できるかはさておき、魅力的なお話が展開されとります。やはりこの作家の本領は幕末にあり、加えてこういった歴史の「傍流」にある人の発掘力は認めざるを得ない。またこの時期は最も脂が乗っていたのかも。
Posted by
久しぶりに司馬遼太郎の本読んだらすごくおもしろかった。主人公の河井継之介に関してはまるで知らなかったけど、素晴らしい人物。7万4千石の長岡藩の中の牧野家の家臣だが、先見の目を持ち、陽明学の考えに基づいた行動は見ていて非常に気持ちがよい。 というか、この本、幕末の話だけど、幕末って...
久しぶりに司馬遼太郎の本読んだらすごくおもしろかった。主人公の河井継之介に関してはまるで知らなかったけど、素晴らしい人物。7万4千石の長岡藩の中の牧野家の家臣だが、先見の目を持ち、陽明学の考えに基づいた行動は見ていて非常に気持ちがよい。 というか、この本、幕末の話だけど、幕末って朱子学的な考え方と陽明学的な考え方の対立にも見える。また、どんなに先見の目があり、考えがあっても人間には立場というものがあるというのが河井継之介を見ているとよくわかる。 統治者からすると朱子学を官学にしたくなるのは非常にわかるが、陽明学を基本とした学問にしたら、もっと日本という国の将来は変わっていたと思うし、現代にもその影響はあったと思う。まぁ陽明学を基本の学問としたら正直江戸幕府はあんなにも続かなかったかもしれないが。朱子学の流れというのは現代にも続いている気がするのだが、それがこう感覚的に日本が廃れてる根本的な原因にもなっているのではないかと思ってしまう。保守的な変化を好まないトップの奴らは本当に嫌いだ。 別にこの本は朱子学だ陽明学だって内容じゃないんだけど、そこのところがすごく読んでいて興味深かった。おれの大好きな三島由紀夫もそういえば陽明学が好きだったな。 上巻にてすでに大政奉還しそうな勢いだったけど、下巻はどういった話になるのだろう。すごく楽しみ。 正直幕末って色々なドラマがあるよな~。前読んだ燃えよ剣は新選組サイドの話だったし、今回の河井継之介は譜代大名の家臣だし、革命側の薩長の話も読んだら楽しそうだ。 現代こそ河井継之介的な人間が必要でしょ!ってすごく思った。
Posted by
最近は、司馬遼太郎の書く 男に、興味がある。 河井継之助の物語。 長岡藩で、もだえる。信濃川を登って行くと、 江戸がある。 器が大きすぎて、小さなことにこだわらない。 というか、不器用な人であるが、常に原理を求める。 急ぐ心。心の命ずるままに、行動する。 その心を、したて上げて...
最近は、司馬遼太郎の書く 男に、興味がある。 河井継之助の物語。 長岡藩で、もだえる。信濃川を登って行くと、 江戸がある。 器が大きすぎて、小さなことにこだわらない。 というか、不器用な人であるが、常に原理を求める。 急ぐ心。心の命ずるままに、行動する。 その心を、したて上げて行く。 欲しいのは、知識ではなく、どう行動するのか。 侠客の侠の字は、ニンベンに挟むとある。 左右の子分に挟まれ、それを従える。 ツラで、全てを察する。ツラで、相手のこころのキビを分かるようになる。 本画は志を表すが、席画は、才気をあらわす。 オレの生命は一個の道具だ。 道具なればこそ、鍬はよく土を耕し、カンナはよく板をけずる。 オレもオレの生命を道具にこの乱世を耕しけづる。 酔生夢死。なすこともなくこの世に生き、そして死んで行く。 その覚悟をする。 河井継之助は考える。 激動の時代に、国をまもり、国を発展させるためにどうするのか? 武士は 刀を大切にして あがめるようにしているが それで良いのだろうか? 銃が登場することで、刀の意味はなくなっていく。 近代的な戦争が始まっているのに,刀で立ち向かおうとする無意味さ。 藩を近代的にするために、チカラをつける。 賭博、売春をやめさせる。 コメから 金への貨幣制度への変換。 自立した考え方。 富国強兵の政策が あまりうまく 展開されていない。 オンナについて 小稲、織部、おすが。妹八絵。 男の領域に口を出さず、うけとめる。 河井継之助はなぜ女郎買いが好きだったのか。 大政奉還をした 慶喜は どのようなことをイメージしたのか。 そして,それに継ぐ 老中たちは。 結局は 次の時代のイメージが 充分に形成されなかった。 ナポレオンのような フランスの皇帝制。 天皇と将軍というものの 人の評価は。 尊王という思想は 水戸藩が 形成したながれだった。楠木正成。 攘夷を唱えていた 薩長は、少なくとも 江戸幕府を倒すための方便だった。 鳥羽伏見での 大きな転換点は どこにあったのか。 薩長には シナリオライターがいた。 覚悟の差異。薩長には 命を張る覚悟を持っていた。 河井継之助は、そのような覚悟を持っていた。
Posted by
越前長岡藩という幕末の中心からは遠く離れた場所で、藩財政を建て直し、最新鋭の武装としてガトリング砲を購入するなど長岡藩存続の道を模索した河合継之助の生涯を描いた作品。再読予定【所蔵】
Posted by
- 1