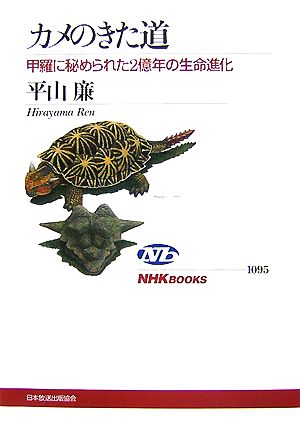カメのきた道 の商品レビュー
卒論前に読んでみた。 先生のらしさ溢れる文体で楽しませて頂いた。 大変読みやすく、カメ初心者におすすめ。
Posted by
私が推薦する図書は『カメがきた道』という本です。本書はカメの進化を古生物学的に紹介した珍しい本です。カメの体の構造、適応拡散から進化までを様々な時代のカメ化石の写真・イラストとともに解説しています。 カメ類が出現した三畳紀は恐竜と哺乳類が出現した時代でもあります。そうした中でカメ...
私が推薦する図書は『カメがきた道』という本です。本書はカメの進化を古生物学的に紹介した珍しい本です。カメの体の構造、適応拡散から進化までを様々な時代のカメ化石の写真・イラストとともに解説しています。 カメ類が出現した三畳紀は恐竜と哺乳類が出現した時代でもあります。そうした中でカメ類は低代謝、言い換えれば低活動少食料で生存するといった戦略を採りました。この戦略において外敵から身を守れる甲羅は大いに役立ちます。甲羅の骨格的構成は三畳紀にほぼ完成しており、現在のカメと比較しても外見的な大きな違いはありません。しかし、捕食圧などに対抗するためのマイナーチェンジは何度か行われています。わかりやすいところでは頭の格納などもこれに含まれます。 本書で紹介されるカメ化石には日本産のものも多く存在します。身近なところでは白山市旧白峯村桑島の化石壁から発見されたものがあります。化石壁は手取層群に属し、世界的にも最古級の現代型潜頸類のカメ化石が発見されています。この他にも日本では特徴的なカメ化石が複数産出しています。 本書はカメを通じて生物の適応拡散や進化に触れることができ、身近な場所からカメの進化史上重要な化石の発見があるという点でも推薦したい本です。 (地球環境学コース 修士1年)
Posted by
は虫類の化石って言うとどうしても恐竜が思い浮かぶわけだけど、亀の化石もあるのね!多いのね!そして地域分布と進化の度合いで化石からわかる気温が今言われている定説と異なるというのはとても興味深い。亀の力で定説が覆るのかもしれない。 目新しくないから忘れてるけど、亀も考えてみればかなり...
は虫類の化石って言うとどうしても恐竜が思い浮かぶわけだけど、亀の化石もあるのね!多いのね!そして地域分布と進化の度合いで化石からわかる気温が今言われている定説と異なるというのはとても興味深い。亀の力で定説が覆るのかもしれない。 目新しくないから忘れてるけど、亀も考えてみればかなり特殊な生き物だよな。オサガメの生態がより詳しくわかってくるとますますおもしろそうだ>亀
Posted by
サブタイトルが「甲羅に秘められた2億年の生命進化」とあるように、化石などに基づいたカメさんたちの進化について考察したややマニアックな1冊。 でもNHKブックスだから、かなり読みやすかったです。 らじは骨系が大好きなので、楽しめました♪ でも、カメが好きって言うより、カメの生態を調...
サブタイトルが「甲羅に秘められた2億年の生命進化」とあるように、化石などに基づいたカメさんたちの進化について考察したややマニアックな1冊。 でもNHKブックスだから、かなり読みやすかったです。 らじは骨系が大好きなので、楽しめました♪ でも、カメが好きって言うより、カメの生態を調べるのが好きな人のお話です。
Posted by
カメの体の仕組みや生態など、広く深く網羅している。 素人の私にはちょっと難しいかなぁと読み進めていくと、福井県の「化石壁」を発掘するあたりから俄然面白くなってきた。さすが専門分野! 日本にも巨大なウミガメがいた事や、新種の発見、発表などワクワクするような臨場感があった。 最後に、...
カメの体の仕組みや生態など、広く深く網羅している。 素人の私にはちょっと難しいかなぁと読み進めていくと、福井県の「化石壁」を発掘するあたりから俄然面白くなってきた。さすが専門分野! 日本にも巨大なウミガメがいた事や、新種の発見、発表などワクワクするような臨場感があった。 最後に、人間の出現によって多くの大型のカメが絶滅したのは、何ともやりきれない・・。
Posted by
カメと一言でいってもたくさんの種類や進化の道筋があるんだな〜と知りました。 化石の発掘作業もところどころ出てきて、面白そうだなと思いました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 中生代の地球で、恐竜は巨大化の道を選び地球上を制覇したかに見えた。 一方、哺乳類は一日食物をとらないと生死にかかわるという高代謝を選択し、餌獲得のために知能を発達させ、次の主役となった。 しかしカメは第三の道である低代謝を選択し、餌がなければ1ヶ月以上でも待つことができる体を獲得した。 その結果、ガラパゴスゾウガメは200歳を超える寿命の固体も確認されている。 あわただしく攻撃的に生きる40年(自然状態でのサルの寿命)とゆっくり打たれ強く生きる200年のどちらに価値があるかはだれにも決められない。 地球生命を相対化する視点から語る、意欲的なカメの進化学入門。 [ 目次 ] 第1章 カメの体の驚異的な仕組み 第2章 多様な環境に進出したカメたち 第3章 謎だらけの起源 第4章 恐竜時代のカメたち―世界への大拡散 第5章 海ともう一つの世界へ―最古のウミガメの姿 第6章 甲羅を力に変えて―哺乳類時代のカメたち 第7章 迷惑な保護者 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
カメの進化や形態についてかなり本格的に書かれた本です。自分は形態学が苦手なのであまりよく理解できなかったのですが、興味がある人にとっては面白いのではないだろうか。個人的には本題とはあまり関係ないオサガメのところだけ印象に残っています。
Posted by
著者は化石爬虫類、特にカメ類を専門とする研究者。 著者によると、カメの本は、ペットとしてのカメ、そうでなければ現生のウミガメに関するものがほとんどだという。化石からカメの進化を辿るこの本は、そうした中では異色の本なのだろう。 (表紙絵の)角の生えたカメや甲羅に突起のあったカメ...
著者は化石爬虫類、特にカメ類を専門とする研究者。 著者によると、カメの本は、ペットとしてのカメ、そうでなければ現生のウミガメに関するものがほとんどだという。化石からカメの進化を辿るこの本は、そうした中では異色の本なのだろう。 (表紙絵の)角の生えたカメや甲羅に突起のあったカメなど、今は絶滅してしまったカメの話もおもしろいと言えばおもしろいのだが、自分にとって一番おもしろかったのは、オサガメが1日100kgのクラゲを食べているらしいとか、カメは代謝が低く1ヶ月食べなくても大丈夫とか、現存のカメに関する豆知識だったりする。本題とはちょっとずれた部分なのだが。 カメの化石は実はあちこちで出ているものらしい。素人の感想だけれど、甲羅がある分、普通(?)の動物より再構成が難しそうだなぁ・・・(下手なジグソーパズルよりきっと難易度が高いぞ)。目の前にあるもののスケッチだって大変なのに、化石を元に、見てきたように精緻な復元画を描く挿絵の小田隆さんもすごいと思う。 *余談だけれど、著者は日本画家の平山郁夫さんの息子なんだそうです。
Posted by
著者によると,カメ研究のは,これまで一般的な書籍になっていなかったそうです. その内容がすごい. 古代生物から徐々にカメの全貌を紐解いていくプロセスは,何となく手に取った「カメ本」としては充実しすぎるほど勉強になる. 初めての「カメ本」,内容の充実,という2つの意味で本書の価...
著者によると,カメ研究のは,これまで一般的な書籍になっていなかったそうです. その内容がすごい. 古代生物から徐々にカメの全貌を紐解いていくプロセスは,何となく手に取った「カメ本」としては充実しすぎるほど勉強になる. 初めての「カメ本」,内容の充実,という2つの意味で本書の価値は高いと考えます. 本当に勉強になる.
Posted by
- 1
- 2