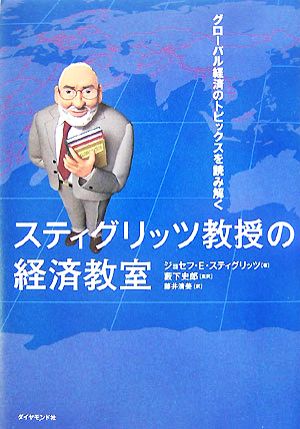スティグリッツ教授の経済教室 の商品レビュー
「経済」は何となく皆が一家言を持ちたくなる分野だが、一般に流布する”一見もっともらしいが正しくない"説などを専門家として批評していく。某大統領に読んでもらいたい。 (2007年購入・読了。2017年売却)
Posted by
この方の本はやはり勉強になる点が多いです。 この本も1週間という時間をかけて、 項目項目で読み進めています。 一気読みすると、相当な根気がいります。 考えながら読むことが多いのです。
Posted by
経済学者として、象牙の塔の住人ではなく実践的な活動を行っていくためには政治家としての要素は避けて通れない。それはわかるのだが、本書には著者の政治的なポリシーがあまりにも強く反映されすぎているために、一流の学者ではなく、タブロイド紙の二流の編集者が書いたような内容になってしまってい...
経済学者として、象牙の塔の住人ではなく実践的な活動を行っていくためには政治家としての要素は避けて通れない。それはわかるのだが、本書には著者の政治的なポリシーがあまりにも強く反映されすぎているために、一流の学者ではなく、タブロイド紙の二流の編集者が書いたような内容になってしまっている。つまり他者に対する批判があまりにも多すぎるのである。 もっともこれは邦題のつけ方に問題があるのかもしれない。元のタイトルは「現状の体制に訴える」というものになっており、それであれば確かに内容とは合っているが、間違っても「経済教室」といえるものではない。 あまりにも反体制的な著者のスタンスに辟易して☆1つでもいいかとも感じたが、環境保護や開発途上国への知的財産の提供など訴えている内容は(倫理的には)間違っていないと思うので☆2つにしておく。
Posted by
ジョゼフ・E・スティグリッツ博士の本。 これは2007年の本なので、まだ世界崩壊前の話である。 故に、一分現在の状況ととは違う処があるが、経済学者の政府関係者に対する愚痴として捉えると非常に面白い。 竹中平蔵が、亀井静香に噛み付くみたいなものか、いや違うな。 とにかくスティ...
ジョゼフ・E・スティグリッツ博士の本。 これは2007年の本なので、まだ世界崩壊前の話である。 故に、一分現在の状況ととは違う処があるが、経済学者の政府関係者に対する愚痴として捉えると非常に面白い。 竹中平蔵が、亀井静香に噛み付くみたいなものか、いや違うな。 とにかくスティグリッツ教授は、ブッシュ政権が大嫌いで、事あるごとにチクチク理論武装して突っ込みまくる。 これはどういう事かと言うと、彼はケインズよりなのである。故にニューディール政策的な公共投資をあまりせず、金融資本だけでぶん回してきたブッシュ政権が大っきらいなのである。 よってゼーリック等も袋叩きにしている。もちろん、アラン・グリーンスパンもだ。 ・・・ちょっとまてよ、と。結局この本の本文って何? それは簡単です。ブッシュ政権が犯した過ちに対する反省文と、私ならこうしましたという論文です。 なので霞関係者の方の中にはスティグリッツ信奉者が比較的多いのかもしれません。 かく言う私もこの本は、某大学教授で某省審議官だった方から頂いたものですので(笑)、霞のかたでしたらどうしてもケインズよりになるだろうなぁと思います。 池田信夫先生と村上グーグル名誉会長はマンキュー派みたいです。 私はとりあえず、スティグリッツ理論は理解したし、親日派っぽいのでスティグリッツ教授の教科書を買いました。でも、読み終わったらマンキューも買ってみたいと思います。たぶんその頃には日本語訳された最新版のマンキューのマクロ経済学の本も出ていることでしょうから。
Posted by
2001年「情報の経済学」構築によりノーベル賞受賞、現コロンビア大学教授のスティグリッツ教授が、ダイヤモンドに寄稿した2003年から2007年にかけての記事をまとめたもの。 2010年現在から過去を振り返りその様相を眺めつつ、ここでとりあげられたトピックスが今なお議論の最中であり...
2001年「情報の経済学」構築によりノーベル賞受賞、現コロンビア大学教授のスティグリッツ教授が、ダイヤモンドに寄稿した2003年から2007年にかけての記事をまとめたもの。 2010年現在から過去を振り返りその様相を眺めつつ、ここでとりあげられたトピックスが今なお議論の最中であり、読み返す意義あり。 こういう本に書いてあるようなマクロな視点って、自分の仕事について考えるときに、眼を通すと良いと思う。自分の仕事と世界の繋がり、なんて想像してみてはいかが? 教授の基本的な価値観は「民主主義」と「社会正義」であり、情報を整理し参加意識の高い市民の育成をしようとする使命感、地球環境維持や貧困の削減追求といったものへの正義感にあふれており、必要ならば相手が世界の最高権力者でも闘う賢人と思慮しました。 内容そのものについて、批評的な読み方ができるほど知識がないので恐縮ですが、とりあえず、頭の中にメモしたキーワードは以下のとおり ■中央銀行はえてしてマネタリズムで「インフレ抑制」だけ考えがち。だがこれは論拠はなくイデオロギーにすぎない。 ■ポピュリストが人気があるのはテクノクラートが知らない何かを知っているからかも、と考えてみるべし ■アメリカ貿易赤字について米政府は過去に日本、今は中国を責任転嫁しようとしているが、それは間違い ■世界銀行、IMFのトップの決め方は、国籍問わないべき ■定言命法はない。勝者と敗者、アメとムチは存在。全体としてパレート優越のバランスを目指せ ■ロシア新財閥に課税を! ■「長期的には我々は皆死んでいる」byケインズ。限られた時間の中で結果を求めるプラグマティズムという視点で政策をチェックせよ ■年金民営化は無駄。政府が管理できるお金を外に出すだけ。しかもコストは増える。民営化=高額な雇用費用利益確保などのコストがかかる。 ■腐敗した国家は開発の妨げになる。世界銀行といった経済ファンクションでも、政治的要素への介入は不可欠 ■過去、対外援助は友好を買うものだった・・・。対外援助には多面的(お金だけでない)投資・活動がセットでないと無駄になる。関税廃止の言葉の罠に気をつけろ! ■グリーンスパン神聖化はおかしい。中央銀行独立、という第三者的立場、客観的立場、ということで彼の行った定言(ブッシュ政権下の減税)がもたらした悲劇。実は中央銀行は独立してない?! ■アメリカがやってきた二国間貿易協定はNG。多角的貿易体制をは買いしてはならない。 ■中国は持続可能な成長を維持するために自身が変わらなければならないことを理解し、政策をたてている。
Posted by
グローバリゼーション、地球環境、国際貿易、中国の台頭、イラク問題…。ノーベル賞経済学者・スティグリッツ教授が世界の重要テーマを鋭く分析。間違いだらけの政策・学説を論破し、正しい考え方を提示する。(TRC MARCより)
Posted by
ジョセフ・スティグリッツが「プロジェクト・シンジケート」に寄稿していた原稿を時系列順にまとめた本。なので、体系的に経済学を学ぶというような「経済教室」ではなく、それぞれのコラムで主題となるトピックについて経済学的な観点から論じられているって感じ。ブッシュ政権やIMFに対する手厳し...
ジョセフ・スティグリッツが「プロジェクト・シンジケート」に寄稿していた原稿を時系列順にまとめた本。なので、体系的に経済学を学ぶというような「経済教室」ではなく、それぞれのコラムで主題となるトピックについて経済学的な観点から論じられているって感じ。ブッシュ政権やIMFに対する手厳しい批判がされているが、ほとんどで対案が示されていて、建設的な批判となっているのはさすがといった感じ。また、反グローバリゼーション的な記載も多いけれど、市民団体のよくわからん抗議活動なんかよりは理性的かつ理論的に書かれており勉強になる。ただ、経済学的には基本的な経済用語くらいは知っておかないとキビしいかなぁ、と思う記載もあるので、初心者向けと思って買うと戸惑うかもしれませんのでご注意を。
Posted by
ノーベル経済学賞受賞者であるスティグリッツ先生による寄稿記事を 『週刊ダイヤモンド』誌が連載していたもの。 内容は、雑誌連載ゆえの区分そのままだったため、 安直な弱輩者は、不謹慎にも気になったトピックのみを読んだ。 第3章以降は、ブッシュ政権の経済政策全般に対する批判に終始しな...
ノーベル経済学賞受賞者であるスティグリッツ先生による寄稿記事を 『週刊ダイヤモンド』誌が連載していたもの。 内容は、雑誌連載ゆえの区分そのままだったため、 安直な弱輩者は、不謹慎にも気になったトピックのみを読んだ。 第3章以降は、ブッシュ政権の経済政策全般に対する批判に終始しながら世界経済を解説。 視覚データ・図が皆無かつ縦書き体裁。 他畑からの読者としては、顰め面をしてしまうことも多い装丁だった。
Posted by
スティグリッツの2003年から2007年にかけての経済コラム集。スティグリッツは、1997年のアジア通貨危機に対するIMFの救済策内対する問題点を経済学的に明らかにした勇猛果敢なマクロ経済学者。 タイを発祥とするアジア通貨危機は、「返済能力の問題」か、あるいは「流動性の問題」...
スティグリッツの2003年から2007年にかけての経済コラム集。スティグリッツは、1997年のアジア通貨危機に対するIMFの救済策内対する問題点を経済学的に明らかにした勇猛果敢なマクロ経済学者。 タイを発祥とするアジア通貨危機は、「返済能力の問題」か、あるいは「流動性の問題」かであった。IMFは通貨危機を「返済能力の問題」と認識したのである。ここが誤診の始まりで、その誤診の上に、構造解改革の要求まで付け加えた。IMFの97年の対応については後日詳細を明記できたらなと思うが・・・・・。 IMFの改革も主導したとされている。 また、フリードマン流のマネタリズムに対しても疑問を呈し、インフレターゲットに対しても「実質金利」を下げることで投資が活発になるという経路について疑問を呈して、これを批判している。実質金利は、短期国債と長期国債の相対的な供給量を変えることによって、資産の価格に影響を与え、よって長期実質金利に影響を与えることが出来るとしている。金融政策は実質金利よりも、むしろ信用のアベイラビリティー(可用性)を通じて景気に影響を及ぼすのである、としている。信用供給の方が重要だと説いている。インフレターゲット(物価安定化金融政策)については、スティグリッツは反対しており、2002年時から「転向」したようである。というのも、「スティグリッツによる日本経済再生の処方箋」として黒木氏が掲載している通り、インフレターゲットを再生の処方箋として述べているからである。 巻頭論文に「21世紀はじめの日本と世界」が掲載。これだけの紙幅があれば、十分に述べたいことが述べられるだろう。似たような経済論集にクルーグマンの「クルーグマン教授の経済入門 (日経ビジネス人文庫)」「良い経済学 悪い経済学 (日経ビジネス人文庫)」があるが、それらとの対比で言うとスティグリッツは「社民」よりの言辞が目立つ。それならそれでいいのだが、その根拠の明示が少なく、理論を説くといった風情がないのも肩透かし気味。 各コラムが、紙幅の関係もあってだろうが、短いので、それぞれに読み応えがないのが非常に残念。 とはいえ社民的なマクロ経済学が、日本のマクロ経済学者には少ないように思うので、彼のような視点からの日本経済に対する指摘は、すこぶる貴重なことであろう。マクロ経済が、あまりに「自由主義」へ傾斜しているのは、その学者が自由主義=価値観からも自由であるとの錯覚を持つことからも、正当性を過激に主張する根拠を与えることになり、「政治的」に危険でさえあるからである。
Posted by
「経済教室」って書いてあるけど経済学について特に良くわかるようになるわけではない。スティグリッツの経済に関する意見書をまとめたようなもの。グローバリゼーションやブッシュ大統領の政策を批判している。グローバリゼーションについてはそれ自体を否定しているわけではないけど、ケインズの「長...
「経済教室」って書いてあるけど経済学について特に良くわかるようになるわけではない。スティグリッツの経済に関する意見書をまとめたようなもの。グローバリゼーションやブッシュ大統領の政策を批判している。グローバリゼーションについてはそれ自体を否定しているわけではないけど、ケインズの「長期的には我々は死んでいる」の言葉を引用して長期的には恩恵を受けるとしても短期的には人々を不幸にするんだからそこに経済政策が必要になるというようなロジックで論を展開している。最近の世界経済のトピックをおさえるという点ではすごくよい本。
Posted by
- 1