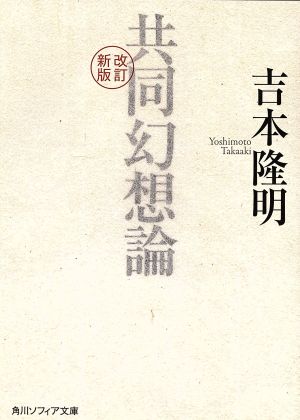共同幻想論 の商品レビュー
NHK『100分de名著』から興味がわいて読んでみたけど、私の凡庸な頭では正直ちょっと理解が追いついていない。 とりあえず、神話(古事記)が政治的な意図をもったものだということに目から鱗だった。 考えてみれば、歴史は勝者がつくるわけだし、当たり前なんだけど、政治と宗教は別物だと...
NHK『100分de名著』から興味がわいて読んでみたけど、私の凡庸な頭では正直ちょっと理解が追いついていない。 とりあえず、神話(古事記)が政治的な意図をもったものだということに目から鱗だった。 考えてみれば、歴史は勝者がつくるわけだし、当たり前なんだけど、政治と宗教は別物だと思っていた。 いやでも、仏教の檀家制度で戸籍を管理したって、どこで知ったんだっけ。キリスト教の布教と植民地支配の歴史だって十分に政治的だ。だから、神道が例外なわけはないのにな。 信仰心とは別に、宗教の物語性は共同幻想として機能しやすく、それが国家としてまとまるのに使い勝手がいい。じゃあ、宗教の共同幻想が薄れたいまの日本には、どんな共同幻想があるんだろう…と考えたけど、p.48に、神話では「習俗と生活威力とがからまった〈幻想〉の位相をしるには、あまり適していない。 」とあった。神話や宗教だけでは日本の国家としての共同幻想を捉えられないのか。 「国家」の共同幻想とはなにか。私の所属している「集団」の共同幻想ってなんだろう。難しい本だなあ、でも面白い。 本書を読んであらためて番組を見直すと、ほかの著作からの引用なんかもあり、さらに面白かった。
Posted by
言っていることがわかるか?と言われたらわかるかもしれないんだけど、文体とか、問題意識とか、それが遠くなんだよね。渋谷陽一はこの本がすげえすげえってずっと言ってたよね。神話ってのの発生とか、つまり、中沢新一的な神話ってのが、例えばシンデレラとかの話とか、これらをどう読むとというサス...
言っていることがわかるか?と言われたらわかるかもしれないんだけど、文体とか、問題意識とか、それが遠くなんだよね。渋谷陽一はこの本がすげえすげえってずっと言ってたよね。神話ってのの発生とか、つまり、中沢新一的な神話ってのが、例えばシンデレラとかの話とか、これらをどう読むとというサスペンスとして読むのがよいというのがやっとわかった気がする。社会以前から、社会へ、それには言語が大きくかかわる。そして、システム
Posted by
吉本隆明 「 共同幻想論 」著者が描いた幻想領域を 国家、部落、男女に あてはめた本。国家論として「国家は共同の幻想である」を展開。幻想は 夢とも心理とも読める。 遠野物語、ハイデガー、モルガンエンゲルス、古事記から幻想性を論述した 禁制(タブー)、他界(死生観)、母系制は面白...
吉本隆明 「 共同幻想論 」著者が描いた幻想領域を 国家、部落、男女に あてはめた本。国家論として「国家は共同の幻想である」を展開。幻想は 夢とも心理とも読める。 遠野物語、ハイデガー、モルガンエンゲルス、古事記から幻想性を論述した 禁制(タブー)、他界(死生観)、母系制は面白い。対幻想はフロイトみたい。 幻想領域の3つの内部構造 *国家、法を問題とした場合 共同幻想 *男女間の問題の場合 対幻想(ペアになっている幻想) *文学理論などの場合 自己幻想 禁制(タブー)の共同幻想 *その中の個人は 禁制の神聖さを強制されながら、その内部にとどまっている *共同幻想は 現実と理念の区別が失われた心の状態で 共同的な禁制を生み出す
Posted by
国家は共同幻想であるとして、 フロイト読解による〈幻想〉から始め、その論理的延長によって、記紀の日本〈国家〉成立のうちに幻想を見つけ出そうとする。 個人的幻想から家族的幻想、共同体的幻想へと広がっていく流れになっている。 筆者にとっては〈幻想〉であるということが特別であることの...
国家は共同幻想であるとして、 フロイト読解による〈幻想〉から始め、その論理的延長によって、記紀の日本〈国家〉成立のうちに幻想を見つけ出そうとする。 個人的幻想から家族的幻想、共同体的幻想へと広がっていく流れになっている。 筆者にとっては〈幻想〉であるということが特別であることのように感じられているようだが、いまやあらゆるものが幻想であるとも言える(それは逆に、真実性を必要としなくても、すべてが現実であるとも言える)。そういう前提に立ってしまえば、〈幻想〉であるという主張のみでは有効性は持たない。すると、別の点に重要性が移行するだろう。おそらくそれは、幻想の軌跡がイコール歴史であるということではないか。とすれば、この書は一つの歴史書と言えるのではないか。 そういった意味で、この著作は「不可能性の時代の歴史書」の側面を持つかもしれない。
Posted by
久しぶりにわからない本だった。 理解できないわけではないし、つまらないわけでもない。こちらの知識不足なのだろうか。 いくつかのキーワードの定義がなんともスッと入ってこなくて、そこが理解の妨げになっている感じ。 きっと、何回か読む本だと思われる。
Posted by
学生のときに読んだが、正直なところ、難解でほとんど理解できなかった 今後も処分せずに本棚に置いておき、再読しようかと思う ばななさんの父親というのにも驚いた
Posted by
うーん。 自己幻想から、対幻想から共同幻想というものが、 大事なのはわかる、分かるんだけれども 原理として建てたいのは分かるんだけれども、 この著書では前半までは対幻想、後半は共同幻想を扱う。 その対象は、想像力しか及びえないところにむかっていくため、 それを原理としておくに...
うーん。 自己幻想から、対幻想から共同幻想というものが、 大事なのはわかる、分かるんだけれども 原理として建てたいのは分かるんだけれども、 この著書では前半までは対幻想、後半は共同幻想を扱う。 その対象は、想像力しか及びえないところにむかっていくため、 それを原理としておくにいはきつい。 個人が、何らかの社会に属する時に 非物理的な空間を媒介としていることを、 吉本はなんとかつかもうとしている。 その理路の底板になっているのは、 ヘーゲルとフロイトだ。この出会い。 しかし、この本は、時間切れと言われてしまったように、 途中で終わる。 このモチーフは、『心的現象論』『母型論』へ受け継がれているんだろうな。 まだだ、まだあきらめない。
Posted by
世界を認識する方法として全幻想領域の構造を解明する際に、自己幻想、対幻想、共同幻想という3つ軸で、各々の相互関係と内部構造をはっきりさせればよいというのは非常にシンプルで明解。特に対幻想の疎外から生まれる共同幻想、そして共同幻想と逆立する自己幻想という関連性にはとても納得。この切...
世界を認識する方法として全幻想領域の構造を解明する際に、自己幻想、対幻想、共同幻想という3つ軸で、各々の相互関係と内部構造をはっきりさせればよいというのは非常にシンプルで明解。特に対幻想の疎外から生まれる共同幻想、そして共同幻想と逆立する自己幻想という関連性にはとても納得。この切り口の鮮やかさに団塊世代が引き込まれたのもわかるような気がする。 文学でも政治でも経済でもない総合性と現在性の両面からアカデミズムに陥ることなく世界を検証していくという人は現在でもあまりいないような気がする。で、世に蔓延るのは合理性・経済性やら、人道・情緒・感情主義という偏ったポジションでしかモノを語れない大学の先生や政治家ばかり。吉本にはもっと活躍して欲しかったし、死後の再評価はもっとされてもいいような。 大学時代に買って、パラパラめくっただけでずっと放置していたのをやっと読んだのだが、これ程の内容とは想定外だった。最後の中上建次の「思想が文学を死滅させ解体させた」というのはややオーバーな気がするが、文学者はそこまで打ちのめされたんだろうか???
Posted by
7/18 p.12迄 7/17 読み始め 国家という幻想…自然科学者にとっての素粒子のようなイメージ…これは解決策なのか 歴史的事実を根拠
Posted by
約1ヶ月半格闘した末、ようやく読み終えることができた! わたしの読書人生の中で最強の出会い、のうちのひとつでした。 今後とも読書にハゲむべし!!
Posted by